『第70回ハートストリングス語りと朗読の会』(2017.12.2、阿佐谷・ハートストリングス)で内藤和美さんが読んだ小説「藤九郎の島」(久生十蘭作)の元資料が判明した。
それは、神沢貞幹『翁草』という随筆集の中の一つの記事であった。『翁草』は全二百巻で、前編百巻が明和九年、後編百巻が寛政三年に完成している。
元となったのは、巻之三十七に収められている「無人島漂流船の事」という文章。
手元に二つの原文がある。さらに現代語訳も見つけた。
●神沢貞幹『翁草:校訂4』(明治38-39年、五車楼書店)
※国立国会図書館デジタルコレクションで公開
●『日本随筆大成〈第三期〉20』(昭和53年、吉川弘文館)
※『翁草』巻之三十六〜六十三を収録
●神沢貞幹『翁草(上下)原本現代訳55・56』(浮橋康彦訳、昭和55年、教育社新書)
※「無人島漂流船の事」は下巻P.160以下
このうち国立国会図書館デジタルコレクションで公開されている画像を転載させてもらう。

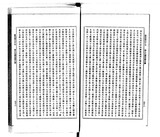



また、「藤九郎の島」は青空文庫で読むことができる。
http://www.aozora.gr.jp/cards/001224/card46102.html
一読して気づいた「藤九郎の島」との違いを箇条書きにしておく。
1、小説のタイトルにもなっている「藤九郎」とはアホウドリのことだが、「無人島漂流船の事」には、その名称は出てこない。
>何鳥か名は存ぜず、掛目三貫目も有之大鳥、島中に居申候、出生一両年の間は、其色黒く下腹計り白く、三年も過候へば全体白くなり、誠に其群居候事、碁盤に石を並べ候如くに候。此の鳥を取り食事に仕候、夏の頃五六七月には、何方へ参候や一羽も居不申候故、其間は魚鮑類を取給べ申候
とある。鳥について述べたのはここだけだ。ここのところは「藤九郎の島」ではこんな風に膨らませている。
>島裏に行ってみると、国方で、藤九郎(阿呆鳥)といっている、掛目三貫匁もあるような大きな海鳥が、何百、何千となく岩磐の上に群居して騒がしく鳴きたてている。白いのもいれば、黒いのもいる。そうしてひとところに群がっているところは、大きな碁盤に黒白の碁石を置きならべたようであった。人間の味をしらず、そばまで行っても人臭いような顔もしないので、いくらでも手掴みでとれた。その肉はひがらくさい臭いがあったが、それさえ厭わなければ、一羽の鳥で、十二人がほどほどに飽くことができた。
2、小説では、佐太夫たち「遠州組」が島に上陸してから、「土佐組」「大阪組」「日向組」と次々に島に流れてくるが、「無人島…」では、遠江の国・新居の一行が無人島に上陸し、生き残りが三人になった後、摂津の国・大坂の人たちが流れてきて、彼らの船を修復して本土に帰ることになっている。土佐組、日向組を登場させたのは久生の演出と思われる。
3、「無人島…」では、登場人物は「太神宮(伊勢神宮)」を信仰しているが、「藤九郎…」の遠州組は禅宗を信仰している。
>ふしぎや、同国のものばかりが一船に乗り合せ、残らず禅宗で宗旨までおなじだ。されば、みなが力を合せ、その気になって一心にやったら、この岩山が畑にならぬものでもあるまいと思うのだ
4、「藤九郎…」では、江戸の土を踏んだところでスパッと物語を終えているが、「無人島…」では、その後の手続きを細かく記して、「記録」という印象を強くしている。
丹念に読み比べたわけではないが、一読して気づいたのはこんなところだ。
全体に、久生の演出や台詞回しが、物語の情感を巧みに盛り上げている。例えば、遠州組・土佐組・大阪組・日向組の生き残りが、それぞれの技術を持ち寄って江戸に帰る船を作り上げることになっているが、こういう演出はとても感動的である。
それは、神沢貞幹『翁草』という随筆集の中の一つの記事であった。『翁草』は全二百巻で、前編百巻が明和九年、後編百巻が寛政三年に完成している。
元となったのは、巻之三十七に収められている「無人島漂流船の事」という文章。
手元に二つの原文がある。さらに現代語訳も見つけた。
●神沢貞幹『翁草:校訂4』(明治38-39年、五車楼書店)
※国立国会図書館デジタルコレクションで公開
●『日本随筆大成〈第三期〉20』(昭和53年、吉川弘文館)
※『翁草』巻之三十六〜六十三を収録
●神沢貞幹『翁草(上下)原本現代訳55・56』(浮橋康彦訳、昭和55年、教育社新書)
※「無人島漂流船の事」は下巻P.160以下
このうち国立国会図書館デジタルコレクションで公開されている画像を転載させてもらう。

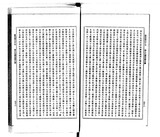



また、「藤九郎の島」は青空文庫で読むことができる。
http://www.aozora.gr.jp/cards/001224/card46102.html
一読して気づいた「藤九郎の島」との違いを箇条書きにしておく。
1、小説のタイトルにもなっている「藤九郎」とはアホウドリのことだが、「無人島漂流船の事」には、その名称は出てこない。
>何鳥か名は存ぜず、掛目三貫目も有之大鳥、島中に居申候、出生一両年の間は、其色黒く下腹計り白く、三年も過候へば全体白くなり、誠に其群居候事、碁盤に石を並べ候如くに候。此の鳥を取り食事に仕候、夏の頃五六七月には、何方へ参候や一羽も居不申候故、其間は魚鮑類を取給べ申候
とある。鳥について述べたのはここだけだ。ここのところは「藤九郎の島」ではこんな風に膨らませている。
>島裏に行ってみると、国方で、藤九郎(阿呆鳥)といっている、掛目三貫匁もあるような大きな海鳥が、何百、何千となく岩磐の上に群居して騒がしく鳴きたてている。白いのもいれば、黒いのもいる。そうしてひとところに群がっているところは、大きな碁盤に黒白の碁石を置きならべたようであった。人間の味をしらず、そばまで行っても人臭いような顔もしないので、いくらでも手掴みでとれた。その肉はひがらくさい臭いがあったが、それさえ厭わなければ、一羽の鳥で、十二人がほどほどに飽くことができた。
2、小説では、佐太夫たち「遠州組」が島に上陸してから、「土佐組」「大阪組」「日向組」と次々に島に流れてくるが、「無人島…」では、遠江の国・新居の一行が無人島に上陸し、生き残りが三人になった後、摂津の国・大坂の人たちが流れてきて、彼らの船を修復して本土に帰ることになっている。土佐組、日向組を登場させたのは久生の演出と思われる。
3、「無人島…」では、登場人物は「太神宮(伊勢神宮)」を信仰しているが、「藤九郎…」の遠州組は禅宗を信仰している。
>ふしぎや、同国のものばかりが一船に乗り合せ、残らず禅宗で宗旨までおなじだ。されば、みなが力を合せ、その気になって一心にやったら、この岩山が畑にならぬものでもあるまいと思うのだ
4、「藤九郎…」では、江戸の土を踏んだところでスパッと物語を終えているが、「無人島…」では、その後の手続きを細かく記して、「記録」という印象を強くしている。
丹念に読み比べたわけではないが、一読して気づいたのはこんなところだ。
全体に、久生の演出や台詞回しが、物語の情感を巧みに盛り上げている。例えば、遠州組・土佐組・大阪組・日向組の生き残りが、それぞれの技術を持ち寄って江戸に帰る船を作り上げることになっているが、こういう演出はとても感動的である。

コメント
コメント一覧 (5)
今日で2017年も終わりですね。今年はハートストリングスに2回もお越しいただきまして感謝申し上げます!
「さるむこ」の挿絵を描かれたのは、中畑ゆかりさんとおっしゃり今井先生の務めていた高校の卒業生だそうです。今井保之さんと組んで何冊も手書きの童話集を創っていらっしゃいます。他の方が挿絵をしていらっしゃる作品もあるのですが、確かに中畑さんの絵が一番しっくりくるようです。「さるむこ」は登場人物のキャラクターがそれぞれとても面白いのでやってみたらどうかとすすめてくださった方があり、この作品を選んだのですが、もう少し鮮やかに、でもさりげなくキャラが作れたらよかったなぁと反省しています。年があけたら第71回の準備を始めねばならず、作品も決めなければならないのですが、困ったことにまだ何も思い浮かびません。3/10のゲストは俳優座の遠藤剛さんです。周五郎さんの作品から選ばれるようです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。御礼をこめて・・。
https://mainichi-jp.cdn.ampproject.org/c/s/mainichi.jp/articles/20151224/k00/00e/040/173000c.amp?usqp=mq331AQGCAEYACAB
山崎勢津子
あけましておめでとうございます。
中畑ゆかりさんについての情報ありがとうございます。温かくて素敵な絵を描かれる方ですね。
ハートストリングスの会は、年に数回とはいえ、作品選びからですから大変ですね。また新しい世界と出会えるのを楽しみにしています。
山本周五郎は、全作品を読んでみたい作家の一人です。まだあまり読んではいませんが。周五郎の文体は、粘着質というか、一文一文じっくりと書いているようなところがあり、スピード感をもって読書することが難しいように思われますが、その分朗読には向くかも知れませんね。
資料も有難うございました。
作品の一つ一つに教えられること多く、また真摯に朗読に向かおうと思います。
是非またご意見をいただければと思っています。
コメントありがとうございます。
ご迷惑でしょうが、ここんところ内藤さん(と平野啓子さん)の「追っかけ」をさせていただいております。年明けにも八重洲ブックセンターで『北越雪譜』を伺いましたが、これも素晴らしい朗読でした。
「藤九郎」を持ちネタにしてくださるのはファンとしてとても嬉しいことです。ここには内藤さんでしか表現できない世界があると思います。
明日の公演は存じていますが、仕事の都合で伺うことができません。とても残念です。でもきっと訪れたお客さんは満足されるでしょう。