'03-04シーズン スペイン・サッカーの戦術的趨勢
デル・ボスケ(元レアル・マドリー監督)に聞く
デル・ボスケ
「マドリーは98年以降、チャンピオンズリーグを3度制した。準決勝にも2度駒を進めている。そして結果だけでなく、プレー内容でも多くの人から賞賛されたのだ。攻撃的スタイルを誇示することに成功し、欧州全体に良い影響を与えたと確信している」
98年CL決勝の相手はユベントス。ユーべは3年連続、イタリア勢として7年連続の決勝進出だった。当時イタリアは欧州の主役の座として君臨しており、セリエAの各チームは戦術的特徴として、ユベントスを筆頭に3分の2が3−4−1−2を採用していた。「マドリーは98年以降、チャンピオンズリーグを3度制した。準決勝にも2度駒を進めている。そして結果だけでなく、プレー内容でも多くの人から賞賛されたのだ。攻撃的スタイルを誇示することに成功し、欧州全体に良い影響を与えたと確信している」
しかしマドリーはイタリアの雄ユベントスを撃破。これを契機にイタリア勢は、以降4年連続で決勝進出を逃し、UEFAリーグランキングでもスペインに首位の座を奪われた。レアル・マドリー、バルセロナ、さらにはバレンシア、デポルティボ・ラコルーニャといった中堅チームまでが、チャンピオンズリーグで活躍した。同時に目立ち始めたのが4−2−3−1の台頭であった。
98年W杯のオランダ代表で4−2−3−1を採用し、チームをベスト4に導いたフース・ヒディンクは、W杯後マドリーの監督に就任。しかし成績不振により、シーズン終盤に辞任。デルボスケはその数カ月後に後釜についた。
4バックを基本にしながら3バックを用いるなど、当初の布陣は流動的だったが、ある時期から4−2−3−1に固定された。
「フィーゴ獲得がその大きな理由だ。攻撃を重視するためでもあった。魅惑的で攻撃的なサッカーを、選手の個性と照合した上で展開する。結果と内容を同時に追求する。結果にこだわって守り勝つサッカーは避ける。この布陣はマドリーの信念に合致していたのだ」
マドリーの4−2−3−1はやや変則的である。「そう、ロベルト・カルロスの存在が大きいからだ。彼は普通のサイドバックではない。カバーエリアが広いから、より高い位置で構えることが出来る。だからジダンが自由に動ける。真ん中からも、その攻撃力を生かすことが出来る。ジダンの獲得には戦略的な整合性があったんだよ。
ロナウドの獲得もしかり。彼には速さがある。モリエンテスに比べ、空中戦では劣るが、そのかわりに深い攻撃ができ、ゲームを支配していなくても、カウンターが利くようになった。攻撃は年々バリエーションが増している。加えて各々には、特別な個人技がある。そういう意味では、マドリーは他とは比較できない特別なチームだと言える。かつてはサッキのミランとか、アヤックスが一時代を築いたが、私も同様に、時代を築くつもりでチーム作りに励んだのだ」
マドリーの躍進に引っ張られ、スペインの他のチームの台頭が目立ってきた。ロナウドの獲得もしかり。彼には速さがある。モリエンテスに比べ、空中戦では劣るが、そのかわりに深い攻撃ができ、ゲームを支配していなくても、カウンターが利くようになった。攻撃は年々バリエーションが増している。加えて各々には、特別な個人技がある。そういう意味では、マドリーは他とは比較できない特別なチームだと言える。かつてはサッキのミランとか、アヤックスが一時代を築いたが、私も同様に、時代を築くつもりでチーム作りに励んだのだ」
「サッカーがとても戦略的になった。ベニテス監督率いるバレンシア、イルレタ監督率いるデポル、アトレティコやマラガでさえイタリア勢より数段戦略的だ。もはやイタリアを羨ましがる必要は全くない」
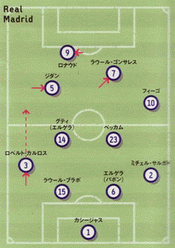 レアル・マドリーの特徴
レアル・マドリーの特徴ラウールは通常"3"の真ん中に入るが、よりFW的。4−4−2に近い4−2−3−1と言える。ジダンは内に入ってゲームメイク、その外側をロベルト・カルロスが激しい上下動で埋める。問題は、前線の選手の守備意識の低さと中盤のフィルターの弱さだろう。
ハビエル・イルレタ(当時デポルティボ・ラコルーニャ監督)に聞く
 ハビエル・イルレタ
ハビエル・イルレタ「布陣は今季も4−2−3−1。しかし昨季とは、若干異なっている。4−2−3−1の"3"の左、つまりルケを理論上のポジションより高く、ストライカーとほぽ同じ高さで使っている。4−2−3−1を左肩上がりにさせた形で、彼の速さをより生かそうとの狙いだ。ショートパスの巧いバレロン("3"の真ん中)もルケの側に若干寄せている。彼の鼻先により質の高いボールを送り込もうという狙いだ。
しかしこの布陣には問題がある。ルケの位置が高いので、相手の右サイドバックはフリーになりがちだ。先のガりシア・ダービー(セルタ戦)がそう。セルタの右サイドバック、アンヘルは常にフリーの状態にあった。でも、それを承知でルケを高い位置に留めた。通常の4−2−3−1に戻し、パスの得意なフランをそこに起用する手もあったが、ルケの速さに懸けた。もちろんカプデビラ(左サイドバック)には、あまり上がるなという指示は出していた。フランを起用した時には、上がれと指示するがね。結局その決断が功を奏し、大勝を飾ることに成功した」
「そりゃ攻めろと指示した、もちろんだ。ゴールを奪える自信があったからね。57分に途中交替でルケを投入。そして2分後にその彼がゴールを決めた。あのアウェーゴールでPSVの士気はガクッと落ちたんだ。試合は2−2からロスタイムに1点とられて敗れたが、大勢に影響はなかった。
後半、相手に疲れの色が見えた時、ルケが見せたスピード突破は、やはり相手に相当なダメージを与えたと思ってる。選手を本来のポジションで起用すれば、自信も芽生えて一番良い部分を引き出すことが出来る。それが相手にダメージを与えることになるのさ。
イタリアのルイジ・リーバって選手知ってるかい。彼なんかはまさにルケだった。私が選手時代にチャンピオンズカップの決勝に進んだ時(74年の決勝、バイエルンに延長再試合の末、敗れる)には、ウファルテという選手がいた。彼の場合は右だった。つまり我々はいま、当時のアトレティコがやっていたことの左バージョンにトライしていることになる」
イルレタ監督と言えば、4−2−3−1と相場が決まっているが、なぜ4−2−3−1にこだわるのか。後半、相手に疲れの色が見えた時、ルケが見せたスピード突破は、やはり相手に相当なダメージを与えたと思ってる。選手を本来のポジションで起用すれば、自信も芽生えて一番良い部分を引き出すことが出来る。それが相手にダメージを与えることになるのさ。
イタリアのルイジ・リーバって選手知ってるかい。彼なんかはまさにルケだった。私が選手時代にチャンピオンズカップの決勝に進んだ時(74年の決勝、バイエルンに延長再試合の末、敗れる)には、ウファルテという選手がいた。彼の場合は右だった。つまり我々はいま、当時のアトレティコがやっていたことの左バージョンにトライしていることになる」
「サッカーで一番大切なのは中盤。オフェンシブな3人と、それを助け、相手のカウンター攻撃にも対応するメディオセントロ(センターハーフ)の2人の計5人で、ボールをポゼッションする。"3"のうち2人はサイドにいる。幅があるのでより支配率は高まる。真ん中からの攻撃というのは難しい。サイドの選手の視野は180度あればオッケーだが、真ん中の選手には360度が求められる。物事は横からの方が見えやすいんだよ。同時にそれが相手の守備をやりにくくさせる。攻撃側に横を突かれ、縦に出られると、カバーすべき視野がとたんに広がる。同時に、中央のマークにも注意を払わねばならないからね」
ラファエル・ベニテス(当時ヴァレンシア監督)に聞く
99-00シーズン、00-01シーズンと、バレンシアは2年連続欧州チャンピオンズ・リーグ決勝に進出。02-03シーズンにはクーペル率いるインテルと準々決勝で対戦した。「もう一度戦えと言われても、私は同じ作戦で臨むつもりです。あの時、放ったシュートは計37本。相手GKの好守を称えるべき試合でした。こちらの攻撃が、最後の瞬間、わずかに精度を乱したとも言えますが、グローバルな戦略に問題があったわけではありません。ホーム、アウェーともに内容で、明らかにインテルを上回った。
スペインでは、勝利と同時に内容が問われます。ファンは結果だけでなく、良いサッカーにも拘っています」
ベニテスも4−2−3−1を基本に置く。スペインでは、勝利と同時に内容が問われます。ファンは結果だけでなく、良いサッカーにも拘っています」
「この布陣は、両サイドの高い位置に選手がいるので、中盤が中央に固まる布陣より、サッカーが美しくなる。なおかつ効率的です。ただ効果的なオフェンスには、アイマールやウーゴ・モラーレス、あるいはバレロンのような特徴的な選手が不可欠です。だから、アイマールが欠場した1月7日のオサスーナ戦(コパ・デル・レイのホーム戦)では、4−4−2で戦いました。
4−2−3−1では2ライン間の動きが問われます。FWが2人の場合は、センターバックやサイドバックの背後に侵入しやすい状況が生まれますが、1人になるとその機会が減る。逆に"3"の真ん中の選手は、相手の中盤選手とセンターバックの間に侵入しやすくなります。アイマールの細やかなステップは、そういう意味で非常に効果的です。一方、センターバックの背後を突くプレーは"3"の両サイドの選手が担います。サイドをスピーディーに崩すことが出来れば、得点チャンスは増大します。両ウイングの位置は、メディオセントロの2人が守備的であれば高く保てますし、攻撃的であれば若干低くなる。これも選手の特徴次第です」
影響を受けたチームや監督は?4−2−3−1では2ライン間の動きが問われます。FWが2人の場合は、センターバックやサイドバックの背後に侵入しやすい状況が生まれますが、1人になるとその機会が減る。逆に"3"の真ん中の選手は、相手の中盤選手とセンターバックの間に侵入しやすくなります。アイマールの細やかなステップは、そういう意味で非常に効果的です。一方、センターバックの背後を突くプレーは"3"の両サイドの選手が担います。サイドをスピーディーに崩すことが出来れば、得点チャンスは増大します。両ウイングの位置は、メディオセントロの2人が守備的であれば高く保てますし、攻撃的であれば若干低くなる。これも選手の特徴次第です」
「我々は、時代と共に外国の様々な監督から戦略を学んできました。私の場合はまずクライフになります。サイド攻撃を重視したその3−4−3の哲学に大きな影響を受けました。一方で、サッキのプレッシング・サッカーにはずっと注目していた。それにマドリーのキンタ・デ・ブイトレ(禿げ鷹の世代=80年代)の要素、つまりチームを指揮したべーナッカーの効率性と審美を見分ける目です。それらを、抱える選手の個性と照合しながら、融合していこうと考えています。
もう一度言いますが、我々はサッカーに実(結果)と美を同時に求めています。"美"はあくまで主観的なモノなので、私の考える実について言わせてもらうと、ハイスピードに乗った技術的に正しいプレーとなります」
実と美の両立、これがスペインサッカーのアイデンティティと言っていいだろう。両者をいかにして両立させるか。スペインサッカーの醍醐味とは、この難解なテーマに取り組む崇高な姿勢にある。もう一度言いますが、我々はサッカーに実(結果)と美を同時に求めています。"美"はあくまで主観的なモノなので、私の考える実について言わせてもらうと、ハイスピードに乗った技術的に正しいプレーとなります」
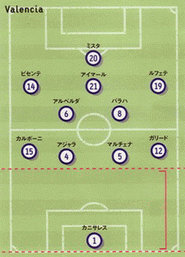 ヴァレンシアの特徴
ヴァレンシアの特徴教科書的な4−2−3−1。図のように高い位置からオフェンシブなプレッシャーをかけることもあれば、自陣に侵入を許せば両ウイングを下げて4−4−1−1に移行することもある。4−2−3−1の柔軟性をうまく生かしている。攻撃においてもサイドアタックを軸に一定のスキームを用意している。
参考文献:Number Plus 2004 CL特集号
トラックバックURL
この記事へのコメント
1. Posted by CSKA352 | December 21, 2006 00:35
98-04ぐらいまでは、リーガやCLをよく見ていたので印象深いですね。
R・マドリーのリズミカルなパス回しが好きでした。
当時のバルサやマンUのようなオランダ流トライアングルを意識したような機械的(デジタル的?)で等速の力強いパス回しではなく、
ポジションや個性の相互理解に基づく軟らかく変化に富んだパス回しと数的優位になってパスコースを増やしてからの崩しがたまりませんでした。
この時期のジュビロ磐田(私の中での理想の日本サッカー)、当時のマドリーをボール支配で圧倒したロコモチフ・モスクワもこのアナログ的なパスワークをするチームでした。
ロナウド・ベッカムがはいって伝統のショートパスによる遅攻が必要なくなって、肝心のボール奪取ができなくなってR・マドリーの魅力は失われて行きました。
R・マドリーのリズミカルなパス回しが好きでした。
当時のバルサやマンUのようなオランダ流トライアングルを意識したような機械的(デジタル的?)で等速の力強いパス回しではなく、
ポジションや個性の相互理解に基づく軟らかく変化に富んだパス回しと数的優位になってパスコースを増やしてからの崩しがたまりませんでした。
この時期のジュビロ磐田(私の中での理想の日本サッカー)、当時のマドリーをボール支配で圧倒したロコモチフ・モスクワもこのアナログ的なパスワークをするチームでした。
ロナウド・ベッカムがはいって伝統のショートパスによる遅攻が必要なくなって、肝心のボール奪取ができなくなってR・マドリーの魅力は失われて行きました。
2. Posted by cska352 | November 02, 2013 16:35
| November 02, 2013 16:35
ギャラクティコ・マドリーは楽しかったです。
ザックジャパンにも真似て欲しいです。
岡崎はFWでいいので右に遠藤や清武のようなクロスの名手を入れる。
左は香川がトップ下の位置に入って長友が攻め上がる。
守備の弱さも似てますが、長友が上がっているあいだはみんなでプレスをかけたいところ。
スピードや高さに頼らないサッカーなら日本人にもできると思います。
名将たちもみんな真似をしているんですね。
ゾーンDFになって相手のことは考えず自分たちのやりたい形だけを追求できるようになりましたね。
チームを結果だけで評価しなければいろんなスタイルから学べます。
ザックジャパンにも真似て欲しいです。
岡崎はFWでいいので右に遠藤や清武のようなクロスの名手を入れる。
左は香川がトップ下の位置に入って長友が攻め上がる。
守備の弱さも似てますが、長友が上がっているあいだはみんなでプレスをかけたいところ。
スピードや高さに頼らないサッカーなら日本人にもできると思います。
名将たちもみんな真似をしているんですね。
ゾーンDFになって相手のことは考えず自分たちのやりたい形だけを追求できるようになりましたね。
チームを結果だけで評価しなければいろんなスタイルから学べます。


