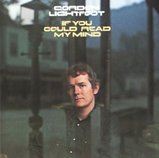ふだんはCDやレコードの紹介なのですが、今日は本の紹介です。でも、あのベストセラー作家、村上春樹氏初の音楽エッセイ集なのですから、この「音楽日記」で紹介するのは問題ないでしょう。「月が消え、恋人に去られ、犬に笑われても、なにがあろうと音楽だけはなくすわけにはいかない。」とオビに書かれています。このブログを見てくれている人なら、このフレーズだけでもフムフムと納得してくれるのではないでしょうか。
ふだんはCDやレコードの紹介なのですが、今日は本の紹介です。でも、あのベストセラー作家、村上春樹氏初の音楽エッセイ集なのですから、この「音楽日記」で紹介するのは問題ないでしょう。「月が消え、恋人に去られ、犬に笑われても、なにがあろうと音楽だけはなくすわけにはいかない。」とオビに書かれています。このブログを見てくれている人なら、このフレーズだけでもフムフムと納得してくれるのではないでしょうか。もともとハルキさんは、音楽ファンとして有名で、作品の中にもさまざまなジャンルのアーティストや曲が出てきます。本人があとがきでも述べているように、彼は20代にジャズ喫茶のマスターだったわけで、ジャズの造詣が深く、和田誠氏のイラスト入りで「ポートレート・イン・ジャズ」という本も出していますし、ジャズ・ベーシストでエッセイストのビル・クロウ氏の著作の翻訳も2冊手がけています。しかし、彼の博識はジャズだけでなくクラシックやロックにもおよびます。90年代、40代の彼はオープン2シーターのハンドルをにぎりながら、パールジャムやR.E.M.をがんがんならしていたようです(確認はしていませんが)。そんな幅の広さを反映してか、この本におさめられている10編はクラシック3編、ジャズ3編、ロック2編、J-POP1編、アメリカン・フォーク1編という割合です。
ロックはブライアン・ウィルソンとブルース・スプリングスティーン。わたしにとっても比較的思い入れのあるミュージシャンだし、ハルキさんがとりあげたアルバムはすべて聴いていたので、すんなり読めました。スプリングスティーンについては、ハルキさんが多くの翻訳をてがけるレイモンド・カーヴァーと同じくワーキングクラスの出身で、ワーキングクラスの若者を生き生きと描いているところにつよく惹かれたようです。多くの人に曲解されている『ボーン・イン・ザ・USA』の背景などについても丁寧な解説。また、類い希なる才能をもちながら時代の波とドラッグに飲み込まれながらも生き延びたブライアンに対しても、愛情あふれる文章です。
ジャズのスタン・ゲッツは聴いたことがあるものの、シダー・ウォルトンなんて名前を聞いたこともありませんでしたし、クラシックのプーランク、ルービンシュタインなんはは、そんな人もいたかな、程度の知識しか持ち合わせていませんでしたが、「読ませる」文章でスラスラと心の中に入ってきます。けだし名文と思えるのは、シューベルトについて書かれた章の末尾に書かれた次ぎのような文章です。「僕らは結局のところ、血肉ある個人的記憶を燃料として、世界を生きている。もし記憶のぬくもりというものがなかったとしたら、太陽系第三惑星上における我々の人生はおそらく、耐え難いまでに寒々しいものになっていたはずだ。だからこそおそらく僕らは恋をするのだし、ときとして、まるで恋をするかのように音楽を聴くのだ。」これほど、音楽の本質をついた文章をほかに見たことがありません。
ハルキさんはあとがきで、「この場合の『スイング』とは、どんな音楽にも通じるグルーヴ、あるいはうねりのうなもの考えていただいていい。それはクラシック音楽にもあるし、ジャズにもあるし、ロック音楽にもあるし、ブルーズにもある。優れた音楽を、優れた本物の音楽として成り立たせているそのような「何か」=something elseのことである。僕としてはその「何か」を、僕なりの言葉を使って、能力の許す限り追いつめてみたかったのだ。」と、書いています。その試みはかなりの確度で成功しているように思えます。筆者がシダー・ウォルトンに見いだし、ウィントン・マルサリスに欠けていると感じるものは、まさにその「何か」だし、スガシカオに見いだした独特の文体やメロディもその「何か」なのでしょう。音楽を奏る側にも常に気になる「何か」を、世界的な文章のスペシャリストであり、きわめて幅広い嗜好と知識を持つ村上春樹氏が、わかりやすい言葉でつきつめたエッセイです。音楽ファンなら一度は読んでみても損はしないと思いますよ。
しかし、この人が音楽を語るボキャブラリーは豊富ですね。本当に聴いてみたくなる臨場感にあふれています。見習いたいものですね(無理だけど)。「デモーニッシュな」とか「じりじりと」というような形容詞や副詞が増えたら、彼の影響かも知れません。やれやれ。そうそう、我らがライ・クーダーは、この本には出てきませんが、ハルキさんはたしか「やがて哀しき外国語」でとりあげていました。「こんな日にはライ・クーダーか、ニッティ・グリッティ・ダート・バンド」でも聴きながら、洗濯でもしたくなる」みたいな文章でした。70年代前半のライのことなんでしょうねぇ。ハルキさんについては、まだまだ書きたいことがあるけど、長くなるのでまたの機会にでも....。