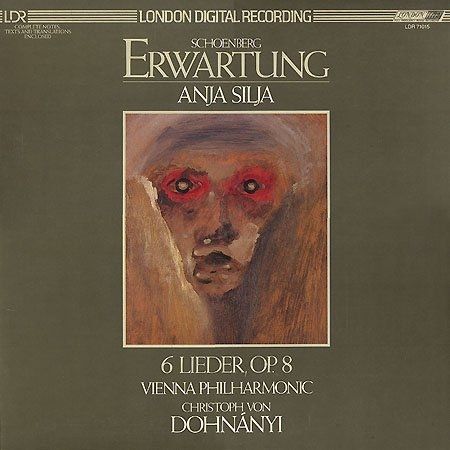シェーンベルクの「グレの歌」(小澤征爾/BSO)
- カテゴリ:
- シェーンベルク
ジェシー・ノーマンの訃報を聞いたのと、このところ新ウィーン楽派の音楽を立て続けに聞いている流れから、シェーンベルクの「グレの歌」を聞いてみました。
フィリップス原盤の小澤征爾/BSOによる1979年のライブ録音で、まだこの曲の録音が多くなかった頃の貴重なアルバムのひとつです。
主な出演者は次のとおりです。
ワルデマール(王):ジェームス・マックラッケン
トーヴェ(少女):ジェシー・ノーマン
山鳩:タティアナ・トロヤノス
農夫:ダヴィッド・アーノルド
道化:キム・スコウン
語り:ヴェルナー・クレンペラー
この曲は、
・CD(LP)2枚にわたる長大なものであること、
・100名を軽く超える大規模なオーケストラと合唱、それに独唱者が必要なためコスト面から演奏困難であること、
・十二音音楽で活躍したシェーンベルクにしては聞きやすい音楽であること、
から、比較的名前は知られているものの、コンサートのみならず録音もそれほど多くはありません。
2011年に東京poが創立100周年を記念して「グレの歌」を取り上げ、やっと生で聞くことができると喜び勇んでチケットまで入手したのに、東日本大震災で中止となり、チケット料金は返金されました。
それから2年後、やっと再演が決まったときには、もう行くことが叶いませんでした。
そして、今年2019年は、なぜか「グレの歌」イヤーになっているようです。
3月に読響(カンブルラン)、4月に都響(大野和士)、10月は東響(ジョナサン・ノット)と、三回もコンサートで演奏されるのです。
実は、この記事を書くにあたって「オペラ対訳プロジェクト」で歌詞対訳を眺めていてこのことを知りました。
しかし、このところ家の修繕やら何やらで、とてもコンサートに行ける環境ではありません…
今回は「オペラ対訳プロジェクト」の翻訳もありますが、もうひとつ、いつもお世話になっている「梅丘歌曲会館」の対訳のお世話になりました。
こちらを選んだのは、ひとつひとつの曲に、翻訳をされた藤井宏之さんが解説を付けておられて、これも読みながら聞いた方が理解しやすいからです。
この曲は、一言でいえば演奏会形式のオペラみたいなものと理解した方がわかりやすいと思います。
粗筋は次のようなものです。
(第1部)
中世のデンマーク王ワルデマールは、少女トーヴェに恋をして、二人は道ならぬ恋に落ちてしまいます。
激しく燃え上がった恋は王妃の知るところとなり、トーヴェは王妃に毒殺されてしまいます。
二人の愛の悲恋の中で死んだトーヴェを悼み、ワルデマールの嘆きを山鳩は歌い上げます。
(第2部)
トーヴェを失ったワルデマールは、悲痛のあまり、あろうことか神に向かって怒りと呪いの言葉を口走ります。
(第3部)
天罰で命を失ったワルデマールは、トーヴェが住んでいたグレの地を亡霊となって部下とともにさまよい、農夫を怖がらせたりします。
最後の審判の日になっても、ワルデマールはトーヴェと切り離すことはできないと、二人の愛を高らかに歌い上げますが、部下たちは墓場の中に戻っていきます。
そのときに吹きわたった一陣の「夏の風」が、森も、虫も、鳥も、再び命の輝きを現して終わります。
ジェシー・ノーマンが歌うトーヴェは、第1部にしか登場しませんけれども、やはり存在感のある声を聞かせてくれています。
この録音の当時、彼女は34歳くらい、ヨーロッパで名声を確立し、METに凱旋帰国した頃でしょうか。
小澤征爾がどんどんテンポを上げていって、オーケストラの方がアンサンブルを乱してもジェシー・ノーマンは余裕と自信をもって歌い切っている感じがします。
ただ、トーヴェにしては声がしっかりしすぎて可憐さに欠けるかなというのと、録音のせいもあるのでしょう、対訳を見ながら聞いていると、ドイツ語が若干聞き取りにくいところがあります。
この曲の中でも比較的有名な、第1部の終わりにある「山鳩の歌」はトロヤノスが歌っています。
性格的な表現が得意なトロヤノスですから、自在に声を操りながら悲しみと同時に、二人の楽しかった日々を朗々と歌い上げているところは、小澤征爾の劇的な伴奏が曲想に似合っているかもしれません。
さて、小澤征爾が指揮するこの録音は、「グレの歌」のオペラ的な側面を強調して、かなりダイナミックに表情豊かな音楽を聞かせてくれています。
わたしが最初に聞いたブーレーズ盤のような、どちらかというと静的な仕上げの音楽とはまるで違いますし、厳しさに満ちたケーゲル盤とも異なります。
この劇的な演奏は、ひょっとするとライブという高揚感がもたらしたものがあったのかもしれません。
これを聞いた聴衆は、恐らくは興奮のるつぼに入って、記憶に残るコンサートであったでしょう。
しかし、録音で客観的な聞き方をしますと、若干のやり過ぎ感が伴うと感じるところもありそうです。
この辺が生の音楽と録音で聞く音楽との違いで、自分が聞いたコンサートのライブ録音をあとから聞くのが怖くなるゆえんでもあります。