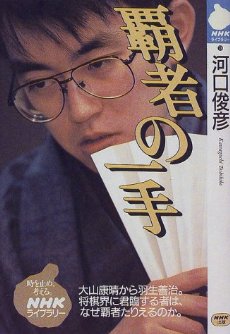おもしろい観戦記を書こうと思ったら、感想を疑ってかかるのが第一歩ということになる。
―――河口俊彦
『新対局日誌 第二集 名人のふるえ』(河出書房新社、2001年)より
―――――――――――――――――――――――――――――――――
何やら神妙そうに、二人が口を合わせて、「▽9六歩では▽8四銀の方が良かったね」などと感想を述べ合っている。
普通の観戦記者なら、「なるほど、なるほど」とメモを取るところだ。
しかし河口俊彦は、そんな言葉を信用していたら面白い観戦記など書けないと言うのである。
本当は、それより遙か以前の▲5八銀で将棋は終わっているのだ。
二人ともそんなことは重々承知の上。
承知の上で、対局者はああだこうだと言葉を継いでいる。
そこらへんの人間の機微を書け。
河口はそう言いたいのだろう。

―――河口俊彦
『新対局日誌 第二集 名人のふるえ』(河出書房新社、2001年)より
―――――――――――――――――――――――――――――――――
何やら神妙そうに、二人が口を合わせて、「▽9六歩では▽8四銀の方が良かったね」などと感想を述べ合っている。
普通の観戦記者なら、「なるほど、なるほど」とメモを取るところだ。
しかし河口俊彦は、そんな言葉を信用していたら面白い観戦記など書けないと言うのである。
本当は、それより遙か以前の▲5八銀で将棋は終わっているのだ。
二人ともそんなことは重々承知の上。
承知の上で、対局者はああだこうだと言葉を継いでいる。
そこらへんの人間の機微を書け。
河口はそう言いたいのだろう。