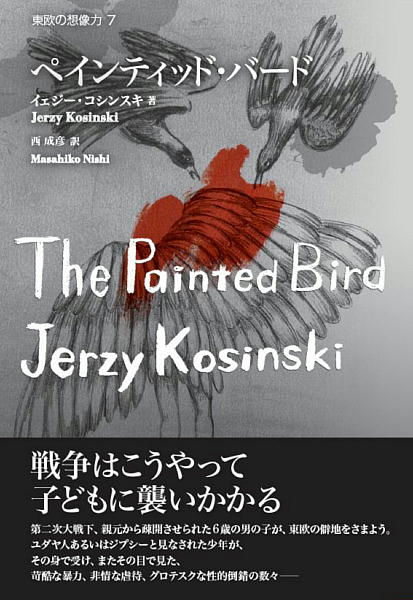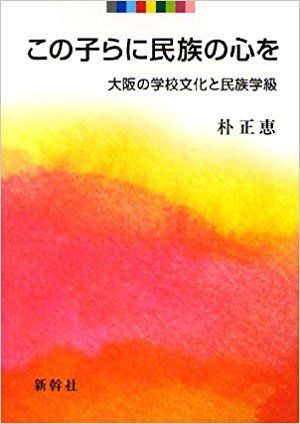 [IV-075]Saturday
[IV-075]Saturday中村一成(1969- )さんの『ルポ思想としての朝鮮籍』岩波書店、2017)は、「朝鮮籍」を持つ六人の日本在住者に対する取材を基にした文字通りの「ルポ」だが、《一九三〇年代、慶尚南道から渡日した祖父母、二人から生まれた私の母は、自らの来歴や在日する思いについて私にほとんど話さなかった》(p. 219)という中村さんの「出自」と、生育歴が、本全体に通奏低音のようにして流れているために、見かけ上も「透明」な「ルポ」ではありえず、それどころか読者にまで、一人の「ダブル」として「朝鮮籍保有者」たちの声に耳を傾けるよう促してくる、ふしぎな「ルポ」である。
その意味では、六人のなかでも、日本人の母を有し、最初は日本籍だったのを、自分の意志で「朝鮮籍」に切り替え、その後、大阪で「民族学級」の講師を務めながら、独自の足跡を刻んでこられた朴正恵(1942- )を扱う「第4部」が、とりわけ緊張感に富む内容だったように思う。
朴正恵さんには『この子らに民族の心を』(新幹社、2008)という著作があるが、そこでも曖昧にぼかされていたさま...ざまなことが、中村さんの手慣れた取材技術を通して、ごっそりと引き出されているのだが、なかでも「ダブル」として育った過去に対する次のようなくだりは、中村さんの「耳」を想像しながら聴くと、いっそう臨場感が増す。
《家庭訪問を繰り返せば親の悩みにも向き合う。多くは夫婦の属性の違いに起因してた。「民族学級で活き活きとして帰ってくるけど、(朝鮮人の)アボジとの会話は弾む一方で私は寂しい思いをしている」とこぼす日本人の母もいた》(p. 139)――こうした思いは、日本人の夫を持ち、子どもを自動的に日本の戸籍に入れて、自分らの「来歴や在日する思い」を話すことをすら封印してしまった中村さんの母親を想像させるに足る内容だったと、想像できる。
また、《一度は、「子どもが使い分けする」って日本人のお母ちゃんが抗議に来てね。「民族学級で朝鮮人やいうても地域では日本人になってる。都合よく使い分けをする子どもになってほしくて民族学級にやったんじゃない」って。あ、自分もそうやったなって思った》(同前)――たとえば、このような朴さんの語りに耳を澄ませる中村さんもまた、ご自身が「ダブル」でいらっしゃるかぎりにおいて、「自分もそうかもしれない」と感じられたに違いないのだ。そして、読んでいる私もまたそう感じる。
それこそ、《一九六二年秋、前年の軍事クーデターで事実上の独裁体制を確立した朴正煕の片腕、金鍾泌が〔中略〕「請求権」交渉で来日するとの報に、朝鮮大学校生たち》が《いきり立》ち、抗議デモに参加したら、《「全員、降りて外登証を提示しろ。持ってない者は連行する!」》と、どやしつけられて、《日本国籍だから外登証を持ってない》ことに気づいたのが、そもそも《朝鮮籍にしようとした理由》だったと語る朴正恵さんの《快活》(pp. 125-6)な笑いを、中村さんの「耳」は、どうとらえたのか?
中村さんの筆致は、元ジャーナリストらしく、自らの「来歴」に関して、じつに控えめなのだが、それでも、読者としては、そこを補わないではいられない。
そして、朴さんが職場にされていた大阪市西成区の長橋小学校の教室に向かった日の思いが次のように書かれている箇所を読み進めながら、私という読者は、ある種のカタルシスに浸ったのだった――《控室に向かいながら、自らを解き放つ子どもたちの歓声が飛び交う様を想像した。週二時間でも民族に触れる時間を持つ意味がいかに大きいかは、その機会を持てなかった者の一人として十分想像できる》(p. 142)。
「その機会を持てなかった者」である中村さんは、朝鮮系だった母親や祖父母が、息子、そして孫を純粋な日本人であるかのように育てようとした、その《決断を批判するつもりはまったくない》と『声を刻む』(インパクト出版会、2005)の「あとがき」(p. 229)に書いておられる。しかし、かりに父親が日本人であっても「民族学級」に子どもを通わせるという選択が、戦後の大阪でならありえたのだ。父親が朝鮮人で、母親が日本人だという朴正恵さんがたどられたような人生が、中村一成さんのような「ダブル」に対しても用意されえたと言えるのかどうか、そこはまさに家父長制という大きな問題が横たわっているので、難しい問いだとは思うのだが、少なくとも、朴正恵さんに対する聴き取りのなかで、中村さんは、ご自身の「ありえたかもしれない過去」をはげしく妄想されたと想像する。少なくともそう想像させてもらったことによって、私の読書体験は、じつに豊かなものになった。
「もしも自分が在日だったら」という想像を膨らませる上で、『ルポ思想としての朝鮮籍』という本は、六人の「朝鮮籍保有者」のお話のかけがえなさもさることながら、耳を立てて、その声を聴き取ろうとされた中村一成さんという一人の「日本国籍保有者」の「胸騒ぎ」が、これまた切々と迫ってくる、そんな一冊である。
 [IV-074]Wednesday
[IV-074]Wednesday