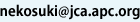本(書評)・映像・メディア評 :
2011年12月20日
本>『靖国の戦後史』田中伸尚
久々の書評シリーズ3。とりあえずこれで終わり。
一発目に書いたことですが、この書評、どうせ長くなるし、興味がないひとには徹底して興味がないネタになろうかとも思うし、このWeblogの客層的にはどうなのかなあとも思います。なので「自分向けじゃないな」と思ったひとはさくさく飛ばしてしまうことをお勧めします。場違いなものをまきちらかしてすまん(=^_^;=)。
「神道って、要するに何なの?」という疑問をめぐって読み散らかした本のうちの一冊。なんだかんだ言いつつおれもずいぶん神社の写真を撮ってきていますので、それなりに興味を惹かれる部分てのが出てきてたりしたのですよ。なので、知ろうと思ったというわけ。
本書は、神道の概要を広く知る上では全く役に立ちませんが、おれがそこはかとなく抱いていた神道への不信感・不快感の原因についてはある程度の手がかりを得ることができ、そういう意味でおれにとっては有益な本でした。なので、紹介しておこうと思いました。
しかしまあ、書いたことの大半が「本書の一片から考えたこと」であり、本書の内容とはあんまし関係がなかったりして、書評というのはオカシイかもしれません(=^_^;=)。


『靖国の戦後史 』田中伸尚
』田中伸尚
岩波新書788
ISBN4-00-430788-0 C0221
2002年6月20日初版初刷
そういうわけで資料として読み始めたんですが、わりと冒頭部であっけにとられるデータが出てきました。まあ、おれが知らなかっただけなんですけど。1945年の出来事に関する記述。以下、本書14ページ、「第一章 甦った靖国神社 1945〜1951年/2 遺族会の誕生と靖国信仰/神社本庁の設立」より。
えーと・・・神社って阿呆の巣窟ですか。
まあ率直な感想がこういうものだったんですが、この感想をおれが抱いた理由について説明しないと、たぶん展開がわけわかんなくなるだろうな。というわけで説明します。
神道の歴史の大胆なダイジェスト。
神道の源流がどこにあったのか、それがどのようなものであったのか、そのあたりについては現段階ではいまだ解明がなされていないようです。まあ飛鳥時代以前の話になりますから、普通にわかんないわな(=^_^;=)。
で、飛鳥時代の6世紀中ごろ(538年説と552年説がある)に日本に仏教が伝来(公伝)。それ以降、明治維新までの実に1300年余りの間、神道と仏教は区別があいまいなものとして扱われることになります。これを「神仏混淆」「神仏習合」などと呼びます。欧米流の宗教潔癖症から見ると想像を絶することであるらしいのだが、ま、各種の仏と各種の神とを対応させるなどして「同じものを別の切り口から見たもの」として扱おうとした、ということだわね。
その途上で、たとえば江戸時代における一般的様相のように「仏教の優越」があったり、江戸時代水戸藩領などにおける様相のように「神道の優越」があったり、そのあたりはまあいろいろ。ただいずれにせよ、飛鳥時代以降の日本には、「純粋な仏教」「純粋な神道」というのは存在しなかった。また、神道は飛鳥時代に仏教と混淆してしまったことから、教義など理論的支柱は仏教によりかかることとなり、神道としての教義が明確化されることがないままに、1300年という時を過ごすこととなった。
明治維新となり、明治政府は天皇のもとに国をまとめるという方針を考え、天皇を神道の神の一員と位置づけることにしました。その際に「その国家の支柱たる神道に教義がないというのは困る」ということになったらしい。そこで明治政府は、突然のように神道にも教義を作ることにした。
それが国家神道なわけですが、当然ながら江戸時代までの「教義のないあいまいな宗教としての神道」と「明確な教義を持つ宗教である国家神道」は、まるっきしの別物ということにならざるを得ません。ていうか、江戸時代までの神道は明らかに「自然宗教(源流がよくわからない自然発生的に生じたとされる宗教)」だったわけだけど、国家神道は誰か人間が教義を書いた宗教なわけでそれは「創唱宗教(特定の個人あるいはグループによって提唱されて形成された宗教。キリスト教や仏教が典型例)」に分類されるものであり、もうその2つは系統として違うだろうと。
なお、明治政府によるこの政策に関して、「神道という宗教が特別視されるとキリスト教が迫害されるのではないか」という懸念を抱いた諸外国が横槍を入れて神道の国教化を阻止、明治政府は「神社は宗教にあらず、習俗なり」という暴論を主張してこれを乗り切ります(1880年代あたり)。いやあ、神道ってば、性格を大胆に歪められただけでは済まず、かわいそうなことに宗教ですらないことにされちゃったんだぜ(=^_^;=)。
で、政府内には神社対応部局が置かれ(最初は1868年の神祇事務科、以降機構はさまざま変転)、政府と国家神道は一体化したものとして運用されることになります。神社は、それなりに優遇されるかわりに、国家神道の名のもとに、政府によって組織化され、格付けされ、統廃合を含めていろいろと介入されることになった。
なお、明治時代以降に、黒住教・金光教・天理教・大本教(正式には「大本」で「教」はつかない)など数多くの神道系の創唱宗教が誕生しており、それらは「教派神道」と呼ばれています。
さて、第二次世界大戦が敗戦に終わり、1945年12月15日に占領軍が「神道指令」と呼ばれる指令を出しました。これは、第二次世界大戦の根源のひとつとして国家神道があるという認識のもとに、政府と国家神道との連携を断ち切ることを目的としたもの。
それまでは国家神道を統べる機構が大日本帝国の政府内にあったわけですが、それはなくなる、と。その政府内にあった機構の代替として作られたのが神社本庁(という宗教法人。役所みたいな名称ですが役所ではありません。ま、役所っぽく見せたかったんだろうなあ)。
その神社本庁に、神社法人のうち実に98.8%もの神社が集まった。そして後日そのことを知ったおれの目は点になり、この書評が始まった、というわけ。
以上、大胆なダイジェスト終わり。
ここから、おれの神道観。
長い神仏習合の歴史があるから「神道ってなに?」「純粋な神道ってどういうもの?」という疑問への明確な答えというのは存在しないわけですけど、しかし明治時代以降の神道が国家神道を軸とすることによって改めて大きく歪められたということは事実であると言っていいとおれは思うんですよ。伝統を重んじるのであれば(そして普通、宗教というのは保守的なものであり、伝統を重んじるものであるはずだ)、神道は明治政府に対して怒りを見せるのが筋なんじゃないんだろうか。第二次世界大戦の敗戦を契機としてアホ政府から離脱しその影響下から脱することができるのなら、それは歓迎するのが当然ではないんだろうか、とおれは思うんですよ。
ところがそうはならず、法人格を持つ神社のうち実に98.8%が、神道を歪めた国家神道の系譜に連なる神社本庁に結集したっていうんでしょ。おまえら伝統を重んじる気持ちはないのか、神社って阿呆の巣窟ですか、とつながっていくわけです。
まあ、大日本帝国が政府内に神社担当部局を置いたのが1868年、神道指令によって政府内から神社担当部局が追い出されたのが1945年、その間78年ほど経っているわけで、その時間は1世代を越えていますから、「組織化され、教義を持ち、統制された姿の神社が当然のものである」という感覚が神道界の中に定着していたであろうことは想像がつきます。また、敗戦後のどたばたの時期ではありますからあえてそこで異議を唱えるのもめんどくさかったのであろうという事情もわからないではありません。
もうひとつ、明治時代に先行した江戸時代には、神社は一般論として仏教寺院の下に置かれ虐げられてきていたわけですし、明治時代以降は優遇されてこの世の春を謳歌したわけだから、明治以降の流れに感謝をするということは当然にあったことだろうし、明治時代以前のような状態に回帰するのは避けたいという気持ちもまた強かったことでしょう。
しかしそれにしても、やっぱ明治政府による神道政策は、神道の姿を歪めるものであったとも思う。それも、かなり深刻かつ決定的に歪めるものだった。
また、大日本帝国は国家経営に失敗して滅びていったわけですが、その失敗の途上に、国家神道ははっきりと足跡を残してしまっている。それって、神道にとっては「黒歴史」と呼ぶべきものではないんだろうか。
国家神道って、もしもおれが神道家であったならば、全力で否定したくなるようなしろものだったはずだ。そういう思いを禁じ得ないんですよね。でも、なんか神道の側には、そういう感覚がないか、あったとしても希薄であるように見える。それはいったいなぜなんだろう、というのがおれの疑問なんですよ。同時に、明治政府がやったことに怒らない神道に対して、おれがそこはかとない不信感・不快感を抱いていることにもつながっている。
また、国家神道って、明治維新の際に新たに作られた創唱宗教なわけで、ある意味「国家が背景についていたとはいえ、たかが教派神道のひとつにすぎない」とも言えると思うんです。国家神道なんて、敗戦の時点で歴史はたかだか78年、2011年時点で計算しても144年の歴史しか持たない新興宗教ではありませんか。飛鳥時代から明治維新までをざっと計算して1300年余り、飛鳥時代以前から存在し少なくとも1300年以上の歴史を持つ旧来の神道が、たかだか78年ないし114年の歴史しか持たない新興宗教の国家神道ごときに牛耳られている状況に甘んじていてどうしようというのだ、とも思うんです。
ここまで、おれの神道観。ま、半分くらい呆れ果てていて、残り半分くらいはしっかりしてくれよと思っている、という感じでしょうか。
とまあ、そんなふうに思っているおれにとって、この『靖国の戦後史』というのは、それなりに改めて衝撃的だったわけですよ。
なんていうの、こうも伝統を軽んじるひとたちがいるんだ、というのはやっぱある種の驚きにつながることです。さらには、伝統を軽んじる姿勢を臆面もなく恥も外聞もなく主張できるというメンタリティが、おれにはよくわからない。しかも、ご本人たちは「伝統を守っているつもり」であるらしいのだ。
このひとたち(=靖国神社国家護持運動とかやってるひとたち)は、本当に神道の信者であるのだろうか? いや、このひとたちは決して「神道」の信者などではなくて、「国家神道」というよく似た名前の別の宗教の信者であると理解すべきなんでしょうけれども。
なんか長々と書いたわりに本の感想の本体部分はわずか数行で終わってしまいましたけど、まあそういうわけで、おれ的には読む価値はある本だったと思います。
なお、本書は基本的に、左系の思想に基づいて書かれているもののように思います。おれは特に左翼系思想へのアレルギーはないんでそこんところは特に気にはなりませんでしたが、左翼思想には根強い戦前全否定は単純に過ぎると考えており、そういう観点からの神道批判と足並みをそろえるつもりはない、ということは明記しておこうと思います。
*
これで終わりにすると神道のワルクチを書いただけに終わってしまうことになりそうなもんで、つけたし。
幸いなことに、これまでの観察からして、現存する神社もまあいろいろで、あいかわらず国家神道の呪縛に囚われたままの神社も数多くあるにせよ、おそらくは国家神道なんてたいして気にもしないままに淡々と明治から昭和の時期を乗り切ってきたのであろう神社というのも少なからず存在しているように見受けられます。神社だって一枚岩ではない、というか。「淡々と国家神道の時代を乗り切ってきた神社」というのは、ある意味で民衆宗教・自然宗教のたくましさを感じさせるようなものでもあり、そういう「動じない姿勢」って宗教のような本来保守的であるはずのものにとっては、とても頼もしいと思ったりもする。
更には、国家神道が終わってすでに半世紀以上が経過しているということもあって、神社本庁のレベルはとにかくとして、氏子のレベルでは、国家神道の記憶は薄れつつあるように思う。まあ、単に記憶を薄れさせちゃっていいのかっていうと疑問はあるわけだが、結果としてそれが、神道が本来の姿(てのが前述の通りよくわからないわけだが)を取り戻す上で役に立つのであれば、「良いこと」だと思うことにしようと思います。
仏教の影響を受けなかった「神道」の姿を想像しにくいのと同じくらいに、国家神道の影響を受けなかった「神道」の姿も、想像しにくい。だけどまあ、それはいずれも、神道にとって「乗り越えていかなくちゃいけない歴史」なんだろうと思う。
いまだ残る国家神道の亡霊をなんとか払拭して、神道が生まれ変わる日が来ることを、おれは祈りたいなあ。まあ、それはおれが生きている間に実現するようななまやさしいものではなく、たぶんまたずいぶんと時間を必要とするのだろうという諦観とともに。
*
おまけ。可能ならば独立した書評を書きたいのだが、たぶんそんな余裕はないだろうと思うので、おまけとして言及し紹介しておきます。
いやあ。海老沢泰久。佐々木譲と並ぶおれの好きな作家だったんですが、最近新刊を見ないなあと思っていたら、死んでたんですね(=^_^;=)。2009年8月13日に十二指腸癌で死去。そら新作が出てこないわけです。
もともと注目したのは『F1地上の夢 』がきっかけ。その後、おれが全く興味を持たない世界であるプロ野球を舞台とした小説『監督
』がきっかけ。その後、おれが全く興味を持たない世界であるプロ野球を舞台とした小説『監督 』で「興味がない世界のことをこれだけ読ませてしまう作家って何なんだ」と驚かされ、同じくほとんど興味がない分野であった料理に関しても『美味礼讃
』で「興味がない世界のことをこれだけ読ませてしまう作家って何なんだ」と驚かされ、同じくほとんど興味がない分野であった料理に関しても『美味礼讃 』できっちり読まされてしまい、なにはともあれすごいなあと思っていたんでした。
』できっちり読まされてしまい、なにはともあれすごいなあと思っていたんでした。
その海老沢泰久が末期にいろいろ書いていたのが「歴史小説」という分野。『青い空』の他に、連作短編で『追っかけ屋 愛蔵 』や『無用庵隠居修行
』や『無用庵隠居修行 』などがあります(個人的には『追っかけ屋 愛蔵』の方が気にいっている。『無用庵隠居修業』は、なんかピンとこなかった)。まあ、著者が死んでしまったということもあってもう実現することはないだろうと思うのですが、『追っかけ屋 愛蔵』は連続ドラマで見たかったなあ、なんて思ったりするくらい。
』などがあります(個人的には『追っかけ屋 愛蔵』の方が気にいっている。『無用庵隠居修業』は、なんかピンとこなかった)。まあ、著者が死んでしまったということもあってもう実現することはないだろうと思うのですが、『追っかけ屋 愛蔵』は連続ドラマで見たかったなあ、なんて思ったりするくらい。
で、『青い空』。
この作品は、「類族」とされる者、つまり摘発されたキリシタンの末裔である主人公が、幕末と明治維新の時期を生き抜いていくという物語です。江戸幕府の仏教優遇策から明治政府の神道優遇策への切り替わりを、類族という、仏教からも神道からも一歩離れたポジションから眺めるという図式になっている。物語として面白かったというだけではなく、その視点の斬新さがなかなかのものでした。
この中に、明治時代に向けて神道の復権を夢見る若い神主が出てきます。この神主は、明治政府の重鎮にいいように利用され、そして物語の途中で何者かに殺されてしまうのですが、彼はおれが思うところの「明治政府に歪められる前の神道」の象徴のように感じられます。
ご興味があれば、幕末や明治維新、そして神道と国家神道というこのあたりの要素の関連本として、ぜひご一読いただければと思います。 続きを読む
一発目に書いたことですが、この書評、どうせ長くなるし、興味がないひとには徹底して興味がないネタになろうかとも思うし、このWeblogの客層的にはどうなのかなあとも思います。なので「自分向けじゃないな」と思ったひとはさくさく飛ばしてしまうことをお勧めします。場違いなものをまきちらかしてすまん(=^_^;=)。
「神道って、要するに何なの?」という疑問をめぐって読み散らかした本のうちの一冊。なんだかんだ言いつつおれもずいぶん神社の写真を撮ってきていますので、それなりに興味を惹かれる部分てのが出てきてたりしたのですよ。なので、知ろうと思ったというわけ。
本書は、神道の概要を広く知る上では全く役に立ちませんが、おれがそこはかとなく抱いていた神道への不信感・不快感の原因についてはある程度の手がかりを得ることができ、そういう意味でおれにとっては有益な本でした。なので、紹介しておこうと思いました。
しかしまあ、書いたことの大半が「本書の一片から考えたこと」であり、本書の内容とはあんまし関係がなかったりして、書評というのはオカシイかもしれません(=^_^;=)。

『靖国の戦後史
岩波新書788
ISBN4-00-430788-0 C0221
2002年6月20日初版初刷
そういうわけで資料として読み始めたんですが、わりと冒頭部であっけにとられるデータが出てきました。まあ、おれが知らなかっただけなんですけど。1945年の出来事に関する記述。以下、本書14ページ、「第一章 甦った靖国神社 1945〜1951年/2 遺族会の誕生と靖国信仰/神社本庁の設立」より。
| 「神道指令」当時、神社は10万6137社を数え、このうち8万7217社が宗教法人法によって宗教法人となり、その約99%の8万6157社が神社本庁に結集した。 |
えーと・・・神社って阿呆の巣窟ですか。
まあ率直な感想がこういうものだったんですが、この感想をおれが抱いた理由について説明しないと、たぶん展開がわけわかんなくなるだろうな。というわけで説明します。
神道の歴史の大胆なダイジェスト。
神道の源流がどこにあったのか、それがどのようなものであったのか、そのあたりについては現段階ではいまだ解明がなされていないようです。まあ飛鳥時代以前の話になりますから、普通にわかんないわな(=^_^;=)。
で、飛鳥時代の6世紀中ごろ(538年説と552年説がある)に日本に仏教が伝来(公伝)。それ以降、明治維新までの実に1300年余りの間、神道と仏教は区別があいまいなものとして扱われることになります。これを「神仏混淆」「神仏習合」などと呼びます。欧米流の宗教潔癖症から見ると想像を絶することであるらしいのだが、ま、各種の仏と各種の神とを対応させるなどして「同じものを別の切り口から見たもの」として扱おうとした、ということだわね。
その途上で、たとえば江戸時代における一般的様相のように「仏教の優越」があったり、江戸時代水戸藩領などにおける様相のように「神道の優越」があったり、そのあたりはまあいろいろ。ただいずれにせよ、飛鳥時代以降の日本には、「純粋な仏教」「純粋な神道」というのは存在しなかった。また、神道は飛鳥時代に仏教と混淆してしまったことから、教義など理論的支柱は仏教によりかかることとなり、神道としての教義が明確化されることがないままに、1300年という時を過ごすこととなった。
明治維新となり、明治政府は天皇のもとに国をまとめるという方針を考え、天皇を神道の神の一員と位置づけることにしました。その際に「その国家の支柱たる神道に教義がないというのは困る」ということになったらしい。そこで明治政府は、突然のように神道にも教義を作ることにした。
それが国家神道なわけですが、当然ながら江戸時代までの「教義のないあいまいな宗教としての神道」と「明確な教義を持つ宗教である国家神道」は、まるっきしの別物ということにならざるを得ません。ていうか、江戸時代までの神道は明らかに「自然宗教(源流がよくわからない自然発生的に生じたとされる宗教)」だったわけだけど、国家神道は誰か人間が教義を書いた宗教なわけでそれは「創唱宗教(特定の個人あるいはグループによって提唱されて形成された宗教。キリスト教や仏教が典型例)」に分類されるものであり、もうその2つは系統として違うだろうと。
なお、明治政府によるこの政策に関して、「神道という宗教が特別視されるとキリスト教が迫害されるのではないか」という懸念を抱いた諸外国が横槍を入れて神道の国教化を阻止、明治政府は「神社は宗教にあらず、習俗なり」という暴論を主張してこれを乗り切ります(1880年代あたり)。いやあ、神道ってば、性格を大胆に歪められただけでは済まず、かわいそうなことに宗教ですらないことにされちゃったんだぜ(=^_^;=)。
で、政府内には神社対応部局が置かれ(最初は1868年の神祇事務科、以降機構はさまざま変転)、政府と国家神道は一体化したものとして運用されることになります。神社は、それなりに優遇されるかわりに、国家神道の名のもとに、政府によって組織化され、格付けされ、統廃合を含めていろいろと介入されることになった。
なお、明治時代以降に、黒住教・金光教・天理教・大本教(正式には「大本」で「教」はつかない)など数多くの神道系の創唱宗教が誕生しており、それらは「教派神道」と呼ばれています。
さて、第二次世界大戦が敗戦に終わり、1945年12月15日に占領軍が「神道指令」と呼ばれる指令を出しました。これは、第二次世界大戦の根源のひとつとして国家神道があるという認識のもとに、政府と国家神道との連携を断ち切ることを目的としたもの。
それまでは国家神道を統べる機構が大日本帝国の政府内にあったわけですが、それはなくなる、と。その政府内にあった機構の代替として作られたのが神社本庁(という宗教法人。役所みたいな名称ですが役所ではありません。ま、役所っぽく見せたかったんだろうなあ)。
その神社本庁に、神社法人のうち実に98.8%もの神社が集まった。そして後日そのことを知ったおれの目は点になり、この書評が始まった、というわけ。
以上、大胆なダイジェスト終わり。
ここから、おれの神道観。
長い神仏習合の歴史があるから「神道ってなに?」「純粋な神道ってどういうもの?」という疑問への明確な答えというのは存在しないわけですけど、しかし明治時代以降の神道が国家神道を軸とすることによって改めて大きく歪められたということは事実であると言っていいとおれは思うんですよ。伝統を重んじるのであれば(そして普通、宗教というのは保守的なものであり、伝統を重んじるものであるはずだ)、神道は明治政府に対して怒りを見せるのが筋なんじゃないんだろうか。第二次世界大戦の敗戦を契機としてアホ政府から離脱しその影響下から脱することができるのなら、それは歓迎するのが当然ではないんだろうか、とおれは思うんですよ。
ところがそうはならず、法人格を持つ神社のうち実に98.8%が、神道を歪めた国家神道の系譜に連なる神社本庁に結集したっていうんでしょ。おまえら伝統を重んじる気持ちはないのか、神社って阿呆の巣窟ですか、とつながっていくわけです。
まあ、大日本帝国が政府内に神社担当部局を置いたのが1868年、神道指令によって政府内から神社担当部局が追い出されたのが1945年、その間78年ほど経っているわけで、その時間は1世代を越えていますから、「組織化され、教義を持ち、統制された姿の神社が当然のものである」という感覚が神道界の中に定着していたであろうことは想像がつきます。また、敗戦後のどたばたの時期ではありますからあえてそこで異議を唱えるのもめんどくさかったのであろうという事情もわからないではありません。
もうひとつ、明治時代に先行した江戸時代には、神社は一般論として仏教寺院の下に置かれ虐げられてきていたわけですし、明治時代以降は優遇されてこの世の春を謳歌したわけだから、明治以降の流れに感謝をするということは当然にあったことだろうし、明治時代以前のような状態に回帰するのは避けたいという気持ちもまた強かったことでしょう。
しかしそれにしても、やっぱ明治政府による神道政策は、神道の姿を歪めるものであったとも思う。それも、かなり深刻かつ決定的に歪めるものだった。
また、大日本帝国は国家経営に失敗して滅びていったわけですが、その失敗の途上に、国家神道ははっきりと足跡を残してしまっている。それって、神道にとっては「黒歴史」と呼ぶべきものではないんだろうか。
国家神道って、もしもおれが神道家であったならば、全力で否定したくなるようなしろものだったはずだ。そういう思いを禁じ得ないんですよね。でも、なんか神道の側には、そういう感覚がないか、あったとしても希薄であるように見える。それはいったいなぜなんだろう、というのがおれの疑問なんですよ。同時に、明治政府がやったことに怒らない神道に対して、おれがそこはかとない不信感・不快感を抱いていることにもつながっている。
また、国家神道って、明治維新の際に新たに作られた創唱宗教なわけで、ある意味「国家が背景についていたとはいえ、たかが教派神道のひとつにすぎない」とも言えると思うんです。国家神道なんて、敗戦の時点で歴史はたかだか78年、2011年時点で計算しても144年の歴史しか持たない新興宗教ではありませんか。飛鳥時代から明治維新までをざっと計算して1300年余り、飛鳥時代以前から存在し少なくとも1300年以上の歴史を持つ旧来の神道が、たかだか78年ないし114年の歴史しか持たない新興宗教の国家神道ごときに牛耳られている状況に甘んじていてどうしようというのだ、とも思うんです。
ここまで、おれの神道観。ま、半分くらい呆れ果てていて、残り半分くらいはしっかりしてくれよと思っている、という感じでしょうか。
とまあ、そんなふうに思っているおれにとって、この『靖国の戦後史』というのは、それなりに改めて衝撃的だったわけですよ。
なんていうの、こうも伝統を軽んじるひとたちがいるんだ、というのはやっぱある種の驚きにつながることです。さらには、伝統を軽んじる姿勢を臆面もなく恥も外聞もなく主張できるというメンタリティが、おれにはよくわからない。しかも、ご本人たちは「伝統を守っているつもり」であるらしいのだ。
このひとたち(=靖国神社国家護持運動とかやってるひとたち)は、本当に神道の信者であるのだろうか? いや、このひとたちは決して「神道」の信者などではなくて、「国家神道」というよく似た名前の別の宗教の信者であると理解すべきなんでしょうけれども。
なんか長々と書いたわりに本の感想の本体部分はわずか数行で終わってしまいましたけど、まあそういうわけで、おれ的には読む価値はある本だったと思います。
なお、本書は基本的に、左系の思想に基づいて書かれているもののように思います。おれは特に左翼系思想へのアレルギーはないんでそこんところは特に気にはなりませんでしたが、左翼思想には根強い戦前全否定は単純に過ぎると考えており、そういう観点からの神道批判と足並みをそろえるつもりはない、ということは明記しておこうと思います。
*
これで終わりにすると神道のワルクチを書いただけに終わってしまうことになりそうなもんで、つけたし。
幸いなことに、これまでの観察からして、現存する神社もまあいろいろで、あいかわらず国家神道の呪縛に囚われたままの神社も数多くあるにせよ、おそらくは国家神道なんてたいして気にもしないままに淡々と明治から昭和の時期を乗り切ってきたのであろう神社というのも少なからず存在しているように見受けられます。神社だって一枚岩ではない、というか。「淡々と国家神道の時代を乗り切ってきた神社」というのは、ある意味で民衆宗教・自然宗教のたくましさを感じさせるようなものでもあり、そういう「動じない姿勢」って宗教のような本来保守的であるはずのものにとっては、とても頼もしいと思ったりもする。
更には、国家神道が終わってすでに半世紀以上が経過しているということもあって、神社本庁のレベルはとにかくとして、氏子のレベルでは、国家神道の記憶は薄れつつあるように思う。まあ、単に記憶を薄れさせちゃっていいのかっていうと疑問はあるわけだが、結果としてそれが、神道が本来の姿(てのが前述の通りよくわからないわけだが)を取り戻す上で役に立つのであれば、「良いこと」だと思うことにしようと思います。
仏教の影響を受けなかった「神道」の姿を想像しにくいのと同じくらいに、国家神道の影響を受けなかった「神道」の姿も、想像しにくい。だけどまあ、それはいずれも、神道にとって「乗り越えていかなくちゃいけない歴史」なんだろうと思う。
いまだ残る国家神道の亡霊をなんとか払拭して、神道が生まれ変わる日が来ることを、おれは祈りたいなあ。まあ、それはおれが生きている間に実現するようななまやさしいものではなく、たぶんまたずいぶんと時間を必要とするのだろうという諦観とともに。
*
おまけ。可能ならば独立した書評を書きたいのだが、たぶんそんな余裕はないだろうと思うので、おまけとして言及し紹介しておきます。
 |  |
| 海老沢泰久 青い空〈上巻〉 | 海老沢泰久 青い空(下巻) |
いやあ。海老沢泰久。佐々木譲と並ぶおれの好きな作家だったんですが、最近新刊を見ないなあと思っていたら、死んでたんですね(=^_^;=)。2009年8月13日に十二指腸癌で死去。そら新作が出てこないわけです。
もともと注目したのは『F1地上の夢
その海老沢泰久が末期にいろいろ書いていたのが「歴史小説」という分野。『青い空』の他に、連作短編で『追っかけ屋 愛蔵
で、『青い空』。
この作品は、「類族」とされる者、つまり摘発されたキリシタンの末裔である主人公が、幕末と明治維新の時期を生き抜いていくという物語です。江戸幕府の仏教優遇策から明治政府の神道優遇策への切り替わりを、類族という、仏教からも神道からも一歩離れたポジションから眺めるという図式になっている。物語として面白かったというだけではなく、その視点の斬新さがなかなかのものでした。
この中に、明治時代に向けて神道の復権を夢見る若い神主が出てきます。この神主は、明治政府の重鎮にいいように利用され、そして物語の途中で何者かに殺されてしまうのですが、彼はおれが思うところの「明治政府に歪められる前の神道」の象徴のように感じられます。
ご興味があれば、幕末や明治維新、そして神道と国家神道というこのあたりの要素の関連本として、ぜひご一読いただければと思います。 続きを読む
2011年12月18日
本>『百姓から見た戦国大名』黒田基樹
久々の書評シリーズ2。
一発目に書いたことですが、この書評、どうせ長くなるし、興味がないひとには徹底して興味がないネタになろうかとも思うし、このWeblogの客層的にはどうなのかなあとも思います。なので「自分向けじゃないな」と思ったひとはさくさく飛ばしてしまうことをお勧めします。場違いなものをまきちらかしてすまん(=^_^;=)。
二発目は『百姓から見た戦国大名』黒田基樹。これは褒めます。
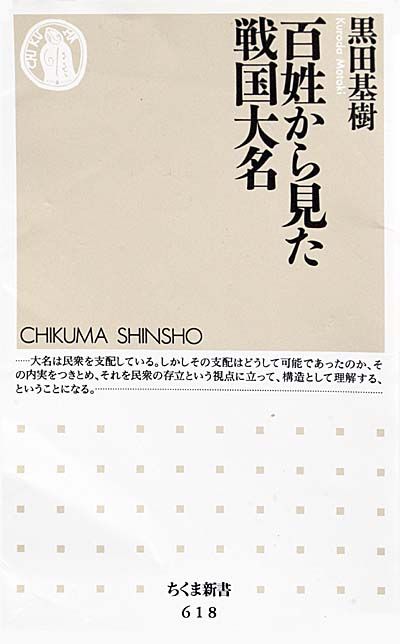

『百姓から見た戦国大名 』黒田基樹
』黒田基樹
ちくま新書618
ISBN4-480-06313-7 C0221
2006年9月10日初版初刷
日本史見直しの系列に属する本だと思います。なんだかんだ言いつつおれも網野善彦の影響を大きく受けてるなあ(苦笑)。で、いろいろな意味で面白かった。いろいろな意味とか言ってても話が拡散するだけだな、ざっくり今回書こうと思っている点をまとめると、「統治に関する意思決定システムの変遷」あたりになるでしょうか。
*
まずは、前回の『民主主義とは何なのか』から引き続きってことになる社会契約論をめぐる論点。
旧来の日本史では、前近代の日本では大衆は虐げられており、主体的な存在ではなく、領主・大名などに隷属している存在ということになっていました。ところが「必ずしもそんなことはなかったみたいだぞ」っていうか、もっとはっきりと「それはぜんぜん違うぞ」っていうのが、最近の日本史見直しにおける流れ。
かいつまんで箇条書きにまとめると以下のような感じになるだろうか。
この「惣村」は、単なる集落としての「村」とは微妙に意味あいが異なります。簡単に説明するなら、「意思決定システムをそなえた主体的な村・集落」というあたりになるだろうか。
中世の頃には生きていくことだけでもたいへんだったわけで、生存しようという目的を共有する地域住民によって地縁・血縁などを基礎として作られた機能集団が「惣村」であった、ということになります。一般の農民などは「惣村」を離れて生きていくことはできなかったから、「惣村」は生存の立脚点でもあった。
なお、「惣村」の掟はまあそれぞれの惣村で決まっていたわけですが、多くが「入札(いれふだ)」と呼ばれる投票制民主主義に基づいて運営されていたということは、記憶にとどめておくべきでしょう。
まあ「村のエラいひと」がある程度は固定されていたのも事実であり代々の庄屋・名主・肝煎とかいたしそれらは世襲制とも解することは可能ですが(まあでもそれは現代の民主主義体制度でも同じようなもんだと思うが(=^_^;=))、それが当然のことだとされていたわけではない。村としての行動の決定や中核メンバーの人選など、構成員の投票によってあらわされた意思に基づいて惣村としての意思決定が行われるというのは珍しいことではなかった。これは平等な投票権を保障するといったシステムではなかったなどの違いはあり近代的な意味あいにおける「投票による民主主義」と並行するものとして扱うのも乱暴ではありますが、「日本において、投票による民主主義は、それなりに定着し尊重されてきた風習であった」ということもまた否定はできないものと思われます。
さて。
なんせこの時代、生きていくだけでも大変だったわけです。ところで、生きていくためには「生産」という手段のほかに「掠奪」という手段があった。「生産」してその範囲で食っていくというのはまあ生業としてまっとうなものではありますが、「掠奪」したって食ってはいけるわけで(ここらへん、本書では「第一章 飢餓と戦争の時代」で扱っています)。で、惣村は、隣の惣村とかと、なにかというと戦っていたわけでございます(ここらへんは、本書では「第二章 村の仕組みと戦争」で扱われています)。
いやあ、日本史における中世の戦いっつーと「大名同士が領土争いでやるものである」という印象をお持ちの方が多いんではないかと思うわけですが(おれはそれ以前にイメージそのものを持っていなかった。日本史には全く興味がないし、世界史選択だったりしたしで、日本史についてはそもそも一般教養すらなかった(=^_^;=))、どうもそれは、見直された現在の日本史の観点からは「根本から間違ったイメージ」となってしまっているらしかった。
第一に、「戦いというのは、大名などの武装集団の専売特許ではなかった。末端の惣村あたりも、きっちり武装しており、主体的かつ積極的に、しかも日常的に、戦っていた」ということ。
第二に、「戦いというのは、領地を争うものと限ったものではなく、農作物・人材などの掠奪もまた重要な目的であった」ということ。
いやあなんていうの。同じ頃にはるか離れたヨーロッパの地でトマス・ホッブズというひとがなんか言ってたわけです。「自然な状態では、人間同士は、闘争的な対立関係となる。欲があるから、自然にそうなる」とかなんとか。ま、「惣村の戦い」は、そこから一歩抜けて「個人レベルでの戦い」が「集団レベルの戦い」に進化した形態だったわけですけれども。
で、戦いですから、勝たなければなりません。そこで、「合力」という制度が生み出される。これは惣村同士が連合体を組み、どこかの惣村が対立する総村から攻撃を受けた場合に、合力を約していた惣村は助っ人として参戦するという制度です。かくして戦いは、個人同士の戦いから惣村同士の戦いへと進歩し、惣村同士の戦いから惣村連合同士の戦いへと規模を拡大し、更に大規模なものへと発展していくことになる。どこまでが助力の対象となるかもどんどん広がっていく。結果として、それなりの既存権力であった大名がひっぱり出されたり、アジールとして確立されていた武装寺社勢力がひっぱり出されたりすることになる。こうなってくると、「惣村の戦い」と「大名の戦い」は、もう区別がつかなくなっていくわけです。
ところで。
いちおうまあ時代は中世ですから、惣村にもそれぞれ「領主」というのがいたりするわけです。惣村は、当然のこととして、領主にも、合力を持ちかける。ところがまあ、領主というのは一帯を仕切っていたりするわけですから、対立する複数の惣村から合力を依頼されたりすることもある。だからといってそこで領主側が合力を断ったりすると、惣村側からすれば「非協力的な、年貢などを納めてもメリットがない、ダメな領主」ということになるわけで、支持を失ったり、極端な場合には別の領主に乗り換えられてしまったりすることになる。だから、領主としても惣村どうしの戦いというのは悩みのタネになっていった。
また、当時の戦いでは、やり返されることを防ぐために相手方の戦力を低下させようということで生産手段の破壊というのもけっこう重要視されており、目先の掠奪のほかに、建物の破壊や未だ収穫には至らない段階の農地の破壊、労働力ともなる人間の誘拐と奴隷化なども並行して行われました。そういうのは地域の生産力を下げますから、領主としても歓迎できることではない(大胆に時代は下がりますが、第二次世界大戦における大東亜共栄圏構想の挫折は、この戦国時代にかたちづくられた日本的な戦略思想を日中戦争に持ち込んで掠奪と生産手段の破壊を派手にやらかしたことが反発をあおってしまったからではないか、という説もあったりしますね。けっこう納得がいく説だと、おれは思っている)。
そこで、惣村と惣村が対立した際には、それぞれの惣村からしてみれば第三者である領主が、第三者という地位を武器に「仲裁」にはいるようになっていった。
この「仲裁」は、惣村からしてみれば、「戦う権利の剥奪」につながるものでもありました。惣村が自らの意思として戦うことを決めたとしても、上層権力がその決議を否定してしまうのだからな。しかしまあ、世の中の流れは止めようもなく「戦うことの抑制」が広がっていく。このようにして、中世の日本にも、トマス・ホッブズが言っていた「相互に自分の権利を差し出すことによって実現される平和」、つまり社会契約論みたいな流れが生じてくる。ま、この段階では、「入札による意思決定」は広域化せず、第三者たる領主・大名などが意思決定をするようになっていくため、「独裁的な封建的体制が確立された」というように説明されることが多いんですが、違う側面から見てみれば「戦う権利の相互放棄と、それによってもたらされる平和の実現であった」と説明することもできる図式だったというわけだ。刀狩りなんかも、別の要素(たとえばアジールとして確立されていた武装寺社勢力の武装解除という目的など)もあったにせよ、この「戦う権利の否定」という要素もまた大きかったことは、たぶん間違いない。
んでもってまあ、こういう「戦う権利を否定する権力の広域化」が行き着くところまで行ったのが「全国統一」ってやつで、豊臣秀吉によって実現され、徳川家康によって安定政権となり、徳川家による全国支配が続いたとされる江戸時代の間は「日本全国から(基本的には)戦いがない状態が実現する」ことになったわけ。
なんかこう、おれが漠然と抱いていた戦国時代の姿とかとは、ぜんぜん違うんすよね。戦国大名というのは対外的には確かに戦う存在ではあったが、国内的には戦いを抑止する存在でもあったと。
ただ、あの時代に「ひたすら戦うことが商売だった専従の武装集団がそれなりの数存在し維持されており、それらが民衆とは無縁のところで、国取り合戦をやっていた」ということは実は考えにくいんです。そんな余力がいったい社会のどこにあったというのだ(=^_^;=)。「生産者兼武装集団である民衆がそれぞれわりと勝手気ままに戦っており、それがボトムアップされた結果として国取り合戦に発展した」という方が、物語としても理解しやすい。ああ、そういうことだったんですか、という感じ。そしてそれが行き着くところまで行ったら「戦いが禁じられた社会」ができあがってしまった、と。
で、かように視点を変えて論理を組み立てなおしてみると、戦国時代から江戸時代への流れというのは、「自らの(戦う・加害する)権利を相互に差し出しあうことによって、自らが攻撃されるような状況を避け、平和な状態を実現した」ものである、ということになる。
この戦国時代から江戸時代にかけての流れというのは、トマス・ホッブズが提示した社会契約論が、現実の政治機構の中で具現化していく流れである、それも見本のように鮮やかにその流れを示したものである、というように見えてはきませんか。
*
第二点。「領主や大名などは、独裁者であったのか」という論点。
明治時代になってからの江戸時代否定、第二次世界大戦の敗戦後におけるそれまでの歴史の全否定、なんてのがありまして、なんかいろいろ日本の歴史についての理解がおかしくなっている感じがするんですよね。
で、明治政府の主張と、第二次世界大戦敗戦後の日本政府の主張とは、微妙に文脈は違うんだが、いずれも「江戸時代(およびそれ以前)は、武家勢力が、民衆を虐げてきた時代であった」という規定になっているように思われます。「封建的」という表現を「絶対悪」みたいに扱うといった傾向なんかも、その流れによるものだと言っていいでしょう。先ごろテレビドラマとしては終わってしまったようですが、『水戸黄門』なんかもそういう歴史観に基づいて物語が構成されてるわけよね。「権力者による理不尽な圧制が行われている」というのが前提となっており、「そこにさらに上層権力者が登場して問題を解決する」というカタルシスが根幹を成す、と。権力の上下関係というピラミッド構造が明確に存在していることが前提とされている。
しかし果たして封建領主や大名というのは、独裁権力であったのか。ていうか、独裁権力であったとするならばそれはいったいどういう理由で権力たり得たのか。独裁権力であったと考える理由はあるのか。
本書からは、そのあたりのことも読み取ることができます。
これは、事例としては主として「プロローグ 代替わりと『世直し』」の項目で紹介されていることがらであり、その後はそういう権力構造のあり方を当然の前提として書き進められているのですが、要するに「民衆に支持されていなかった領主・大名は、領主・大名であり続けることはできなかった」ということです。つまり、領主・大名の権力は、民衆の支持に裏付けられたものであり、民衆の意思に反する政治を長期にわたって継続することができるような独裁権力ではなかった、ということでもあります。
代表例として、小田原北条家における氏康から氏政への代替わり(1559年)、甲斐武田家における信虎から信玄への代替わり(1541年)などが挙げられています。これらはいずれも飢饉を背景としたもので(当時としては、飢饉は「為政者の徳が足らないために起きるもの」という発想があり、飢饉が発生したら為政者の人気は落ちた)、人気がない者をトップに据えていると政権の維持が難しくなるため、代替わりをしたのだという分析が加えられています。なお、北条氏康から北条氏政への代替わりは禅譲ですが、武田信虎から武田信玄への代替わりはクーデターによるもので、後者は「ほっといたら武田家による甲斐支配が危うくなる」という武田信玄の強い危機感に基づくものではないか、という推測も述べられています(実際、武田信玄はその後の政策での人気取りに成功したこともあって、甲斐においてはいまだに評価が高いとされる)。
また、先に述べたことの繰り返しとなりますが、惣村は、上層権力からの理不尽な要求に対しては「契約継続の拒否」「一揆」「逃散」などの抵抗をしたり、可能ならば契約相手を乗り換えるといったこともやっています。ですから、江戸時代のイメージに根強くあるような「大名に隷属する存在」というのはかなり実態からは乖離したものであったようにも思われます。こういった抵抗を招くような不人気な領主・大名は、長期政権の維持はできなかったのではないかと考えられるのです。
もうひとつ、事例としては、「上杉謙信の出稼ぎ関東侵攻(1560〜1567年)」なんかも、人気取り政策のうちにあげられるかも。本書では「第一章 飢餓と戦争の時代」のうちの「上杉謙信の関東侵攻」で扱われています。
上杉謙信(長尾影虎)がテリトリーとしていた越後ですが、冬になると雪に閉ざされる場所なわけです。やることがない。そこで、やることがなくなった農民を糾合して、上杉謙信は出稼ぎ侵攻を行っていた、と。まあ当時、関東には北条氏に逆らえる政治権力がなくなっており、北条氏と対立する勢力から上杉に対して支援要請(ま、大規模な合力の要請だわな)を受けていたとはいえ、そんなひとさまの都合だけで兵を出せるほどの余裕があったとは思われません。これは多分に上杉側・越後側の都合があったはずである、と。
で、要するに、冬の間やることがない農民にとってみても、その期間に関東に侵攻し、掠奪をし、雪のない関東で正月を過ごして、雪が消える頃に越後に帰るという関東侵攻ツアーは、それなりに人気が高い行事だったということなのでしょう。そうでもなけりゃ、んな8回も続けて恒例行事のように「冬にだけ関東に侵攻して掠奪」なんてことが繰り返されたはずはないんで。
そうか上杉謙信の関東侵攻って「大人気! 出稼ぎ掠奪ツアー」だったのかあ。少なくとも「国取合戦のひとつ」と考えるよりは、はるかにわかりやすいし納得もいくわな。
同時に「大衆の人気取りに走った政策というのは、しばしば迷惑なものである」という今に通じる真理がそこにも存在した、とか言えるかもしれないわけですが(=^_^;=)。
で、なんだね。ちょっと強引かなあと思いつつなんだけどね。
これってば、「投票によらない民主主義」とも呼べるものなのではないか。なにをもって民意の確認とするかっていうあたりがしごく微妙であり、民主主義と呼べるかどうかという点にも疑問はあるのだけれども、でも「民意を基盤として権力が成立していた」と理解することもできそうなわけで。
まあ、んなことを言ったら、独裁制の政権だって倒れるときは倒れるわけで、「独裁制は民意を基盤として成立する」なんてことも言えるようになっちゃったりするんだけどね(=^_^;=)。
*
ここまで書いてきてちょっと不安になったので念のために付け足しておくんですが。
本書は、おれが書いたような論点をベースとして書かれた本ではないし、このような主張をしている本でもありません。ただ、書かれた内容をある特定の方向から眺めてみると、このように読み解くこともできるのではないか、ということです。前回批評した『民主主義とは何か』のようなはっきりとした主義主張(しかしいまひとつ同意しがたい粗雑な主義主張)と並べてみたとき、本書がもともと考えていたのではないだろう側面が垣間見えてきた、とでも言えばいいんでしょうか。というか、並べて論じることではじめて見えてくるものがあると気づいたのでおれはこんな書評を書こうと思った、ということですが。
*
以下、おまけとして書いておこうと思ったこと。
たぶんね、他にもいろいろ興味深い論点は探せると思うんですよ。この本だけじゃなくて、日本史の見直しの流れって、いろんな意味でエキサイティングで。
そうねえなんていうかねえ。おれはそういうわけで日本史は忌避して生きてきました。大学受験のときも世界史選択だったし。でも、おぼろげレベルで知っている日本史と、最近の見直しが加えられた日本史は、なんかまったく違うもののようにも見える。そして、見直しが行われた以降の日本史って、けっこう面白いんです。特に、見直し以前と見直し以降の差分が、とても興味深い。
日本史が嫌いだった方、おいでになろうかと思います。でも最近の日本史って、こんなふうにいろいろと面白い・・・ような気がします。久しぶりに日本史の関連書物とかを、立ち読みとかしてみませんか。気に入ったものがあったら改めてお勉強してみても、楽しいんじゃないかなあ。とか、突然妙な提案をして、この書評を締めようと思います。
ではまた。 続きを読む
一発目に書いたことですが、この書評、どうせ長くなるし、興味がないひとには徹底して興味がないネタになろうかとも思うし、このWeblogの客層的にはどうなのかなあとも思います。なので「自分向けじゃないな」と思ったひとはさくさく飛ばしてしまうことをお勧めします。場違いなものをまきちらかしてすまん(=^_^;=)。
二発目は『百姓から見た戦国大名』黒田基樹。これは褒めます。
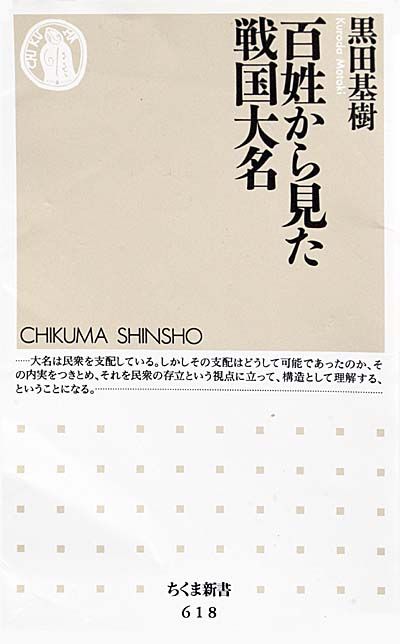
『百姓から見た戦国大名
ちくま新書618
ISBN4-480-06313-7 C0221
2006年9月10日初版初刷
日本史見直しの系列に属する本だと思います。なんだかんだ言いつつおれも網野善彦の影響を大きく受けてるなあ(苦笑)。で、いろいろな意味で面白かった。いろいろな意味とか言ってても話が拡散するだけだな、ざっくり今回書こうと思っている点をまとめると、「統治に関する意思決定システムの変遷」あたりになるでしょうか。
*
まずは、前回の『民主主義とは何なのか』から引き続きってことになる社会契約論をめぐる論点。
旧来の日本史では、前近代の日本では大衆は虐げられており、主体的な存在ではなく、領主・大名などに隷属している存在ということになっていました。ところが「必ずしもそんなことはなかったみたいだぞ」っていうか、もっとはっきりと「それはぜんぜん違うぞ」っていうのが、最近の日本史見直しにおける流れ。
かいつまんで箇条書きにまとめると以下のような感じになるだろうか。
| ・ | 中世の日本には「惣村」などと呼ばれる小規模の統治システム、集落単位での意思決定システムがあり、それはけっこう中世を通じて一貫して確立され機能していた。特に鎌倉時代後期(13世紀くらいか)から江戸時代以前(16世紀くらいまでか)の時期には、「惣村」は社会システムの上できわめて重要な存在であった。 |
| ・ | 「惣村」は、領主や大名などの上層権力と、原則として対等の関係にあり、相互の関係は契約によって規定されていた。惣村は上層権力に隷属する存在だったわけではなく、惣村側が契約先の上層権力を選んだり納得がいかなければ一揆や逃散などの抵抗をしたりということもあり、なかなかにしたたかで独立性のある存在であった。 |
この「惣村」は、単なる集落としての「村」とは微妙に意味あいが異なります。簡単に説明するなら、「意思決定システムをそなえた主体的な村・集落」というあたりになるだろうか。
中世の頃には生きていくことだけでもたいへんだったわけで、生存しようという目的を共有する地域住民によって地縁・血縁などを基礎として作られた機能集団が「惣村」であった、ということになります。一般の農民などは「惣村」を離れて生きていくことはできなかったから、「惣村」は生存の立脚点でもあった。
なお、「惣村」の掟はまあそれぞれの惣村で決まっていたわけですが、多くが「入札(いれふだ)」と呼ばれる投票制民主主義に基づいて運営されていたということは、記憶にとどめておくべきでしょう。
まあ「村のエラいひと」がある程度は固定されていたのも事実であり代々の庄屋・名主・肝煎とかいたしそれらは世襲制とも解することは可能ですが(まあでもそれは現代の民主主義体制度でも同じようなもんだと思うが(=^_^;=))、それが当然のことだとされていたわけではない。村としての行動の決定や中核メンバーの人選など、構成員の投票によってあらわされた意思に基づいて惣村としての意思決定が行われるというのは珍しいことではなかった。これは平等な投票権を保障するといったシステムではなかったなどの違いはあり近代的な意味あいにおける「投票による民主主義」と並行するものとして扱うのも乱暴ではありますが、「日本において、投票による民主主義は、それなりに定着し尊重されてきた風習であった」ということもまた否定はできないものと思われます。
さて。
なんせこの時代、生きていくだけでも大変だったわけです。ところで、生きていくためには「生産」という手段のほかに「掠奪」という手段があった。「生産」してその範囲で食っていくというのはまあ生業としてまっとうなものではありますが、「掠奪」したって食ってはいけるわけで(ここらへん、本書では「第一章 飢餓と戦争の時代」で扱っています)。で、惣村は、隣の惣村とかと、なにかというと戦っていたわけでございます(ここらへんは、本書では「第二章 村の仕組みと戦争」で扱われています)。
いやあ、日本史における中世の戦いっつーと「大名同士が領土争いでやるものである」という印象をお持ちの方が多いんではないかと思うわけですが(おれはそれ以前にイメージそのものを持っていなかった。日本史には全く興味がないし、世界史選択だったりしたしで、日本史についてはそもそも一般教養すらなかった(=^_^;=))、どうもそれは、見直された現在の日本史の観点からは「根本から間違ったイメージ」となってしまっているらしかった。
第一に、「戦いというのは、大名などの武装集団の専売特許ではなかった。末端の惣村あたりも、きっちり武装しており、主体的かつ積極的に、しかも日常的に、戦っていた」ということ。
第二に、「戦いというのは、領地を争うものと限ったものではなく、農作物・人材などの掠奪もまた重要な目的であった」ということ。
いやあなんていうの。同じ頃にはるか離れたヨーロッパの地でトマス・ホッブズというひとがなんか言ってたわけです。「自然な状態では、人間同士は、闘争的な対立関係となる。欲があるから、自然にそうなる」とかなんとか。ま、「惣村の戦い」は、そこから一歩抜けて「個人レベルでの戦い」が「集団レベルの戦い」に進化した形態だったわけですけれども。
で、戦いですから、勝たなければなりません。そこで、「合力」という制度が生み出される。これは惣村同士が連合体を組み、どこかの惣村が対立する総村から攻撃を受けた場合に、合力を約していた惣村は助っ人として参戦するという制度です。かくして戦いは、個人同士の戦いから惣村同士の戦いへと進歩し、惣村同士の戦いから惣村連合同士の戦いへと規模を拡大し、更に大規模なものへと発展していくことになる。どこまでが助力の対象となるかもどんどん広がっていく。結果として、それなりの既存権力であった大名がひっぱり出されたり、アジールとして確立されていた武装寺社勢力がひっぱり出されたりすることになる。こうなってくると、「惣村の戦い」と「大名の戦い」は、もう区別がつかなくなっていくわけです。
ところで。
いちおうまあ時代は中世ですから、惣村にもそれぞれ「領主」というのがいたりするわけです。惣村は、当然のこととして、領主にも、合力を持ちかける。ところがまあ、領主というのは一帯を仕切っていたりするわけですから、対立する複数の惣村から合力を依頼されたりすることもある。だからといってそこで領主側が合力を断ったりすると、惣村側からすれば「非協力的な、年貢などを納めてもメリットがない、ダメな領主」ということになるわけで、支持を失ったり、極端な場合には別の領主に乗り換えられてしまったりすることになる。だから、領主としても惣村どうしの戦いというのは悩みのタネになっていった。
また、当時の戦いでは、やり返されることを防ぐために相手方の戦力を低下させようということで生産手段の破壊というのもけっこう重要視されており、目先の掠奪のほかに、建物の破壊や未だ収穫には至らない段階の農地の破壊、労働力ともなる人間の誘拐と奴隷化なども並行して行われました。そういうのは地域の生産力を下げますから、領主としても歓迎できることではない(大胆に時代は下がりますが、第二次世界大戦における大東亜共栄圏構想の挫折は、この戦国時代にかたちづくられた日本的な戦略思想を日中戦争に持ち込んで掠奪と生産手段の破壊を派手にやらかしたことが反発をあおってしまったからではないか、という説もあったりしますね。けっこう納得がいく説だと、おれは思っている)。
そこで、惣村と惣村が対立した際には、それぞれの惣村からしてみれば第三者である領主が、第三者という地位を武器に「仲裁」にはいるようになっていった。
この「仲裁」は、惣村からしてみれば、「戦う権利の剥奪」につながるものでもありました。惣村が自らの意思として戦うことを決めたとしても、上層権力がその決議を否定してしまうのだからな。しかしまあ、世の中の流れは止めようもなく「戦うことの抑制」が広がっていく。このようにして、中世の日本にも、トマス・ホッブズが言っていた「相互に自分の権利を差し出すことによって実現される平和」、つまり社会契約論みたいな流れが生じてくる。ま、この段階では、「入札による意思決定」は広域化せず、第三者たる領主・大名などが意思決定をするようになっていくため、「独裁的な封建的体制が確立された」というように説明されることが多いんですが、違う側面から見てみれば「戦う権利の相互放棄と、それによってもたらされる平和の実現であった」と説明することもできる図式だったというわけだ。刀狩りなんかも、別の要素(たとえばアジールとして確立されていた武装寺社勢力の武装解除という目的など)もあったにせよ、この「戦う権利の否定」という要素もまた大きかったことは、たぶん間違いない。
んでもってまあ、こういう「戦う権利を否定する権力の広域化」が行き着くところまで行ったのが「全国統一」ってやつで、豊臣秀吉によって実現され、徳川家康によって安定政権となり、徳川家による全国支配が続いたとされる江戸時代の間は「日本全国から(基本的には)戦いがない状態が実現する」ことになったわけ。
なんかこう、おれが漠然と抱いていた戦国時代の姿とかとは、ぜんぜん違うんすよね。戦国大名というのは対外的には確かに戦う存在ではあったが、国内的には戦いを抑止する存在でもあったと。
ただ、あの時代に「ひたすら戦うことが商売だった専従の武装集団がそれなりの数存在し維持されており、それらが民衆とは無縁のところで、国取り合戦をやっていた」ということは実は考えにくいんです。そんな余力がいったい社会のどこにあったというのだ(=^_^;=)。「生産者兼武装集団である民衆がそれぞれわりと勝手気ままに戦っており、それがボトムアップされた結果として国取り合戦に発展した」という方が、物語としても理解しやすい。ああ、そういうことだったんですか、という感じ。そしてそれが行き着くところまで行ったら「戦いが禁じられた社会」ができあがってしまった、と。
で、かように視点を変えて論理を組み立てなおしてみると、戦国時代から江戸時代への流れというのは、「自らの(戦う・加害する)権利を相互に差し出しあうことによって、自らが攻撃されるような状況を避け、平和な状態を実現した」ものである、ということになる。
この戦国時代から江戸時代にかけての流れというのは、トマス・ホッブズが提示した社会契約論が、現実の政治機構の中で具現化していく流れである、それも見本のように鮮やかにその流れを示したものである、というように見えてはきませんか。
*
第二点。「領主や大名などは、独裁者であったのか」という論点。
明治時代になってからの江戸時代否定、第二次世界大戦の敗戦後におけるそれまでの歴史の全否定、なんてのがありまして、なんかいろいろ日本の歴史についての理解がおかしくなっている感じがするんですよね。
で、明治政府の主張と、第二次世界大戦敗戦後の日本政府の主張とは、微妙に文脈は違うんだが、いずれも「江戸時代(およびそれ以前)は、武家勢力が、民衆を虐げてきた時代であった」という規定になっているように思われます。「封建的」という表現を「絶対悪」みたいに扱うといった傾向なんかも、その流れによるものだと言っていいでしょう。先ごろテレビドラマとしては終わってしまったようですが、『水戸黄門』なんかもそういう歴史観に基づいて物語が構成されてるわけよね。「権力者による理不尽な圧制が行われている」というのが前提となっており、「そこにさらに上層権力者が登場して問題を解決する」というカタルシスが根幹を成す、と。権力の上下関係というピラミッド構造が明確に存在していることが前提とされている。
しかし果たして封建領主や大名というのは、独裁権力であったのか。ていうか、独裁権力であったとするならばそれはいったいどういう理由で権力たり得たのか。独裁権力であったと考える理由はあるのか。
本書からは、そのあたりのことも読み取ることができます。
これは、事例としては主として「プロローグ 代替わりと『世直し』」の項目で紹介されていることがらであり、その後はそういう権力構造のあり方を当然の前提として書き進められているのですが、要するに「民衆に支持されていなかった領主・大名は、領主・大名であり続けることはできなかった」ということです。つまり、領主・大名の権力は、民衆の支持に裏付けられたものであり、民衆の意思に反する政治を長期にわたって継続することができるような独裁権力ではなかった、ということでもあります。
代表例として、小田原北条家における氏康から氏政への代替わり(1559年)、甲斐武田家における信虎から信玄への代替わり(1541年)などが挙げられています。これらはいずれも飢饉を背景としたもので(当時としては、飢饉は「為政者の徳が足らないために起きるもの」という発想があり、飢饉が発生したら為政者の人気は落ちた)、人気がない者をトップに据えていると政権の維持が難しくなるため、代替わりをしたのだという分析が加えられています。なお、北条氏康から北条氏政への代替わりは禅譲ですが、武田信虎から武田信玄への代替わりはクーデターによるもので、後者は「ほっといたら武田家による甲斐支配が危うくなる」という武田信玄の強い危機感に基づくものではないか、という推測も述べられています(実際、武田信玄はその後の政策での人気取りに成功したこともあって、甲斐においてはいまだに評価が高いとされる)。
また、先に述べたことの繰り返しとなりますが、惣村は、上層権力からの理不尽な要求に対しては「契約継続の拒否」「一揆」「逃散」などの抵抗をしたり、可能ならば契約相手を乗り換えるといったこともやっています。ですから、江戸時代のイメージに根強くあるような「大名に隷属する存在」というのはかなり実態からは乖離したものであったようにも思われます。こういった抵抗を招くような不人気な領主・大名は、長期政権の維持はできなかったのではないかと考えられるのです。
もうひとつ、事例としては、「上杉謙信の出稼ぎ関東侵攻(1560〜1567年)」なんかも、人気取り政策のうちにあげられるかも。本書では「第一章 飢餓と戦争の時代」のうちの「上杉謙信の関東侵攻」で扱われています。
上杉謙信(長尾影虎)がテリトリーとしていた越後ですが、冬になると雪に閉ざされる場所なわけです。やることがない。そこで、やることがなくなった農民を糾合して、上杉謙信は出稼ぎ侵攻を行っていた、と。まあ当時、関東には北条氏に逆らえる政治権力がなくなっており、北条氏と対立する勢力から上杉に対して支援要請(ま、大規模な合力の要請だわな)を受けていたとはいえ、そんなひとさまの都合だけで兵を出せるほどの余裕があったとは思われません。これは多分に上杉側・越後側の都合があったはずである、と。
で、要するに、冬の間やることがない農民にとってみても、その期間に関東に侵攻し、掠奪をし、雪のない関東で正月を過ごして、雪が消える頃に越後に帰るという関東侵攻ツアーは、それなりに人気が高い行事だったということなのでしょう。そうでもなけりゃ、んな8回も続けて恒例行事のように「冬にだけ関東に侵攻して掠奪」なんてことが繰り返されたはずはないんで。
そうか上杉謙信の関東侵攻って「大人気! 出稼ぎ掠奪ツアー」だったのかあ。少なくとも「国取合戦のひとつ」と考えるよりは、はるかにわかりやすいし納得もいくわな。
同時に「大衆の人気取りに走った政策というのは、しばしば迷惑なものである」という今に通じる真理がそこにも存在した、とか言えるかもしれないわけですが(=^_^;=)。
で、なんだね。ちょっと強引かなあと思いつつなんだけどね。
これってば、「投票によらない民主主義」とも呼べるものなのではないか。なにをもって民意の確認とするかっていうあたりがしごく微妙であり、民主主義と呼べるかどうかという点にも疑問はあるのだけれども、でも「民意を基盤として権力が成立していた」と理解することもできそうなわけで。
まあ、んなことを言ったら、独裁制の政権だって倒れるときは倒れるわけで、「独裁制は民意を基盤として成立する」なんてことも言えるようになっちゃったりするんだけどね(=^_^;=)。
*
ここまで書いてきてちょっと不安になったので念のために付け足しておくんですが。
本書は、おれが書いたような論点をベースとして書かれた本ではないし、このような主張をしている本でもありません。ただ、書かれた内容をある特定の方向から眺めてみると、このように読み解くこともできるのではないか、ということです。前回批評した『民主主義とは何か』のようなはっきりとした主義主張(しかしいまひとつ同意しがたい粗雑な主義主張)と並べてみたとき、本書がもともと考えていたのではないだろう側面が垣間見えてきた、とでも言えばいいんでしょうか。というか、並べて論じることではじめて見えてくるものがあると気づいたのでおれはこんな書評を書こうと思った、ということですが。
*
以下、おまけとして書いておこうと思ったこと。
たぶんね、他にもいろいろ興味深い論点は探せると思うんですよ。この本だけじゃなくて、日本史の見直しの流れって、いろんな意味でエキサイティングで。
そうねえなんていうかねえ。おれはそういうわけで日本史は忌避して生きてきました。大学受験のときも世界史選択だったし。でも、おぼろげレベルで知っている日本史と、最近の見直しが加えられた日本史は、なんかまったく違うもののようにも見える。そして、見直しが行われた以降の日本史って、けっこう面白いんです。特に、見直し以前と見直し以降の差分が、とても興味深い。
日本史が嫌いだった方、おいでになろうかと思います。でも最近の日本史って、こんなふうにいろいろと面白い・・・ような気がします。久しぶりに日本史の関連書物とかを、立ち読みとかしてみませんか。気に入ったものがあったら改めてお勉強してみても、楽しいんじゃないかなあ。とか、突然妙な提案をして、この書評を締めようと思います。
ではまた。 続きを読む
2011年12月16日
本>『民主主義とは何なのか』長谷川三千子
久々の書評。次に書く『百姓から見た戦国大名』の書評に続きます。この2冊を連携させて批評するってのも乱暴だけどな(=^_^;=)、しかしけっこう深いところに密接に関係するテーマがあったりしたわけよ。書誌情報・目次全文は「続き」に格納してあります。
なお、どうせ長くなるし、興味がないひとには徹底して興味がないネタになろうかとも思うし、このWeblogの客層的にはどうなのかなあとも思います。なので「自分向けじゃないな」と思ったひとはさくさく飛ばしてしまうことをお勧めします。ちょっといろいろありまして、ここらへんの思想関連のネタも、不十分ながら文書化しておきたい事情ができてきたんすよ。本来なら別のWeblogでも立ち上るとかしてそっちでやるべきなのかもしれないんだけどね。
では、参ります。
一発目は、文春新書の『民主主義とは何なのか』長谷川三千子。遠慮会釈なく貶しちゃいます。貶すのってけっこうムズカシくて、一歩間違うとダークサイドフォースに足を取られることになっちゃうんですけどねー、うまくいくんだろうか。


『民主主義とは何なのか 』長谷川三千子
』長谷川三千子
文春新書191
ISBN4-16-660191-1 C0230
2001年9月20日初版初刷
いやあ、残念な本だ。全面的にクズ本なわけではなくて、部分的には見るべき部分はあるし興味深い分析もあるんだけど、根本のところがどうもダメっぽい。どうも著者は思想的には右翼傾向を持っているようなのだが、その結果目が曇ったっていうか、ウヨってやっぱダメなのかな、という感じ。ここまでちゃんと調べてお勉強をしているのに、しかしなんだってまた根底のところで道筋を間違ったまま行っちゃうかなあ。
基本線として、「民主主義」を絶対視することに対して、異議を唱えている本です。もっと厳密に定義すると、「投票による民主主義」が対象ですね。「投票によらない民主主義なんてものがあるのか」というのは、今回はツッコミになんないのでそこんところヨロシク。
んで、それを至上のもの・当然の前提として扱うことに対する異議申し立て。まあ、投票による民主主義なんてろくなもんじゃありませんから、それは良しとします。ていうか、そこらへんには同意したから買ってきたわけだけどさ。
ただ、どうも著者の頭の中では、「投票による民主主義は、日本にはもともとは存在せず、欧米から持ち込まれたものである→だから日本にはなじまない」という物語が存在しているようなんですね。「そんなものを持ち込んだがゆえに第二次世界大戦敗戦後の日本は道を間違えたんだ」とか言いたそうであります。基本線、その路線で「投票による民主主義」を批判するという骨組みを作ってしまっている。しかしいくらなんでもそれは違うだろうと、おれは思うわけです。投票による民主主義なんてわりと誰もがすぐに考え付く方法論だし、日本にだって当然あったんだからさ(次回の『百姓から見た戦国大名』で詳説)。
その先の章では、ギリシャ時代からフランス革命などを経て近代まで、欧米における投票による民主主義に対する分析と批判が展開されます。この部分は、まあそれなりに精緻に組み立てられていると言えるし、読む価値はある・・・と思う。このあたりの分析は、ジョン・ロックに全ての責任があるかどうかというあたりを除いて、おれの分析とさほど食い違わない。まあ、かなり煽りぶっこんでいるのが気になるし、目次を見ればわかる通りで「インチキ」「ペテン師」「プロパガンダ」などの否定的言辞が垂れ流されていることからけっこう感情的に書いているんじゃないかという懸念が禁じ得ないんだけど。
というわけで、分析部分などには見るべきところがあるのだが、基本骨格のところでコケちゃっているので、おれ的な評価は「残念な本」ってことになるわけ。
古来の日本には投票による民主主義はなかったのか。いやあ、あったんすよね、それもかなり古い時期から。「投票」「選挙」とは呼ばれておらず「入札(いれふだ)」と呼ばれていたのですが。入札がはじまった時期をおれは知らないんだけれども、戦国時代にはすでに確立された風習となっていた。へたすりゃそこから1000年くらいは遡るのではないか。そして、それは江戸時代も貫いてずーっと惣村の統治機構として存在し続けており、明治時代になだれ込んでいる。
惣村における「投票による民主主義」がそれだけでは立ち行かなくなった理由あたりは次回の『百姓から見た戦国大名』の書評で触れます。そのあたりは洋の東西を問わずみんな似たような失敗をやってきてるわねー、って感じ。ある意味、相互に関係なんかないままにしかし同じように失敗するというこの普遍性こそが、投票による民主主義が抱える根本的な問題を明らかにする現象であり、その問題点を解析するための手がかりになるんではないかとかおれは思う。なんでそういうおいしい題材がすぐそこにころがっているのに、「日本は違う」とかいうお馬鹿な思い込みで、そこをスルーできちゃうのかがおれにはよくわからない。
いずれにせよ、「投票による民主主義は、ギリシャ時代から続く欧米固有の思想であり、日本にはなじまない」という立ち位置はおかしい。そこがおかしい以上、今の日本がうまく動いていないとしても、その理由を「むりやり西欧の思想を輸血したせいである」とかいうあたりにこじつけるのは、無駄っていうか、間違いっていうか、徒労というか、そういうものにしかなり得ない。んなこと言うたかてなんら意義ある提案にも提言にもなりゃしませんぜ、ってことになります。
*
近世ヨーロッパにおける社会契約論との関係の部分について。
社会契約論は、「第四章 インチキとごまかしの産物 − 人権」において、民主主義思想の根源とされる人権がどのようなものであったのかについての考察部分で、その理論的支柱をどう受け止めるべきなのかという観点で、言及されています。
著者は、トマス・ホッブズの社会契約論をジョン・ロックが換骨奪胎したことが、人権概念が異常に肥大化するという結果を導いたとして、ジョン・ロックを激しく非難しているのですが、なんかそれは違うような気がする。
トマス・ホッブズ(1588〜1679)が『リヴァイアサン(1651)』によって提示した社会契約論の新しい切り口と(あくまでも「新しい切り口」。トマス・ホッブズがはじめて社会契約論を提示したわけではない)、その後に展開された社会契約論を基礎とする国家主権論、国家主権の根底となるものとして位置づけられた人権思想との間には、かなりの乖離があるのは確かだ。本書の指摘通りに「なんか流れがおかしい」とは、おれも思うのである(ただし、トマス・ホッブズ以前の社会契約論も含めて眺めるなら、単に「トマス・ホッブズが異端だった」と位置づけることも可能。その異端のトマス・ホッブズの説が注目すべき新たな視点を提供したものである、という点は見落とせない重要な点なんだけれども)。
本書では、トマス・ホッブズの思想を換骨奪胎したのはジョン・ロック(1632〜1704)であるとし、そのジョン・ロックが実はペテン師でありインチキをぶちまいて民主主義思想をゆがめたのだ、としています。まあそこらへんについておれはちゃんと裏を取っていないし、その分析が正しいかどうかについての断定的な判断は避けようと思いますが。
トマス・ホッブズの社会契約論とは、簡単に説明すると、こんな感じになるでしょうか。
ルールなき状態(これをホッブズは「自然な状態」と考えた)では、人間同士は闘争的な対立関係となる。欲があるから、自然にそうなる。そこでは、たとえば「殺し合い」も当然のこととされる。しかし人間誰しも自分が殺されたくはない。そこで、殺されたくない者同士で、「わたしはあなたを殺さない。そのかわり、あなたもわたしを殺さない」と相互に約束(双務的な契約)をする。つまり、「自分が相手を殺す権利、あるいは自分が相手を殺すという選択肢」を相互に放棄しあうことで、闘争的関係を終わらせることができる。それが「社会契約(Social Contract)」である。社会のルールは、この「社会契約」によって正当化される。
それまでは、社会のルールは「神」などの人間社会にとって外的な存在によってしか正当化され得なかったが、この「ホッブズの社会契約論という思想」は、社会のルールの力の根源を人間界の中に持ち込み、社会を人間界の中で完結させることができるようにしたという点で画期的でした。
ホッブズ以前にも社会契約論というのは存在していました(本書は、ホッブズ以前の社会契約論の流れには、ほとんど触れていない。天賦人権説にはちょっとだけ触れているけれども)。『戦争と平和の法(1625)』で有名なグロティウス(1583〜1645)あたりも社会契約論に言及していたらしいな。おれはグロティウスのそういう側面をほとんど知らなかったが。
ホッブズ以前の社会契約論に共通することは、「自然な状態では、人間は自由で平等であり幸せであった」という原始共産制みたいな感覚で自然な状態を規定していたことだったらしい(おれはそこんところに、旧約聖書の「エデンの園」につながるような、ユダヤ教以来の宗教感覚があるように感じたりするのだけれども)。「自然な状態は、闘争状態であった」とするホッブズの社会契約論は、そのユートピア的前提を崩したところに意味がある。トマス・ホッブズの思想の特徴でありいちばん輝かしいところは、この自然状態の定義の部分であり、そこを高く評価していることについて、著者は正しい。ただ、その後のところがなぁ。
社会契約論という大枠の流れの中ではトマス・ホッブズの後継世代であるジョン・ロックやジャン・ジャック・ルソー(1712〜1778)は、当初の自然な状態を「闘争状態」ではなく「自由で平等で平和な状態」と規定しており(つまり「先祖返り」してしまっており)、従って「自らの権利をみんなが少しづつ差し出すこと」を社会契約であるとは位置づけていません。そこんところを、著者は「ジョン・ロックというペテン師がインチキをやった」と述べている。
しかしなー。トマス・ホッブズの位置づけが難しくなるという問題はあるんだけど、ジョン・ロックはトマス・ホッブズの後継者なのではなくて古典的社会契約論系の思想の後継者であると規定するならば、「ジョン・ロックは、異端的社会契約論のトマス・ホッブズの思想をつまみ食いして、自分の主張に取り入れた程度である」と考えることもできる。ていうか、その方が適切なんじゃないんだろうか。そう考えた場合、ジョン・ロックは、「それまでの主流だった社会契約論に則って思想を組み立てただけであり、トマス・ホッブズの思想を換骨奪胎したペテン師でインチキヤローである、とまで言うのは言いがかり」ってことになるような気がする。まあ、「少なくとも、トマス・ホッブズの説のすごさがわからなかった程度には、ジョン・ロックというやつは、鈍感なやつだった」ということくらいは言ってもいいかもしれないけれども。
ていうか、社会契約論に基づく国家主権の正当化や、大幅にダイジェストした場合の国家権力の根源としての人権思想を批判する際に、それらの間違いの責任をジョン・ロックに集約しようとするのは、ちぃっと乱暴だと思うんだよなあ。トマス・ホッブズの思想についていけなかったその世代の愚鈍な知識人たちが集団的に間違えたのである、とした方が正しいんじゃないんだろうか。
ついでなのだが、トマス・ホッブズは別に特にクローズアップして言及してはいなかったと思うんだが、「人権」なるもの。
この「人権」というのは、もともと誰もが持っているものとかではなく、至上のものでも当然の前提となるものでもなくて、この社会契約に基づく「他者に尊重される部分」のことなんだと、おれは理解している。「基本的人権」という概念は、いちいちその先まで遡って確認するのもめんどくさいから「公理」としておきましょう、という議論打ち切り基準という意味合いが強いんではなかろうか。
ま、「公理」ですからその命題が正しいかどうかは別問題なんですが、「公理=正しいからそれ以上考える必要がないこと」と理解するという誤解は根強い。ただ、誤解は根強いのだが、それは「公理概念」に関する誤解なのであって、「人権概念」に特別に誤解が生じているわけではないだろうとも思う。なにはともあれ「人権は最大限に尊重すべきもの」みたいに教えてしまう現在の教育にももちろん問題はあって、それが公理概念としての「人権」を更なる誤解に導いているということは言えるんだけどね。
いやあ。社会契約論についておれが悩んだポイントは過去に2つほどあって。
ひとつは、犯罪者の位置づけという法哲学的論点。犯罪というのは、特に殺人などの自然的犯罪というのは、社会契約に反する行いであるがゆえに処罰が可能であると構成されるものなのだが、じゃあいったいいつどこで処罰の客体となる者が社会契約を結んだことにすればいいのかというのが、よくわからない。人間の始期の段階で自然に契約を結んだことが擬制される、とかってのはちぃっと乱暴だろう(=^_^;=)。というか、相互非殺人などの社会契約をそもそも締結していないと主張された場合、その殺人者をどういう根拠で処罰できるんだろうか、という論点。
もうひとつは、人間外の存在と人権とのかねあいという論点。たとえば希少な猛獣と人間との摩擦が生じた場合に、どこまで人命(つまり、基本的人権のひとつである生存権)を尊重すればいいのかという論点。相手が人間であり社会契約を前提とできるのならば、その社会契約に基づいて善悪を判断できる。しかし相手が人間ではなく、明らかに社会契約を結んでいない場合、そこに「人権」という視点を持ち込むことに意味はあるのか。これは自然保護訴訟など必ずしも人間の利害のみでは完結しない対立についてどのようにして法的枠組みに取り込んでいくかというあたりで、争点となってくる場合があります(「人命のためならば何をやっても許される」といった極端な考え方は、しばしば人間界の枠を越えてはみ出してしまい、人間以外の存在に迷惑を及ぼすということです。「人命」を「幸福追求権」などの他の人権にまで拡張すると、その問題点はさらに顕著なものとなる)。
いずれにせよ、社会契約・国家主権・人権のいずれもが「人間界の中のローカルルールである」というあたりの基本をふまえておけば、さほど深刻な対立要因とはならないような気がしているんですけどね。「人間界にとってはとても重要ではある。しかしたかが人間界のローカルルールなのであり、人間界のローカルルールにすぎない」という二面性を過不足なく理解しておけば済む話なんである、と。
前半のさらに一部、「とても重要」だけが一人歩きしているような状況はあって、それは間違っているのだけれども、ただ本書のように「それは重要なものではない」と一方的に主張されても、それはそれで違うんじゃないかという気がする。「たかが、されど」みたいなもんだね。
*
もうひとつ、投票による民主主義の制度としての評価について。
こういうものに絶対評価がなじむのかどうかよくわかりませんが、「投票による民主主義」を絶対評価するとしたら、まあ「ろくな制度じゃない」というのが正当な評価だろうと、おれも思います。「投票による民主主義」が唯一絶対の正しい方法論であるかのように扱われている気配があるんだが、それは明らかに間違っている。投票による民主主義が失敗した事例なんてのはいくらでもある。ワイマール共和国が投票による民主主義によって崩壊しナチス政権が誕生したことを「投票による民主主義の失敗」と位置づけることは可能だろうし、20世紀末から21世紀にかけて極東の日本という国で投票による民主主義のせいで政治がぐちゃぐちゃに混迷したという事例を「投票による民主主義の失敗」のリアルな事例として取り上げることも可能だろう。ギリシャ時代から現代に至るまで、「投票による民主主義の失敗」の事例は、山積みになっている。
問題なのは、相対評価をしたときにどうなるかってことの方だね。
投票による民主主義以外の統治制度としては、とりあえず「絶対王政」ってやつがあります。類似品だが「独裁制」や「神権政治」なんてのもある。いまのところ明確な定義はないが、というか具体的な制度提案はないが、「投票によらない民主主義」てのもあるかもしれない。
それらのうちのどれかが「投票による民主主義」よりもましな制度であるのなら、さっさと「投票による民主主義」なんか捨ててそのよりましな制度に乗り換えるのが吉というものだろう。
問題なのは、「絶対王政」にせよ「独裁制」にせよ「神権政治」にせよ、それらはそれらでけっこうな数の失敗の事例を積み重ねて来ているということだ。
うまくころがれば「投票による民主主義」だってそれなりに機能することがあるだろうし、現代思想では極悪なもののように受け止められている「独裁制」だって良い独裁者を得られれば悪いものじゃないだろう。だからといって、うまくいった事例があることを理由として、特定の制度を持ち上げることが正しいようには思えない。
なんていうかこう、すべての制度は、同じくらいに「ろくな制度じゃない」ということを前提とした上で考えるべきであるのだが、ろくな選択肢はないんだけれどもしかしわれわれは、それらの「いずれも等しくろくなもんじゃない制度」からどれかを選ばなければならないという、そういう状態に置かれているのだ。救いがないかもしれませんが、でもどうせ救いがないのなら、それを真正面から認めておいた方が気が楽だ。
その中で「投票による民主主義」は、「失敗は、特定の誰かのせいで起きたものではなく、自分らひとりひとりの責任で起きたのだ」ということを引き受けさせるという観点からは、それなりに有効なのではないだろうかと、おれは思ってます。まあ、「失敗したのは政治家のせい」とか言ってしまって自分の責任を認めない有権者とかってのも多数いるわけだから、そういう意味では「投票による民主主義が有権者に当然に求める責任」てのも形骸化しているのかもしれませんが。
制度としての「投票による民主主義」なんてものは、要するに制度でしかなく、道具でしかないわけです。まあ確かに、百円ショップで売っている工具のように「出来の悪い道具」ってのはあるわけだしスナップオンの工具のように「すばらしい出来の道具」てのもあるわけだが、しかし道具は道具なんで、うまくいかない理由を道具のせいにしてもはじまらないんじゃないんだろうか。
「投票による民主主義」という道具は、至上の価値を持つ絶対の道具なわけではない。それは確認しておかなくちゃいけないし、あたかも至上の価値を持つ絶対の道具ででもあるかのように教育されてしまうという現状はオカシイとおれは思う。ただ、使い方によっては有益にもなる道具なんであって、否定してどうなるってものでもない。
著者は、結語の章で「(投票による)民主主義とは『人間に理性を使わせないシステム』である」と述べているし、実際そういう側面はあるだろうと思う(そしてなぜか、その後突然、著者は聖徳太子による「十七条憲法」を持ち出してくるのだが)。しかし人間に理性を使わせるのってたいへんにむずかしいことなのであって、それはどの道具を選ぶかによって解決できるような楽な問題ではないのではないんだろうか。
そんなこんなで、「本書は、なんか問題の所在を決定的に見誤っているのではなかろうか」という残念な読後感につながっていったのでありました。
*
腰巻のフレーズは編集者がつけるものであり著者には責任はないと思うんだが、本書の腰巻には「これでもあなたは民主主義を信じますか?」という惹句がつけられています。いやあ、(投票による)民主主義というものは「道具」なのであって、信じたり信じなかったりする対象ではないだろう。この腰巻の惹句こそが、実は本書が道を誤ったことの象徴になっているのではないだろうか、とか最後にイヤミを書いて、この書評を締めようと思います。
ではまた。 続きを読む
なお、どうせ長くなるし、興味がないひとには徹底して興味がないネタになろうかとも思うし、このWeblogの客層的にはどうなのかなあとも思います。なので「自分向けじゃないな」と思ったひとはさくさく飛ばしてしまうことをお勧めします。ちょっといろいろありまして、ここらへんの思想関連のネタも、不十分ながら文書化しておきたい事情ができてきたんすよ。本来なら別のWeblogでも立ち上るとかしてそっちでやるべきなのかもしれないんだけどね。
では、参ります。
一発目は、文春新書の『民主主義とは何なのか』長谷川三千子。遠慮会釈なく貶しちゃいます。貶すのってけっこうムズカシくて、一歩間違うとダークサイドフォースに足を取られることになっちゃうんですけどねー、うまくいくんだろうか。

『民主主義とは何なのか
文春新書191
ISBN4-16-660191-1 C0230
2001年9月20日初版初刷
いやあ、残念な本だ。全面的にクズ本なわけではなくて、部分的には見るべき部分はあるし興味深い分析もあるんだけど、根本のところがどうもダメっぽい。どうも著者は思想的には右翼傾向を持っているようなのだが、その結果目が曇ったっていうか、ウヨってやっぱダメなのかな、という感じ。ここまでちゃんと調べてお勉強をしているのに、しかしなんだってまた根底のところで道筋を間違ったまま行っちゃうかなあ。
基本線として、「民主主義」を絶対視することに対して、異議を唱えている本です。もっと厳密に定義すると、「投票による民主主義」が対象ですね。「投票によらない民主主義なんてものがあるのか」というのは、今回はツッコミになんないのでそこんところヨロシク。
んで、それを至上のもの・当然の前提として扱うことに対する異議申し立て。まあ、投票による民主主義なんてろくなもんじゃありませんから、それは良しとします。ていうか、そこらへんには同意したから買ってきたわけだけどさ。
ただ、どうも著者の頭の中では、「投票による民主主義は、日本にはもともとは存在せず、欧米から持ち込まれたものである→だから日本にはなじまない」という物語が存在しているようなんですね。「そんなものを持ち込んだがゆえに第二次世界大戦敗戦後の日本は道を間違えたんだ」とか言いたそうであります。基本線、その路線で「投票による民主主義」を批判するという骨組みを作ってしまっている。しかしいくらなんでもそれは違うだろうと、おれは思うわけです。投票による民主主義なんてわりと誰もがすぐに考え付く方法論だし、日本にだって当然あったんだからさ(次回の『百姓から見た戦国大名』で詳説)。
その先の章では、ギリシャ時代からフランス革命などを経て近代まで、欧米における投票による民主主義に対する分析と批判が展開されます。この部分は、まあそれなりに精緻に組み立てられていると言えるし、読む価値はある・・・と思う。このあたりの分析は、ジョン・ロックに全ての責任があるかどうかというあたりを除いて、おれの分析とさほど食い違わない。まあ、かなり煽りぶっこんでいるのが気になるし、目次を見ればわかる通りで「インチキ」「ペテン師」「プロパガンダ」などの否定的言辞が垂れ流されていることからけっこう感情的に書いているんじゃないかという懸念が禁じ得ないんだけど。
というわけで、分析部分などには見るべきところがあるのだが、基本骨格のところでコケちゃっているので、おれ的な評価は「残念な本」ってことになるわけ。
古来の日本には投票による民主主義はなかったのか。いやあ、あったんすよね、それもかなり古い時期から。「投票」「選挙」とは呼ばれておらず「入札(いれふだ)」と呼ばれていたのですが。入札がはじまった時期をおれは知らないんだけれども、戦国時代にはすでに確立された風習となっていた。へたすりゃそこから1000年くらいは遡るのではないか。そして、それは江戸時代も貫いてずーっと惣村の統治機構として存在し続けており、明治時代になだれ込んでいる。
惣村における「投票による民主主義」がそれだけでは立ち行かなくなった理由あたりは次回の『百姓から見た戦国大名』の書評で触れます。そのあたりは洋の東西を問わずみんな似たような失敗をやってきてるわねー、って感じ。ある意味、相互に関係なんかないままにしかし同じように失敗するというこの普遍性こそが、投票による民主主義が抱える根本的な問題を明らかにする現象であり、その問題点を解析するための手がかりになるんではないかとかおれは思う。なんでそういうおいしい題材がすぐそこにころがっているのに、「日本は違う」とかいうお馬鹿な思い込みで、そこをスルーできちゃうのかがおれにはよくわからない。
いずれにせよ、「投票による民主主義は、ギリシャ時代から続く欧米固有の思想であり、日本にはなじまない」という立ち位置はおかしい。そこがおかしい以上、今の日本がうまく動いていないとしても、その理由を「むりやり西欧の思想を輸血したせいである」とかいうあたりにこじつけるのは、無駄っていうか、間違いっていうか、徒労というか、そういうものにしかなり得ない。んなこと言うたかてなんら意義ある提案にも提言にもなりゃしませんぜ、ってことになります。
*
近世ヨーロッパにおける社会契約論との関係の部分について。
社会契約論は、「第四章 インチキとごまかしの産物 − 人権」において、民主主義思想の根源とされる人権がどのようなものであったのかについての考察部分で、その理論的支柱をどう受け止めるべきなのかという観点で、言及されています。
著者は、トマス・ホッブズの社会契約論をジョン・ロックが換骨奪胎したことが、人権概念が異常に肥大化するという結果を導いたとして、ジョン・ロックを激しく非難しているのですが、なんかそれは違うような気がする。
トマス・ホッブズ(1588〜1679)が『リヴァイアサン(1651)』によって提示した社会契約論の新しい切り口と(あくまでも「新しい切り口」。トマス・ホッブズがはじめて社会契約論を提示したわけではない)、その後に展開された社会契約論を基礎とする国家主権論、国家主権の根底となるものとして位置づけられた人権思想との間には、かなりの乖離があるのは確かだ。本書の指摘通りに「なんか流れがおかしい」とは、おれも思うのである(ただし、トマス・ホッブズ以前の社会契約論も含めて眺めるなら、単に「トマス・ホッブズが異端だった」と位置づけることも可能。その異端のトマス・ホッブズの説が注目すべき新たな視点を提供したものである、という点は見落とせない重要な点なんだけれども)。
本書では、トマス・ホッブズの思想を換骨奪胎したのはジョン・ロック(1632〜1704)であるとし、そのジョン・ロックが実はペテン師でありインチキをぶちまいて民主主義思想をゆがめたのだ、としています。まあそこらへんについておれはちゃんと裏を取っていないし、その分析が正しいかどうかについての断定的な判断は避けようと思いますが。
トマス・ホッブズの社会契約論とは、簡単に説明すると、こんな感じになるでしょうか。
ルールなき状態(これをホッブズは「自然な状態」と考えた)では、人間同士は闘争的な対立関係となる。欲があるから、自然にそうなる。そこでは、たとえば「殺し合い」も当然のこととされる。しかし人間誰しも自分が殺されたくはない。そこで、殺されたくない者同士で、「わたしはあなたを殺さない。そのかわり、あなたもわたしを殺さない」と相互に約束(双務的な契約)をする。つまり、「自分が相手を殺す権利、あるいは自分が相手を殺すという選択肢」を相互に放棄しあうことで、闘争的関係を終わらせることができる。それが「社会契約(Social Contract)」である。社会のルールは、この「社会契約」によって正当化される。
それまでは、社会のルールは「神」などの人間社会にとって外的な存在によってしか正当化され得なかったが、この「ホッブズの社会契約論という思想」は、社会のルールの力の根源を人間界の中に持ち込み、社会を人間界の中で完結させることができるようにしたという点で画期的でした。
ホッブズ以前にも社会契約論というのは存在していました(本書は、ホッブズ以前の社会契約論の流れには、ほとんど触れていない。天賦人権説にはちょっとだけ触れているけれども)。『戦争と平和の法(1625)』で有名なグロティウス(1583〜1645)あたりも社会契約論に言及していたらしいな。おれはグロティウスのそういう側面をほとんど知らなかったが。
ホッブズ以前の社会契約論に共通することは、「自然な状態では、人間は自由で平等であり幸せであった」という原始共産制みたいな感覚で自然な状態を規定していたことだったらしい(おれはそこんところに、旧約聖書の「エデンの園」につながるような、ユダヤ教以来の宗教感覚があるように感じたりするのだけれども)。「自然な状態は、闘争状態であった」とするホッブズの社会契約論は、そのユートピア的前提を崩したところに意味がある。トマス・ホッブズの思想の特徴でありいちばん輝かしいところは、この自然状態の定義の部分であり、そこを高く評価していることについて、著者は正しい。ただ、その後のところがなぁ。
社会契約論という大枠の流れの中ではトマス・ホッブズの後継世代であるジョン・ロックやジャン・ジャック・ルソー(1712〜1778)は、当初の自然な状態を「闘争状態」ではなく「自由で平等で平和な状態」と規定しており(つまり「先祖返り」してしまっており)、従って「自らの権利をみんなが少しづつ差し出すこと」を社会契約であるとは位置づけていません。そこんところを、著者は「ジョン・ロックというペテン師がインチキをやった」と述べている。
しかしなー。トマス・ホッブズの位置づけが難しくなるという問題はあるんだけど、ジョン・ロックはトマス・ホッブズの後継者なのではなくて古典的社会契約論系の思想の後継者であると規定するならば、「ジョン・ロックは、異端的社会契約論のトマス・ホッブズの思想をつまみ食いして、自分の主張に取り入れた程度である」と考えることもできる。ていうか、その方が適切なんじゃないんだろうか。そう考えた場合、ジョン・ロックは、「それまでの主流だった社会契約論に則って思想を組み立てただけであり、トマス・ホッブズの思想を換骨奪胎したペテン師でインチキヤローである、とまで言うのは言いがかり」ってことになるような気がする。まあ、「少なくとも、トマス・ホッブズの説のすごさがわからなかった程度には、ジョン・ロックというやつは、鈍感なやつだった」ということくらいは言ってもいいかもしれないけれども。
ていうか、社会契約論に基づく国家主権の正当化や、大幅にダイジェストした場合の国家権力の根源としての人権思想を批判する際に、それらの間違いの責任をジョン・ロックに集約しようとするのは、ちぃっと乱暴だと思うんだよなあ。トマス・ホッブズの思想についていけなかったその世代の愚鈍な知識人たちが集団的に間違えたのである、とした方が正しいんじゃないんだろうか。
ついでなのだが、トマス・ホッブズは別に特にクローズアップして言及してはいなかったと思うんだが、「人権」なるもの。
この「人権」というのは、もともと誰もが持っているものとかではなく、至上のものでも当然の前提となるものでもなくて、この社会契約に基づく「他者に尊重される部分」のことなんだと、おれは理解している。「基本的人権」という概念は、いちいちその先まで遡って確認するのもめんどくさいから「公理」としておきましょう、という議論打ち切り基準という意味合いが強いんではなかろうか。
ま、「公理」ですからその命題が正しいかどうかは別問題なんですが、「公理=正しいからそれ以上考える必要がないこと」と理解するという誤解は根強い。ただ、誤解は根強いのだが、それは「公理概念」に関する誤解なのであって、「人権概念」に特別に誤解が生じているわけではないだろうとも思う。なにはともあれ「人権は最大限に尊重すべきもの」みたいに教えてしまう現在の教育にももちろん問題はあって、それが公理概念としての「人権」を更なる誤解に導いているということは言えるんだけどね。
いやあ。社会契約論についておれが悩んだポイントは過去に2つほどあって。
ひとつは、犯罪者の位置づけという法哲学的論点。犯罪というのは、特に殺人などの自然的犯罪というのは、社会契約に反する行いであるがゆえに処罰が可能であると構成されるものなのだが、じゃあいったいいつどこで処罰の客体となる者が社会契約を結んだことにすればいいのかというのが、よくわからない。人間の始期の段階で自然に契約を結んだことが擬制される、とかってのはちぃっと乱暴だろう(=^_^;=)。というか、相互非殺人などの社会契約をそもそも締結していないと主張された場合、その殺人者をどういう根拠で処罰できるんだろうか、という論点。
もうひとつは、人間外の存在と人権とのかねあいという論点。たとえば希少な猛獣と人間との摩擦が生じた場合に、どこまで人命(つまり、基本的人権のひとつである生存権)を尊重すればいいのかという論点。相手が人間であり社会契約を前提とできるのならば、その社会契約に基づいて善悪を判断できる。しかし相手が人間ではなく、明らかに社会契約を結んでいない場合、そこに「人権」という視点を持ち込むことに意味はあるのか。これは自然保護訴訟など必ずしも人間の利害のみでは完結しない対立についてどのようにして法的枠組みに取り込んでいくかというあたりで、争点となってくる場合があります(「人命のためならば何をやっても許される」といった極端な考え方は、しばしば人間界の枠を越えてはみ出してしまい、人間以外の存在に迷惑を及ぼすということです。「人命」を「幸福追求権」などの他の人権にまで拡張すると、その問題点はさらに顕著なものとなる)。
いずれにせよ、社会契約・国家主権・人権のいずれもが「人間界の中のローカルルールである」というあたりの基本をふまえておけば、さほど深刻な対立要因とはならないような気がしているんですけどね。「人間界にとってはとても重要ではある。しかしたかが人間界のローカルルールなのであり、人間界のローカルルールにすぎない」という二面性を過不足なく理解しておけば済む話なんである、と。
前半のさらに一部、「とても重要」だけが一人歩きしているような状況はあって、それは間違っているのだけれども、ただ本書のように「それは重要なものではない」と一方的に主張されても、それはそれで違うんじゃないかという気がする。「たかが、されど」みたいなもんだね。
*
もうひとつ、投票による民主主義の制度としての評価について。
こういうものに絶対評価がなじむのかどうかよくわかりませんが、「投票による民主主義」を絶対評価するとしたら、まあ「ろくな制度じゃない」というのが正当な評価だろうと、おれも思います。「投票による民主主義」が唯一絶対の正しい方法論であるかのように扱われている気配があるんだが、それは明らかに間違っている。投票による民主主義が失敗した事例なんてのはいくらでもある。ワイマール共和国が投票による民主主義によって崩壊しナチス政権が誕生したことを「投票による民主主義の失敗」と位置づけることは可能だろうし、20世紀末から21世紀にかけて極東の日本という国で投票による民主主義のせいで政治がぐちゃぐちゃに混迷したという事例を「投票による民主主義の失敗」のリアルな事例として取り上げることも可能だろう。ギリシャ時代から現代に至るまで、「投票による民主主義の失敗」の事例は、山積みになっている。
問題なのは、相対評価をしたときにどうなるかってことの方だね。
投票による民主主義以外の統治制度としては、とりあえず「絶対王政」ってやつがあります。類似品だが「独裁制」や「神権政治」なんてのもある。いまのところ明確な定義はないが、というか具体的な制度提案はないが、「投票によらない民主主義」てのもあるかもしれない。
それらのうちのどれかが「投票による民主主義」よりもましな制度であるのなら、さっさと「投票による民主主義」なんか捨ててそのよりましな制度に乗り換えるのが吉というものだろう。
問題なのは、「絶対王政」にせよ「独裁制」にせよ「神権政治」にせよ、それらはそれらでけっこうな数の失敗の事例を積み重ねて来ているということだ。
うまくころがれば「投票による民主主義」だってそれなりに機能することがあるだろうし、現代思想では極悪なもののように受け止められている「独裁制」だって良い独裁者を得られれば悪いものじゃないだろう。だからといって、うまくいった事例があることを理由として、特定の制度を持ち上げることが正しいようには思えない。
なんていうかこう、すべての制度は、同じくらいに「ろくな制度じゃない」ということを前提とした上で考えるべきであるのだが、ろくな選択肢はないんだけれどもしかしわれわれは、それらの「いずれも等しくろくなもんじゃない制度」からどれかを選ばなければならないという、そういう状態に置かれているのだ。救いがないかもしれませんが、でもどうせ救いがないのなら、それを真正面から認めておいた方が気が楽だ。
その中で「投票による民主主義」は、「失敗は、特定の誰かのせいで起きたものではなく、自分らひとりひとりの責任で起きたのだ」ということを引き受けさせるという観点からは、それなりに有効なのではないだろうかと、おれは思ってます。まあ、「失敗したのは政治家のせい」とか言ってしまって自分の責任を認めない有権者とかってのも多数いるわけだから、そういう意味では「投票による民主主義が有権者に当然に求める責任」てのも形骸化しているのかもしれませんが。
制度としての「投票による民主主義」なんてものは、要するに制度でしかなく、道具でしかないわけです。まあ確かに、百円ショップで売っている工具のように「出来の悪い道具」ってのはあるわけだしスナップオンの工具のように「すばらしい出来の道具」てのもあるわけだが、しかし道具は道具なんで、うまくいかない理由を道具のせいにしてもはじまらないんじゃないんだろうか。
「投票による民主主義」という道具は、至上の価値を持つ絶対の道具なわけではない。それは確認しておかなくちゃいけないし、あたかも至上の価値を持つ絶対の道具ででもあるかのように教育されてしまうという現状はオカシイとおれは思う。ただ、使い方によっては有益にもなる道具なんであって、否定してどうなるってものでもない。
著者は、結語の章で「(投票による)民主主義とは『人間に理性を使わせないシステム』である」と述べているし、実際そういう側面はあるだろうと思う(そしてなぜか、その後突然、著者は聖徳太子による「十七条憲法」を持ち出してくるのだが)。しかし人間に理性を使わせるのってたいへんにむずかしいことなのであって、それはどの道具を選ぶかによって解決できるような楽な問題ではないのではないんだろうか。
そんなこんなで、「本書は、なんか問題の所在を決定的に見誤っているのではなかろうか」という残念な読後感につながっていったのでありました。
*
腰巻のフレーズは編集者がつけるものであり著者には責任はないと思うんだが、本書の腰巻には「これでもあなたは民主主義を信じますか?」という惹句がつけられています。いやあ、(投票による)民主主義というものは「道具」なのであって、信じたり信じなかったりする対象ではないだろう。この腰巻の惹句こそが、実は本書が道を誤ったことの象徴になっているのではないだろうか、とか最後にイヤミを書いて、この書評を締めようと思います。
ではまた。 続きを読む
2011年02月06日
本>『ちばの鉄道一世紀』
いやあ、なんだな。
こないだ『鉄道忌避伝説の謎』のことを書いていたら、コメントの中で『ちばの鉄道一世紀』のことが出てきたんですよね。あーなんかそんな本があったなーなんて思っていたところ『ちばの鉄道一世紀』が書棚の中から手招きをしておりました。これは断じておれが買った本ではないんですが(=^_^;=)、たぶん買ったのは母親なんですが、なんでこんな本買ったかなあ。鉄道に興味があったようには見えなかったんだが。
てゆーか、おれももう読んではいたんですがどこに埋まっているかわからないのがうちの常でどうせ出てくるもんかと思っていたわけですが、出てきたもので読み直してみました。

ちばの鉄道一世紀
奥付を見て気づいたのですが、出版者としてはあまりメジャーとは言えない崙書房(ろんしょぼう・千葉県流山市に本社を置く、どちらかというと地方小出版系の会社です)の本なのに、わずか3ヶ月で増刷がかかっています。けっこう好評な本だったみたいです。もっとも、15年も前の本ですから新本での入手は難しいようです。閲覧時点で中古は3点で3800〜5500円とけっこう高くて、こちらからも高い評価を受けているらしいことがわかります。
そーですねー。基本線として概観本ですから、細かい情報がてんこ盛りとかいう本ではありません。目次情報(追記内にあります)を見てもらえばわかることだけど、収録路線は、JRが10路線、私鉄が18項目20路線、廃止路線が15項目18路線、計画線未成線が4路線。330ページの中にこんだけの路線を詰め込んでいますからね、ひとつひとつの鉄道は猛烈なスピードで走り抜けてしまいます。しかしまあこちら方面にあんまし興味を持っていないひととかにしてみれば情報てんこ盛り本なのかもしれません。とか言いつつしかし、ある特定の切り口からざーっと眺めて見るというのはそれなりに楽しいことではあるわけで。はい、楽しゅうございました。
著者の白土さんは以前から存じておりましたが、それはとにかく、地方史家(郷土史家)の執筆によるものなので、デフォルトでは警戒対象本です。ですが、ちゃんとした歴史研究者である中川浩一が推薦文を書いてますし、参考文献などもちゃんと記されており常識的な研究手段に基づいているものと思うことができ、それなりに意地悪くチェックをしつつ読みましたが明らかにおかしいところは見つかりませんでした。一昔前によくあったような書き飛ばし型の地方史ではなく、ちゃんとした概説本のレベルに達していると思います。
また、もともとはそういうわけで千葉日報の連載記事として書かれたものだそうですが、そうは思いにくい高い質に達していると言っていいんじゃないかなあとも思います。まあ、千葉日報ですからね、地方紙って、影響力を頼りに書き飛ばしをやるメジャー紙と比べるともともと質は高いのですが。
というかなあ。白土貞夫にせよ中川浩一にせよ、その筋では有名な鉄ヲタ(=^_^;=)ですからね、ヲタがヲタとしてのフォースを全力発揮したらこうなっちゃいました、ということなんじゃなかろうかという気がします。そういう方向でヲタパワーが機能するのならば、それはとても良いことだろう。ある意味、「鉄道ピクトリアル」や「鉄道友の会」の人脈が生み出した、ちょっと珍しい郷土史本とも言えるのではないかと思います。ときどきこういう本が出来上がってしまうから郷土史本とかって面白いんだよね、高い上に打率が悪いからなかなか買えないんだけどね(=^_^;=)。
不満もなくはなく。
元が新聞連載だったというスペースの都合のせいなんでしょうかね、地図情報がほとんどないというあたりが微妙な不満です。とはいえ古い写真や紙情報などの貴重な画像情報はそれなりに掲載されているんすよね。地図にはニーズがないという判断だったんでしょうかね。なんかよくわからない事情があったんでしょう(=^_^;=)。ていうか、おれが地図情報を他人より強く求めているってだけの話かもしれませんが。
*
しかしなんだねー。読み直して改めて思ったんですけど、千葉県って鉄道が多かったのねー。まあ東京の隣だから通勤用路線がぼろぼろあるのは当たり前かもしれませんが、世の中には新潟県みたいに私鉄が1本も残っていない県があったり、沖縄県みたいにそもそも鉄道が1本もない時代が長かった県があったりするわけで、それと比べるとこの数はいったい何なんだというくらいの数です。
埼玉や神奈川も鉄道は多いんだけど、大半が大手に買収されてしまってますよね。なんだってまた千葉県って、こう、会社数が多いままくることができたんだろう。ちなみに、おれが残存私鉄の中でもっとも気に入っているのは山万ユーカリが丘線です。「小湊鉄道だろ」とか予想したひと、ごめんなさいね(=^_^;=)。 続きを読む
こないだ『鉄道忌避伝説の謎』のことを書いていたら、コメントの中で『ちばの鉄道一世紀』のことが出てきたんですよね。あーなんかそんな本があったなーなんて思っていたところ『ちばの鉄道一世紀』が書棚の中から手招きをしておりました。これは断じておれが買った本ではないんですが(=^_^;=)、たぶん買ったのは母親なんですが、なんでこんな本買ったかなあ。鉄道に興味があったようには見えなかったんだが。
てゆーか、おれももう読んではいたんですがどこに埋まっているかわからないのがうちの常でどうせ出てくるもんかと思っていたわけですが、出てきたもので読み直してみました。

ちばの鉄道一世紀
奥付を見て気づいたのですが、出版者としてはあまりメジャーとは言えない崙書房(ろんしょぼう・千葉県流山市に本社を置く、どちらかというと地方小出版系の会社です)の本なのに、わずか3ヶ月で増刷がかかっています。けっこう好評な本だったみたいです。もっとも、15年も前の本ですから新本での入手は難しいようです。閲覧時点で中古は3点で3800〜5500円とけっこう高くて、こちらからも高い評価を受けているらしいことがわかります。
そーですねー。基本線として概観本ですから、細かい情報がてんこ盛りとかいう本ではありません。目次情報(追記内にあります)を見てもらえばわかることだけど、収録路線は、JRが10路線、私鉄が18項目20路線、廃止路線が15項目18路線、計画線未成線が4路線。330ページの中にこんだけの路線を詰め込んでいますからね、ひとつひとつの鉄道は猛烈なスピードで走り抜けてしまいます。しかしまあこちら方面にあんまし興味を持っていないひととかにしてみれば情報てんこ盛り本なのかもしれません。とか言いつつしかし、ある特定の切り口からざーっと眺めて見るというのはそれなりに楽しいことではあるわけで。はい、楽しゅうございました。
著者の白土さんは以前から存じておりましたが、それはとにかく、地方史家(郷土史家)の執筆によるものなので、デフォルトでは警戒対象本です。ですが、ちゃんとした歴史研究者である中川浩一が推薦文を書いてますし、参考文献などもちゃんと記されており常識的な研究手段に基づいているものと思うことができ、それなりに意地悪くチェックをしつつ読みましたが明らかにおかしいところは見つかりませんでした。一昔前によくあったような書き飛ばし型の地方史ではなく、ちゃんとした概説本のレベルに達していると思います。
また、もともとはそういうわけで千葉日報の連載記事として書かれたものだそうですが、そうは思いにくい高い質に達していると言っていいんじゃないかなあとも思います。まあ、千葉日報ですからね、地方紙って、影響力を頼りに書き飛ばしをやるメジャー紙と比べるともともと質は高いのですが。
というかなあ。白土貞夫にせよ中川浩一にせよ、その筋では有名な鉄ヲタ(=^_^;=)ですからね、ヲタがヲタとしてのフォースを全力発揮したらこうなっちゃいました、ということなんじゃなかろうかという気がします。そういう方向でヲタパワーが機能するのならば、それはとても良いことだろう。ある意味、「鉄道ピクトリアル」や「鉄道友の会」の人脈が生み出した、ちょっと珍しい郷土史本とも言えるのではないかと思います。ときどきこういう本が出来上がってしまうから郷土史本とかって面白いんだよね、高い上に打率が悪いからなかなか買えないんだけどね(=^_^;=)。
不満もなくはなく。
元が新聞連載だったというスペースの都合のせいなんでしょうかね、地図情報がほとんどないというあたりが微妙な不満です。とはいえ古い写真や紙情報などの貴重な画像情報はそれなりに掲載されているんすよね。地図にはニーズがないという判断だったんでしょうかね。なんかよくわからない事情があったんでしょう(=^_^;=)。ていうか、おれが地図情報を他人より強く求めているってだけの話かもしれませんが。
*
しかしなんだねー。読み直して改めて思ったんですけど、千葉県って鉄道が多かったのねー。まあ東京の隣だから通勤用路線がぼろぼろあるのは当たり前かもしれませんが、世の中には新潟県みたいに私鉄が1本も残っていない県があったり、沖縄県みたいにそもそも鉄道が1本もない時代が長かった県があったりするわけで、それと比べるとこの数はいったい何なんだというくらいの数です。
埼玉や神奈川も鉄道は多いんだけど、大半が大手に買収されてしまってますよね。なんだってまた千葉県って、こう、会社数が多いままくることができたんだろう。ちなみに、おれが残存私鉄の中でもっとも気に入っているのは山万ユーカリが丘線です。「小湊鉄道だろ」とか予想したひと、ごめんなさいね(=^_^;=)。 続きを読む
2011年01月08日
本>佐々木譲の、面白いけどなぜか感動のない作品群
そういうわけで、おれには気に入った作家が何人かいます。佐々木譲はその最右翼。過去にも幾度となくこのWeblogでも言及しています。ま、全作品を漏れなく読んでいるというほどの熱心な読者ではありませんし、どうにも合わずに読まないことにしている作品群もありますが(北海道ウェスタン系とかは、おれはだめだなあ)。おれはそれが誰であろうとも信者になる気はないので、まあまあ健全な感覚かなあと思うわけですが。
ところで、その佐々木譲の作品の中でわけわからないのが、「たいへんに面白いのだが、なぜか感動がない作品群」というやつ。面白いんですよ。だから、ものすごいスピードで読み進んでしまったりします。最近読んだ『疾駆する夢』なんて、文庫本上下1400ページの大部の作品なんですが、イキオイで一晩で読み終わりそうになり、あまりにもったいないのでなんとか途中で打ち切って二晩に分けたくらいで。
しかし読み終わったところで、不思議なくらいに感動がないんですね。「あ、終わった」みたいな感じ(=^_^;=)。これはいったいなんだ、というのを考えはじめちゃったわけです。
ぱっと思い浮かぶところで、このカテゴリに該当するのは以下の2作品。
この『警官の血』は、三代にわたる警視庁警察官の家系を追った大河小説。第二次世界大戦敗戦後の大量採用期に警官になりその後芋坂跨線橋から転落死した初代、新左翼への潜入操作を命じられ公安警察官として大手柄をあげたが人格が崩壊し薬物事犯の逮捕に際して殉職した二代目、知能犯部門の刑事として綱渡りをしつつ実績をあげていく三代目、の三代記です。
最近、初代と二代目が勤務したことになっている天王寺駐在所をはじめとする場所の舞台めぐりをしてきたのはすでにご報告した通り。日暮里駅脇の芋坂跨線橋も第一部のエンディングに登場しています。
この『疾駆する夢』は、第二次世界大戦後に会社を起こして自動車の大メーカー(っていうか中堅メーカー)にまで育て上げた経営者の一代記です。メーカーは架空の「多門自動車」と名づけられていますが、まあホンダや松下やソニーを彷彿とさせるなかなかにエキサイティングな物語です。こちらはまぁ、舞台めぐりはやってません。
やー。いずれも面白いんですよ。
なんていうか、どちらも大河小説ですから前半から中盤にかけてはものごころついて以降のおれの人生と重なってなくてあんまし実感はないんですが、個々のエピソードを構成するできごとは、それなりに知識があるものが多い。ああ、あの頃はそういう時代だったのね、といった部分はあるわけです。
たとえば『警官の血』では、敗戦直後の上野の浮浪児やヤミ市とか安保闘争(1960年と1970年)とか大菩薩峠事件(1969年。これは第二次安保闘争に関するもの)とか。『疾駆する夢』では、1963年から行われたことになっているル・マン24時間耐久レースへの挑戦とか(時代は10年違うんだが、1973年からのシグマ・オートモティヴという日本のチームによるル・マン挑戦を、ちょっと思い起こさせる)、マスキー法対策での大騒ぎ事件(1970年頃)とか。個々のエピソードは、とても綿密な調査・取材に裏付けられて組み立てられており、面白い。でも、そういう念入りな調査に裏付けられて組み立てられた数十年分の膨大なエピソードを読み通すと、そこにはその膨大なエピソードを受け止めるオチらしきものがないままに、すんなり物語が終わってしまうというか。
おれ、なにがなんでもオチをつけろっていう感覚はないような気がするんですよね。世の中、実際にはそうそうオチなんかつかないってのはわかってますし。また『疾駆する夢』のもしかするとオチかもしれないエピソードがおれにとってオチではないのは、だいぶ前の文庫版下巻1/3あたりで見えてしまっていたからかもしれず(ああ、冒頭から触れられている新社長ってこいつの息子か娘なのね、ということ)、そうだったらそれはおれの特殊事情。
でね。なんかまあ、普通はこう、「読んだどーっ」みたいなそれなりの感動があるわけだけど、それがない。それはないんだけど、ないことが不満なわけでもない。これって、すんごく珍しい読後感なんですよ。この奇異な読後感が、けっこう興味深い。
まあそういうわけで、どこを切り取ってもそれなりに興味深いエピソードが散りばめられています。なのでおれは、ときおり手に取っては適当なページをひらいていくつかのエピソードを読む、みたいな読み返し方をしています。なんていうの、全体として大河小説かもしれないんですが、連作短編を拾い読みするみたいな読み方になってるのね。基本線として、おれはけっこう気に入っているのだろうけどなあ、なんか位置づけがうまく決まらない。
佐々木譲作品としては、どっちかっつうと「比較的短い時間に起きた出来事を、濃密に描き出す作品群」の方に、おれは感動します。
たとえば『ベルリン飛行指令 』だと、いろいろ前置きはあるけど主たる物語は零式艦上戦闘機が日本を飛び立ってベルリンに着陸するまでの間に展開されている。たとえば『エトロフ発緊急電
』だと、いろいろ前置きはあるけど主たる物語は零式艦上戦闘機が日本を飛び立ってベルリンに着陸するまでの間に展開されている。たとえば『エトロフ発緊急電 』では、これまたいろいろ前置きはあるけれども、主たる物語は、アメリカ合衆国のスパイであるケニー斉藤が日本に潜入したところから大日本帝国海軍の機動部隊が単冠湾を出航して真珠湾攻撃に向かうまでの間に展開されている。たとえば『夜にその名を呼べば
』では、これまたいろいろ前置きはあるけれども、主たる物語は、アメリカ合衆国のスパイであるケニー斉藤が日本に潜入したところから大日本帝国海軍の機動部隊が単冠湾を出航して真珠湾攻撃に向かうまでの間に展開されている。たとえば『夜にその名を呼べば 』では、さらにまたいろいろ前置きはあるんだけど主たる物語は「スパイの濡れ衣を着せられて東側に亡命した男が帰国してくるはずの前後半日程度」に圧縮されている。『真夜中の遠い彼方
』では、さらにまたいろいろ前置きはあるんだけど主たる物語は「スパイの濡れ衣を着せられて東側に亡命した男が帰国してくるはずの前後半日程度」に圧縮されている。『真夜中の遠い彼方 』に至っては、舞台は新宿歌舞伎町に限られ、プロローグとエピローグを除けば時間もそこでの凝縮された数時間だけだし、短編だけど『鉄騎兵、跳んだ
』に至っては、舞台は新宿歌舞伎町に限られ、プロローグとエピローグを除けば時間もそこでの凝縮された数時間だけだし、短編だけど『鉄騎兵、跳んだ 』ではモトクロスのスプリントレースがはじまって終わるまでの間に小説が終わってしまうのだからな(いや、カットバックはあるんだけどね)。
』ではモトクロスのスプリントレースがはじまって終わるまでの間に小説が終わってしまうのだからな(いや、カットバックはあるんだけどね)。
なんかこう、小説と読者との間には、あるいは小説家と読者との間には、いろいろな相性とかあるんでしょうね。おれの場合、他には海老沢泰久の場合、長編は相性が良いのだが、短編は徹底して合わなかったりします。二三冊は買ったのだけどあとはもう海老沢泰久の短編集は跨いで通ろうと思っているな(=^_^;=)。
おれにとって佐々木譲は、ある程度は長く、だけどとんでもなく長くはないような微妙な長さの長編小説で、しかも濃密な時間を切り取るタイプの作品がなじむ作家である、ということなのでしょう。
この佐々木譲の大河小説2作品は、こういう相性問題みたいなものを自覚するきっかけになったみたいな面があります。感動の有無を通じて、そういう「自分に還ってくる視点」を提供してくれた。
そういう点で、本読みとしてのおれにとってけっこう重要な作品群であるように感じています。 続きを読む
ところで、その佐々木譲の作品の中でわけわからないのが、「たいへんに面白いのだが、なぜか感動がない作品群」というやつ。面白いんですよ。だから、ものすごいスピードで読み進んでしまったりします。最近読んだ『疾駆する夢』なんて、文庫本上下1400ページの大部の作品なんですが、イキオイで一晩で読み終わりそうになり、あまりにもったいないのでなんとか途中で打ち切って二晩に分けたくらいで。
しかし読み終わったところで、不思議なくらいに感動がないんですね。「あ、終わった」みたいな感じ(=^_^;=)。これはいったいなんだ、というのを考えはじめちゃったわけです。
ぱっと思い浮かぶところで、このカテゴリに該当するのは以下の2作品。
 警官の血・上(新潮文庫) |  警官の血・下(新潮文庫) |
この『警官の血』は、三代にわたる警視庁警察官の家系を追った大河小説。第二次世界大戦敗戦後の大量採用期に警官になりその後芋坂跨線橋から転落死した初代、新左翼への潜入操作を命じられ公安警察官として大手柄をあげたが人格が崩壊し薬物事犯の逮捕に際して殉職した二代目、知能犯部門の刑事として綱渡りをしつつ実績をあげていく三代目、の三代記です。
最近、初代と二代目が勤務したことになっている天王寺駐在所をはじめとする場所の舞台めぐりをしてきたのはすでにご報告した通り。日暮里駅脇の芋坂跨線橋も第一部のエンディングに登場しています。
 疾駆する夢・上(小学館文庫) |  疾駆する夢・下(小学館文庫) |
この『疾駆する夢』は、第二次世界大戦後に会社を起こして自動車の大メーカー(っていうか中堅メーカー)にまで育て上げた経営者の一代記です。メーカーは架空の「多門自動車」と名づけられていますが、まあホンダや松下やソニーを彷彿とさせるなかなかにエキサイティングな物語です。こちらはまぁ、舞台めぐりはやってません。
やー。いずれも面白いんですよ。
なんていうか、どちらも大河小説ですから前半から中盤にかけてはものごころついて以降のおれの人生と重なってなくてあんまし実感はないんですが、個々のエピソードを構成するできごとは、それなりに知識があるものが多い。ああ、あの頃はそういう時代だったのね、といった部分はあるわけです。
たとえば『警官の血』では、敗戦直後の上野の浮浪児やヤミ市とか安保闘争(1960年と1970年)とか大菩薩峠事件(1969年。これは第二次安保闘争に関するもの)とか。『疾駆する夢』では、1963年から行われたことになっているル・マン24時間耐久レースへの挑戦とか(時代は10年違うんだが、1973年からのシグマ・オートモティヴという日本のチームによるル・マン挑戦を、ちょっと思い起こさせる)、マスキー法対策での大騒ぎ事件(1970年頃)とか。個々のエピソードは、とても綿密な調査・取材に裏付けられて組み立てられており、面白い。でも、そういう念入りな調査に裏付けられて組み立てられた数十年分の膨大なエピソードを読み通すと、そこにはその膨大なエピソードを受け止めるオチらしきものがないままに、すんなり物語が終わってしまうというか。
おれ、なにがなんでもオチをつけろっていう感覚はないような気がするんですよね。世の中、実際にはそうそうオチなんかつかないってのはわかってますし。また『疾駆する夢』のもしかするとオチかもしれないエピソードがおれにとってオチではないのは、だいぶ前の文庫版下巻1/3あたりで見えてしまっていたからかもしれず(ああ、冒頭から触れられている新社長ってこいつの息子か娘なのね、ということ)、そうだったらそれはおれの特殊事情。
でね。なんかまあ、普通はこう、「読んだどーっ」みたいなそれなりの感動があるわけだけど、それがない。それはないんだけど、ないことが不満なわけでもない。これって、すんごく珍しい読後感なんですよ。この奇異な読後感が、けっこう興味深い。
まあそういうわけで、どこを切り取ってもそれなりに興味深いエピソードが散りばめられています。なのでおれは、ときおり手に取っては適当なページをひらいていくつかのエピソードを読む、みたいな読み返し方をしています。なんていうの、全体として大河小説かもしれないんですが、連作短編を拾い読みするみたいな読み方になってるのね。基本線として、おれはけっこう気に入っているのだろうけどなあ、なんか位置づけがうまく決まらない。
佐々木譲作品としては、どっちかっつうと「比較的短い時間に起きた出来事を、濃密に描き出す作品群」の方に、おれは感動します。
たとえば『ベルリン飛行指令
なんかこう、小説と読者との間には、あるいは小説家と読者との間には、いろいろな相性とかあるんでしょうね。おれの場合、他には海老沢泰久の場合、長編は相性が良いのだが、短編は徹底して合わなかったりします。二三冊は買ったのだけどあとはもう海老沢泰久の短編集は跨いで通ろうと思っているな(=^_^;=)。
おれにとって佐々木譲は、ある程度は長く、だけどとんでもなく長くはないような微妙な長さの長編小説で、しかも濃密な時間を切り取るタイプの作品がなじむ作家である、ということなのでしょう。
この佐々木譲の大河小説2作品は、こういう相性問題みたいなものを自覚するきっかけになったみたいな面があります。感動の有無を通じて、そういう「自分に還ってくる視点」を提供してくれた。
そういう点で、本読みとしてのおれにとってけっこう重要な作品群であるように感じています。 続きを読む
2011年01月04日
本>日本初「水車の作り方」の本
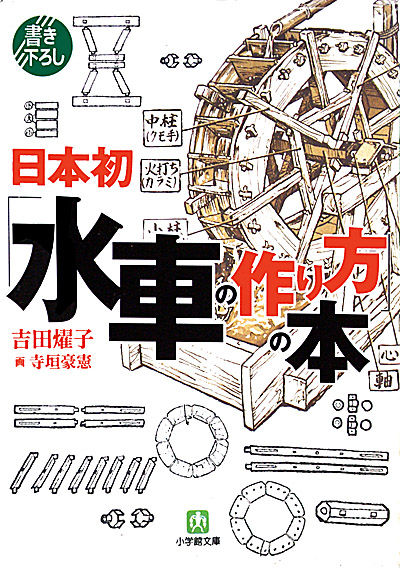
日本初「水車の作り方」の本 (小学館文庫)
どう説明すりゃいいのかなあ。なんだかよくわからない本です。あ、つまらなかったという意味ではありません。えーとこれは先に目次を紹介した方がいいんだろうなあ。というわけでまずは書誌情報と目次をどうぞ。
== 書誌情報 ==
日本初「水車の作り方」の本
著:吉田燿子 イラスト:寺垣豪憲
(講談社文庫552)
2000年8月1日 初版第1刷発行
講談社 ISBN4-09-411371-1
552円+税
==目次(簡略かつやや増補版)==
・口絵(巻頭グラビア)
・はじめに
・なぜ水車は“コットンコットンと回る”か
・水車作りに挑戦する
水車のイロハ
城端町を訪ねる
水輪作りに挑戦
動力部分を解剖する
<水車大工列伝1 野瀬秀拓>
・広げよう、水車の世界
楽しいからくり水車
揚水水車の世界
<水車大工列伝2 妹川矩雄>
・全国水車見て歩き
映画の中の水車(長野県穂高町・群馬県大間々町)
小鹿田の唐臼の響き・・・大分県日田市
鮭と水車の「真昼の決闘」・・・北海道千歳市
水車からくりが奏でる鎮魂歌・・・鹿児島県知覧町
・おわりに
・「水車の作り方」の寸法の目安
・もっと教わる、見に行くための問い合わせ先一覧
・参考文献
水車とひとくちにいっても、大別して2種類あります。ひとつはかったんこっとんのんびり回っている日本の原風景的な水車(一般的には木造)。もうひとつはびゅーんとまわっている発電用などの近代水車(一般的には金属製。マイクロ発電用小規模水車なんかはこっちの一分野でしょう)。本書は前者の水車を扱っています。
んで、専門書ではありませんね。小学館文庫で専門書を出してどうする。まあ、入門書ってことになるんですかね。ここに入門希望者がいるっていうか、入門書のニーズがあると思った編集者(文中では「Sさん」としか触れられていない)がなによりも凄かったってことかもしれません。
水車くらいはあちこちで見た覚えはあります。でも、せいぜい民家園なんかにある保存建築物・再現建築物として、あるいは観光用の装飾品・外装品として蕎麦屋が作りつけたもの、そのくらいしか見てないんですよね。とても珍しい、つまり一般的ではない建築物としてしか目にはいっていませんでしたから、知識があるかっつうと、おれにはありません。
本書が扱っているのはわりと初歩の知識、あるいは(作り方のあたりは)ある程度偏った知識なんだろうと思います。たとえば、こんなのどうよ。左から「下掛け」「胸掛け」「上掛け」と呼ぶらしい。左と右のものの存在は知っていましたが名前は知りませんでした。中央のタイプは存在すら知りませんでした。ほー、って感じ。

他にもこう、水車には大別して「動力用」と「揚水用」の2種類があるとか、地域や大工によって水輪(と呼ばれる円形の部品)をどう支えるかという補強の様式が異なるとか、基礎の基礎でおれが知らないこと、っていうか意識してこなかったことがずいぶんあるんだなぁ、とか。世の中には「水車キット」なる商品があってそれがけっこういいお値段で取引されているとかいうあたりも目鱗でございました。
水車の作り方あたりになると無駄に中途半端にディープな方向に暴走しているようにも思いましたが、「読んで楽しむ製作マニュアル」と思えばいいんだろうな。
ついでになんですなあ。「胸掛け」「上掛け」だと、水を貯める羽根部分の設計でずいぶん効率が違ってくるなんていう指摘も。あーそりゃそうだろうなあ。どういう設計だとより良い効率を得られるのかとか考え始めたらけっこう止まらなくなってしまいますた。こういうの、思考ゲームとしてけっこう面白いんだよなあ。どうでもいいんだけど下記。
 |  |  |
左が、比較的多く見られる放射状の水受板を持つ水車。上掛けの場合、円周の1/4の範囲で水の重さを回転力に変換することができますが、胸掛けの場合には衝動水車(水の勢いを使うもの)としては機能しますが、水の重さは無駄になります。
真ん中は、水受板に傾斜をつけた水車。この図では45度傾けていますが、一般には20度くらいまでらしい。45度で設計すると水を溜めることができる距離が円周の1/3くらいまで伸び、貯水量も増えますので、だいぶ効率は改善されます。
右は、おれがさっき思いついたもの。水輪の円周に沿って水溜板を追加。水を受ける口が狭まってしまいますが、水を溜めることができる距離は円周の1/2近くまで伸び、量は更に多くなりますから、上掛け・胸掛けのいずれであろうとも、水の重量をそれなりに効率良く回転力に変換できるはずです。水量は左端で満タンになるくらいでちょうどいいはずで、あとは水量と見比べて幅を決めればいい。いちばん左のやつと比べると、同じ水量で少なくとも4倍くらいの動力を発生させることができるはずです。
江戸時代に生まれて水車大工としてこれを思いついていたら、それなりに名工として言い伝えられていたかしらんなあ(笑)。でも水輪の半分くらいが板でふさがれている水車って、見慣れたものではないので、風景として美しいかどうかっつうと微妙なところだな(=^_^;=)。
本書の欠落点は、そうだなあ。水車の実用性のあたりでしょうか。
まあ今となっては、水車は動態保存+多少の実用性とか、観光目的の装飾用とか、そのくらいの位置づけしかないでしょう。でもまあ、もともとは実用性のあるものとして誕生し、重用されてきたものです。そういう側面での解説は、浅い。
現在では揚水ポンプと組み合わせればどんな水車でもそこそこ回せますけれども、ポンプアップされた水で回すのって邪道でしょう(ついでですが、観光用の下掛け巨大水車とかってのも、おれはくだんないと思う。下掛け水車だったら直径にはたいした意味がないじゃん)。
限られた自然水流でうまく回すにはどうしたらいいかという積み重ねられてきたのであろう知恵あたりにも、もうちょっと言及してほしかったなあ。
おれは特にこう水車に詳しくなろうと思っていないのですけどねー、でも必要性の薄い知識を学ぶのって楽しいものですからねー、そういう意味ではこういう軽い入門書っていいもんだわぁ。類似のベクトルの持ち主の方にとっては好適な本ではなかろうかと思うのでございます。
ただ、学術本ではないし筆者はかなり気をつけて信頼性を文面に反映している気配が感じられますが(つまり信頼性が薄い部分については伝聞形式にするなどしているように思えますが)、結果として根拠情報や文献を確認した上での信頼性の高い記述となっているとは限りません。まあなんていうの、教科書なんかもそうだけど、通説に属する範囲では書き飛ばしがある可能性があり必ずしも信じられるわけではない、という懸念が残る。おれだったら、別ソースを確認するまでは、この本を根拠としてなにかを主張することはないだろうなあ、という感じ。そういう本は少なくはないから特段のマイナス要因とはならないけどね(ふっ)。
評価。
★★★☆☆
ただまあ念のためだけど、そういうわけだから「入口としての価値」に限定しておきたい。
*
さてしかしここで話は終わらない。
いやね。あんまし買う気もないのですが、もっと詳しい木造水車造りの本とかないもんかなと思ってざっと探してみたんですよ。案外、みつからないものですねえ。「小型水車製作ガイドブック (自然エネルギー・ガイド)
さらにあっと驚いたことにはだな。
本の紹介をするにあたりいちいち書誌情報とかを細かく入力するのもめんどっちいなあアマゾンを頼ってしまおうかなあとか思ったわけですよ。本書については結局入力しちゃったけど。
んでこの本についてもリンクを貼って飛び先を見てみた。そしたらまあ、2000年8月に初版初刷の本だから新本の入手が無理なのはしょうがないんですが、中古本の値段がものすごいのね。調べた時点(2011/1/3閲覧)で7点出てるんだけど、4700円から8000円くらいのけっこうな値付けになってるんですよ。ほんの10年前に税別552円で売られてた入門書だぜ、なぜにしてそれが揃ってこのお値段に?(=^_^;=)
水車にどうしてこんなニーズがあるの? この文庫本、オークションとかに出せばそのくらいのお値段がついてしまう本だっていうの? ていうか、おれが知らないうちに世間では水車ブームが巻き起こっていたとかそういう話なんだろうか(違うな。だったら増刷かかってるはずだし)。
なんかこう信じがたいんですけど、誰か理由を知りませんか(=^_^;=)。
*
おまけのおまけ。
実物の水車・水車小屋はそういうわけであまり目にするものではなく、おれは「千葉県立房総のむら」のものと「川崎市立日本民家園」のものくらいしか写真を撮っていません。いずれも中は見ていない。
どこか近場で水車をじっくり見ることができる場所はないかなあ、と思って探したところ、わたらせ渓谷鉄道が走っている大間々の山奥、小平の里に野口水車保存館というのがあるらしかった。なんかデマンドバスが走っているらしいので、公共交通機関だけでたどりつけそうです。
精米動力として使われてきた屋内型の大型胸掛水車を持つ水車小屋が移築され、精米機器まできっちり復元の上で動態保存されているらしい。水車は10rpmのもので、動力軸3軸が連動しており、精米用の搗臼が16連、挽臼が1基、更に木製ベルトコンベアまであるという話。まあ、イメージとしては水車ってのどかなものだけど、当時としてはおもいっきし近代的な工業施設だったわけで決してのどか一方なものではなかったわけでな(=^_^;=)。
隣には屋外型上掛け水車もあるとのこと。
それから、上記「房総のむら」のものと「日本民家園」のものの再確認でしょうかねー。前者は搗臼2基、後者は少なくとも搗臼と挽臼がそれぞれ1基づつ、くらいの構成らしい。いずれも小規模なものではあります。
あと、ざーっと関東圏内で実用水車を探してみたところ、少なくとも以下のものがあるらしい。
・吉井水車小屋(千葉県南房総市吉沢)※実用
・駒村清明堂(茨城県石岡市小幡)※実用
・日光市大室の水車 ※実用
・武蔵野の水車経営農家(東京都三鷹市大沢6丁目)※有形文化財
商業装飾品ではない保存用・観光用のものではこんなところか。3行目以降はInfoAtlasというサイトで紹介されていたもの。
・板橋区立水車公園(東京都板橋区四葉)
・茨城県民の森(茨城県那珂市戸)
・山吹の里歴史公園(埼玉県越生町)
・根搦み前水田(東京都羽村市)
・薬師池公園(東京都町田市)
・向島用水親水路(東京都日野市)
・鍋島松濤公園(東京都渋谷区)
・片倉城跡公園(東京都八王子市)
・恩多野火止水車苑(東京都東村山市)
・青梅市郷土博物館(東京都青梅市)
・郷土の森(東京都府中市)
・小平ふるさと村(東京都小平市)
*
というわけで、ではまた。
2011年01月01日
本>『乗ろうよ! ローカル線』 - 第2章は面白かった
これもまた、「そらねっと通信局」さんに教えてもらった本です。
面白かったのは、第2章と、第4章の一部だけだったのだが、その2ヶ所がけっこうおれの興味にはまりましたねえ。読んでよかった。
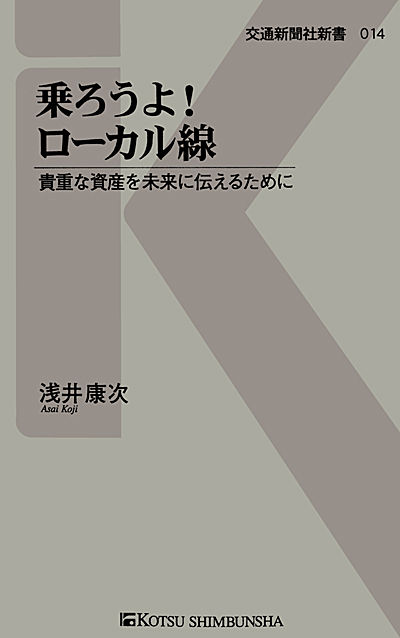

著者の浅井康次氏は日本政策投資銀行の重役行員で、プロの金融屋さんです。
えーと。おれは経済にはまるっきしうといっていうか、基本線興味はなくお勉強をする気もないので、率直なところこの本の対象読者ではないような気がします。しかしまあ、公共交通機関についていろいろ考える上でそちら方面の知識がぜんぜんないってのも大問題なので、ときにはこういう本も読んでみようかと。おれ的にはとても評価が高い阿川大樹さんの小説『D列車でいこう』をもっとちゃんと面白がるためにはある程度こちら方面の素養も必要だろうしなあ。
当然のこととして、おれには本書はあまり深く理解はできませんでしたが、しかし案外面白く読めたのでございます。
以下、章立ては「追記」内に記してある目次を参照のこと。
中でも興味深かったのは第2章「ローカル線の運営と展望」。よくわかっていない分際でこういうことを言ってはあかんのかもしれませんが、しょーじき食いたりないというか、もっとつっこんでほしかったなぁという感じ。後述。
第4章「路面電車は走る」は、もう一冊別の本を書けばって感じ。この章の中、「路面電車で町づくり」で触れられている「コンパクトシティ構想」ってけっこう重要な政策であり、さらっと紹介されている富山市の事例なんかはもっと詳しく知りたいとは思いましたが、まあこの一冊の中に押し込むのは紙幅が足らず無理という判断だったんだろうなと。ま、都市交通の話なんであって「ローカル線をどうすっか」という話とは微妙に違うという要素もあるし。
対して、第3章「“三セク鉄道だより”から」は、著者的には「数字が並ぶ硬い話ばかりでは読者が飽きるのではないか」という気遣いがあったようで、第三セクター鉄道等協議会の機関紙『三セク鉄道だより』からの転載でまとめられているものですけれども、おれ的にはこの本で現場の声を読みたいとは思わなかったなあ。各鉄道の現状紹介をするのなら、それは寄稿でやるのではなくて、著者の視点で情報の取捨選択をして書き直したもので読みたかった。
第5章「がんばれ観光鉄道」は、まあこれだけで一冊作るのは無理だろうから、この本に入れるしかなかったかもしれませんが(=^_^;=)、こちらもおれ的には場違いだった感じ。ていうか、ポイントがぼやけちゃったんじゃないだろうか。
つまるところが、おれ的には、「興味を惹かれたその2ヶ所をもっとふくらませた別の本が読みたくなったぞ」って感じです。
以下、もっぱら第2章がらみ。
指摘として興味深かったのは、そうだなあ。86ページあたりから述べられているタイプ別分析。
ここでは「A:人口希薄地の生活路線(過疎・生活型)」「B:一定人口集中地域における幹線の枝線輸送機能(フィーダー型)」「C:首都圏・中京圏・京阪神・北九州/福岡圏の通勤通学・レクリエーションなど(大都市圏補完型)」「D:中核都市(人口30万以上)における基幹または補完的交通機能(地方中核都市型)」に分類して分析をしているのですが、それぞれのグループの中でどのような要素を強化すれば改善が見込めるかというのを考察しています。
あっちゃー、という結果だったのが「A:」のグループ。因果関係を規定する数式を成立させることができず、「何をどうやっても改善は困難」という結論に。著者は「過疎生活型では自家用車などのとの競争はすでに決着(している)」「誤解を恐れずに言いますと、市場競争原理が過疎エリアにおいてはもはや働かなくなっており、そこでは事業者はたとえ運賃を半額にしても、新車を投入してスピードアップしたとしても、さしたる効果は期待できない」とまで述べています。
まあだからといって諦めて廃止しちゃえ、という結論にはつなげておらず、「事業者の自助努力には自ずと限界があり、クルマ社会にあるこれらの路線の維持については別段の配慮を要する」としてはいるのですが。
もうひとつ。
とかなんとか言いつつ、「赤字だとやっていけない」ことになっているわけです。いやあ、おれは赤字か黒字かだけで判断するようなこっちゃないだろ、と思っているわけですが、思うだけなら勝手なんだよねえ。
このあたりについて、第2章の最後に「費用便益分析でみる鉄道の重要性」という項目があって、そこで実にこう薄く触れられています。いやあおれ、この本の中でなによりもここが重要なんじゃないかとか思ったんですが。
紹介されているのは1999年に国が出した「鉄道プロジェクトに関する便益計算マニュアル」なるものだそうで。まあ手がかりはつかめましたから必要ならば原文にあたりゃいいんですけど。
引用すると「事業者の収支・採算だけでなく、鉄道利用者の時短効果・移動コスト低減効果や交通事故軽減効果、CO2排出削減効果、渋滞緩和などの諸便益を、投資などの費用と比較考慮してプロジェクトの採択を決すべき」というもの。いくつか具体的な数字(値段)も掲載されていますが(たとえばCO2排出量の削減については2300円/カーボン・トンで計算する、など)、まあ最終章でさらっと触れられているだけですから、それ以上のことは本書からはわからないんですが。
実践事例としては、上田交通別所線で行われた利用動向調査で「存在効果」なる便益の計算が行われたというものがあるそうです。
なんていうか、前に『D列車でいこう』の書評でも触れた「鉄道の機軸機能(「そこに継続的に公共交通機関があり続ける公算が強い」という信頼って、人がその場所に住み続ける上で、すごく重要なことなんじゃないんだろうか、ってやつ)」なんかも、便益計算には当然に繰り込まれるべきものでしょう。
このあたりが金額という数字でちゃんと出てくるようになれば、鉄道に公金をつっこむとしても、単なる「赤字補填」というような消極的な印象からはだいぶ離れ事態は好転するのではないだろうか、ということですね。
まあ、これ以上つっこむとなったら新書の扱い範囲としては微妙なんでないかという編集判断があったんでしょうねえ。専門書や報告書を探せばそれなりに面白く詳しい資料は出てくるんじゃないかとも思いますし、手がかりとしては十分。
ただまあなんていうかこう。『乗ろうよ! ローカル線』っていうタイトル、なんとかならんものだったんだろうか。このタイトルではしょもないローカル線ガイド本のようにも見えるわけで、内容を知らなければおれは手に取ることすらなかったような気がします。ついでに、サブタイトルの『貴重な資産を未来に伝えるために』とあわせると『乗って残そう○○線』系の机上の空論本にすら見えてしまうぞ、と(=^_^;=)。
ま、交通新聞社新書って2009年夏に刊行がスタートしたシリーズみたいですし、まだまだ編集サイドにも模索があるのでしょう。
というわけで、200ページあまりのうち50ページくらいだけがおれ的には興味を惹いた本ではあるのですが、案外評価は高かったのでございます。
★★★☆☆ 続きを読む
面白かったのは、第2章と、第4章の一部だけだったのだが、その2ヶ所がけっこうおれの興味にはまりましたねえ。読んでよかった。
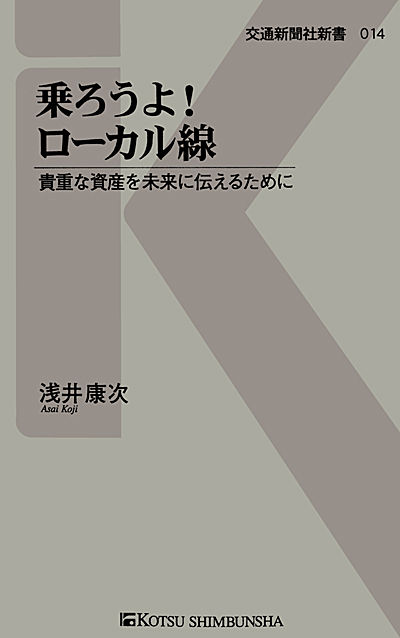
著者の浅井康次氏は日本政策投資銀行の重役行員で、プロの金融屋さんです。
えーと。おれは経済にはまるっきしうといっていうか、基本線興味はなくお勉強をする気もないので、率直なところこの本の対象読者ではないような気がします。しかしまあ、公共交通機関についていろいろ考える上でそちら方面の知識がぜんぜんないってのも大問題なので、ときにはこういう本も読んでみようかと。おれ的にはとても評価が高い阿川大樹さんの小説『D列車でいこう』をもっとちゃんと面白がるためにはある程度こちら方面の素養も必要だろうしなあ。
当然のこととして、おれには本書はあまり深く理解はできませんでしたが、しかし案外面白く読めたのでございます。
以下、章立ては「追記」内に記してある目次を参照のこと。
中でも興味深かったのは第2章「ローカル線の運営と展望」。よくわかっていない分際でこういうことを言ってはあかんのかもしれませんが、しょーじき食いたりないというか、もっとつっこんでほしかったなぁという感じ。後述。
第4章「路面電車は走る」は、もう一冊別の本を書けばって感じ。この章の中、「路面電車で町づくり」で触れられている「コンパクトシティ構想」ってけっこう重要な政策であり、さらっと紹介されている富山市の事例なんかはもっと詳しく知りたいとは思いましたが、まあこの一冊の中に押し込むのは紙幅が足らず無理という判断だったんだろうなと。ま、都市交通の話なんであって「ローカル線をどうすっか」という話とは微妙に違うという要素もあるし。
対して、第3章「“三セク鉄道だより”から」は、著者的には「数字が並ぶ硬い話ばかりでは読者が飽きるのではないか」という気遣いがあったようで、第三セクター鉄道等協議会の機関紙『三セク鉄道だより』からの転載でまとめられているものですけれども、おれ的にはこの本で現場の声を読みたいとは思わなかったなあ。各鉄道の現状紹介をするのなら、それは寄稿でやるのではなくて、著者の視点で情報の取捨選択をして書き直したもので読みたかった。
第5章「がんばれ観光鉄道」は、まあこれだけで一冊作るのは無理だろうから、この本に入れるしかなかったかもしれませんが(=^_^;=)、こちらもおれ的には場違いだった感じ。ていうか、ポイントがぼやけちゃったんじゃないだろうか。
つまるところが、おれ的には、「興味を惹かれたその2ヶ所をもっとふくらませた別の本が読みたくなったぞ」って感じです。
以下、もっぱら第2章がらみ。
指摘として興味深かったのは、そうだなあ。86ページあたりから述べられているタイプ別分析。
ここでは「A:人口希薄地の生活路線(過疎・生活型)」「B:一定人口集中地域における幹線の枝線輸送機能(フィーダー型)」「C:首都圏・中京圏・京阪神・北九州/福岡圏の通勤通学・レクリエーションなど(大都市圏補完型)」「D:中核都市(人口30万以上)における基幹または補完的交通機能(地方中核都市型)」に分類して分析をしているのですが、それぞれのグループの中でどのような要素を強化すれば改善が見込めるかというのを考察しています。
あっちゃー、という結果だったのが「A:」のグループ。因果関係を規定する数式を成立させることができず、「何をどうやっても改善は困難」という結論に。著者は「過疎生活型では自家用車などのとの競争はすでに決着(している)」「誤解を恐れずに言いますと、市場競争原理が過疎エリアにおいてはもはや働かなくなっており、そこでは事業者はたとえ運賃を半額にしても、新車を投入してスピードアップしたとしても、さしたる効果は期待できない」とまで述べています。
まあだからといって諦めて廃止しちゃえ、という結論にはつなげておらず、「事業者の自助努力には自ずと限界があり、クルマ社会にあるこれらの路線の維持については別段の配慮を要する」としてはいるのですが。
もうひとつ。
とかなんとか言いつつ、「赤字だとやっていけない」ことになっているわけです。いやあ、おれは赤字か黒字かだけで判断するようなこっちゃないだろ、と思っているわけですが、思うだけなら勝手なんだよねえ。
このあたりについて、第2章の最後に「費用便益分析でみる鉄道の重要性」という項目があって、そこで実にこう薄く触れられています。いやあおれ、この本の中でなによりもここが重要なんじゃないかとか思ったんですが。
紹介されているのは1999年に国が出した「鉄道プロジェクトに関する便益計算マニュアル」なるものだそうで。まあ手がかりはつかめましたから必要ならば原文にあたりゃいいんですけど。
引用すると「事業者の収支・採算だけでなく、鉄道利用者の時短効果・移動コスト低減効果や交通事故軽減効果、CO2排出削減効果、渋滞緩和などの諸便益を、投資などの費用と比較考慮してプロジェクトの採択を決すべき」というもの。いくつか具体的な数字(値段)も掲載されていますが(たとえばCO2排出量の削減については2300円/カーボン・トンで計算する、など)、まあ最終章でさらっと触れられているだけですから、それ以上のことは本書からはわからないんですが。
実践事例としては、上田交通別所線で行われた利用動向調査で「存在効果」なる便益の計算が行われたというものがあるそうです。
なんていうか、前に『D列車でいこう』の書評でも触れた「鉄道の機軸機能(「そこに継続的に公共交通機関があり続ける公算が強い」という信頼って、人がその場所に住み続ける上で、すごく重要なことなんじゃないんだろうか、ってやつ)」なんかも、便益計算には当然に繰り込まれるべきものでしょう。
このあたりが金額という数字でちゃんと出てくるようになれば、鉄道に公金をつっこむとしても、単なる「赤字補填」というような消極的な印象からはだいぶ離れ事態は好転するのではないだろうか、ということですね。
まあ、これ以上つっこむとなったら新書の扱い範囲としては微妙なんでないかという編集判断があったんでしょうねえ。専門書や報告書を探せばそれなりに面白く詳しい資料は出てくるんじゃないかとも思いますし、手がかりとしては十分。
ただまあなんていうかこう。『乗ろうよ! ローカル線』っていうタイトル、なんとかならんものだったんだろうか。このタイトルではしょもないローカル線ガイド本のようにも見えるわけで、内容を知らなければおれは手に取ることすらなかったような気がします。ついでに、サブタイトルの『貴重な資産を未来に伝えるために』とあわせると『乗って残そう○○線』系の机上の空論本にすら見えてしまうぞ、と(=^_^;=)。
ま、交通新聞社新書って2009年夏に刊行がスタートしたシリーズみたいですし、まだまだ編集サイドにも模索があるのでしょう。
というわけで、200ページあまりのうち50ページくらいだけがおれ的には興味を惹いた本ではあるのですが、案外評価は高かったのでございます。
★★★☆☆ 続きを読む
2010年12月30日
本>『鉄道忌避伝説の謎』 - なんかもやもやとした読後感
えー。前から読みたいと思ってたんですが、書泉ブックタワーにいったら在庫があったので入手してきました。タイトルに「なんかもやもやとした読後感」と入れてありますが、それは本の責任でも著者の責任でもありません。読んだおれの側の責任。そのあたりは、あとで詳しく。


最初に「鉄道忌避伝説」について確認。
鉄道黎明期に起きたとされる、「宿場町がすたれる」「養蚕業に悪影響が出る」「火災が起きる」などの今となっては理由にならないような理由によって、鉄道を拒否した町があったと言い伝えられている現象。各地にそういう話が残されており、信じているひとも多い。
しかしどうもそれは間違いっつうかうそっぱちっつうかであるらしい、鉄道忌避なんて現実にはなかったんではないか、というのが本書の主張。主張っていうか、もう歴史学界的には鉄道忌避なんかなかったというのが通説になっているようであり、これはその説明を目指した一般向けの啓蒙書ですね。なので「鉄道忌避伝説」と表現しています。おれもこの事象を語るときには、文脈上での判断を経て、おおむね間違いなく「伝説」をつけているなあ。
いまこれを読んで「え、鉄道忌避って事実じゃなかったの?」と思ったひと、この本はたぶんあなたにとって面白いから、ぜひ読んでみなはれ。
えーと。
この本の楽しみ方としては「検証可能性」とか「資料にあたることの重要性の指摘」とか「都市伝説の伝播の歴史」とかに絞った方がいいかもしれないんですが、そこには棹差しちゃう。ていうか、ごく普通に考えておかしいって思うことないですか、ほんのちょっと考えればおかしいとわかるようなことにはビンカンに気づけた方がいいですぜ、みたいな話にしてしまおうと思うわけですよ。ゴリ押しだなぁ(=^_^;=)。
個人的にはだいぶ前から、具体的には1990年頃からでしたか、「鉄道忌避なんてなかったんでないのか」と疑ってました(それ以前はそもそも興味がなかった)。きっかけは中仙道の旧道めぐり。鈴鹿8時間耐久を見た帰りに、アバウトに中仙道の旧道をたどって中津川から高崎まで走ってみたんです。旧道筋って面白いな、なんて思った。で、なんでそれが「鉄道忌避なんてなかったんでないのか」と思うことにつながったのかっつうと、旧街道つながりで、次の2つの事例がきっかけです(ただし根拠は後づけ。当時はとりあえず、フツーに地図を見ただけで、素朴に「おかしいんじゃないか」と思ったということです)。
以下、地図はGoogleMap上に作った説明用地図の切り出しで、各地図左下の「より大きな地図で 鉄道忌避伝説 を表示」のリンクをクリックすれば別窓でGoogleMapの該当エリアがひらきます。
まずは龍ヶ崎。
※より大きな地図で 鉄道忌避伝説 を表示
黒線は常磐線、赤線は水戸街道の旧道(江戸時代中期以降)、青線は水戸街道の古道(江戸時代初期)。青丸は旧水戸街道の宿場町です。赤線が4本あるのは小貝川出水時の迂回用の枝道が作られていたせいで、いちばん右が本通りといって江戸時代の本道、次が中通りといって明治時代の本道(旧国道)、残り2本は椚木廻りと大廻りといってあまり重視されていなかったルートです。
龍ヶ崎には「古くから栄えた町だったのだが、鉄道忌避があって、常磐線が通らなかった。なのでのちに町民が自力で竜ヶ崎鉄道(現関東鉄道竜ヶ崎線)を作らなければならなくなった」という鉄道忌避伝説が残されています。しかしなあ。この地図を見れば一目瞭然だと思うんですが、常磐線のルートとして龍ヶ崎経由ルートが選ばれる可能性って、もともと「皆無」だったんじゃないでしょうか。
確かに江戸時代初期の水戸街道古道は「我孫子~布佐~龍ヶ崎~若柴」というルートであり、取手や藤代宮和田は経由していませんでした。しかしこれは小貝川の氾濫原を避けての迂回路だったと思われるものであり、江戸時代もわりと早い時期(17世紀)に「我孫子~取手~藤代宮和田~若柴」というルートに付け替えられています。明治になって国道指定がなされた際(1885年)にも、中通りが指定されており、龍ヶ崎ルートは採用されていません。龍ヶ崎は確かにずっと町として栄え続けていましたが、それは決して水戸街道の宿場町として栄えていたわけじゃなかった。
にもかかわらず、なぜにして水戸街道鉄道として企画された常磐線が龍ヶ崎を通らなくちゃならんのよ。
鉄道忌避は、「そこに鉄道を通そうという計画が立てられたが、現地住民が鉄道を嫌って反対したため、別のところを通った」という物語なわけでしょう。「最初から鉄道を通そうという計画が立案されたわけがない場所」には、原理的に、鉄道忌避などおこり得ないのです。なのになんで龍ヶ崎に鉄道忌避伝説が誕生したんだろうか。
もうひとつは流山。流山の鉄道忌避伝説にも根拠はないんですが、龍ヶ崎よりはもうちょっとかわいそうな物語があります(=^_^;=)。まず小図。
※より大きな地図で 鉄道忌避伝説 を表示
赤線が旧水戸街道、黒線が常磐線、緑線は日光街道旧道(日本橋~千住宿は水戸街道兼用)。薄墨の太線は後述。こちらも、常磐線は順当に旧水戸街道に沿って走っており、まあフツーに計画案を立てたらこうなるよなって感じかと思います。常磐線に「流山に立ち寄れ」と言っても、そりゃ無理だっぺって感じ。
続いて大図。
※より大きな地図で 鉄道忌避伝説 を表示
えー、常磐線は、常磐炭田の石炭を東京に運ぶことを最大の目的として計画された路線であり、都市部(具体的には上野から千住あたりまで)に鉄道を通すとなると土地買収とかがめんどくせーという理由から、最初は川口分岐案というのが立案されました。んで、いちおう仮測量程度は行われたらしい。そのルートが薄墨で記したもの。結局ルートは確定されませんでしたから、アバウトな範囲で記すことしかできません。計画線がこの太いラインの中におさまっていたという保証はできませんが、まるっきしの間違いにはなっていないでしょう。
しかし免許申請直後に鉄道局より「上野から直接水戸に向かえ」という指示が出されます。現在の日暮里から南千住あたりまでは別線の隅田川線(貨物線)を流用し、北千住あたりの市街地はなんとか強引に突破することになり、具体的計画として固まったときにはおおむね旧水戸街道沿いのルートになりました。そもそも人の流動とかを考えていたわけではない上に、町の格としても流山が松戸より上だったわけじゃない。普通に考えて、川口分岐案がなくなった時点で常磐線が流山を通る可能性なんかなくなっていたんじゃないんだろうか。
いったん「わが町に鉄道が来る」という期待を持たされてしまった以上、流山の悔しさは龍ヶ崎の比ではなかったものと思います。んで、こちらものちに流山軽便鉄道(現流鉄)が作られることになりました。わざわざ自前の鉄道を作らなければならなくなったことに同情するにやぶさかではない。しかしそこから「鉄道忌避」に話がつながっていく理由がよくわからない(=^_^;=)。
なんかこう、この2つって常磐線南部の鉄道忌避伝説の両巨頭だったりするわけですが、その2つが2つともこのテータラクだったもので、このあたりからもう「鉄道忌避ってほんとにあったんかいな」という感覚になってたわけです。だってさーあんたさー、普通に地図を見たら「常磐線が通るわけがなかっただろーが」とか思いませんか(=^_^;=)。
もうちょい北にいくと、石岡~水戸間で常磐線は水戸街道旧道を大きく逸れて走っていてそこにも鉄道忌避伝説があるらしいのですが、そちらは「先に開通していた水戸線に合流することで新規建設距離を短くしようとした」という合理的説明ができますから、そっちも鉄道忌避伝説は間違いなのが明らかです。
ご参考までに常磐線と水戸街道旧道が大きくずれているあたりの水戸街道旧道地図。
で、いったん本書に戻ります。戻ったところであいかわらず逸走するだけなのはわかっているのですけど、いちおう書評だからね。
本書は啓蒙書であり、丁寧に資料を紹介しつつ、「鉄道忌避という現象があったことが確認できる事例はひとつもない」ということを説明しています(伊勢参宮鉄道におけるものについても、「時間をくれ」以上のものではない)。また、資料調査などが甘かった時代に書かれた地方史などに鉄道忌避が文書化され、それが各地の学校副読本などに掲載されることで、根拠がないままに広まってしまったという現象についても、具体的な証拠を添えて、説明しています。そういう話はとても面白うございました。
ただ、根底のところの「そもそも鉄道の敷設計画がなく、鉄道忌避などできたはずがない場所に、なぜ鉄道忌避伝説が生まれたのか」については、何も記されていませんでした。いやまあなんだ、「いまさらそんなことを調べられっかい」と著者は言うのではなかろうかと思うし、おれもそう思うし、ここでへたな推測を付け加えたら本の格だって落ちるでしょうし、無理もない選択だったとは思うのですが。
おれはねー。鉄道忌避伝説の発端は、「鉄道の誘致に失敗したことを悔しく思った人々の愚痴」あたりなんじゃないかなーとは思うんですよねえ。あるいは「誘致に積極的でなかったひとへの悪口」がエスカレートしたとか。それにしても、そもそも誘致が無理だったはずの場所ですからねえ、「愚痴」にせよ「悪口」にせよ、その段階ではかなり根拠レスで低質な流言飛語レベルのものであったことは間違いないわけですが。
しかしそこから「鉄道忌避伝説の誕生」っていうか、あるいはもう「鉄道忌避伝説がなぜ開発されたのか」「どうしてそんな物語が思い浮かんだのか」とか表現したのがいいかもしれませんが、そうつながっていった経緯が、おれにはわけわかんないのです。
おれの感覚では、八つ当たりとしか言いようのない愚痴・悪口から派生してそこそこ説得力があるらしい説を作り出してしまうってのは、これはもうそれはもう高度な創作性の結果としか思えないんですよね。そういう高度な創作性が全国的に同時並行で発揮されたというのは、シンクロニシティ(共時性:因果関係がないのに同じようなことが同時並行で起きること)とかいうレベルのものではなくもっと奇跡的な偶然のなせるわざのはずで、たいへんに考えにくいのです。天才的な創作能力を持つやつがそこらじゅうにいたわけがないだろうし、天才的なひらめきがたまたま大量に同じベクトルを示したとか言ったらそれは奇跡の乱発を認めることになっちゃうだろう(=^_^;=)。
にもかかわらずどうしてこんな展開になっちゃったんだろうか。
私的なWeblogでの読書感想文ですし、ここでおれは推測を平然と書き飛ばしてしまおうと思うのですが、どこか(まあそれが複数の場所であってもいいが、少数の複数にとどまる)で創作された物語が伝播した可能性とかって、あるように思う。まあにちゃんねるあたりを見ていれば「おれには絶対に思いつけない独創的な悪口」とかって普通にあるわけだから、こんなことを疑問に思っていては青いのかもしれないんですが。
こんな仮説は、提出したとしても立証は困難でしょうけれども、ていうかどういう条件が整えば立証できるのかということを考えると酔いつぶれて寝てしまいたくなったりしますが(=^_^;=)、1900年になる前に起きたはずの鉄道忌避という現象が伝説として定着したのは本書によると1950年代以降であるってことなので、その半世紀の間になんかしら伝言ゲームのように水面下の流言飛語としてアイディアが広まってしまいそれが同時多発的に顕在化したとかいうことは考えられなくもない、ような気がしているのでございます。
なんかねー。そのあたりの解明の根拠とできるような古文書がどこかから掘り出されてきたりしませんかねえ。誰かの日記みたいな古文書の中にちょっとした言及があったりしたら、なかなか面白い新展開につながるかもしれないのですが、とか夢想している今日このごろなのでございます。ははは(=^_^;=)。
そういうわけで個人的なもやもやは残るのですが、それはあくまで個人的なものにすぎないという自覚もあります。おれは、この本を、高く評価しようと思います。ではまた。
★★★★★
※水戸街道旧道筋などのデータは、陸軍迅速測図から旧道筋を作るという別途しこしこやってるプロジェクトのものから流用しました。それはそれでまたチャンスをみつけて紹介しようと思います。 続きを読む

最初に「鉄道忌避伝説」について確認。
鉄道黎明期に起きたとされる、「宿場町がすたれる」「養蚕業に悪影響が出る」「火災が起きる」などの今となっては理由にならないような理由によって、鉄道を拒否した町があったと言い伝えられている現象。各地にそういう話が残されており、信じているひとも多い。
しかしどうもそれは間違いっつうかうそっぱちっつうかであるらしい、鉄道忌避なんて現実にはなかったんではないか、というのが本書の主張。主張っていうか、もう歴史学界的には鉄道忌避なんかなかったというのが通説になっているようであり、これはその説明を目指した一般向けの啓蒙書ですね。なので「鉄道忌避伝説」と表現しています。おれもこの事象を語るときには、文脈上での判断を経て、おおむね間違いなく「伝説」をつけているなあ。
いまこれを読んで「え、鉄道忌避って事実じゃなかったの?」と思ったひと、この本はたぶんあなたにとって面白いから、ぜひ読んでみなはれ。
えーと。
この本の楽しみ方としては「検証可能性」とか「資料にあたることの重要性の指摘」とか「都市伝説の伝播の歴史」とかに絞った方がいいかもしれないんですが、そこには棹差しちゃう。ていうか、ごく普通に考えておかしいって思うことないですか、ほんのちょっと考えればおかしいとわかるようなことにはビンカンに気づけた方がいいですぜ、みたいな話にしてしまおうと思うわけですよ。ゴリ押しだなぁ(=^_^;=)。
個人的にはだいぶ前から、具体的には1990年頃からでしたか、「鉄道忌避なんてなかったんでないのか」と疑ってました(それ以前はそもそも興味がなかった)。きっかけは中仙道の旧道めぐり。鈴鹿8時間耐久を見た帰りに、アバウトに中仙道の旧道をたどって中津川から高崎まで走ってみたんです。旧道筋って面白いな、なんて思った。で、なんでそれが「鉄道忌避なんてなかったんでないのか」と思うことにつながったのかっつうと、旧街道つながりで、次の2つの事例がきっかけです(ただし根拠は後づけ。当時はとりあえず、フツーに地図を見ただけで、素朴に「おかしいんじゃないか」と思ったということです)。
以下、地図はGoogleMap上に作った説明用地図の切り出しで、各地図左下の「より大きな地図で 鉄道忌避伝説 を表示」のリンクをクリックすれば別窓でGoogleMapの該当エリアがひらきます。
まずは龍ヶ崎。
※より大きな地図で 鉄道忌避伝説 を表示
黒線は常磐線、赤線は水戸街道の旧道(江戸時代中期以降)、青線は水戸街道の古道(江戸時代初期)。青丸は旧水戸街道の宿場町です。赤線が4本あるのは小貝川出水時の迂回用の枝道が作られていたせいで、いちばん右が本通りといって江戸時代の本道、次が中通りといって明治時代の本道(旧国道)、残り2本は椚木廻りと大廻りといってあまり重視されていなかったルートです。
龍ヶ崎には「古くから栄えた町だったのだが、鉄道忌避があって、常磐線が通らなかった。なのでのちに町民が自力で竜ヶ崎鉄道(現関東鉄道竜ヶ崎線)を作らなければならなくなった」という鉄道忌避伝説が残されています。しかしなあ。この地図を見れば一目瞭然だと思うんですが、常磐線のルートとして龍ヶ崎経由ルートが選ばれる可能性って、もともと「皆無」だったんじゃないでしょうか。
確かに江戸時代初期の水戸街道古道は「我孫子~布佐~龍ヶ崎~若柴」というルートであり、取手や藤代宮和田は経由していませんでした。しかしこれは小貝川の氾濫原を避けての迂回路だったと思われるものであり、江戸時代もわりと早い時期(17世紀)に「我孫子~取手~藤代宮和田~若柴」というルートに付け替えられています。明治になって国道指定がなされた際(1885年)にも、中通りが指定されており、龍ヶ崎ルートは採用されていません。龍ヶ崎は確かにずっと町として栄え続けていましたが、それは決して水戸街道の宿場町として栄えていたわけじゃなかった。
にもかかわらず、なぜにして水戸街道鉄道として企画された常磐線が龍ヶ崎を通らなくちゃならんのよ。
鉄道忌避は、「そこに鉄道を通そうという計画が立てられたが、現地住民が鉄道を嫌って反対したため、別のところを通った」という物語なわけでしょう。「最初から鉄道を通そうという計画が立案されたわけがない場所」には、原理的に、鉄道忌避などおこり得ないのです。なのになんで龍ヶ崎に鉄道忌避伝説が誕生したんだろうか。
もうひとつは流山。流山の鉄道忌避伝説にも根拠はないんですが、龍ヶ崎よりはもうちょっとかわいそうな物語があります(=^_^;=)。まず小図。
※より大きな地図で 鉄道忌避伝説 を表示
赤線が旧水戸街道、黒線が常磐線、緑線は日光街道旧道(日本橋~千住宿は水戸街道兼用)。薄墨の太線は後述。こちらも、常磐線は順当に旧水戸街道に沿って走っており、まあフツーに計画案を立てたらこうなるよなって感じかと思います。常磐線に「流山に立ち寄れ」と言っても、そりゃ無理だっぺって感じ。
続いて大図。
※より大きな地図で 鉄道忌避伝説 を表示
えー、常磐線は、常磐炭田の石炭を東京に運ぶことを最大の目的として計画された路線であり、都市部(具体的には上野から千住あたりまで)に鉄道を通すとなると土地買収とかがめんどくせーという理由から、最初は川口分岐案というのが立案されました。んで、いちおう仮測量程度は行われたらしい。そのルートが薄墨で記したもの。結局ルートは確定されませんでしたから、アバウトな範囲で記すことしかできません。計画線がこの太いラインの中におさまっていたという保証はできませんが、まるっきしの間違いにはなっていないでしょう。
しかし免許申請直後に鉄道局より「上野から直接水戸に向かえ」という指示が出されます。現在の日暮里から南千住あたりまでは別線の隅田川線(貨物線)を流用し、北千住あたりの市街地はなんとか強引に突破することになり、具体的計画として固まったときにはおおむね旧水戸街道沿いのルートになりました。そもそも人の流動とかを考えていたわけではない上に、町の格としても流山が松戸より上だったわけじゃない。普通に考えて、川口分岐案がなくなった時点で常磐線が流山を通る可能性なんかなくなっていたんじゃないんだろうか。
いったん「わが町に鉄道が来る」という期待を持たされてしまった以上、流山の悔しさは龍ヶ崎の比ではなかったものと思います。んで、こちらものちに流山軽便鉄道(現流鉄)が作られることになりました。わざわざ自前の鉄道を作らなければならなくなったことに同情するにやぶさかではない。しかしそこから「鉄道忌避」に話がつながっていく理由がよくわからない(=^_^;=)。
なんかこう、この2つって常磐線南部の鉄道忌避伝説の両巨頭だったりするわけですが、その2つが2つともこのテータラクだったもので、このあたりからもう「鉄道忌避ってほんとにあったんかいな」という感覚になってたわけです。だってさーあんたさー、普通に地図を見たら「常磐線が通るわけがなかっただろーが」とか思いませんか(=^_^;=)。
もうちょい北にいくと、石岡~水戸間で常磐線は水戸街道旧道を大きく逸れて走っていてそこにも鉄道忌避伝説があるらしいのですが、そちらは「先に開通していた水戸線に合流することで新規建設距離を短くしようとした」という合理的説明ができますから、そっちも鉄道忌避伝説は間違いなのが明らかです。
ご参考までに常磐線と水戸街道旧道が大きくずれているあたりの水戸街道旧道地図。
で、いったん本書に戻ります。戻ったところであいかわらず逸走するだけなのはわかっているのですけど、いちおう書評だからね。
本書は啓蒙書であり、丁寧に資料を紹介しつつ、「鉄道忌避という現象があったことが確認できる事例はひとつもない」ということを説明しています(伊勢参宮鉄道におけるものについても、「時間をくれ」以上のものではない)。また、資料調査などが甘かった時代に書かれた地方史などに鉄道忌避が文書化され、それが各地の学校副読本などに掲載されることで、根拠がないままに広まってしまったという現象についても、具体的な証拠を添えて、説明しています。そういう話はとても面白うございました。
ただ、根底のところの「そもそも鉄道の敷設計画がなく、鉄道忌避などできたはずがない場所に、なぜ鉄道忌避伝説が生まれたのか」については、何も記されていませんでした。いやまあなんだ、「いまさらそんなことを調べられっかい」と著者は言うのではなかろうかと思うし、おれもそう思うし、ここでへたな推測を付け加えたら本の格だって落ちるでしょうし、無理もない選択だったとは思うのですが。
おれはねー。鉄道忌避伝説の発端は、「鉄道の誘致に失敗したことを悔しく思った人々の愚痴」あたりなんじゃないかなーとは思うんですよねえ。あるいは「誘致に積極的でなかったひとへの悪口」がエスカレートしたとか。それにしても、そもそも誘致が無理だったはずの場所ですからねえ、「愚痴」にせよ「悪口」にせよ、その段階ではかなり根拠レスで低質な流言飛語レベルのものであったことは間違いないわけですが。
しかしそこから「鉄道忌避伝説の誕生」っていうか、あるいはもう「鉄道忌避伝説がなぜ開発されたのか」「どうしてそんな物語が思い浮かんだのか」とか表現したのがいいかもしれませんが、そうつながっていった経緯が、おれにはわけわかんないのです。
おれの感覚では、八つ当たりとしか言いようのない愚痴・悪口から派生してそこそこ説得力があるらしい説を作り出してしまうってのは、これはもうそれはもう高度な創作性の結果としか思えないんですよね。そういう高度な創作性が全国的に同時並行で発揮されたというのは、シンクロニシティ(共時性:因果関係がないのに同じようなことが同時並行で起きること)とかいうレベルのものではなくもっと奇跡的な偶然のなせるわざのはずで、たいへんに考えにくいのです。天才的な創作能力を持つやつがそこらじゅうにいたわけがないだろうし、天才的なひらめきがたまたま大量に同じベクトルを示したとか言ったらそれは奇跡の乱発を認めることになっちゃうだろう(=^_^;=)。
にもかかわらずどうしてこんな展開になっちゃったんだろうか。
私的なWeblogでの読書感想文ですし、ここでおれは推測を平然と書き飛ばしてしまおうと思うのですが、どこか(まあそれが複数の場所であってもいいが、少数の複数にとどまる)で創作された物語が伝播した可能性とかって、あるように思う。まあにちゃんねるあたりを見ていれば「おれには絶対に思いつけない独創的な悪口」とかって普通にあるわけだから、こんなことを疑問に思っていては青いのかもしれないんですが。
こんな仮説は、提出したとしても立証は困難でしょうけれども、ていうかどういう条件が整えば立証できるのかということを考えると酔いつぶれて寝てしまいたくなったりしますが(=^_^;=)、1900年になる前に起きたはずの鉄道忌避という現象が伝説として定着したのは本書によると1950年代以降であるってことなので、その半世紀の間になんかしら伝言ゲームのように水面下の流言飛語としてアイディアが広まってしまいそれが同時多発的に顕在化したとかいうことは考えられなくもない、ような気がしているのでございます。
なんかねー。そのあたりの解明の根拠とできるような古文書がどこかから掘り出されてきたりしませんかねえ。誰かの日記みたいな古文書の中にちょっとした言及があったりしたら、なかなか面白い新展開につながるかもしれないのですが、とか夢想している今日このごろなのでございます。ははは(=^_^;=)。
そういうわけで個人的なもやもやは残るのですが、それはあくまで個人的なものにすぎないという自覚もあります。おれは、この本を、高く評価しようと思います。ではまた。
★★★★★
※水戸街道旧道筋などのデータは、陸軍迅速測図から旧道筋を作るという別途しこしこやってるプロジェクトのものから流用しました。それはそれでまたチャンスをみつけて紹介しようと思います。 続きを読む
2010年12月28日
『進化する路面電車』書評の続き。独立車輪方式への違和感。
年末年始で一足お先に暇になったもんで。ていうか、先日一本仕上げてまた失業状態に戻ったもんですから、またしばらく暇になるんだと思うのですが。
先日、書評『進化する路面電車』で言及した、当該書籍において決定的に欠落していた技術的要素についての説明です。おれには欠落を埋めることはできません。ただ、どのように欠落していたのかについての説明はできます。あ、・・・ええと、できるんじゃないかなあと。
当該書籍をぼろかすにけなした罪滅ぼしとして、その説明をしようと思います。誰かにその欠落を埋めていただけるとありがたいなあ、と思いつつ。
前提。現代では一般的な二条式鉄道に限定しての説明です。モノレールとか新交通システムとかには適用がありません。
レールと車輪の関係。いちばん安定している状態というのは、次の図版の状態です。

レールの中心と車輪の中心が合致している状態が、いちばん安定した状態です。直線では、理想的にはこのような状態であり、車輪は、そして列車も、まっすぐに走ります。一般に、「レールと車輪のフランジ(内側のでっぱった部分)が触れることで脱線せずに走ることができる」と思われていますが、それは間違いなんです。フランジは、非常用の安全策に過ぎず、レールとフランジは、普通は、接することがありません。
では、どのようにして鉄道の車輪は、そしてあの大きな車体が、曲がることができるのか。その説明を、次の図版で示します。

車輪がカーブにかかると、レールは曲がっているのに車輪はまっすぐに進もうとしますから、車輪は外側に振られます。上図では、右がカーブの内側。なので、車輪は左側に振られています。そして、レールと車輪のあたる場所が、ちょっとずれます。
ところで、一般的な二条式鉄道の車輪には、踏面勾配というわずかな傾斜がつけられています。車輪は円筒ではなく、円錐形を切り出したかたちになっているわけです。そして、あたる場所が変わると半径が変わるようになっています。図で赤く記した部分がレールと車輪があたっているところで、外側(左側)は円周が大きくなり、内側(左側)は円周が小さくなります。すると、車輪は右方向に曲がろうとするのですね。
なので、二条式鉄道の車輪は、自然に右に曲がっていきます。カーブするときでも、普通は、レールと車輪のフランジが接することはありません(急カーブではレールと車輪のフランジが接する場合がありますが、そうなるとレールも車輪もすりへってしまうことになりますので、そういう場合には接する部分に潤滑油を塗布するなどの対策が必要になります。また、この作用が振動を引き起こしてしまうこともあって、そうなると蛇行動というややこしい現象を引き起こしたりすることもあるんですが)。
で、だね。一般の鉄道の車輪の場合になぜこのように自動的にカーブを回れるのかというと、それは、左右の車輪が車軸でつながっており、踏面傾斜のせいでうまくバランスするからなんですね。左右の回転数が一致していなければ、そういう作用は生まれません。
左右の回転数が揃っていなかったら、直線でもまっすぐ走れるとは限りませんし、カーブでも自動的に曲がっていくということはない。蛇行動どころではなくて、直線でも左右でもレールにフランジをぶつけまくって走ることになるんじゃないかという懸念があるわけですよ。急カーブ以外でもレールとフランジの接触部分に潤滑油を塗りまくっておかないとまともに走れないんじゃないか、レールもフランジも磨耗しまくってえれえメンテナンスコストがかかるんでないか、とまあ普通にそういう心配をするんじゃないかと思うわけです。
*
車軸を持たない超低床車に対する伝統的な鉄道事業者(特に技術者)の忌避感を簡単にまとめると、そういうことになるんじゃなかろうか。そこを上手に説明してくれるテキストが存在するのなら、車輌側のメンテナンスの手間とかはさて置いて、忌避感を減じることにつながるのではないか。
おれは、すでに述べたとおり、「超低床車という解法」には、まったく好感を持っていませんし、コストパフォーマンスという観点からもそうそう採用できる方法論ではないと思っています。「高床式車輌と高いプラットフォームの組み合わせによるコンヴェンショナルな解法」の方が百倍マシだと思っている。だけどさ。
もしも超低床車という技術が定着するなら、徐々にコストパフォーマンスを改善し、それはそれで未来にとっては良いことかもしれないと思う程度の柔軟性は持っているつもりです。なので誰かが、この「コンヴェンショナルな鉄道技術と超低床車という新しい鉄道技術の橋渡し」をしてくれると、とてもありがたいと思う。
誰か、卓越したエンジニアでありかつ啓蒙家の方、そういうテキストを書いてみませんか。おれはそれを読みたい。
というわけで、まったくもってオチはついてませんし、おれにオチをつける能力もありませんが、ネタフリくらいはできるかもしれないとか思うもんで、また長々と暇にあかして駄文を書いてみました。
あとはよしなに。
====
このエントリには、コメントやトラックバックを許可していません。コメントやトラックバックは元ネタのページにお願いします。
先日、書評『進化する路面電車』で言及した、当該書籍において決定的に欠落していた技術的要素についての説明です。おれには欠落を埋めることはできません。ただ、どのように欠落していたのかについての説明はできます。あ、・・・ええと、できるんじゃないかなあと。
当該書籍をぼろかすにけなした罪滅ぼしとして、その説明をしようと思います。誰かにその欠落を埋めていただけるとありがたいなあ、と思いつつ。
前提。現代では一般的な二条式鉄道に限定しての説明です。モノレールとか新交通システムとかには適用がありません。
レールと車輪の関係。いちばん安定している状態というのは、次の図版の状態です。

レールの中心と車輪の中心が合致している状態が、いちばん安定した状態です。直線では、理想的にはこのような状態であり、車輪は、そして列車も、まっすぐに走ります。一般に、「レールと車輪のフランジ(内側のでっぱった部分)が触れることで脱線せずに走ることができる」と思われていますが、それは間違いなんです。フランジは、非常用の安全策に過ぎず、レールとフランジは、普通は、接することがありません。
では、どのようにして鉄道の車輪は、そしてあの大きな車体が、曲がることができるのか。その説明を、次の図版で示します。

車輪がカーブにかかると、レールは曲がっているのに車輪はまっすぐに進もうとしますから、車輪は外側に振られます。上図では、右がカーブの内側。なので、車輪は左側に振られています。そして、レールと車輪のあたる場所が、ちょっとずれます。
ところで、一般的な二条式鉄道の車輪には、踏面勾配というわずかな傾斜がつけられています。車輪は円筒ではなく、円錐形を切り出したかたちになっているわけです。そして、あたる場所が変わると半径が変わるようになっています。図で赤く記した部分がレールと車輪があたっているところで、外側(左側)は円周が大きくなり、内側(左側)は円周が小さくなります。すると、車輪は右方向に曲がろうとするのですね。
なので、二条式鉄道の車輪は、自然に右に曲がっていきます。カーブするときでも、普通は、レールと車輪のフランジが接することはありません(急カーブではレールと車輪のフランジが接する場合がありますが、そうなるとレールも車輪もすりへってしまうことになりますので、そういう場合には接する部分に潤滑油を塗布するなどの対策が必要になります。また、この作用が振動を引き起こしてしまうこともあって、そうなると蛇行動というややこしい現象を引き起こしたりすることもあるんですが)。
で、だね。一般の鉄道の車輪の場合になぜこのように自動的にカーブを回れるのかというと、それは、左右の車輪が車軸でつながっており、踏面傾斜のせいでうまくバランスするからなんですね。左右の回転数が一致していなければ、そういう作用は生まれません。
左右の回転数が揃っていなかったら、直線でもまっすぐ走れるとは限りませんし、カーブでも自動的に曲がっていくということはない。蛇行動どころではなくて、直線でも左右でもレールにフランジをぶつけまくって走ることになるんじゃないかという懸念があるわけですよ。急カーブ以外でもレールとフランジの接触部分に潤滑油を塗りまくっておかないとまともに走れないんじゃないか、レールもフランジも磨耗しまくってえれえメンテナンスコストがかかるんでないか、とまあ普通にそういう心配をするんじゃないかと思うわけです。
*
車軸を持たない超低床車に対する伝統的な鉄道事業者(特に技術者)の忌避感を簡単にまとめると、そういうことになるんじゃなかろうか。そこを上手に説明してくれるテキストが存在するのなら、車輌側のメンテナンスの手間とかはさて置いて、忌避感を減じることにつながるのではないか。
おれは、すでに述べたとおり、「超低床車という解法」には、まったく好感を持っていませんし、コストパフォーマンスという観点からもそうそう採用できる方法論ではないと思っています。「高床式車輌と高いプラットフォームの組み合わせによるコンヴェンショナルな解法」の方が百倍マシだと思っている。だけどさ。
もしも超低床車という技術が定着するなら、徐々にコストパフォーマンスを改善し、それはそれで未来にとっては良いことかもしれないと思う程度の柔軟性は持っているつもりです。なので誰かが、この「コンヴェンショナルな鉄道技術と超低床車という新しい鉄道技術の橋渡し」をしてくれると、とてもありがたいと思う。
誰か、卓越したエンジニアでありかつ啓蒙家の方、そういうテキストを書いてみませんか。おれはそれを読みたい。
というわけで、まったくもってオチはついてませんし、おれにオチをつける能力もありませんが、ネタフリくらいはできるかもしれないとか思うもんで、また長々と暇にあかして駄文を書いてみました。
あとはよしなに。
====
このエントリには、コメントやトラックバックを許可していません。コメントやトラックバックは元ネタのページにお願いします。
2010年12月23日
本>『進化する路面電車』 - だめじゃん、こんな視点。
この本、「そらねっと通信局」さんで教えてもらいました。そらねっとさんも微妙な評価をしており、その視点にはおれも同調する部分があったもので、入手しに行ったんでした。「交通新聞社新書」というのが創刊されていたというのも初耳だったため、そのラインナップを見たかったということもあった。
で、評価。だめじゃん、こんな視点。
この本は、総体としてLRT(Light Rail Transit=新世代路面電車のシステム)とLRV(Light rail vehicle=新世代路面電車の車輌)を混同した、ちょっと前に氾濫してた「駄目駄目な路面電車論」の焼き直しでしかないでしょう。うーん、なんでこんなんなっちゃうかなぁ。


先に、本書のサブタイトルである「超低床電車はいかにして国産化されたのか」という、技術解説の側面について書きます。メインタイトルである「進化する路面電車」という観点からの欠落点については、そのあとで辛辣に触れることにします。
技術史的には、そこそこの資料性はありました。『Project X』を野次馬的視点から見てるレベルでは、まあまあ上手にまとめていると評価することができるかもしれません。ただ、なんかこう、予定調和的な展開に思えるし、著者たちの調査能力がわからないので、しょーじき鵜呑みにはしない方がいいと思います。
技術論的には、全く評価できません。
たとえば「ボルスタレス台車」について「台車は車体を直接支えるボルスタレス台車であり、車体に対して回転することは不可能だ(70ページ)」「ボルスタレス台車であり、台車は車体と直結していて回転はしない(94ページ)」といった記述があるけれども、これは明確に間違いです。車体に対してある程度は回転できるタイプの、通常のボギー台車と同様のボルスタレス台車はいくらでも存在しています(例:DT50&TR235/DT61&TR246/DT71&TR255/NP128)。っていうか、いまどきの電車気動車用の新造台車はかなりの割合でボルスタレス台車になっているわけで。
まあ超低床車用台車の一部についてそれをボルスタレス台車と表現しても間違いではないでしょうが、それはボルスタレス台車のごくごく狭い一部分にすぎない。
ボルスタレス台車が車体に対して固定されているっていうのは明らかに間違いなんだが、しかしなんでこんなところで間違えたんだろうか。なぜにして共著者や編集者はその間違いに気づかなかったんだろうか(呆然)。
また、鉄道車両としての左右独立懸架(独立車輪式)については、鉄道運営者側に強い忌避感があるとされていますが、その忌避感をとくための説明がまったくなされていません。鉄道車輌がレールに沿って曲がっていけるのは左右の車輪が車軸でつながっており、車輪の踏面がちょっと傾斜していて、うまく曲がれるようバランスするためです。左右の車輪が車軸でつながっていない左右独立懸架型には、既存の知識が使えないんですね。鉄道運営者ではないけれども、おれも左右独立懸架の鉄道車輌がなんで安定してカーブを曲がれるのか理解できていないし、多少不安に思っています。
左右独立懸架式も実用化されている以上、問題なく走れるのだということはわかっているけれども、ということはなぜ問題がないのかの説明だって簡単にできるんじゃないだろうか。その説明がまったくないということは、どこが重要な問題であるのかについて理解できていないということを意味しているように思える。
いやあなんだね、読者側のニーズもいろいろですから不足があるのはある程度しょうがないかもしれないとは思うんですが、それにしてもちょっとねえ。なんか違う、なんか違うんだよって感じ。
ぼろかすですが、以上で記述内容についての評価は終わり。続いて、本書の欠落点、交通政策的位置づけについての評価をします。
*
路面電車をより便利なものとする方法については、いくつかの方策が提案されています。本書で触れられていない重要なネタとしては、信用乗車制などの運賃収受方法に関するものがあります。また、乗り入れなどを含めた路線設計なども使い勝手を大きく左右するものとなるでしょう。
この本は総合的にLRTや路面電車を扱っているわけではなく、運賃収受方式や路線設計などについては、まったくといっていいほど言及がありません。きれいさっぱり欠落しています。「進化する路面電車」というタイトルを背負う本としては、これは重大な欠落点ではないかと思います。
この本は超低床車を主眼に置いています。超低床車導入の主目的はバリアフリー化でしょう。バリアフリー化という目的の実現手段としては、「超低床車と低いプラットフォーム」の他に「高床式車輌と高いプラットフォーム」という組み合わせがあります。
このどちらかが圧倒的な優位性を持つわけではなく、それぞれの場でどちらがより適切であるかを判断しなければなりません。超低床車を導入するという判断の前に、そのどちらがより適切であるかという判断を、必ず、しなければならない。そこをふっとばして、あたかも超低床車が切り札であるかのように言うのは、ミスリーディングというものでしょう。
また、LRT(Light Rail Transit)というのは交通システム全体を意味する名称であり、LRV(Light rail vehicle)というのはLRTの要素のひとつである車輌のことです。この2つは全然違う概念です。LRVを導入したところでその路面電車がLRTになるわけじゃない。あたかもLRVを導入すればそこはLRTとして再生する、といった幻想がありましたし、今でもありますが、でもそれは間違いなんだ。ある路線をLRTとして育てあげるためには、運賃収受方式などもひっくるめたさまざまな「どういう方法を採用するか」という議論をかたづけ、総合的な改善をしなければならない。そういう視点がなければ、必ず間違ってしまうのです。
もうひとつついでに言っておくと、「LRV=超低床電車」というわけではなくて、高床式のLRVてのもあり得ます。東急電鉄世田谷線の300型や都営荒川線の8500型・9000型・8800型あたりは、高床式のLRVと呼んでいいものだと思いますが、本書にはそういう視点もないようです。
話を戻して。
「超低床車と低いプラットフォームの組み合わせ」と「高床式車輌と高いプラットフォームの組み合わせ」というのは、いずれもバリアフリー化を目的とした解法です。これは老人や障害者にとってのみ意味がある方法論ではなく、乗降時間の短縮などの副次的メリットももたらしますので、まあまあ重要なことです。そして、手法としては前述の通り「超低床車と低いプラットフォームの組み合わせ」と「高床式車輌と高いプラットフォームの組み合わせ」というのがあるわけです。
現状は「高床式車輌と低いプラットフォーム」という組み合わせが圧倒的に多い。なので、具体的には「高床式車輌を超低床式車輌に入れ替える」のと「低いプラットフォームを高いプラットフォームに改める」のとの二者択一になります。
どっちを選んでも良くて、あとはどちらが楽であるか、で決めればいい。どちらが楽かというのは、それぞれの路線がおかれている状況で異なりますし、どの程度の設備投資が可能であるかによっても左右されます。

<岡山電鉄MOMO> 超低床車と低いプラットフォームの組み合わせ

<都電荒川線> 高床式車輌(都電8500型)と高いプラットフォームの組み合わせ
個別具体的に述べますと。
LRT化について、「超低床車と低いプラットフォームという組み合わせ」が望ましい路線というのは存在するかもしれません。あまり車輌数が多くなく停車場数が多い事業者で高価な車輌の総入れ替えが可能なら、この選択肢がベストでしょう。新設路線でもこの選択肢はあり得る(実例として富山ライトレールがあります。おれは、富山ライトレールは高床式+高いプラットフォームで作るべきだったと思っていますが)。
もっとも、既存事業者のうちこの選択肢が圧倒的に正しいと言える路線を、おれは思いつかないのですが。ていうか、「超低床車で統一する」という方法論は、並外れた例外的なものすごいどこかからの財政的支援かなんかがない限り、採用し得るものではないんではないかという気がしてなりません。
対して、「高床式車輌と高いプラットフォームという組み合わせ」が望ましいと思われる路線は、少なくありません。そして現実的可能性としては、こちらの方が良い場合が多いのではないかと、おれは思っている。
すでにこの方法を全面的に採用した路線としては東京都交通局荒川線や東急電鉄世田谷線があります。筑豊電鉄あたりも、バリアフリー化をするのなら、既存車輌の軽改造とプラットフォームの嵩上げという手法の方が賢いでしょう。いずれも専用敷区間が圧倒的に多い、あるいは専用敷区間しかない路線ですが、そういう路線の第一選択はこちらだと思う(富山ライトレールも、基本線このカテゴリだと思うんだよなあ)。
路面区間が多い路線でも、たとえば岡山電軌はプラットフォーム嵩上げ式の方がいいんじゃないのかなぁ。プラットフォームの設置が困難な2ヶ所の電停(中納言駅と小橋駅)をどうするかという頭の痛い問題はありますけれども、それ以外の全電停はプラットフォームを嵩上げする余地がある、と思う。岡山電軌がかなりの数採用しているセンターリザベーションと中央分離帯を活用した電停というメリットが生きることにもなろうかと思います。
どちらがいいか断言しにくい路線も数多くあるのですが、ざっくり言うと「全車輌の入れ替えによる超低床化」よりは「既存車輌の改造とプラットフォーム嵩上げ」の方が、コストが安い場合が多いのではないかと思います。
後者については、東急世田谷線が2001年2月10日夜から11日朝にかけてやった工事の記録がありますので、興味がある方はご覧になってください(準備篇・当日篇)。

<東急世田谷線体質改善工事・当日篇> 2001年2月11日早朝 [direct]
でだよ。この段落で述べることはけっこう大事なことだと思うんだが。
個人的には、「わずかな数の超低床車を導入してしまい、身動きが取れなくなる」という現象が各地で発生していることが、気になっています。近代化のシンボルとして導入するだけであり根本的な改善を目指さない、というのであれば、わずかな数の超低床車の導入というのは、ありかもしれません。しかし全車輌を超低床車に入れ替えるとか、特定の運用については圧倒的な割合を超低床車とするとか、そういうことを実現する具体的な目論見がないままに少数の超低床車を導入するのは、賢いとは思えない(広島電鉄の超低床車の導入にはそういう懸念を感じたのですが、あそこはそれなりに気合を入れて数をそろえたみたいなので、まあなによりという感じ。しかし宮島線を超低床にする意味があったのかどうかは疑問)。
へたをすると、期待を背負った超低床車が、「高床式車輌とホームの嵩上げ」という選択肢を封じるという効果をもたらし、それぞれの最適な未来を模索する道を狭めてしまうということすら、あるのではないか。現実的に、はやりの超低床車を中途半端に導入した結果そうなっている路線がそこそこあるように、おれは感じているのです。
*
書評に戻ります。
本書が「路面電車の進化」という論点を扱うのであれば、信用乗車制などの運用技術もひっくるめて、扱うべきだった。単にLRVの技術紹介や国産化へのプロジェクトXをやりたいのならば、そちらに絞って「路面電車の未来」などという大それたテーマには言及すべきではなかったし、技術的解説にもっと力を入れ、紙幅をさき、精度を上げるべきだった。
結果として本書は、これまでに幾多積み重ねられてきた誤解の延長線上にある本になってしまったような気がします。
著者のひとりである史絵.さんというのは鉄道アイドルの一人であるらしいので、それなりにファンの方もおいでになるのでしょう。そのファンの方々を軒並み敵に回すことになるのかもしれませんし、それはものすごくめんどくさい状況を引き起こすことなのかもしれません。しかし、たいへん申し訳ないのだが、わたしはこの本には、とても低い評価しかあげられない。共著者及び編集者の鉄道ジャーナリズムに関する評価も同様。
だめじゃん、こんな視点。
★☆☆☆☆
====
このエントリには続編があります。
追記には書誌情報と目次情報があります。 続きを読む
で、評価。だめじゃん、こんな視点。
この本は、総体としてLRT(Light Rail Transit=新世代路面電車のシステム)とLRV(Light rail vehicle=新世代路面電車の車輌)を混同した、ちょっと前に氾濫してた「駄目駄目な路面電車論」の焼き直しでしかないでしょう。うーん、なんでこんなんなっちゃうかなぁ。

先に、本書のサブタイトルである「超低床電車はいかにして国産化されたのか」という、技術解説の側面について書きます。メインタイトルである「進化する路面電車」という観点からの欠落点については、そのあとで辛辣に触れることにします。
技術史的には、そこそこの資料性はありました。『Project X』を野次馬的視点から見てるレベルでは、まあまあ上手にまとめていると評価することができるかもしれません。ただ、なんかこう、予定調和的な展開に思えるし、著者たちの調査能力がわからないので、しょーじき鵜呑みにはしない方がいいと思います。
技術論的には、全く評価できません。
たとえば「ボルスタレス台車」について「台車は車体を直接支えるボルスタレス台車であり、車体に対して回転することは不可能だ(70ページ)」「ボルスタレス台車であり、台車は車体と直結していて回転はしない(94ページ)」といった記述があるけれども、これは明確に間違いです。車体に対してある程度は回転できるタイプの、通常のボギー台車と同様のボルスタレス台車はいくらでも存在しています(例:DT50&TR235/DT61&TR246/DT71&TR255/NP128)。っていうか、いまどきの電車気動車用の新造台車はかなりの割合でボルスタレス台車になっているわけで。
まあ超低床車用台車の一部についてそれをボルスタレス台車と表現しても間違いではないでしょうが、それはボルスタレス台車のごくごく狭い一部分にすぎない。
ボルスタレス台車が車体に対して固定されているっていうのは明らかに間違いなんだが、しかしなんでこんなところで間違えたんだろうか。なぜにして共著者や編集者はその間違いに気づかなかったんだろうか(呆然)。
また、鉄道車両としての左右独立懸架(独立車輪式)については、鉄道運営者側に強い忌避感があるとされていますが、その忌避感をとくための説明がまったくなされていません。鉄道車輌がレールに沿って曲がっていけるのは左右の車輪が車軸でつながっており、車輪の踏面がちょっと傾斜していて、うまく曲がれるようバランスするためです。左右の車輪が車軸でつながっていない左右独立懸架型には、既存の知識が使えないんですね。鉄道運営者ではないけれども、おれも左右独立懸架の鉄道車輌がなんで安定してカーブを曲がれるのか理解できていないし、多少不安に思っています。
左右独立懸架式も実用化されている以上、問題なく走れるのだということはわかっているけれども、ということはなぜ問題がないのかの説明だって簡単にできるんじゃないだろうか。その説明がまったくないということは、どこが重要な問題であるのかについて理解できていないということを意味しているように思える。
いやあなんだね、読者側のニーズもいろいろですから不足があるのはある程度しょうがないかもしれないとは思うんですが、それにしてもちょっとねえ。なんか違う、なんか違うんだよって感じ。
ぼろかすですが、以上で記述内容についての評価は終わり。続いて、本書の欠落点、交通政策的位置づけについての評価をします。
*
路面電車をより便利なものとする方法については、いくつかの方策が提案されています。本書で触れられていない重要なネタとしては、信用乗車制などの運賃収受方法に関するものがあります。また、乗り入れなどを含めた路線設計なども使い勝手を大きく左右するものとなるでしょう。
この本は総合的にLRTや路面電車を扱っているわけではなく、運賃収受方式や路線設計などについては、まったくといっていいほど言及がありません。きれいさっぱり欠落しています。「進化する路面電車」というタイトルを背負う本としては、これは重大な欠落点ではないかと思います。
この本は超低床車を主眼に置いています。超低床車導入の主目的はバリアフリー化でしょう。バリアフリー化という目的の実現手段としては、「超低床車と低いプラットフォーム」の他に「高床式車輌と高いプラットフォーム」という組み合わせがあります。
このどちらかが圧倒的な優位性を持つわけではなく、それぞれの場でどちらがより適切であるかを判断しなければなりません。超低床車を導入するという判断の前に、そのどちらがより適切であるかという判断を、必ず、しなければならない。そこをふっとばして、あたかも超低床車が切り札であるかのように言うのは、ミスリーディングというものでしょう。
また、LRT(Light Rail Transit)というのは交通システム全体を意味する名称であり、LRV(Light rail vehicle)というのはLRTの要素のひとつである車輌のことです。この2つは全然違う概念です。LRVを導入したところでその路面電車がLRTになるわけじゃない。あたかもLRVを導入すればそこはLRTとして再生する、といった幻想がありましたし、今でもありますが、でもそれは間違いなんだ。ある路線をLRTとして育てあげるためには、運賃収受方式などもひっくるめたさまざまな「どういう方法を採用するか」という議論をかたづけ、総合的な改善をしなければならない。そういう視点がなければ、必ず間違ってしまうのです。
もうひとつついでに言っておくと、「LRV=超低床電車」というわけではなくて、高床式のLRVてのもあり得ます。東急電鉄世田谷線の300型や都営荒川線の8500型・9000型・8800型あたりは、高床式のLRVと呼んでいいものだと思いますが、本書にはそういう視点もないようです。
話を戻して。
「超低床車と低いプラットフォームの組み合わせ」と「高床式車輌と高いプラットフォームの組み合わせ」というのは、いずれもバリアフリー化を目的とした解法です。これは老人や障害者にとってのみ意味がある方法論ではなく、乗降時間の短縮などの副次的メリットももたらしますので、まあまあ重要なことです。そして、手法としては前述の通り「超低床車と低いプラットフォームの組み合わせ」と「高床式車輌と高いプラットフォームの組み合わせ」というのがあるわけです。
現状は「高床式車輌と低いプラットフォーム」という組み合わせが圧倒的に多い。なので、具体的には「高床式車輌を超低床式車輌に入れ替える」のと「低いプラットフォームを高いプラットフォームに改める」のとの二者択一になります。
どっちを選んでも良くて、あとはどちらが楽であるか、で決めればいい。どちらが楽かというのは、それぞれの路線がおかれている状況で異なりますし、どの程度の設備投資が可能であるかによっても左右されます。

<岡山電鉄MOMO> 超低床車と低いプラットフォームの組み合わせ

<都電荒川線> 高床式車輌(都電8500型)と高いプラットフォームの組み合わせ
個別具体的に述べますと。
LRT化について、「超低床車と低いプラットフォームという組み合わせ」が望ましい路線というのは存在するかもしれません。あまり車輌数が多くなく停車場数が多い事業者で高価な車輌の総入れ替えが可能なら、この選択肢がベストでしょう。新設路線でもこの選択肢はあり得る(実例として富山ライトレールがあります。おれは、富山ライトレールは高床式+高いプラットフォームで作るべきだったと思っていますが)。
もっとも、既存事業者のうちこの選択肢が圧倒的に正しいと言える路線を、おれは思いつかないのですが。ていうか、「超低床車で統一する」という方法論は、並外れた例外的なものすごいどこかからの財政的支援かなんかがない限り、採用し得るものではないんではないかという気がしてなりません。
対して、「高床式車輌と高いプラットフォームという組み合わせ」が望ましいと思われる路線は、少なくありません。そして現実的可能性としては、こちらの方が良い場合が多いのではないかと、おれは思っている。
すでにこの方法を全面的に採用した路線としては東京都交通局荒川線や東急電鉄世田谷線があります。筑豊電鉄あたりも、バリアフリー化をするのなら、既存車輌の軽改造とプラットフォームの嵩上げという手法の方が賢いでしょう。いずれも専用敷区間が圧倒的に多い、あるいは専用敷区間しかない路線ですが、そういう路線の第一選択はこちらだと思う(富山ライトレールも、基本線このカテゴリだと思うんだよなあ)。
路面区間が多い路線でも、たとえば岡山電軌はプラットフォーム嵩上げ式の方がいいんじゃないのかなぁ。プラットフォームの設置が困難な2ヶ所の電停(中納言駅と小橋駅)をどうするかという頭の痛い問題はありますけれども、それ以外の全電停はプラットフォームを嵩上げする余地がある、と思う。岡山電軌がかなりの数採用しているセンターリザベーションと中央分離帯を活用した電停というメリットが生きることにもなろうかと思います。
どちらがいいか断言しにくい路線も数多くあるのですが、ざっくり言うと「全車輌の入れ替えによる超低床化」よりは「既存車輌の改造とプラットフォーム嵩上げ」の方が、コストが安い場合が多いのではないかと思います。
後者については、東急世田谷線が2001年2月10日夜から11日朝にかけてやった工事の記録がありますので、興味がある方はご覧になってください(準備篇・当日篇)。

<東急世田谷線体質改善工事・当日篇> 2001年2月11日早朝 [direct]
でだよ。この段落で述べることはけっこう大事なことだと思うんだが。
個人的には、「わずかな数の超低床車を導入してしまい、身動きが取れなくなる」という現象が各地で発生していることが、気になっています。近代化のシンボルとして導入するだけであり根本的な改善を目指さない、というのであれば、わずかな数の超低床車の導入というのは、ありかもしれません。しかし全車輌を超低床車に入れ替えるとか、特定の運用については圧倒的な割合を超低床車とするとか、そういうことを実現する具体的な目論見がないままに少数の超低床車を導入するのは、賢いとは思えない(広島電鉄の超低床車の導入にはそういう懸念を感じたのですが、あそこはそれなりに気合を入れて数をそろえたみたいなので、まあなによりという感じ。しかし宮島線を超低床にする意味があったのかどうかは疑問)。
へたをすると、期待を背負った超低床車が、「高床式車輌とホームの嵩上げ」という選択肢を封じるという効果をもたらし、それぞれの最適な未来を模索する道を狭めてしまうということすら、あるのではないか。現実的に、はやりの超低床車を中途半端に導入した結果そうなっている路線がそこそこあるように、おれは感じているのです。
*
書評に戻ります。
本書が「路面電車の進化」という論点を扱うのであれば、信用乗車制などの運用技術もひっくるめて、扱うべきだった。単にLRVの技術紹介や国産化へのプロジェクトXをやりたいのならば、そちらに絞って「路面電車の未来」などという大それたテーマには言及すべきではなかったし、技術的解説にもっと力を入れ、紙幅をさき、精度を上げるべきだった。
結果として本書は、これまでに幾多積み重ねられてきた誤解の延長線上にある本になってしまったような気がします。
著者のひとりである史絵.さんというのは鉄道アイドルの一人であるらしいので、それなりにファンの方もおいでになるのでしょう。そのファンの方々を軒並み敵に回すことになるのかもしれませんし、それはものすごくめんどくさい状況を引き起こすことなのかもしれません。しかし、たいへん申し訳ないのだが、わたしはこの本には、とても低い評価しかあげられない。共著者及び編集者の鉄道ジャーナリズムに関する評価も同様。
だめじゃん、こんな視点。
★☆☆☆☆
====
このエントリには続編があります。
追記には書誌情報と目次情報があります。 続きを読む
2010年11月20日
本>Take the 'D' train (D列車でいこう by 阿川大樹)
突然ですが、読書感想文(=^_^;=)です。


※徳間書店単行本版『D列車でいこう』表紙。装画・西田直哉、装幀 (装丁)・鳥居和昌。
えー。いろいろ煽りのコピーがちりばめられた帯とかついてます。表紙イラストも派手なボンデージのねーちゃんがまんなかにいたりします。いい表紙だとは思うものの、なんかしらおれの印象とは違うんだよね。おれ的にはもっと地味で、もっと穏やかで、淡々とした物語だったりします。
で、いい本でした。おれ、幾度か読み返すだろうと思う。この本、2010年11月6日に小田急線喜多見駅前の古本屋で買ったのですが(なので阿川大樹さんには印税収入ははいってなかった。あとで文庫版を買いなおした)、なんだってまたこの本の購入者はこれを古本屋に売るかなあとか思いました。ゲットしたのは初版1刷だぜ、いぇい(って初版趣味なんかないくせに(=^_^;=)>おれ)。
この煽りぶっこみまくった表紙ですが、左から、元建設省(現国土交通省)の官僚で天下り退職金として受け取った2億円のどう使ってもいい金を持っている悠々自適の田中博さん、三十路に足を踏み入れた金融会社社員でロックシンガーでのちに退職してプロジェクトの社長となる深田由希さん、深田の上司でのちに退職して部下となる銀行支店長の河原崎慎平さん、のお三方です。
この3人が組んで、田中さんの2億円をもとでに、すでに廃線が決まっている赤字ローカル線「山花鉄道(*1)」の存続を目指す、というのが物語の骨子。
おれさあ。にちゃんねるやらWikipediaやらで、やたら鉄ヲタよばわりされるんですよねえ。でもおれ、鉄ヲタという自覚はまったくないし、まあ多少の知識はあるかしれないけれどもんなもん鉄道に限ったことじゃなくてたいていのことについてそこらの凡人よりは知識があるわけで鉄道は珍しい分野じゃねーし、おまいらいったい何を言っているんだみたいな気分でいたわけです、ずーっと(今回は高飛車な路線だなあ(=^_^;=))。
で、何がどう違うのかがよくわからないでいたんですが。
おぼろげに思っていたのは、「おれは生きている鉄道が好きなんであって、鉄道そのものにはたいして興味がない。何かをつなぐ媒介となるものが好きなのであって、鉄道はそういう範囲で興味を惹くだけなんだ」ってことだったような気がする。おれの鉄道趣味の主たる対象は軽便鉄道というレトロフューチャーでありそれは(事実上はもう現代の日本では)滅びたものなのであって、今の鉄道に興味がある部分とは明らかに食い違っている。そいやおれ、街道やら河川やらもそこそこ好きだったりするんだよな。そういう視点から見る限り、「つなぐもののワン・オヴ・ゼム」としてならば、まあまあやっぱ鉄道って面白いし、好きだなあとか思ったりもするわけですが(*2)。
で、この本、基本線としていわゆるところの鉄ヲタとは桁違いに鉄道には興味がない鉄道素人衆お三方が、まるでゲームでもやるかのように(←念のためだが、悪い意味じゃない)、縁もゆかりもなかったローカル線の廃止を食い止めるために奮闘する物語です。その「鉄ヲタではない視点」てのが、なんか妙に気持ちいいものだったりしたわけ。
たとえば。「年間3000万円の赤字を解消するためにはどうすればいいか」を計算するところ。週あたりせいぜい500人程度だけ乗客を増やせればいい、一日あたりだったらたったの70人だぞ、そのくらいならなんかちょっとしたきっかけで呼び込める数字のような気がしてこないか、みたいな議論がはじまる。そうなのよなあ、実際その程度だったりすることが少なくないのよなあ(*3)。
んで、とりあえず乗客っていうか収入を増やそうみたいな話になり、田舎の風景がどーたらとかありがちなことを言い始めて、しかし即座に「田舎の過当競争」とか「老舗の田舎以外には観光客は来ない」とかいう、よく見かける状況を実に的確に言い当てる秀逸な表現が出てきてのブレスト段階での叩きあいに発展するあたりで、なんかもう「あるあるネタ」みたいになってきちゃったんすよね。「田舎の老舗」なんていますぐキャッチコピーに使えそうだったりするしぃ。
さらに似たネタ並べるなら。自叙伝の自費出版をやってる出版社とか(*4)、ライブハウスとかのビジネスモデルが出てきてまして。「自叙伝出版もライブハウスも構造的には同じじゃないかあ」っていう指摘あたりで大笑い。チケットノルマのある公演系って演劇だろうが合唱団だろうがぜーんぶ同じ構造抱えてるぞーとか思うし(=^_^;=)(これも、本書の中で指摘されてます。それはそれでいいんじゃないかっていう位置づけでもあります。そして、そういうビジネスモデルに基づいてのプランも考えちゃうわけ)(*5)。
ひとつだけこの延長線上で本書中で具体的に提案されているプランを紹介しておくと、「運転士の資格と体験運転を売る」ってやつ。
そういえばいすみ鉄道が「自腹で訓練を受けて運転士の免許を取ってくれ、そしたら採用するから」というプランを発表してけっこうな毀誉褒貶があったりしてましたが、その原案かもしれないプランがこの本の中に書かれています。いすみ鉄道の関係者がこの本を読んでいたという証拠は、現時点ではまったくつかんでいませんけれども。
この本のはもっと過激な内容で、「本物とまったく同じ免許取得講習から営業列車の体験運転まで全部をセットにしたお金持ち対象者をターゲットとした観光パッケージを売り出す」というもの。「退職金がはいった金持ちの中には、営業列車の運転ができるのならば、数百万くらいなら出すやついるだろ」というのはまあそのとおりだろうなあ、みたいな。やっぱほれ、運転士って、やってみたいじゃん(=^_^;=)。その「希少なチャンス」に「数百万円の私費を投じる」ことの是非は、各自が勝手に考えればよろしい。自己責任で私費を投じるという判断に対してけなす必要なんか、どこにもないだろう(*6)。
ま、再生計画で使われるプランはほかにもあるし、プランを並べて紹介するのが目的ではないので、あとのプランを知りたければ、本を読んでください。
まあ、この本で提示されたプランは、この本に登場する山花鉄道という路線のシチュエーションに即してのみリアリティを持つもので、そのまま現実の赤字ローカル線に持ち込めるようなものではありません。てか、どこまでリアルなのかっていう論点はフツーにあり得るわけだし、この本の物語にしても「うまくころがりすぎているのではないか」ってきらいはあるわけだけど(それを言いはじめたら大半のフィクションはだめぽだけどな)。
ただそれでも、実効性がないのはもうほとんど経験則になっている、安易で手垢がついてしまった「『乗って残そう○○線』という掛け声をかけるだけ作戦(*7)」よりはだいぶマシなんじゃないか、という気がする(しみじみひでえ言い方だけどなあ。でも、あえてそう言い切っちゃう)。ていうか、考え方のベクトルが、っていうかな。
まあ、元建設省(現国土交通省)の官僚と若手およびヴェテランの金融屋という客観的にもエリートである人材が全力でかかるという話ですから、そうそう空虚なプランしか出てこないようでは物語として成り立たないわけですけど。でも、フィクションとしてではなく、現実的にもこういう路線はありなんじゃないのかなあ。
おれの分野的にはなあ。えーと、かなり失敗する可能性も高い・・・っていうか必ずしもおれは信頼してないんでこんなやつらを使うことを提案していいのかどうか迷うところだが、駄目プランを出してきたら果敢に却下するという安全弁はきっちり心がけた上で「広告代理店を相手に、路線復活のためのコンペティションへの参加を呼びかける」とかってのはありかもしんないとか思った。空虚な仕事に倦んでおり、多少は鉄道に好感を持っていて、そしてしばしば社内では不遇をかこっている広告代理店の中のキレ者を何人か本気にできればめっけもん、って感じでしょうか。
ふと問題だなあと思ったのは、全国のローカル線がいっせいにこういうことをはじめたとしたら、「『鉄道再生計画の過当競争』というさらにどっしょーもない状況」になりかねない、ということあたりかもしれません。日本では、誰かが成功すると一気に雪崩を打って真似をするからなあ、具体的な脅威としてそういうのはある。どのように棲み分けるかとか、どこもかしこも似たようなものばっかにならないように色分けをきっちりするとかいう調整ができないと、総崩れで終わることになったりするかもしれませんしねえ。
まあそんなことはどっかが成功してから心配すればいいことなんですが(=^_^;=)(*8)。
それなりに大事なつけたし。
この『D列車でいこう』、徳間書店から文庫本が出たようです。けっこう売れ行きがいいいらしく、今ならそこらへんで平積みになっていそうですので、探しやすいかもしれません。文庫版の表紙は上の単行本版のものとは違い、以下のもの。んー、地味にはなったけど、表紙の出来としては単行本版のもののがいいような気がする。


※徳間書店文庫版『D列車でいこう』表紙。カバーイラスト・石居麻耶、カバーデザイン・波戸恵。
ま、そんなこんなで、おれは阿川大樹という、海老沢泰久・佐々木譲・川端裕人に続く、好みの作家を発見したのかもしれません。ほかの本もあたってみよう。
*
どうでもいいおまけ、その1。
単行本初版初刷の131ページから135ページあたりにかけて、文庫本初版初刷の183ページから188ページにかけて、深田由希が、1995年1月17日に、神戸で線路の上を歩いたことを語るシーンがあるんですよ。阪神淡路大震災の日です(*9)。その中に「あんな状況でもレールの上を歩いていたとき、線路を辿っていけば必ず思ったところに辿り着くんだという絶対的な安心感があった」という表現が出てきます。「実際は自分の足で歩いていたんだけど、そこにいる自分が鉄道というものに守られていたというか」と続く。さらに「いまはもうセンチメンタルな気持ちより、まず数字を見て、(中略)ビジネスとしてすごく面白い」と続いており、それはとても正しいとおれは思うのだけど、でも前提のおセンチなところだってきっと大事なんだぜとか言ってあげたくなったりした。
その「絶対的な安心感」って、おれが「軌道系交通機関には、バスなどにはない、交通の基軸機能を持っている」とか言ってきた話に近いんじゃないだろうかなんて、ふと思った。「そこに継続的に公共交通機関があり続ける公算が強い」という信頼って、人がその場所に住み続ける上で、すごく重要なことなんじゃないんだろうかってこと。都市では特に顕著だけど、地方でもこれって大事なことだろう。
もちろんそれがバス路線であったとしても「その路線は、少なくともここしばらくは、絶対に廃止しない」という確約ができるのならば、同じ機能を果たすことはできるんですよ。でもバス路線は、制度の上で路線廃止が楽にやれ、減便だって簡単にできますから、約束の担保として「バス路線では弱い」ってことは言えると思うんだわ。いまや鉄道すらその約束としては弱くなってしまっているのだけれども、そういう約束ができない社会って、社会として弱体化を免れ得ないのではないのかなあ、なんてね。そういう意味で、もう日本は駄目なのかもしれません。
どうでもいいおまけ、その2。
タイトルの『D列車でいこう』てのは、当然のことですがビリー・ストレイホーン作曲でデューク・エリントン楽団の演奏で有名になったジャズ作品『Take the 'A' Train(A列車で行こう)』を下敷きにしたものだと思いますが、ついでなんでもうひとつ、山野浩一の『X電車で行こう』てのもあります(ハヤカワ文庫JA)。話をかんたんにまとめちゃうと「壮大な規模でただただひたすら電車ごっこを繰り広げる」というもの。
これもなかなかいい作品なんで、ご興味がおありでしたらぜひ。アニメ化もされていますが、例によって小説とはまったく異なるものです。
どうでもいいおまけ、その3。
こういう小説を読むと、イメージキャスティングとかしちゃうんだよな。役者を選べるような仕事は1本もしたことがないくせにな。いい小説を読むとよくこうやって遊ぶもので、またやってみました。現実的には、無名な舞台役者とかから探してきて「これをおまえの出世作にしたる」とか大見得を切る方が、安くあがり、楽しいような気がするけどもな。
トリプル主演の紅一点、深田由希さん役には、星野真里さんなんかどうでしょーか。年齢もまあまあ合致してるし、演技力とか美人度とかにはまったく問題ないし、ボンデージ系ロックシンガーくらいは軽くこなせるでしょう。歌唱力については知らないけど問題があるようならそこは吹き替えにしてもいい。
河原崎慎平さんなんだけど、しばらく考えたんだけど、遠藤憲一さんなんてどうだろう。元殺し屋役だった『湯けむりスナイパー』で見せてくれていたような律儀さを持つ銀行の支店長なんて、すげえはまるんじゃないかなあ。
最後に、田中博さん。神保悟志さんはどうだろうか。設定と若干年齢差があるけど、若作りをさせるよりは老けさせる方が楽だし安全だし。『相棒』の「ピルイーター」で見せてくれたような醒めたキャラクターで淡々と田中博を演じてもらえたらなあ。
もっとも、遠藤健一さんと神保悟志さんを並べると若干キャラがかぶるような気がしなくもない。うまく演出すれば相乗効果も期待できるような気がするんだけど綱渡りになるだろうなあ。深田由希役に二人して立ち向かってちょうどバランス、くらいでいいんじゃないかっていう気もします・・・っておふたかたに失礼かもしらんが(=^_^;=)。
この駄文を書いたことで、なにかがどこかでいい方向にころがってくれるといいなあ、なんて、世の中に対してちょっとリクエストしておきます。ではまた。
*
*1
ところで、おれ鉄ヲタじゃないから思い当たる路線がないんだけど、作中の「桐生型」という車輌にも思い当たるふしがないんだけど、この山花鉄道って、どこかモデルになってる路線があるんだろうか。「山花、という楽器メーカー」が「ヤマハ」をモデルにしたものなのだろうということは容易に想像がつくんだけど、「山葉線」という路線はないしなあ(ヤマハは、山葉寅楠さんというひとが創立したメーカーなんです)。
そいや松浦鉄道が「名前が同じなのだからお願いできませんか」っつーて松浦亜弥に知名度向上のための協力話を持ちかけ、しかしあっさり断られたというケースがあったような、おぼろげな記憶があります。松浦亜弥にとっても悪い話じゃなかっただろうに、断ったマネジメント担当とか駄目駄目だったんじゃねーの、とか思うおれ。
*2
あ、ほれ。おれってコンピュータネットワークってけっこう好きじゃないですかあ。パソコン通信もインターネットも。でだ。
もうほとんどのひとが忘れている作品だと思うんだが、山口よしのぶによる『名物!たびてつ友の会』っていう漫画作品があったんですよ。その中に未成線(途中まで建設されたのだが結局開通にはいたらなかった路線)を扱った『幻の佐久間線』というエピソードがあったんですよね。主人公のIT企業の営業さんが、結局鉄道が通らなかった田舎に営業にいって、「人と人とをつなぐ技術」についてしみじみしちゃうっていう話です。
まあ、IT側から見たときには、それだけだったら話は浅いしありがちで無駄な公共事業なんじゃねーの、みたいな感じもあったんですが、たぶん大事なんだが描かれなかったことがあったんだろうと思うことにして見過ごします。
*3
おれはまあ、廃線のサイクリングロード化工事やバス専用道路化工事に何十億もの金を投じる余裕が実際にはあるんだから(苦笑するしかないんだが、前者が80億円、後者が10億円)、「年間数千万円程度の赤字ならば赤字補填をすりゃいいじゃん」とか思っているのですが。
ま、どこにある金をどこに流すかというスキームがぼろぼろだからそこから見直さないと話はじまんない面はあって、しかしそんな見直しが有効に実現するのを待っていたら鉄道っていうか公共交通機関が持たないってのが現実で、頭痛いんだけどね。
*4
自叙伝本商法、最近けっこう詐欺商法とかゆーて問題になってきているのだが、個人的には「ちゃんと本を渡すところまでこぎつけていたら、詐欺呼ばわりをするのは言いすぎじゃん」とか思ってます。ただ、プロとしての編集の手間を惜しんでいる会社が多そうに見えるのがちょっとなんだなあ、詐欺ってほど悪くはないが手抜きくらいのそしりは免れ得ないのではないか、という気配はあり。
ついでに、「本にしたとしてもみすぼらしい人生にしかならないひと」(ひでえ言い方だなあ)にまで売り込まない、という程度の矜持は最低限のものとして、必要かもしんない。
*5
早い話が「誰が真の顧客なのかという視点から見直せばビジネスモデルの見え方も違ってくる」ってこと。自叙伝商法は、人生を見直して肯定的な気分になりたいご老人に満足してもらい、対価をいただく。本の読者は顧客じゃない。チケットノルマのある音楽・演劇などは、出演者に場を売るのが目的だからお客さんは出演者、見に来るひとはお客じゃない。そう割り切ればそうそう理不尽な商売には見えないだろ、ってこと。
自叙伝を書くご老人や出演者などに満足してもらえなかったら商売として成り立たないのだが、そこだけ満足してもらえればそれで良くて、そこで読者や観客にへたにひきずられると道を見誤る。それはそれで、割り切りとしてはありだろうな。
*6
いすみ鉄道の自費運転士募集に対してぶつけられた悪口の大半、あるいは全ては、この路線のどっしょーもないものだった。誰かが趣味にいくら使おうがそんなもんほっとけっちゅうの。
ただ、いすみ鉄道の方法論も全面的に肯定できるわけでもない。いすみ鉄道の運転士募集は、一発だけのイベントではなく継続的な勤務を前提としたものであり、ところがそのいすみ鉄道は経営的にけっこう危機な状況にあるわけで、「自腹で免許を取ってはもらったけれども、運転すべき路線がなくなってしまう」という最悪のシナリオだってあり得る。もしそのリスクについての認識が食い違っていたら、けっこう悲しい顛末になるかもしれない。
*7
覚えている範囲で、「乗って残そう○○線」とか言っていたにもかかわらず廃止を免れ存続できた路線って、北勢線くらいのような気がする(証拠)。その北勢線にしても「乗客が増えて存続にこぎつけた」わけではない。もしかすっと南海電鉄貴志川線(現わかやま電鉄)でも存続派活動家が言ってたかもしれないけど(微妙にベクトルが違う立看板の証拠)。
この2線は、公共交通機関の位置づけを見直すという流れを作り出すことができたからこそ存続できたんじゃないのかと思う。存続決定後は乗客は増えて収支も好転しつつあるようだけど、乗ってるひとは残そうと思って乗ってるわけじゃない、使い途があるから乗ってるだけなんで、その2つの事象の間には天と地くらいの開きがあるんだ。貴志川線は「猫駅長ブーム」の火付け役にまでなっちゃいましたからねえ。猫的にはあんまし幸せじゃないような気がするんだけれども、誰だか知らんけど観光資源として猫駅長のプランを売り出すことを考えたやつはすごかった(もともとは単に、売店のひとが自分ちの猫をかわいがってただけだったんだが(=^_^;=))。
まあ乗客を増やし収入を増やすというのは王道なんだけれども、「採算が取れるほどの乗客なんて、そうそう簡単にはみつからない」という前提を確認していないがゆえにこのフレーズを安易に出せているような気がしてならないんだ。だからこの「乗って残そう○○線」というフレーズを出せるところは、「どんづまりの開き直り」であるか「考えが浅く現実を変えられるだけの力がないことの表明」であるか、どちらかになってしまう。前者ならもう「死ぬ気でがんばれ」とエールを送るしかないんだけど、後者だと痛々しくて見ていられない。
ある意味でおれにとっては、「乗って残そう○○線」というフレーズは「それが出てきたらもうだめなんじゃなかろうかと判断していい」という指標フレーズになっちゃってる。「『憲法違反』という訴因は敗訴を覚悟した証である」みたいなもんだね。
*8
鉄道再生までを視野にいれたものじゃないとは思うんだけど、2010年5月公開の、山陰は一畑電鉄を舞台にした『Railways』という映画があったっしょ。あの映画のプロモーションの一部に、そこはかとなく『D列車でいこう』と似たにおいを感じたりするんですよね。
似たもの並立でコケそうになったら、逆にこんな感じで「全国の赤字ローカル線連合」でぱーっと話題を立ち上げて「あなたの好きな場所を選んで行ってみませんか」といったベクトルの縦断的観光キャンペーンをやる、なんてのはありかしんない。
ま、いずれにせよどこかが成功してからのちの話ですが。
*9
久々に本職のお仕事が迷い込んできていたのだが、なんかついにディレクターから編集オペレータに格下げになったような気もしてるわけですが(それって格下げなのか(=^_^;=))、オペレータへの格下げはいいんだけどなんでマシンがマッキントッシュなんだーと悲鳴をあげていたりもするわけですが(=^_^;=)、その仕事に阪神淡路大震災が登場。「耐震性の訴求にまだ阪神淡路を使うつもりかっ」という感じもなきにしもあらずだけど、逆に言えば15年ほどは都市型の震災って起きてないってことなんだよな(都市型ではないやつは、新潟や岩手でありました。忘れてるわけじゃありません)。
この本を買った当日にも阪神淡路の映像を編集してたものですから、なんかシンクロニシティだなあみたいな妙なインパクトもあったんでした。 続きを読む

※徳間書店単行本版『D列車でいこう』表紙。装画・西田直哉、装幀 (装丁)・鳥居和昌。
えー。いろいろ煽りのコピーがちりばめられた帯とかついてます。表紙イラストも派手なボンデージのねーちゃんがまんなかにいたりします。いい表紙だとは思うものの、なんかしらおれの印象とは違うんだよね。おれ的にはもっと地味で、もっと穏やかで、淡々とした物語だったりします。
で、いい本でした。おれ、幾度か読み返すだろうと思う。この本、2010年11月6日に小田急線喜多見駅前の古本屋で買ったのですが(なので阿川大樹さんには印税収入ははいってなかった。あとで文庫版を買いなおした)、なんだってまたこの本の購入者はこれを古本屋に売るかなあとか思いました。ゲットしたのは初版1刷だぜ、いぇい(って初版趣味なんかないくせに(=^_^;=)>おれ)。
この煽りぶっこみまくった表紙ですが、左から、元建設省(現国土交通省)の官僚で天下り退職金として受け取った2億円のどう使ってもいい金を持っている悠々自適の田中博さん、三十路に足を踏み入れた金融会社社員でロックシンガーでのちに退職してプロジェクトの社長となる深田由希さん、深田の上司でのちに退職して部下となる銀行支店長の河原崎慎平さん、のお三方です。
この3人が組んで、田中さんの2億円をもとでに、すでに廃線が決まっている赤字ローカル線「山花鉄道(*1)」の存続を目指す、というのが物語の骨子。
おれさあ。にちゃんねるやらWikipediaやらで、やたら鉄ヲタよばわりされるんですよねえ。でもおれ、鉄ヲタという自覚はまったくないし、まあ多少の知識はあるかしれないけれどもんなもん鉄道に限ったことじゃなくてたいていのことについてそこらの凡人よりは知識があるわけで鉄道は珍しい分野じゃねーし、おまいらいったい何を言っているんだみたいな気分でいたわけです、ずーっと(今回は高飛車な路線だなあ(=^_^;=))。
で、何がどう違うのかがよくわからないでいたんですが。
おぼろげに思っていたのは、「おれは生きている鉄道が好きなんであって、鉄道そのものにはたいして興味がない。何かをつなぐ媒介となるものが好きなのであって、鉄道はそういう範囲で興味を惹くだけなんだ」ってことだったような気がする。おれの鉄道趣味の主たる対象は軽便鉄道というレトロフューチャーでありそれは(事実上はもう現代の日本では)滅びたものなのであって、今の鉄道に興味がある部分とは明らかに食い違っている。そいやおれ、街道やら河川やらもそこそこ好きだったりするんだよな。そういう視点から見る限り、「つなぐもののワン・オヴ・ゼム」としてならば、まあまあやっぱ鉄道って面白いし、好きだなあとか思ったりもするわけですが(*2)。
で、この本、基本線としていわゆるところの鉄ヲタとは桁違いに鉄道には興味がない鉄道素人衆お三方が、まるでゲームでもやるかのように(←念のためだが、悪い意味じゃない)、縁もゆかりもなかったローカル線の廃止を食い止めるために奮闘する物語です。その「鉄ヲタではない視点」てのが、なんか妙に気持ちいいものだったりしたわけ。
たとえば。「年間3000万円の赤字を解消するためにはどうすればいいか」を計算するところ。週あたりせいぜい500人程度だけ乗客を増やせればいい、一日あたりだったらたったの70人だぞ、そのくらいならなんかちょっとしたきっかけで呼び込める数字のような気がしてこないか、みたいな議論がはじまる。そうなのよなあ、実際その程度だったりすることが少なくないのよなあ(*3)。
んで、とりあえず乗客っていうか収入を増やそうみたいな話になり、田舎の風景がどーたらとかありがちなことを言い始めて、しかし即座に「田舎の過当競争」とか「老舗の田舎以外には観光客は来ない」とかいう、よく見かける状況を実に的確に言い当てる秀逸な表現が出てきてのブレスト段階での叩きあいに発展するあたりで、なんかもう「あるあるネタ」みたいになってきちゃったんすよね。「田舎の老舗」なんていますぐキャッチコピーに使えそうだったりするしぃ。
さらに似たネタ並べるなら。自叙伝の自費出版をやってる出版社とか(*4)、ライブハウスとかのビジネスモデルが出てきてまして。「自叙伝出版もライブハウスも構造的には同じじゃないかあ」っていう指摘あたりで大笑い。チケットノルマのある公演系って演劇だろうが合唱団だろうがぜーんぶ同じ構造抱えてるぞーとか思うし(=^_^;=)(これも、本書の中で指摘されてます。それはそれでいいんじゃないかっていう位置づけでもあります。そして、そういうビジネスモデルに基づいてのプランも考えちゃうわけ)(*5)。
ひとつだけこの延長線上で本書中で具体的に提案されているプランを紹介しておくと、「運転士の資格と体験運転を売る」ってやつ。
そういえばいすみ鉄道が「自腹で訓練を受けて運転士の免許を取ってくれ、そしたら採用するから」というプランを発表してけっこうな毀誉褒貶があったりしてましたが、その原案かもしれないプランがこの本の中に書かれています。いすみ鉄道の関係者がこの本を読んでいたという証拠は、現時点ではまったくつかんでいませんけれども。
この本のはもっと過激な内容で、「本物とまったく同じ免許取得講習から営業列車の体験運転まで全部をセットにしたお金持ち対象者をターゲットとした観光パッケージを売り出す」というもの。「退職金がはいった金持ちの中には、営業列車の運転ができるのならば、数百万くらいなら出すやついるだろ」というのはまあそのとおりだろうなあ、みたいな。やっぱほれ、運転士って、やってみたいじゃん(=^_^;=)。その「希少なチャンス」に「数百万円の私費を投じる」ことの是非は、各自が勝手に考えればよろしい。自己責任で私費を投じるという判断に対してけなす必要なんか、どこにもないだろう(*6)。
ま、再生計画で使われるプランはほかにもあるし、プランを並べて紹介するのが目的ではないので、あとのプランを知りたければ、本を読んでください。
まあ、この本で提示されたプランは、この本に登場する山花鉄道という路線のシチュエーションに即してのみリアリティを持つもので、そのまま現実の赤字ローカル線に持ち込めるようなものではありません。てか、どこまでリアルなのかっていう論点はフツーにあり得るわけだし、この本の物語にしても「うまくころがりすぎているのではないか」ってきらいはあるわけだけど(それを言いはじめたら大半のフィクションはだめぽだけどな)。
ただそれでも、実効性がないのはもうほとんど経験則になっている、安易で手垢がついてしまった「『乗って残そう○○線』という掛け声をかけるだけ作戦(*7)」よりはだいぶマシなんじゃないか、という気がする(しみじみひでえ言い方だけどなあ。でも、あえてそう言い切っちゃう)。ていうか、考え方のベクトルが、っていうかな。
まあ、元建設省(現国土交通省)の官僚と若手およびヴェテランの金融屋という客観的にもエリートである人材が全力でかかるという話ですから、そうそう空虚なプランしか出てこないようでは物語として成り立たないわけですけど。でも、フィクションとしてではなく、現実的にもこういう路線はありなんじゃないのかなあ。
おれの分野的にはなあ。えーと、かなり失敗する可能性も高い・・・っていうか必ずしもおれは信頼してないんでこんなやつらを使うことを提案していいのかどうか迷うところだが、駄目プランを出してきたら果敢に却下するという安全弁はきっちり心がけた上で「広告代理店を相手に、路線復活のためのコンペティションへの参加を呼びかける」とかってのはありかもしんないとか思った。空虚な仕事に倦んでおり、多少は鉄道に好感を持っていて、そしてしばしば社内では不遇をかこっている広告代理店の中のキレ者を何人か本気にできればめっけもん、って感じでしょうか。
ふと問題だなあと思ったのは、全国のローカル線がいっせいにこういうことをはじめたとしたら、「『鉄道再生計画の過当競争』というさらにどっしょーもない状況」になりかねない、ということあたりかもしれません。日本では、誰かが成功すると一気に雪崩を打って真似をするからなあ、具体的な脅威としてそういうのはある。どのように棲み分けるかとか、どこもかしこも似たようなものばっかにならないように色分けをきっちりするとかいう調整ができないと、総崩れで終わることになったりするかもしれませんしねえ。
まあそんなことはどっかが成功してから心配すればいいことなんですが(=^_^;=)(*8)。
それなりに大事なつけたし。
この『D列車でいこう』、徳間書店から文庫本が出たようです。けっこう売れ行きがいいいらしく、今ならそこらへんで平積みになっていそうですので、探しやすいかもしれません。文庫版の表紙は上の単行本版のものとは違い、以下のもの。んー、地味にはなったけど、表紙の出来としては単行本版のもののがいいような気がする。

※徳間書店文庫版『D列車でいこう』表紙。カバーイラスト・石居麻耶、カバーデザイン・波戸恵。
ま、そんなこんなで、おれは阿川大樹という、海老沢泰久・佐々木譲・川端裕人に続く、好みの作家を発見したのかもしれません。ほかの本もあたってみよう。
*
どうでもいいおまけ、その1。
単行本初版初刷の131ページから135ページあたりにかけて、文庫本初版初刷の183ページから188ページにかけて、深田由希が、1995年1月17日に、神戸で線路の上を歩いたことを語るシーンがあるんですよ。阪神淡路大震災の日です(*9)。その中に「あんな状況でもレールの上を歩いていたとき、線路を辿っていけば必ず思ったところに辿り着くんだという絶対的な安心感があった」という表現が出てきます。「実際は自分の足で歩いていたんだけど、そこにいる自分が鉄道というものに守られていたというか」と続く。さらに「いまはもうセンチメンタルな気持ちより、まず数字を見て、(中略)ビジネスとしてすごく面白い」と続いており、それはとても正しいとおれは思うのだけど、でも前提のおセンチなところだってきっと大事なんだぜとか言ってあげたくなったりした。
その「絶対的な安心感」って、おれが「軌道系交通機関には、バスなどにはない、交通の基軸機能を持っている」とか言ってきた話に近いんじゃないだろうかなんて、ふと思った。「そこに継続的に公共交通機関があり続ける公算が強い」という信頼って、人がその場所に住み続ける上で、すごく重要なことなんじゃないんだろうかってこと。都市では特に顕著だけど、地方でもこれって大事なことだろう。
もちろんそれがバス路線であったとしても「その路線は、少なくともここしばらくは、絶対に廃止しない」という確約ができるのならば、同じ機能を果たすことはできるんですよ。でもバス路線は、制度の上で路線廃止が楽にやれ、減便だって簡単にできますから、約束の担保として「バス路線では弱い」ってことは言えると思うんだわ。いまや鉄道すらその約束としては弱くなってしまっているのだけれども、そういう約束ができない社会って、社会として弱体化を免れ得ないのではないのかなあ、なんてね。そういう意味で、もう日本は駄目なのかもしれません。
どうでもいいおまけ、その2。
タイトルの『D列車でいこう』てのは、当然のことですがビリー・ストレイホーン作曲でデューク・エリントン楽団の演奏で有名になったジャズ作品『Take the 'A' Train(A列車で行こう)』を下敷きにしたものだと思いますが、ついでなんでもうひとつ、山野浩一の『X電車で行こう』てのもあります(ハヤカワ文庫JA)。話をかんたんにまとめちゃうと「壮大な規模でただただひたすら電車ごっこを繰り広げる」というもの。
これもなかなかいい作品なんで、ご興味がおありでしたらぜひ。アニメ化もされていますが、例によって小説とはまったく異なるものです。
どうでもいいおまけ、その3。
こういう小説を読むと、イメージキャスティングとかしちゃうんだよな。役者を選べるような仕事は1本もしたことがないくせにな。いい小説を読むとよくこうやって遊ぶもので、またやってみました。現実的には、無名な舞台役者とかから探してきて「これをおまえの出世作にしたる」とか大見得を切る方が、安くあがり、楽しいような気がするけどもな。
トリプル主演の紅一点、深田由希さん役には、星野真里さんなんかどうでしょーか。年齢もまあまあ合致してるし、演技力とか美人度とかにはまったく問題ないし、ボンデージ系ロックシンガーくらいは軽くこなせるでしょう。歌唱力については知らないけど問題があるようならそこは吹き替えにしてもいい。
河原崎慎平さんなんだけど、しばらく考えたんだけど、遠藤憲一さんなんてどうだろう。元殺し屋役だった『湯けむりスナイパー』で見せてくれていたような律儀さを持つ銀行の支店長なんて、すげえはまるんじゃないかなあ。
最後に、田中博さん。神保悟志さんはどうだろうか。設定と若干年齢差があるけど、若作りをさせるよりは老けさせる方が楽だし安全だし。『相棒』の「ピルイーター」で見せてくれたような醒めたキャラクターで淡々と田中博を演じてもらえたらなあ。
もっとも、遠藤健一さんと神保悟志さんを並べると若干キャラがかぶるような気がしなくもない。うまく演出すれば相乗効果も期待できるような気がするんだけど綱渡りになるだろうなあ。深田由希役に二人して立ち向かってちょうどバランス、くらいでいいんじゃないかっていう気もします・・・っておふたかたに失礼かもしらんが(=^_^;=)。
この駄文を書いたことで、なにかがどこかでいい方向にころがってくれるといいなあ、なんて、世の中に対してちょっとリクエストしておきます。ではまた。
*
*1
ところで、おれ鉄ヲタじゃないから思い当たる路線がないんだけど、作中の「桐生型」という車輌にも思い当たるふしがないんだけど、この山花鉄道って、どこかモデルになってる路線があるんだろうか。「山花、という楽器メーカー」が「ヤマハ」をモデルにしたものなのだろうということは容易に想像がつくんだけど、「山葉線」という路線はないしなあ(ヤマハは、山葉寅楠さんというひとが創立したメーカーなんです)。
そいや松浦鉄道が「名前が同じなのだからお願いできませんか」っつーて松浦亜弥に知名度向上のための協力話を持ちかけ、しかしあっさり断られたというケースがあったような、おぼろげな記憶があります。松浦亜弥にとっても悪い話じゃなかっただろうに、断ったマネジメント担当とか駄目駄目だったんじゃねーの、とか思うおれ。
*2
あ、ほれ。おれってコンピュータネットワークってけっこう好きじゃないですかあ。パソコン通信もインターネットも。でだ。
もうほとんどのひとが忘れている作品だと思うんだが、山口よしのぶによる『名物!たびてつ友の会』っていう漫画作品があったんですよ。その中に未成線(途中まで建設されたのだが結局開通にはいたらなかった路線)を扱った『幻の佐久間線』というエピソードがあったんですよね。主人公のIT企業の営業さんが、結局鉄道が通らなかった田舎に営業にいって、「人と人とをつなぐ技術」についてしみじみしちゃうっていう話です。
まあ、IT側から見たときには、それだけだったら話は浅いしありがちで無駄な公共事業なんじゃねーの、みたいな感じもあったんですが、たぶん大事なんだが描かれなかったことがあったんだろうと思うことにして見過ごします。
*3
おれはまあ、廃線のサイクリングロード化工事やバス専用道路化工事に何十億もの金を投じる余裕が実際にはあるんだから(苦笑するしかないんだが、前者が80億円、後者が10億円)、「年間数千万円程度の赤字ならば赤字補填をすりゃいいじゃん」とか思っているのですが。
ま、どこにある金をどこに流すかというスキームがぼろぼろだからそこから見直さないと話はじまんない面はあって、しかしそんな見直しが有効に実現するのを待っていたら鉄道っていうか公共交通機関が持たないってのが現実で、頭痛いんだけどね。
*4
自叙伝本商法、最近けっこう詐欺商法とかゆーて問題になってきているのだが、個人的には「ちゃんと本を渡すところまでこぎつけていたら、詐欺呼ばわりをするのは言いすぎじゃん」とか思ってます。ただ、プロとしての編集の手間を惜しんでいる会社が多そうに見えるのがちょっとなんだなあ、詐欺ってほど悪くはないが手抜きくらいのそしりは免れ得ないのではないか、という気配はあり。
ついでに、「本にしたとしてもみすぼらしい人生にしかならないひと」(ひでえ言い方だなあ)にまで売り込まない、という程度の矜持は最低限のものとして、必要かもしんない。
*5
早い話が「誰が真の顧客なのかという視点から見直せばビジネスモデルの見え方も違ってくる」ってこと。自叙伝商法は、人生を見直して肯定的な気分になりたいご老人に満足してもらい、対価をいただく。本の読者は顧客じゃない。チケットノルマのある音楽・演劇などは、出演者に場を売るのが目的だからお客さんは出演者、見に来るひとはお客じゃない。そう割り切ればそうそう理不尽な商売には見えないだろ、ってこと。
自叙伝を書くご老人や出演者などに満足してもらえなかったら商売として成り立たないのだが、そこだけ満足してもらえればそれで良くて、そこで読者や観客にへたにひきずられると道を見誤る。それはそれで、割り切りとしてはありだろうな。
*6
いすみ鉄道の自費運転士募集に対してぶつけられた悪口の大半、あるいは全ては、この路線のどっしょーもないものだった。誰かが趣味にいくら使おうがそんなもんほっとけっちゅうの。
ただ、いすみ鉄道の方法論も全面的に肯定できるわけでもない。いすみ鉄道の運転士募集は、一発だけのイベントではなく継続的な勤務を前提としたものであり、ところがそのいすみ鉄道は経営的にけっこう危機な状況にあるわけで、「自腹で免許を取ってはもらったけれども、運転すべき路線がなくなってしまう」という最悪のシナリオだってあり得る。もしそのリスクについての認識が食い違っていたら、けっこう悲しい顛末になるかもしれない。
*7
覚えている範囲で、「乗って残そう○○線」とか言っていたにもかかわらず廃止を免れ存続できた路線って、北勢線くらいのような気がする(証拠)。その北勢線にしても「乗客が増えて存続にこぎつけた」わけではない。もしかすっと南海電鉄貴志川線(現わかやま電鉄)でも存続派活動家が言ってたかもしれないけど(微妙にベクトルが違う立看板の証拠)。
この2線は、公共交通機関の位置づけを見直すという流れを作り出すことができたからこそ存続できたんじゃないのかと思う。存続決定後は乗客は増えて収支も好転しつつあるようだけど、乗ってるひとは残そうと思って乗ってるわけじゃない、使い途があるから乗ってるだけなんで、その2つの事象の間には天と地くらいの開きがあるんだ。貴志川線は「猫駅長ブーム」の火付け役にまでなっちゃいましたからねえ。猫的にはあんまし幸せじゃないような気がするんだけれども、誰だか知らんけど観光資源として猫駅長のプランを売り出すことを考えたやつはすごかった(もともとは単に、売店のひとが自分ちの猫をかわいがってただけだったんだが(=^_^;=))。
まあ乗客を増やし収入を増やすというのは王道なんだけれども、「採算が取れるほどの乗客なんて、そうそう簡単にはみつからない」という前提を確認していないがゆえにこのフレーズを安易に出せているような気がしてならないんだ。だからこの「乗って残そう○○線」というフレーズを出せるところは、「どんづまりの開き直り」であるか「考えが浅く現実を変えられるだけの力がないことの表明」であるか、どちらかになってしまう。前者ならもう「死ぬ気でがんばれ」とエールを送るしかないんだけど、後者だと痛々しくて見ていられない。
ある意味でおれにとっては、「乗って残そう○○線」というフレーズは「それが出てきたらもうだめなんじゃなかろうかと判断していい」という指標フレーズになっちゃってる。「『憲法違反』という訴因は敗訴を覚悟した証である」みたいなもんだね。
*8
鉄道再生までを視野にいれたものじゃないとは思うんだけど、2010年5月公開の、山陰は一畑電鉄を舞台にした『Railways』という映画があったっしょ。あの映画のプロモーションの一部に、そこはかとなく『D列車でいこう』と似たにおいを感じたりするんですよね。
似たもの並立でコケそうになったら、逆にこんな感じで「全国の赤字ローカル線連合」でぱーっと話題を立ち上げて「あなたの好きな場所を選んで行ってみませんか」といったベクトルの縦断的観光キャンペーンをやる、なんてのはありかしんない。
ま、いずれにせよどこかが成功してからのちの話ですが。
*9
久々に本職のお仕事が迷い込んできていたのだが、なんかついにディレクターから編集オペレータに格下げになったような気もしてるわけですが(それって格下げなのか(=^_^;=))、オペレータへの格下げはいいんだけどなんでマシンがマッキントッシュなんだーと悲鳴をあげていたりもするわけですが(=^_^;=)、その仕事に阪神淡路大震災が登場。「耐震性の訴求にまだ阪神淡路を使うつもりかっ」という感じもなきにしもあらずだけど、逆に言えば15年ほどは都市型の震災って起きてないってことなんだよな(都市型ではないやつは、新潟や岩手でありました。忘れてるわけじゃありません)。
この本を買った当日にも阪神淡路の映像を編集してたものですから、なんかシンクロニシティだなあみたいな妙なインパクトもあったんでした。 続きを読む
2009年11月25日
角川春樹『笑う警官』を見てきた
佐々木譲原作/角川春樹脚本・監督の『笑う警官』を見てきた。なんかものすげえ釈然としませんでした。ものすげえ釈然としなかったもので4日ほど考えてしまいました。
ようやくまとまったので書く。ま、こんなところだろうと思う。
佐々木譲のどこが凄いのか。おれの観点からは、それは「しっかりと事実関係をふまえ社会的背景をおさえた上で、きっちりエンターティンメントとして物語を成立させる」ということであるように思います。社会派作家というのは珍しくもありませんが、それらの多くは自分の問題意識を重視するあまり問題意識を共有できない読者には響かない作品にしてしまう。エンターティンメント作家というのも珍しくありませんが、こちらは物語を練ることに熱中してしまい反射効として社会性を希薄にしてしまう。
まあ、どこにどうバランスポイントを求めるかというのは作家や読者が勝手に決めればいいことなんですが、おれは「佐々木譲はそのバランス感覚という点で特筆すべきものがある」ような気がする。映画『笑う警官』は、残念ながら佐々木譲がせっかく組み立てたその絶妙なバランスをぶっこわしてしまっていた。
いやあ。そこを生かさないのなら佐々木譲作品を原作に選ぶ意味はないのではないか。なんか悲しいなぁ。
実は、見始めてしばらくの間は「ずいぶん話をはしょって進めてるなあ」と思っていたんですよね。まあ小説を忠実に映画にすると何時間になるかわかんないことが多いわけで、尺を詰めるために話をはしょることは珍しくもない。そのせいだろうと思ってました。しかしそうじゃなくて、いらん要素を新たに付け加え話を無駄にややこしくした結果尺が足らずオリジナルの物語をはしょらざるを得なくなったのだ、ということだったようです。もちろん付け加えた部分があればいずれにせよオリジナルの物語とは衝突したりするのでそのまま作るわけにはいかなくなるんですが。
原作つきの映画を10本見ると、少なく見積もってうち9本で、「なんで物語に手を入れるんだろう」と思ってしまいます。すぐれた原作にほれこんで映画化をしようと思ったのならば、その原作の世界を忠実に再現することに熱中すれば良いではないか。
まあ原作通りに作ろうとすると金も時間もかかるから無理です、っていうケースは多々あります。そこでしょうがなしの妥協としてはしょるのは、それはそれでしょうがない、かもしれません(*1)。
しかしね。逆のパターン、「余計なことを付け加えてぐっちゃぐちゃ」っていうのは、あまり多くは見かけないんですよね。まだ「換骨奪胎全然違う物語になっちゃいました」のが多いくらいだ。
なんだってまた角川春樹はこんな隘路に陥ってしまったんですかねえ。結果として原作の『笑う警官』ではクライマックスとなる重要なシーンが大きくカットされてしまっていたりして、ちょっとかなわんなあって感じでございます。
余計なことの中には佐伯宏一(大森南朋)と小島百合(松雪泰子)とのロマンスなんかも含まれます。それは、続編の『警察庁から来た男』の伏線になってる話だろーが。
配役だの演出だのにも山ほど駄目出しをしたいところがありますが、まあそこらへんはここで長く書いても意味ないから、自粛しときます。
ただまあなんだ。貶し一本調子ってのもなんですので。
映画はなんだかなぁでしたけど、小説は凄いんです。あちこちのweblogの感想とか見てると「原作が悪いのか監督が悪いのか」みたいな声がちらほらあった。原作、読んでみてください。あれはもう全くの別物だから。
ところで、最後にバーのマスターやってた大友さんが橋の上から投げ捨ててたの、誰の死体だったんでしょうか。おれ、わかんなかったんですけど。
*1
佐々木譲の『真夜中の遠い彼方』の映画化作品である若松孝二の『われに撃つ用意あり』はこっちのパターン。とはいえ、必要予算と現実的予算が「百対一」とか食い違っていて映画化しようと思うのは、それは「無謀」というものだろう。『われに撃つ』は、ちょっと評価のしようがないくらいの駄作だった。
*
おまけ。
物語の舞台は札幌です。札幌市電も何カットか出てきたりします。

<札幌市電> 中央図書館前駅に停車中のM100 [direct]
で、物語の舞台は札幌。重要な場所として、すすきののバーとか、北海道警本部とか、北海道議会議事堂とかがあります。ところがですね、ほとんど札幌でロケをやっていないっぽいんですね。
最後に目的地として登場する北海道議会議事堂なんて、コレですもん↓。おーい・・・。

<茨城県庁三の丸庁舎> 正面 [direct]
いやさあ。見た瞬間「三の丸庁舎じゃん・・・」と思うやつなんてどうせ多くはないだろうと思うんですよ(*2)。ついでに、『笑う警官』以降の佐々木譲の北海道警シリーズって北海道警のスキャンダルを重要な要素としていますから、北海道警の撮影許可を取るのはたいへんだろうとも思うわけです。いらん制約つけられたりするだろうしな。しかしね。
今だったらCGとかいっくらでも手はあるんじゃねーの、それなりに金かけて大作映画作るんだったらさ。
この佐々木譲の「北海道警シリーズ」てのは「北海道」というのを重要な軸としている作品群なわけでなあ。もうちょっとなんとかなんとかなんなかったんでしょうかねえ。それとも、そんなことはどうでもいいとか思っちゃったんかしら。
*2
本体のページにも書いてあるんですが、フィルムコミッションががんばりすぎてて、茨城県庁三の丸庁舎はもう露出過多になりつつあります。いい建物ではあるんだけどねーやつも忙しすぎるとか思っているのではないか。
今改めてざっと調べたところ、三の丸庁舎の主な出演実績は以下のとおり。
・日本テレビ「小泉純一郎5つの謎」
・TBSテレビ「松本清張ドラマ“波の塔”」
・TBS「検察審査会」
・フジテレビ「遥かなる約束」
・フジテレビ「紅の紋章」
・フジテレビ「潮風の診療所〜岬のドクター奮戦記」
・フジテレビ「医龍」
・フジテレビ「壁ぎわ税務官」
・テレビ朝日「相棒」
・テレビ朝日「PS 羅生門」
・テレビ朝日「仮面ライダーカブト」
・テレビ朝日「警視庁捜査一課9係」
・テレビ朝日「愛と死をみつめて」
・テレビ朝日「富豪刑事」
・テレビ東京「新米事件記者・三咲2」
・テレビ東京 「上を向いて歩こう〜坂本九物語〜」
・映画「日本の青空」
・映画「NANA2」
・映画「日本以外全部沈没」
・映画「バブルへGO!」
・映画「県庁の星」
・映画「半落ち」
・・・他、ものすごく多数。
ようやくまとまったので書く。ま、こんなところだろうと思う。
佐々木譲のどこが凄いのか。おれの観点からは、それは「しっかりと事実関係をふまえ社会的背景をおさえた上で、きっちりエンターティンメントとして物語を成立させる」ということであるように思います。社会派作家というのは珍しくもありませんが、それらの多くは自分の問題意識を重視するあまり問題意識を共有できない読者には響かない作品にしてしまう。エンターティンメント作家というのも珍しくありませんが、こちらは物語を練ることに熱中してしまい反射効として社会性を希薄にしてしまう。
まあ、どこにどうバランスポイントを求めるかというのは作家や読者が勝手に決めればいいことなんですが、おれは「佐々木譲はそのバランス感覚という点で特筆すべきものがある」ような気がする。映画『笑う警官』は、残念ながら佐々木譲がせっかく組み立てたその絶妙なバランスをぶっこわしてしまっていた。
いやあ。そこを生かさないのなら佐々木譲作品を原作に選ぶ意味はないのではないか。なんか悲しいなぁ。
実は、見始めてしばらくの間は「ずいぶん話をはしょって進めてるなあ」と思っていたんですよね。まあ小説を忠実に映画にすると何時間になるかわかんないことが多いわけで、尺を詰めるために話をはしょることは珍しくもない。そのせいだろうと思ってました。しかしそうじゃなくて、いらん要素を新たに付け加え話を無駄にややこしくした結果尺が足らずオリジナルの物語をはしょらざるを得なくなったのだ、ということだったようです。もちろん付け加えた部分があればいずれにせよオリジナルの物語とは衝突したりするのでそのまま作るわけにはいかなくなるんですが。
原作つきの映画を10本見ると、少なく見積もってうち9本で、「なんで物語に手を入れるんだろう」と思ってしまいます。すぐれた原作にほれこんで映画化をしようと思ったのならば、その原作の世界を忠実に再現することに熱中すれば良いではないか。
まあ原作通りに作ろうとすると金も時間もかかるから無理です、っていうケースは多々あります。そこでしょうがなしの妥協としてはしょるのは、それはそれでしょうがない、かもしれません(*1)。
しかしね。逆のパターン、「余計なことを付け加えてぐっちゃぐちゃ」っていうのは、あまり多くは見かけないんですよね。まだ「換骨奪胎全然違う物語になっちゃいました」のが多いくらいだ。
なんだってまた角川春樹はこんな隘路に陥ってしまったんですかねえ。結果として原作の『笑う警官』ではクライマックスとなる重要なシーンが大きくカットされてしまっていたりして、ちょっとかなわんなあって感じでございます。
余計なことの中には佐伯宏一(大森南朋)と小島百合(松雪泰子)とのロマンスなんかも含まれます。それは、続編の『警察庁から来た男』の伏線になってる話だろーが。
配役だの演出だのにも山ほど駄目出しをしたいところがありますが、まあそこらへんはここで長く書いても意味ないから、自粛しときます。
ただまあなんだ。貶し一本調子ってのもなんですので。
映画はなんだかなぁでしたけど、小説は凄いんです。あちこちのweblogの感想とか見てると「原作が悪いのか監督が悪いのか」みたいな声がちらほらあった。原作、読んでみてください。あれはもう全くの別物だから。
ところで、最後にバーのマスターやってた大友さんが橋の上から投げ捨ててたの、誰の死体だったんでしょうか。おれ、わかんなかったんですけど。
*1
佐々木譲の『真夜中の遠い彼方』の映画化作品である若松孝二の『われに撃つ用意あり』はこっちのパターン。とはいえ、必要予算と現実的予算が「百対一」とか食い違っていて映画化しようと思うのは、それは「無謀」というものだろう。『われに撃つ』は、ちょっと評価のしようがないくらいの駄作だった。
*
おまけ。
物語の舞台は札幌です。札幌市電も何カットか出てきたりします。

<札幌市電> 中央図書館前駅に停車中のM100 [direct]
で、物語の舞台は札幌。重要な場所として、すすきののバーとか、北海道警本部とか、北海道議会議事堂とかがあります。ところがですね、ほとんど札幌でロケをやっていないっぽいんですね。
最後に目的地として登場する北海道議会議事堂なんて、コレですもん↓。おーい・・・。

<茨城県庁三の丸庁舎> 正面 [direct]
いやさあ。見た瞬間「三の丸庁舎じゃん・・・」と思うやつなんてどうせ多くはないだろうと思うんですよ(*2)。ついでに、『笑う警官』以降の佐々木譲の北海道警シリーズって北海道警のスキャンダルを重要な要素としていますから、北海道警の撮影許可を取るのはたいへんだろうとも思うわけです。いらん制約つけられたりするだろうしな。しかしね。
今だったらCGとかいっくらでも手はあるんじゃねーの、それなりに金かけて大作映画作るんだったらさ。
この佐々木譲の「北海道警シリーズ」てのは「北海道」というのを重要な軸としている作品群なわけでなあ。もうちょっとなんとかなんとかなんなかったんでしょうかねえ。それとも、そんなことはどうでもいいとか思っちゃったんかしら。
*2
本体のページにも書いてあるんですが、フィルムコミッションががんばりすぎてて、茨城県庁三の丸庁舎はもう露出過多になりつつあります。いい建物ではあるんだけどねーやつも忙しすぎるとか思っているのではないか。
今改めてざっと調べたところ、三の丸庁舎の主な出演実績は以下のとおり。
・日本テレビ「小泉純一郎5つの謎」
・TBSテレビ「松本清張ドラマ“波の塔”」
・TBS「検察審査会」
・フジテレビ「遥かなる約束」
・フジテレビ「紅の紋章」
・フジテレビ「潮風の診療所〜岬のドクター奮戦記」
・フジテレビ「医龍」
・フジテレビ「壁ぎわ税務官」
・テレビ朝日「相棒」
・テレビ朝日「PS 羅生門」
・テレビ朝日「仮面ライダーカブト」
・テレビ朝日「警視庁捜査一課9係」
・テレビ朝日「愛と死をみつめて」
・テレビ朝日「富豪刑事」
・テレビ東京「新米事件記者・三咲2」
・テレビ東京 「上を向いて歩こう〜坂本九物語〜」
・映画「日本の青空」
・映画「NANA2」
・映画「日本以外全部沈没」
・映画「バブルへGO!」
・映画「県庁の星」
・映画「半落ち」
・・・他、ものすごく多数。
2009年07月23日
映画『私は猫ストーカー』
本日のお散歩。なんとにゃく映画『私は猫ストーカー』を見に行く。特に理由はないというか、星野真里がハセキョンの次のマイブームであるせいとでも申しますか(=^_^;=)。
ついでなんで最近更新できていない猫ページ用の写真も散らしておきます。更新が滞っている理由は後述。

最近顔見知りになった薄茶色の子。まあ道路にはいつくばるのとかってデフォルトですよね。
えーと個人的には、映画の評価は低いです(でも最後まで読め(=^_^;=))。
なんていうか、プライベートフィルムっぽいルックを目指したのかもしれませんが、かなりはずしちゃってたなあという感じ。アマチュアフィルムじゃないんだから整音くらいちゃんとやってくれとも思った。聞こえなくてもいい台詞だったのかもしれませんが、ならばそういう処理の仕方があるだろうし。
そいから、おれアンチロマンって嫌いじゃないしこういうテーマならば淡々とやってきゃよさそうに思うんですが、無理にドラマを盛り込もうとしてるようにも見えてそこらへんもマイナス。

こないだ出先で知り合った子。愛想が良かったのでノラじゃないのかもしれません。木の上に雀がとまったので勇んで木登りをしたのだが逃げられてしまいますた。
決定的だったのは、星野真里が宮崎将なのかな、に、不忍池のほとりで猫ストーキングの方法を教えるシーン。
シーンそのものが、そもそもいらんかったような気がする。
それに、迷い猫を探しながら不忍池まで来てしまうのですが、迷い猫は根津か入谷かどっかそこらへんの子であるはずなのに不忍池までその猫を探しにきたら「熟達の猫ストーカー」という星野真里の設定が崩れてしまうではあーりませんか、と(なぜ崩れるのかわからないひと多いと思うが理由は聞かないでくれ)。
だいたいここで二人とたわむれる猫が、どう見ても野良猫に見えんのです。若くて育ちの良いとてもかわいがられて育った「人間を恐れていない猫」なんですよね。おまいらちゃんとオーディションしたのか、その猫の演技力はどうだったのか、いったいどういう演出をつけたのだ、と。
いやあ、なんかもう容赦ないわけですが(=^_^;=)。

お馴染み貞一貞子です。しかし最近その定位置が後述のアカブチンに取られてしまいまして、ごく稀にしか見かけなくなってしまいました。
けなしてばかりってのもなんですので。
えーと、まず。そういうわけで星野真理はかわいかったっす。はぁと。
それからなんだなぁ。
おれ的には車の下を確認するのとか道路にねっころがるのとかはもうデフォルトの行動なんで、星野真理の行動に違和感はなくあったりまえのことではあったのですが、そういう感覚がないひとにはそれなりに面白いんじゃないかというシーンがありましたね。他者観察ネタってゆーか。
んで、そういうわけで映画的にはちょっとどーかという気がしなくもなかったわけだが、原作とされている浅生ハルミン氏の本は、エッセイらしいんですね。
これね。元は淡々としたエッセイなのに、そこにむりやりドラマツルギーを構築して映画に仕上げようと試みたからこうなっちゃっただけなんかもしれない。まだ読んでないんだけどもエッセイは期待できるんじゃないかなあという気がした。本屋で見かけたら手に取ってみましょう。気に入ったら買うかもしれない(ってゆーか、最近近場から本屋が消滅しちゃってさあ。徒歩20分圏内にはそれなりの規模の郊外型書店が、徒歩40分圏内には近隣最大規模の書店が、あるのですが、いずれもおれの動線にはいってないんだよな)。
んで、と。「猫のいる風景」更新遅れの言いわけ。



1枚目。知り合った頃のアカブチン。ちゃんと正座をしている礼儀正しいコだった。
2枚目。最近のアカブチン。道路で寝っころがっており、挨拶もしやがらねえ横柄でずぶとい猫になってしまった。近づくと逃げやがるんだけど。
3枚目。数日前のアカブチン。もういっちょまえの歴戦の勇者気分であられるらしい。睥睨されちゃってるもんなー。戦歴も増え自信をつけているようでもある(=^_^;=)。
いやー。鉄道のある風景の方のシステム開発をいろいろ進めていたのですが、猫のいる風景のシステム更新が遅れてて、バージョン合わせをしないと動かない・・・はずなんですよね。たいして手間ではないとは思うんですが気分的に面倒でさ(=^_^;=)。
というわけで、まあおいおい、近いうちに。

スーパー裏のコ。最近誰も見かけなくなっていたのですが、誰もいなくなったわけではなかったらしい。おなかが大きいような気がするんですが、このコ男の子だったような気がするんだよなあ。単にメタボなだけかもしれません。
*
んで、映画を見たあとは、近所のストーキングエリアへ。ま、有名なバーとかが並んでるところですよ。エリア内無許可撮影禁止なんで見かけても写真撮れないんだよなーでもゲリラしちゃうもんねとか思いながら行ったわけですが、天気のせいかほとんど誰にも会わず。若干2にゃんのみ。
そのあと渋谷にまわって東急渋谷駅。コンデジでしか撮ってなかったものでクォリティアップ狙い。だんだん最後の日も近づいてきていますし。
最後に東急世田谷線。最近広告電車がなくなっちゃったらしいので原色をまとめ撮り。日没まで粘って終了。
更新は、鉄道ネタはなるべく早めに。猫ネタは・・・まあがんばりますって感じです(=^_^;=)。ではまた。
ついでなんで最近更新できていない猫ページ用の写真も散らしておきます。更新が滞っている理由は後述。

最近顔見知りになった薄茶色の子。まあ道路にはいつくばるのとかってデフォルトですよね。
えーと個人的には、映画の評価は低いです(でも最後まで読め(=^_^;=))。
なんていうか、プライベートフィルムっぽいルックを目指したのかもしれませんが、かなりはずしちゃってたなあという感じ。アマチュアフィルムじゃないんだから整音くらいちゃんとやってくれとも思った。聞こえなくてもいい台詞だったのかもしれませんが、ならばそういう処理の仕方があるだろうし。
そいから、おれアンチロマンって嫌いじゃないしこういうテーマならば淡々とやってきゃよさそうに思うんですが、無理にドラマを盛り込もうとしてるようにも見えてそこらへんもマイナス。

こないだ出先で知り合った子。愛想が良かったのでノラじゃないのかもしれません。木の上に雀がとまったので勇んで木登りをしたのだが逃げられてしまいますた。
決定的だったのは、星野真里が宮崎将なのかな、に、不忍池のほとりで猫ストーキングの方法を教えるシーン。
シーンそのものが、そもそもいらんかったような気がする。
それに、迷い猫を探しながら不忍池まで来てしまうのですが、迷い猫は根津か入谷かどっかそこらへんの子であるはずなのに不忍池までその猫を探しにきたら「熟達の猫ストーカー」という星野真里の設定が崩れてしまうではあーりませんか、と(なぜ崩れるのかわからないひと多いと思うが理由は聞かないでくれ)。
だいたいここで二人とたわむれる猫が、どう見ても野良猫に見えんのです。若くて育ちの良いとてもかわいがられて育った「人間を恐れていない猫」なんですよね。おまいらちゃんとオーディションしたのか、その猫の演技力はどうだったのか、いったいどういう演出をつけたのだ、と。
いやあ、なんかもう容赦ないわけですが(=^_^;=)。

お馴染み貞一貞子です。しかし最近その定位置が後述のアカブチンに取られてしまいまして、ごく稀にしか見かけなくなってしまいました。
けなしてばかりってのもなんですので。
えーと、まず。そういうわけで星野真理はかわいかったっす。はぁと。
それからなんだなぁ。
おれ的には車の下を確認するのとか道路にねっころがるのとかはもうデフォルトの行動なんで、星野真理の行動に違和感はなくあったりまえのことではあったのですが、そういう感覚がないひとにはそれなりに面白いんじゃないかというシーンがありましたね。他者観察ネタってゆーか。
んで、そういうわけで映画的にはちょっとどーかという気がしなくもなかったわけだが、原作とされている浅生ハルミン氏の本は、エッセイらしいんですね。
これね。元は淡々としたエッセイなのに、そこにむりやりドラマツルギーを構築して映画に仕上げようと試みたからこうなっちゃっただけなんかもしれない。まだ読んでないんだけどもエッセイは期待できるんじゃないかなあという気がした。本屋で見かけたら手に取ってみましょう。気に入ったら買うかもしれない(ってゆーか、最近近場から本屋が消滅しちゃってさあ。徒歩20分圏内にはそれなりの規模の郊外型書店が、徒歩40分圏内には近隣最大規模の書店が、あるのですが、いずれもおれの動線にはいってないんだよな)。
んで、と。「猫のいる風景」更新遅れの言いわけ。



1枚目。知り合った頃のアカブチン。ちゃんと正座をしている礼儀正しいコだった。
2枚目。最近のアカブチン。道路で寝っころがっており、挨拶もしやがらねえ横柄でずぶとい猫になってしまった。近づくと逃げやがるんだけど。
3枚目。数日前のアカブチン。もういっちょまえの歴戦の勇者気分であられるらしい。睥睨されちゃってるもんなー。戦歴も増え自信をつけているようでもある(=^_^;=)。
いやー。鉄道のある風景の方のシステム開発をいろいろ進めていたのですが、猫のいる風景のシステム更新が遅れてて、バージョン合わせをしないと動かない・・・はずなんですよね。たいして手間ではないとは思うんですが気分的に面倒でさ(=^_^;=)。
というわけで、まあおいおい、近いうちに。

スーパー裏のコ。最近誰も見かけなくなっていたのですが、誰もいなくなったわけではなかったらしい。おなかが大きいような気がするんですが、このコ男の子だったような気がするんだよなあ。単にメタボなだけかもしれません。
*
んで、映画を見たあとは、近所のストーキングエリアへ。ま、有名なバーとかが並んでるところですよ。エリア内無許可撮影禁止なんで見かけても写真撮れないんだよなーでもゲリラしちゃうもんねとか思いながら行ったわけですが、天気のせいかほとんど誰にも会わず。若干2にゃんのみ。
そのあと渋谷にまわって東急渋谷駅。コンデジでしか撮ってなかったものでクォリティアップ狙い。だんだん最後の日も近づいてきていますし。
最後に東急世田谷線。最近広告電車がなくなっちゃったらしいので原色をまとめ撮り。日没まで粘って終了。
更新は、鉄道ネタはなるべく早めに。猫ネタは・・・まあがんばりますって感じです(=^_^;=)。ではまた。
2006年01月28日
「ALWAYS 三丁目の夕日」を見てきた
いやあ、いろいろと話題になってた映画なもんで、見てきました。
話題のベクトルとしては、そうね、まあひとつは昭和ノスタルジーですね。しかしまあ、なんかとんでもない特撮をいろいろやっているらしいと聞いていて、おれ的にはそっちの方に興味を持っていた。たしかに、とんでもないことをいろいろやっていました。特撮って手間を惜しまなければもうここまでやれるところまで来てしまったんだなぁ、みたいな。技術的には、モーション・コントロール・カメラを使って撮影した素材の合成あたりがものすごかった。しかしまあ、そんなことは映画としてはどーでもいいことだ。
なんかね。主人公のひとりである六子が上野駅に到着するシーンあたりで、思わず歓声を上げてしまいました。どっかでこの感じはデジャ・ヴュだった。何なのかを考えてみたところ、どうやら「ジュラシックパーク」で最初に恐竜が登場するシーンと感じが似ている。二度と、あるいは永遠に、見ることができないだろうと諦めていたシーンが目の前に展開しているという驚き、みたいなものでしょうか。ま、上野駅のシーンあたりなら古い写真とかでいくらでも見れるんですけど、今のルックの映像として見ることが出来るというのはやっぱり驚きなわけで(ルックちゅうのもわかりづらいのだが、映画なんかにしても、画質やらなんやらが時代によって異なるもので、2006年の映画のルックは明らかに当時のニュース映画のルックとは異なるんだ)。
物語は、ドラマチックじゃないです。「となりのトトロ」なんかと同じように、ドラマらしいドラマがあるわけじゃない。そりゃまあ、ドラマが全然ないようなヌーヴェルバーグなものとは違ってそれなりに小さなドラマは積み重ねられているんで「物語の筋がないものに付き合わされる」ような苦痛はないんですが、にしても細かな日常の風景が積み重ねられていくだけで、この映画は始まって終わります。そのせいか、プログラムにもあらすじを紹介する項目がなかったような気がする(笑)。
しかしまあ、人生なんてそうそうドラマチックなもんじゃないしね。無理やりドラマを仕込まれてもおれはついていけなくて困るので、これでかまいません。
その淡々とした日常が2時間にわたって展開されるわけですけど、2時間、違和感なく昭和の風景が展開されるわけなのだなあ。ぼーっとBGVのように眺めているとキモチいいっていうか。ま、見る価値はある映画だったと思います。たぶんおれはDVDが出たら買ってしまうのではないだろうか。
さて。いちおう風景ネタとつなげておく。
ここしばらく(もう10年くらいになるんだなあ)、ふつーの町並みの風景ってのを撮り続けてきてるわけですが。改めて昭和の風景を眺めるということは、今の町並みとの差分を確認することにもなったりするわけです。
ずいぶん変わったようでもあり、たいして変わっていないようでもあり。まあ、町並みなんてある日突然がらっと変わるものではなく(いや、ときどきそういう変わり方をする場合もあるのだが)、穏やかにゆっくりと変わって行くもの。その時間的な連続性を意識しないと「どう変わったのか」がわかりづらいものだったりもします。その差分を確認することもまた、ちょっと楽しいものではありました。
====
おまけ。
上野駅から鈴木オート(虎ノ門のあたりが想定されていたらしい)まで六子が移動する際の車窓に堺屋ビルが出てきました。堺屋ビルは、上野池之端の古いビルで、正確な建築年代はおれにはわかっていないのだが、大正年代のものであるらしい。おそらく関東大震災復興建築のひとつでしょう。

<堺屋商店ビル>
こんなのがさりげなく登場したりするのも、楽しかった。
話題のベクトルとしては、そうね、まあひとつは昭和ノスタルジーですね。しかしまあ、なんかとんでもない特撮をいろいろやっているらしいと聞いていて、おれ的にはそっちの方に興味を持っていた。たしかに、とんでもないことをいろいろやっていました。特撮って手間を惜しまなければもうここまでやれるところまで来てしまったんだなぁ、みたいな。技術的には、モーション・コントロール・カメラを使って撮影した素材の合成あたりがものすごかった。しかしまあ、そんなことは映画としてはどーでもいいことだ。
なんかね。主人公のひとりである六子が上野駅に到着するシーンあたりで、思わず歓声を上げてしまいました。どっかでこの感じはデジャ・ヴュだった。何なのかを考えてみたところ、どうやら「ジュラシックパーク」で最初に恐竜が登場するシーンと感じが似ている。二度と、あるいは永遠に、見ることができないだろうと諦めていたシーンが目の前に展開しているという驚き、みたいなものでしょうか。ま、上野駅のシーンあたりなら古い写真とかでいくらでも見れるんですけど、今のルックの映像として見ることが出来るというのはやっぱり驚きなわけで(ルックちゅうのもわかりづらいのだが、映画なんかにしても、画質やらなんやらが時代によって異なるもので、2006年の映画のルックは明らかに当時のニュース映画のルックとは異なるんだ)。
物語は、ドラマチックじゃないです。「となりのトトロ」なんかと同じように、ドラマらしいドラマがあるわけじゃない。そりゃまあ、ドラマが全然ないようなヌーヴェルバーグなものとは違ってそれなりに小さなドラマは積み重ねられているんで「物語の筋がないものに付き合わされる」ような苦痛はないんですが、にしても細かな日常の風景が積み重ねられていくだけで、この映画は始まって終わります。そのせいか、プログラムにもあらすじを紹介する項目がなかったような気がする(笑)。
しかしまあ、人生なんてそうそうドラマチックなもんじゃないしね。無理やりドラマを仕込まれてもおれはついていけなくて困るので、これでかまいません。
その淡々とした日常が2時間にわたって展開されるわけですけど、2時間、違和感なく昭和の風景が展開されるわけなのだなあ。ぼーっとBGVのように眺めているとキモチいいっていうか。ま、見る価値はある映画だったと思います。たぶんおれはDVDが出たら買ってしまうのではないだろうか。
さて。いちおう風景ネタとつなげておく。
ここしばらく(もう10年くらいになるんだなあ)、ふつーの町並みの風景ってのを撮り続けてきてるわけですが。改めて昭和の風景を眺めるということは、今の町並みとの差分を確認することにもなったりするわけです。
ずいぶん変わったようでもあり、たいして変わっていないようでもあり。まあ、町並みなんてある日突然がらっと変わるものではなく(いや、ときどきそういう変わり方をする場合もあるのだが)、穏やかにゆっくりと変わって行くもの。その時間的な連続性を意識しないと「どう変わったのか」がわかりづらいものだったりもします。その差分を確認することもまた、ちょっと楽しいものではありました。
====
おまけ。
上野駅から鈴木オート(虎ノ門のあたりが想定されていたらしい)まで六子が移動する際の車窓に堺屋ビルが出てきました。堺屋ビルは、上野池之端の古いビルで、正確な建築年代はおれにはわかっていないのだが、大正年代のものであるらしい。おそらく関東大震災復興建築のひとつでしょう。

<堺屋商店ビル>
こんなのがさりげなく登場したりするのも、楽しかった。
-- Livedoor's --