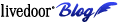2010年08月10日
『シルビアのいる街で』〜石畳が奏でる音〜
監督:ホセ・ルイス・ゲリン
出演:グザヴィエ・ラフィット ピラール・ロペス・デ・アジャラ ダーニア・ツィシーほか
【あらすじ】(goo映画より)
朝、青年はホテルの一室で目を覚まし、地図を片手に街を歩き出した。2日目、演劇学校の前にあるカフェで、青年はそこにいる女性たちをひとりひとり観察し、ノートにデッサンを描く。やがてガラス越しにひとりの女性の姿を見つけた青年は、カフェを出て行く彼女の後を追う。後ろから女性に「シルビア」と声をかける青年だが、返事はない。女性を見失いかける青年だが、市電に乗り込む姿を見つけ、後を追う…。
夏休み映画の「中〆」に、元々はイメージフォーラムで『シルビアのいる街で』を見て、
その後ユーロスペースで『ペルシャ猫を誰も知らない』を見るという段取りで、
朝一番にイメージフォーラムに行ってみると、イメージフォーラム前には
私がこれまでお目にかかったことのないほど長い行列ができていました。
1ブロックをとりまくほどの行列の長さにおそれをなし、ここは予定を変更して
ユーロスペースで『ペルシャ猫を誰も知らない』を見てから
再びイメージフォーラムに行ってみると、運良く『シルビアのいる街で』を
見ることができました。
『シルビアのいる街で』は、ハスミン(蓮實重彦)のみならず、ビクトル・エリセ監督が
「今のスペインで最も優れた監督」 と絶賛していることもあって、
これほどの動員となったのでしょう。
たしかに、この作品はハスミンが絶賛しそうな「映画らしい映画」でもありました。
話らしい話はなく、主人公の男がカフェで女性を見る、そこで目に留まった女性のあとを
つけるということだけで作品を成立させています。
私はこの作品の中盤にあたる、女性のあとをつけるシーンを見ていると、
エリック・ロメールの『パリのランデヴー』第三話の「母と子 1907年」
を思い出しました。
そのあらすじは、goo映画によると
ピカソ美術館の近くに住む画家(ミカエル・クラフト)を知人の知り合いのスウェーデン女(ヴェロニカ・ヨハンソン)が訪ねる。彼は彼女を美術館に連れていく。八時に会う約束をしてアトリエに帰るその途中、彼は若い女(ベネディクト・ロワイヤン)とすれ違い、彼女を追って美術館に入る。彼女は『母と子1907年』の前に座る。彼はスウェーデン女と合流し、その名画の前で例の女性にわざと聞こえるように絵の講釈を始める。彼女が席を立ち、彼はあわてて別れを告げて女を追って美術館を出て、道で声をかけると…。
「母と子 1907年」の舞台はパリ、『シルビアのいる街で』の舞台はストラスブールと
違っているのですが、いずれもヌーヴェルヴァーグならではの空気感があります。
さらに『シルビアのいる街で』は、モフセン・マフマルバフ監督の『サイレンス』や、
山下敦弘監督『天然コケッコー』と同じく「音の映画」であるともいえるでしょう。
『シルビアのいる街で』で聞こえる足音、ビンが転がる音、自転車の音、路面電車の音
などは定点観測した音ではなく、観測点が「遍在」している、人工的な音であるところに
特徴がありました。
いうなれば、この作品の音は、人が耳をすませて聴こうとした音に近いものがあります。
劇場の外に出てみると、青山通りを往来する車の音が、これまでと違ったものに
聞こえるほどでした。まさにこの作品には「聴覚を変容させる力」があるのかも
しれません。
ビクトル・エリセ監督の作風と違うとは思いますが、ホセ・ルイス・ゲリン監督の
これからの動向も、ぜひ追いかけていきたいものです。