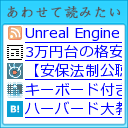認知
2010年08月06日
5日にいいだ人形劇フェスタで行なわれたシンポジウムがなかなか面白かったので、個人的にちょっとまとめておきたい。
『0・1・2歳にとって人形劇とは何か』というテーマだったけど、「みる・演じる・考えるそれぞれの立場から」というサブタイトルが付いていた。
登壇したのは次の方で
松村由美子(子育てサロン おしゃべりサラダ代表)
西村和子(人形劇団クラルテ)
松崎行代(飯田女子短期大学准教授)
それぞれの立場を代表するお三方というわけだった。
司会に高松和子(いいだ人形劇フェスタ実行委員長)。会場からの質疑も含めて2時間はあっという間だった。
僕は30分ほど遅刻して、西村さんが実演者の立場から語っているところだった。なので、あくまで途中から聞いた印象です。
西村さんの話を聞くと、若い母親が孤立して子育ての悩みを抱えている現状だとか、子どもの養育環境が貧しくなっている状況で、乳幼児周辺の事柄も消費の対象として市場に取り込もうとする傾向があるなかで、そういう状況に抗するという意味合いでも、乳幼児向けの人形劇に取り組もうという流れが生まれているらしいことが伺えた。
◎西村さんの活動に関するページ
「クラルテあかちゃん劇場」実施報告
シンポジウムでのいろいろな話をまとめると、親たちも、かつての世代より遊び経験にも乏しいので、日常のなかから子どもと遊べる場を生み出すことが苦手であって、そういう状況を埋め合わせるために、人形劇へのニーズが高まっている面があるのだという。
人形劇フェスタでも、0・1・2歳向けの人形劇公演をいままで企画してきていて、「表方」としてフェスタに関わってきた松村由美子さんのお話は、そうした現場で、何かと不安を抱えがちな若い母親でも安心して赤ちゃんを連れてこられるような会場作りに取り組んで来た、細かな心配りを語っていた。そういう配慮の積み重ねがあったから、人形劇フェスタは続いてきたんだなと感じた。
松崎行代さんは、エンゼルプラン以降、子育て支援に助成が行なわれるようになったが、0・1・2歳向けの人形劇という取り組みが広がるタイミングと符合する。コンテンツを求めるようになった乳幼児をあずかる施設と、公演の機会が減少しつつある人形劇団の間の利害が一致したという背景があったのではないか、という話を人形劇団に対するアンケート調査による裏付けをしつつ語っていた。
◎飯田女子短大
幼児教育専攻:講師からのメッセージ
ネットで検索したら、次の論文が書かれているそうで、今回の話は成果の一部だったのだろう。
松崎さんは、0・1・2歳向けの公演では、人形を操作する演者が表に出るスタイルが多いのだけど、発達段階的に、笑い声を立てたり声を発したりといった反応を示さない3歳未満の乳幼児を相手にするとき、背後に隠れてしまうと演じ手も不安になるのではないか?といった指摘をしていて面白かった。
人形劇に携わるベテランの人から、「0・1・2歳向けに上演することは、恐ろしくてできない」という戸惑いの声が上がったのも、観客としての子どもに対する創り手の真摯な姿勢を感じさせられた。
会場からの声も含めて、人形劇を創る側からは、現実と虚構の区別のない世界を生きている0・1・2歳向けだからこそ、人形劇の表現を広げる可能性があるのではないか、という指摘もあがった。その一方で、0・1・2歳には人形劇は不要だという考えの人も少なくないので、シンポジウムでも、そういう論戦がもっと行なわれてよかったという指摘もあった。
それを受けて、松崎さんは、3歳未満向けの人形劇は、虚構を楽しむ劇というよりは、人形を媒介にした遊びになっていることが多いので、本来の人形劇とは違うのではないか、という問題提起もしていた。
また、3歳未満であると特に、親が一緒に見るということが重要な問題になるという指摘もあがり、母親と子どものコミュニケーションにどのように関われるかという問題提起もあったのだけど、高松さんは逆に「近年、人形劇には、親のウケに気をとられている作品が多い傾向があり、それではいけないというのが、今回のシンポジウムの裏テーマだった」とおっしゃっていて興味深かった。
たとえば、観劇においてどう笑うかということでも、上級生と一緒に見ると三歳くらいのこどもが「ここで笑って良いんだ」と学んだりすることもある、という話も挙がって、観客としての子どもがどういう集団を作っているかによってアプローチも違ってくるというところにまで話題が及ぶこともあった。
保育園だったか幼稚園だったか、そういう幼児教育の現場に長年いたという高松さんの話によると、かつてなら、プロの人形劇団を園で呼んで、上演費を頭割りにしたら、親御さんは喜んで払ってくれたけれど、昨今は「保育費の内に入らないんですか?」とクレームをつけられたりして難しい、という。助成金ベースで人形劇を上演することは、芸術としての人形劇の将来を考える上で、果たして良い事なのか?という疑問もあがっていた。
いずれにせよ、社会のあり方の大きな変化が、子供向けの文化的な取り組みのあり方を大きく変容させつつあって、そうした状況の変動に単に翻弄されるだけでなく、何か働きかけようとする積極的な行動の積み重ねがあるのだという、その一端を垣間見せてくれるシンポジウムだった。
少子化や核家族化といった、家族形態の変化、行政のあり方の変化と平行して、人形劇というジャンルの本質そのものが問われるような状況があって、これは、助成のあり方と言うことも含めて、多少状況は違うとはいえ、現代演劇やコンテンポラリーダンスと、同時代的な現象が別の仕方で人形劇の世界にも現れているのだなと思った。
もちろん、作品としての恒久性を前提にして、良い芸術を鑑賞するというマナーを子どもが身につけることを目指すという人形劇のあり方も、当然どこかで生き残るだろうし、継続されるべきなのだろうと思う。そうなると、対象年齢別に作品のあり方を変えていく、それに応じてみる人も集める、という作法にも、まだまだ生き残る意義があるのかもしれない。
だけど、親子向けだとか、未就学児だけとか、比較的均質な観客を集めるというあり方を前提としないような、もっとフレキシブルで即興的な場というのが成り立たないものかな、という風な感想を抱かなくもなかった。
アーティスト・イン・児童館の事例なんかを身近に感じてきた自分からすると、大人が完成させたものを子どもに示す、という上演の回路とは別の場のあり方もあるような気もする。逆に、上演的ではない関係性の場所に、人形劇の技法がいろいろとヒントをもたらす可能性もあるのではないだろうか。
人形劇の人形というのは、生身の人間よりもより類型的だったり抽象的でありえたりするし、ある種の原初的なパターンみたいなものにまで表現媒体を還元していくことも出来るのが人形劇と言うジャンルなので、一面では、人間の認知のあり方の根本に触れるところがあるような気がする。
そういう面で、遊びと芸術の境目にいろいろ未踏の領域があるという風に感じる作り手が居るのも当然だと思う。
たとえば、ハンス・マイヤーの『ハプニングと沈黙』とかを読むと、1920年代の街頭演劇の事例などにも言及しながら、演劇の可能性を「遊び」の内に見出していたりする。
固定された舞台/客席という構造を前提としない人形劇的な何かというのは、いくらでも展開可能なのだろうし、実際にそういう試みはいろいろあるのだろう。
近代的な芸術理念の本質を問い返すような営みは、20世紀の哲学や思想の動向も踏まえながら、いろいろと行なわれてきたのだろうけど、0・1・2歳という発達段階にあるというか、そういう人たちのことを考えると、たとえば、虚構ということの意味合いを、改めて問い直すような糸口がいろいろ見出せるのかもしれないな、という風なことも思った。