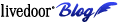【オープンルーム。Bulletin boad.】
February 14, 2009
種をまく〜北原さんへのメール。[Planting seeds~Mail to Mr.Kitahara.]
あらゆる環境や思想が根絶やしにされてしまった現在に生きる我々がもう一度それらを取り戻すためにどうすれば良いのか?技術継承の場、批評の場、セーフティーネットとしての場、それら三つが必要なのだと思います。最早技術の伝承は企業との連携なくしては出来ません。フィルムメーカーやカメラメーカーあるいは機材レンタル会社などがセミナーや研究会という形で技術を学ぶ場を提供していくべきでしょう。またCML(Cinematographer's Mailing List)のようなものが早く日本でも出来ると良いと思います。レッドユーザーJPの掲示板などはとても良い試みだと思っています。批評もネットが一番なのでしょうが、これは個別にやっていても少しも広がっていきません。そこにアクセスすればあらゆる議論が閲覧出来るようなビッグサイトが必要だと思います。映画情報サイトの多くはそういうコーナーを設けていますがあまりにもレベルが低い。一定以上のレベルを取り込める場(=プロユース)があれば良いと思います。それがあるなら私のブログなどいつでも閉じても良いです。
セーフティーネットの場は解り難いかもしれませんが、今で言うならワーキングシェアでしょうか。撮影所では正統な競争と同時に仕事の斡旋なども頻繁に行われていたはずです。成る可く多くの人間が業界に生き残っていて欲しいと単純に思いますが、少数の人間に仕事が集中する状況というのは決して良いことだとは思いません。量というのは質を向上させます。多くの人の様々な個性がぶつかり合って、その混沌の中から初めて素晴らしいものが生まれてくる。そうは思いませんか?CM業界ではキャメラマンでいられる期間は10年程度と言われています。しかも第一線で活躍出来るのはせいぜい30人程度だとも聞きました。その30人程度の人たちがぎりぎりのスケジュールで働いている(働かされている)に過ぎません。CMは言ってしまえば商売には違いありませんが、文化の側面を強く持っています。文化というのは長い時間をかけて熟成していくものです。キャメラマン個人でさえ10年経ってようやく見えてくるものは沢山あります。寧ろそこからがスタートなのかもしれません。けれど日本のCM業界は長いスパンでは物事を見ていません。逆に映画界は一本立ちする時期が遅過ぎる。だからいつまでたっても若返り出来ない。CMに限らず、早晩日本映画も誰にも見向きもされない時期がやってきます。人の気持ちを繋ぎ止めるだけの豊かさを失いかけているからです。こうした場を作るのがもっとも難しい。逆に言えば、これさえ巧く機能し始めたら全ては好転すると思います。
場をどうやって作り上げていくかでしたね。戦後60年以上をかけて壊れてしまったものは、一朝一夕で直るものでもありますまい。それ以上の時間が必要です。これといった有効な方法は残念ながらありません。私が生きているうちに良い方向に向うとは到底思えません(苦笑)。只ただ愚直に根気よく発言していくしかないでしょう。それが何らかの萌芽を促すことを信じて。本来ならJSC(日本撮影監督協会)のような組織がそうしたことを率先してやるべきなのでしょうが、形骸化・硬直化した組織は流れを変える力を何ら持っていません。わたしも一応そのメンバーですが、新参者が自由に振る舞えるような包容力を持った場所ではありません。スピードも遅い。過去の財産を食い潰しているだけに見えます。それに先人に倣うならそうした組織も一つではいかにも不足です。
セーフティーネットの場は解り難いかもしれませんが、今で言うならワーキングシェアでしょうか。撮影所では正統な競争と同時に仕事の斡旋なども頻繁に行われていたはずです。成る可く多くの人間が業界に生き残っていて欲しいと単純に思いますが、少数の人間に仕事が集中する状況というのは決して良いことだとは思いません。量というのは質を向上させます。多くの人の様々な個性がぶつかり合って、その混沌の中から初めて素晴らしいものが生まれてくる。そうは思いませんか?CM業界ではキャメラマンでいられる期間は10年程度と言われています。しかも第一線で活躍出来るのはせいぜい30人程度だとも聞きました。その30人程度の人たちがぎりぎりのスケジュールで働いている(働かされている)に過ぎません。CMは言ってしまえば商売には違いありませんが、文化の側面を強く持っています。文化というのは長い時間をかけて熟成していくものです。キャメラマン個人でさえ10年経ってようやく見えてくるものは沢山あります。寧ろそこからがスタートなのかもしれません。けれど日本のCM業界は長いスパンでは物事を見ていません。逆に映画界は一本立ちする時期が遅過ぎる。だからいつまでたっても若返り出来ない。CMに限らず、早晩日本映画も誰にも見向きもされない時期がやってきます。人の気持ちを繋ぎ止めるだけの豊かさを失いかけているからです。こうした場を作るのがもっとも難しい。逆に言えば、これさえ巧く機能し始めたら全ては好転すると思います。
場をどうやって作り上げていくかでしたね。戦後60年以上をかけて壊れてしまったものは、一朝一夕で直るものでもありますまい。それ以上の時間が必要です。これといった有効な方法は残念ながらありません。私が生きているうちに良い方向に向うとは到底思えません(苦笑)。只ただ愚直に根気よく発言していくしかないでしょう。それが何らかの萌芽を促すことを信じて。本来ならJSC(日本撮影監督協会)のような組織がそうしたことを率先してやるべきなのでしょうが、形骸化・硬直化した組織は流れを変える力を何ら持っていません。わたしも一応そのメンバーですが、新参者が自由に振る舞えるような包容力を持った場所ではありません。スピードも遅い。過去の財産を食い潰しているだけに見えます。それに先人に倣うならそうした組織も一つではいかにも不足です。
February 13, 2009
幸せな時代〜北原さんへのメール。[Good Old Days~Mail to Mr.Kitahara.]
戦後およそ10年ほどで日本映画はその黄金期を迎えます。50年代始めから60年代の中頃までの14〜5年は考えただけでもワクワクする時期です。小津安二郎がいて、黒澤明がいて、溝口健二がいる。そして彼らを支えたのは優秀なキャメラマンです。厚田雄春、中井朝一、宮川一夫。さらには成瀬巳喜男には玉井正夫、川島雄三には高村倉太郎や岡崎宏三。数え挙げたら幾らでも出てきます。皆撮影所で育った一流の技術者です。当時は撮影所内のみならず各映画会社が競い合って技術を磨いていました。ですからモチベーションも相当高かったに違いありません。私などは、そうした諸先輩の素晴らしい仕事を知らずしてキャメラマンを名のることなど恥ずべきことではないかと思っているのですが、今となっては彼らの名前すら聞いたことのない人たちが日本の映像業界の主流になっているのかもしれません。彼らの仕事が如何に素晴らしいか、何ゆえ何度繰り返し観ても見飽きないか。映像の世界を豊かにするために、そのことがもっと分析され、評価されるべきでしょう。
おそらく撮影所という場が果たした役割というのは、技術を学ぶ場だけに留まらず、正統な批評眼/価値観を受け渡しする場でもあったと思います。あの時代の映像が優れていたのは、映画会社が5社6社とあり、各社の中でも撮影所によって独自の流儀を持っていたからです。それが相互に良い影響を与えていました。継承と批評。それらがバランスよく配分されていた日本映画の黄金期とは本当に幸せな時代であったのかもしれません。
何処かで観たようなアングルやコンポジションあるいはトーンやレイアウトをセンスよくまとめられればキャメラマンとして仕事が成立してしまう今の時代、地に足の着いたキャメラマンがどれだけいるのでしょうか。技術面で言えば、テクノロジーの進化はさほど技術を身につけなくともそこそこのものを創ることが出来てしまう状況を生みました。例えばフィルム性能の向上です。宮川一夫さんは露出を計るために、セット全面に暗幕を張って、その誤差をとことん避けようとしたと聞いたことがあります。それだけ微妙なものだった。僕がチーフの頃でさえメーターの目盛の針一本にまでこだわっていましたが、今ではデジタルカメラの露出計を頼りにしている者さえいます。半絞り程度の違いなら何の問題もなく写せてしまう。それが人から物事を学び、追究する姿勢を奪っていきました。技術の進歩は諸刃の剣でもあります。一方でそれらは(例えば畑違いからの)新たな才能の参入を容易にします。思想面で言えば、これはもうはっきり言って出鱈目です。北原さんとも見解を一にする事柄だと思いますが、戦争が、連綿と受け継いできた価値観を分断してしまった。おそらく団塊の世代以降の数世代は失った価値観を取り戻すことは出来ないでしょう。日本映画の黄金期は戦後ですが、それは正統な価値観を受け継いできた人たちの生き残りが辛うじて映像の発展期と上手く噛み合ったということだったと思います。(つづく)
おそらく撮影所という場が果たした役割というのは、技術を学ぶ場だけに留まらず、正統な批評眼/価値観を受け渡しする場でもあったと思います。あの時代の映像が優れていたのは、映画会社が5社6社とあり、各社の中でも撮影所によって独自の流儀を持っていたからです。それが相互に良い影響を与えていました。継承と批評。それらがバランスよく配分されていた日本映画の黄金期とは本当に幸せな時代であったのかもしれません。
何処かで観たようなアングルやコンポジションあるいはトーンやレイアウトをセンスよくまとめられればキャメラマンとして仕事が成立してしまう今の時代、地に足の着いたキャメラマンがどれだけいるのでしょうか。技術面で言えば、テクノロジーの進化はさほど技術を身につけなくともそこそこのものを創ることが出来てしまう状況を生みました。例えばフィルム性能の向上です。宮川一夫さんは露出を計るために、セット全面に暗幕を張って、その誤差をとことん避けようとしたと聞いたことがあります。それだけ微妙なものだった。僕がチーフの頃でさえメーターの目盛の針一本にまでこだわっていましたが、今ではデジタルカメラの露出計を頼りにしている者さえいます。半絞り程度の違いなら何の問題もなく写せてしまう。それが人から物事を学び、追究する姿勢を奪っていきました。技術の進歩は諸刃の剣でもあります。一方でそれらは(例えば畑違いからの)新たな才能の参入を容易にします。思想面で言えば、これはもうはっきり言って出鱈目です。北原さんとも見解を一にする事柄だと思いますが、戦争が、連綿と受け継いできた価値観を分断してしまった。おそらく団塊の世代以降の数世代は失った価値観を取り戻すことは出来ないでしょう。日本映画の黄金期は戦後ですが、それは正統な価値観を受け継いできた人たちの生き残りが辛うじて映像の発展期と上手く噛み合ったということだったと思います。(つづく)
February 11, 2009
場所〜北原さんからのメール。[Base~Mail from Mr.Kitahara.]
「知る、理解する、そして実践する」を重層的に反復することでしか「叡智」への道は開かれない。かつて千葉で行われたレクチャーで、ダライラマ14世が、そういっていたことを思いおこします。知り得たことを自らにかみくだき、その理解を外部との関係性のなかで実践していく。その実践によって帰ってきたものをふまえて、もう一度知ることにたちかえる。そしてさらなる理解を深め、実践の舞台に投げかける。知性はこの地道な反復なくして鍛錬されることはありません。そして教養とはその力強い知性の基礎となる支柱であり、歴史を通じて、実に多くのさまざまな叡智が獲得してきた財産のことであろうかと思います。教養がないということは、知性の、あるいは大きく人間を形づくるものの土台が、すこぶる脆弱であるということです。この教養の問題こそが、ぼくが2月5日のメールでふれた「なるべく早期に抽出し、明確化しなければならない」、技術と人の心とにきたしている齟齬のひとつにほかなりません。
「私が常々思うのは(自分を含め)映像に携る人たちが映像を勉強していないと言うことです。映像にも基本的な文法があり、その実践の中で発見/発明された技法と技術があります。それを知ることなくしては、未来へと進むことも出来ません。」という大木さんの意見に強く共感します。技術や教養といった財産は、連綿と受け継いでいかれるものです。しかしながら今日においては、それらを継承したり、共有したりする「場所」を見つけることがむずかしくなっていることも事実です。圧倒的な情報の量や種類がせっかくあるのだからこそ、それらを再構成し、他との連携やぶつかりあいのなかで発展させていく「場所」が必要なのではないかと、大木さんはそう考えているように察します。
以前は、撮影所の存在がその役割をはたしていました。映画を作るということが、な
んら特別なことではなく、製作という仕事をめぐって、日々、実践と鍛錬が行われ、
技術に関する情報もまたひんぱんに行き来していたことでしょう。知識や理解だけで
なく、それを実地で試すことのできる「場所」が撮影所にはあった。技術者にとって、また、技術を引き継いでいくものにとって、「場所」とは、かくも重要な意味をもっていると思います。
撮影所という入れものが瓦解し、そこに入れられていた多くの技術者が野に放たれて
しまっている現在、大木さんばかりでなく、ひとりひとりが、そのリユニオンの必要
性をさまざまな形で感じていることと思います。ただそれをどう具体的にしていった
らいいかが、でてこないように思います。そんななかで、インターネットサイトはそ
の有効な手段となりましょう。しかし、それだけでは充分とはいえないように思いま
す。やはり、機材なり技術なりを真ん中において、お互いの顔と顔をつきあわせるこ
とがなにより大切だと考えます。
大木さんの卓越した解説で明らかになった「アラビアのロレンス」のワンショット。
あの最良のショットを選択するためには、人と人とを結びつける信頼、そしてそれを
育んでいく時間と関係性が、必要かつ不可欠です。ぼくたちが、もう一度取り戻すべ
くは、行動を動機づける理念とそれを学習し実践していく「場所」、そして人と人と
のコミュニケーションだと思います。次回は、そのあたりの見解を聞かせてください。
「私が常々思うのは(自分を含め)映像に携る人たちが映像を勉強していないと言うことです。映像にも基本的な文法があり、その実践の中で発見/発明された技法と技術があります。それを知ることなくしては、未来へと進むことも出来ません。」という大木さんの意見に強く共感します。技術や教養といった財産は、連綿と受け継いでいかれるものです。しかしながら今日においては、それらを継承したり、共有したりする「場所」を見つけることがむずかしくなっていることも事実です。圧倒的な情報の量や種類がせっかくあるのだからこそ、それらを再構成し、他との連携やぶつかりあいのなかで発展させていく「場所」が必要なのではないかと、大木さんはそう考えているように察します。
以前は、撮影所の存在がその役割をはたしていました。映画を作るということが、な
んら特別なことではなく、製作という仕事をめぐって、日々、実践と鍛錬が行われ、
技術に関する情報もまたひんぱんに行き来していたことでしょう。知識や理解だけで
なく、それを実地で試すことのできる「場所」が撮影所にはあった。技術者にとって、また、技術を引き継いでいくものにとって、「場所」とは、かくも重要な意味をもっていると思います。
撮影所という入れものが瓦解し、そこに入れられていた多くの技術者が野に放たれて
しまっている現在、大木さんばかりでなく、ひとりひとりが、そのリユニオンの必要
性をさまざまな形で感じていることと思います。ただそれをどう具体的にしていった
らいいかが、でてこないように思います。そんななかで、インターネットサイトはそ
の有効な手段となりましょう。しかし、それだけでは充分とはいえないように思いま
す。やはり、機材なり技術なりを真ん中において、お互いの顔と顔をつきあわせるこ
とがなにより大切だと考えます。
大木さんの卓越した解説で明らかになった「アラビアのロレンス」のワンショット。
あの最良のショットを選択するためには、人と人とを結びつける信頼、そしてそれを
育んでいく時間と関係性が、必要かつ不可欠です。ぼくたちが、もう一度取り戻すべ
くは、行動を動機づける理念とそれを学習し実践していく「場所」、そして人と人と
のコミュニケーションだと思います。次回は、そのあたりの見解を聞かせてください。
February 08, 2009
コストパフォーマンス、教養〜北原さんへのメール。[Cost-performance and education~Mail to Mr. Kitahara. ]
「コストパフォーマンス」を制作に拘る「態度」の中のひとつの選択肢と混同するとややこしいことになると思うのですが、コストを考える、或いはスタッフが被る種々の負担軽減を考えることは責任ある立場にいる者として当然であろうと思います。無尽蔵にお金を使うことは出来ないのですから、その予算の中で最大限のクオリティを追求することは技術者の裁量の一部です。そして、そうした制約があったからこそ様々な工夫がなされてきました。問題は、追求されるべきクオリティの何たるかを大多数が知らないということではないでしょうか。テレシネルームや編集室のちっぽけなモニターでしか映像を見たことのない若い子たちにプリントラッシュを見せると皆一様にその美しさに驚きます。おそらく70mmのニュープリントを観たならもっと驚くでしょう。技術者としての私はそれが想像出来るから映画館に出向かないだけです(傲慢かつ怠慢と言われればそうですね)。無限の選択肢の中から何を選ぶかは夫々の技術者の能力にかかっていると思いますが、どれだけの選択肢を持っているのかは偏に「教養」に拘る事柄だと思います。ところが、その「教養」の標準値が果てしなく下がっている。それは昨今の経済的な締め付けだけでは説明出来ません。
私が常々思うのは(自分を含め)映像に携る人たちが映像を勉強していないと言うことです。映像にも基本的な文法があり、その実践の中で発見/発明された技法と技術があります。それを知ることなくしては、未来へと進むことも出来ません。
『アラビアのロレンス』でロレンス率いる騎馬隊(?)がアカバ市街に攻め込むシーンがあります。確か、そのシーンの後半部分は馬と駱駝を駆った大軍勢が街を物凄い勢いで通り抜け海岸線に至るまでが大ロングのワンカットで捉えられています。そこではカメラは少しだけ平行移動して、最後に「海に向いた大砲」をフレームに納めます。今なら差し詰め大クレーンを使ってよりダイナミックな撮り方をしたり、そのシーンの前半部分よりも更に細かなカット割りで見せるかもしれません。より大きなクレーンが登場するのも、細かなカット割りの有効性をキャメラマンが気付くのもずっと後のことです。けれど、もし1963年にそんな技法があったとして、デビット・リーンが、あるいはF・ヤングとN・ローグでもいいのですが、それを選択したかどうか。もしくはそうした撮り方を発見/発明したか。僕はそれはあり得ないと考えます。海を遠景に望むアングルはその直後の美しい夕景シーンで登場しますから巧妙に避けられています。トルコ兵側からのアングルもほとんどない。大方は横パンか平行移動だけです。あの文脈の中でカメラが俯瞰に入ることは(撮影されたのは街を望む丘の上で俯瞰と言えなくもないですが、ティルト角度は極めて水平に近い)物語の基調となる水平の動きをぶち壊しかねない。あそこで細々とした戦況のディティールを見せることは、その後の、ロレンスたちが敗走するトルコ兵を虐殺するシーンを台無しにします。あそこで選ばれたフレームは考えうる中で最良のものです。『アラビアのロレンス』にはそのようなシーンとそれらの相互作用が沢山あります。だからいつまで経っても古びません。
ただ単に迫力が出るとか目新しいとかという動機でフレームを選んではいけないのです。今、映像を創る側がそれをどれだけ自覚しているか。北原さんの用語に従えば、差し詰め、どれだけ「配慮」できるかということでしょうか?残念なことに、無教養であるが故にそうした「配慮」はほとんど理解されないのです。
February 07, 2009
態度と配慮〜北原さんからのメール。[Attitude and consideration~Mail from Mr. Kitahara. ]
たくさんの論点をひろいあげたいところですが、今日は「態度と配慮」ということばからはじめたいと思います。
まず「態度」ですが、これは大木さんが使う「選択」ととても近く、また、おおいに関係するものだと思います。大木さんのことばを引きます。
「撮影というのは常に選択です。(どの部署でも変りませんが)上に立つ者ほど究極の選択を迫られます。その決断が正しく出来る人だけがキャメラマンとして残っていきます。」
選択をするというのは、まさに「態度」を表明することにほかなりません。そのひとつひとつの選択が、そのひとの「態度」を形作るのであります。すなわち「態度」の問題とは、どんな選択をしているのかを自らに問う所作なのです。そしてそれはある判断の彼岸、価値の基準をつまびらかにすることになります。そのとき、一体何をもってその選択に臨んだのか、何に心をくだいたのか、いかなる風に感じ、考えたのか。ぼくが「配慮」ということばを使うのはこの領域における事柄なのです。
「矜持」はこのふたつのことばと不可分です。もちろんすべてのキャメラマンにそれぞれことなった矜持があると思いますし、それに正解を求めるたぐいのものではないでしょう。しかしだからこそ、キャメラマンばかりでなく、すべての撮影にかかわるそのひとりひとりに、その「態度と配慮」を問いたいし、ぶつかりあってみたいと思うのです。現在、ハード面などの技術の変化とともに、制作現場のパラダイムシフトを、ぼくたちは身をもって経験しているわけです。ふたたび大木さんのことばを引いてみます。
「技術者であるということは、結局のところ、現代においては、コストパフォーマンスと不可分な存在では居られません。」
シフトした先は、この「コストパフォーマンス」なるものが、露骨に前面に押し出された場所です。それは確かに大切なことと思いますが、「態度と配慮」が照射するのがそこにしかいたらない、あるいは「制作する=つくりだす」行為を押しのけてまでのプライオリティが与えられるのは、いかがなものかと思います。故人となった淀川長治さんは、ただただ「映画をお金もうけの道具にしないでほしい。」と訴えていました。実存主義的に「何が」「何に」先立つのかと内省するとき、このことばはぼくのなかではとても有効で、「態度と配慮」をめぐる大きな基準となっています。『アラビアのロレンス』をテキストにして、大木さんはこういっています。
「あの当時、F・ヤングとN・ローグに躊躇があったかどうか。コスト面では然程なかったと推察しますが、他の面に関して言えばやはりそれはあったと思います。(例えばあの当時のカメラの大きさ重さなど考えたら砂漠での撮影自体を躊躇しますよ)それでもあの砂漠であの引き画を撮ったということは、制作に拘った人々がそれをすべき理由を見つけたからです。」
60年代初頭から今にいたって、撮影というものが見失ったもののひとつが、この「制作に拘った人々がそれをすべき」と考えた「理由」なのではないかと思います。ご存知の通り、撮影という映像制作の現場は、実に多くのひとの力が必要であり、かかわるものであります。それだけのひとたちが考える「すべき理由」、それだけのひとたちや力を動かすだけの「すべき理由」を、コストパフォーマンスをのぞいた「どこ」と「なに」に見いだすのでしょうか。目の前に大きな技術変革があるからこそ、それに挑むだけの「態度と配慮」を明らかにしなければならないと考えるのです。
February 06, 2009
『アラビアのロレンス』をテキストとして〜北原さんへのメール。["Lawrence of Arabia" to be a text~Mail to Mr.Kitahara.]
技術者であるということは、結局のところ、現代においてはコストパフォーマンスと不可分な存在では居られません。あの当時、F・ヤングとN・ローグに躊躇があったかどうか。コスト面では然程なかったと推察しますが、他の面に関して言えばやはりそれはあったと思います。(例えばあの当時のカメラの大きさ重さなど考えたら砂漠での撮影自体を躊躇しますよ)それでもあの砂漠であの引き画を撮ったということは、制作に拘った人々がそれをすべき理由を見つけたからです。素っ気ないようですが、それだけのことだと思います。
撮影というのは常に選択です。(どの部署でも変りませんが)上に立つ者ほど究極の選択を迫られます。その決断が正しく出来る人だけがキャメラマンとして残っていきます。非効率的でもそれをした方が良いか、それをせずともクオリティを保てるのか、クオリティを犠牲にしても効率的に進める(=スタッフを守り、予算を守る)べきか、ああすればよかったなどは後からの話であって、その場その場で下した判断はその時点では(彼/彼女の中では)ベストです。
クオリティを保つことが技術者のなすべきことの第一であるというのは大前提です。しかし総ての面でそれが出来るのはほんの一握りのクリエイターであって、それは才能と同時に幸運/時運にも恵まれた人たちです。多くの技術者は、夫々のレベルに応じて、多かれ少なかれ何らかの妥協をしています。(残念なことに、妥協させられていることにすら気が付かない人もいますが・・・。)
映像に対する「態度と配慮」が正確に何をさしているのかは掴みかねていますので、私なりの解釈で筆を進めます。技術の進歩と比例するように人と人との繋がりが希薄になってしまったことは確かです。技術の進歩とは人が「それ」をわざわざしなくとも済むようになるということです。それによって、人により深く考える余裕が生まれるかといえばそのようなことはなくて、寧ろ更に楽になるような方向へと考えが流れていきます。そして人の力を借りなければ出来なかったことが比較的簡単に出来るようになると、他者を説得する手間を省くようになります。そこには映像を作り上げていくダイナミズムは生まれようもなく、映像は極めて精巧にその手抜きを反映しますから、映像はどんどん痩せ細っていきます。それでも優秀なクリエイターたちであるなら、その時代の要請に則って、「態度と配慮」を実行しているとは考えませんか?全体のレベルを問題にしても仕方のないことです。ある一定の量が満たされれば、その中の数%は、確実に過去の名作と比べても退けをとるものではないでしょう。また、そう信じなければ仕事など出来ません。
おそらく、僕ら(敢えてそう言わせてもらいますが)のような映画史に取り込まれてしまった人間が理解しにくいのは、映画史と無関係でいた人たちの映像が多く存在していると言うことです。そしてそんな彼らがまた新たな映画史を創ろうとしていることに対する戸惑いでしょう。紀里谷氏を引き合いに出したのは※そういうことです。予告編を見る限り彼の“映画”に映画が百年の間に獲得してきたものに対するリスペクトは何処にも見受けられません。僕があまり知らないTVやアニメやゲームなどが彼の創造の源なのでしょう。
今僕がこの大転換期に際して心していることは新しい技術を恐れないということです。技術者にとって一番の問題は原理主義的な態度に出ることだと思っています。僕たちはどちらかに留まっていてはいけないのです。新たな何かが生まれるのは何かと何かが衝突したときです。人と人が、技術と技術が、あるいは技術と人が出会うことでしかCREATIVITYは獲得出来ない。僕はどちらかと言えば引きこもり系の人間です。けれどもの作りにおいて刺激を避けることと労を惜しむことは忌むべきものなのだと思っています。「砂漠のような、画的に平坦で変化に乏しい難しい舞台」にも何かを見つけ出すことがキャメラマン本来の仕事ですよ(笑)
的外れなことを書いてしまったら許して下さい。ではでは。
※以前に送ったメールで私は『Goemon』の公開を控える紀里谷和明監督とデビット・リーン監督を比べてみれば「たった4、50年の間に起こったことが朧げながら見えてくる」と北原さんを挑発している。
February 05, 2009
『アラビアのロレンス』をテキストとして〜北原さんからのメール。["Lawrence of Arabia" to be a text~Mail from Mr.Kitahara.]
麻生総理のよく使うことばに「矜持」というのがありますが、なにに重きを置くかということを、自らに問うことが大切なように思います。キャメラマン或はミキサーとして、いち技術者の「矜持」や理念の中心を見直してみたいと以前より考えていました。どうなのでしょうか、たとえば今、引き画を撮りたいと、しかもすごく引いた画を撮りたいと思うとき、撮影者のなかでなにかしらの躊躇は起こるものなのでしょうか?アンゲロプロスでもなんでもいいのですが、共通のテキストとして『ロレンス』を用いるならば、ここそこにでてくる「全景」は果たして今も、なんの逡巡もなしに撮り得るものなのでしょうか?
以前、撮影で観客席を取る時に、エキストラを100人いれて撮影し、後はそれを「移植」して、あたかも満員の状況を作るという方法がとられたのですが、これはキャメラマンとしては一体どうなのでしょうか?もちろん様々な「大人の事情」をふまえて納得して撮影にのぞんでいることと思いますが、もし忸怩たる気持ちがあるのでしたら、いかなる納得の仕方があるのかうかがってみたいです。
たとえるならば「合成」は近代における「電気」みたいなもので、映像表現の世界では、もはやそれなしでは考えられないものなのでしょう。『ロレンス』の時代はそれがなかった。今という時代はそれが「ある」のだから使う。それでいいと思うのですが、ぼくが気にしているのは、物事に向かううえでの人の心の機微ともいえる「態度と配慮」なのであります。
ぼくたちが迎えているのは、技術的な革命であることは間違いありません。しかしそこでテクノロジーと人の心の歩みゆきの間に齟齬をきたしているのであるなら、それはなるべく早期に抽出し、明確化しなければならないと考えます。さもなくばせっかくの進化(?)も実をつけないままの枯木となってしまうでしょう。
あらためて『ロレンス』はいいテキストになるでしょう。ぼくも演劇少年のはしくれです。一回性の大切さも理解しているつもりですが、もし大木さんが、ふたたび65ミリの『ロレンス』を観たなら、必ずや撮影技術や撮影そのものへの「態度と配慮」に想いをはせることと確信しております。
キャメラマンは砂漠のような、画的に平坦で変化に乏しい難しい舞台での撮影に何を考えるのでしょうか?先日観た『ワールド・オブ・ライズ』も中東が舞台でしたが、『ロレンス』の経験を踏襲しているようでもあり、また何かを失っているようにも感じました。
とここまで一気に書いてきたのですが、毎度のことながら支離滅裂ですね。伝わるものなのか一抹の不安はあります。いつも気にしているのは、技術のひとり歩きは困るということです。技術の進歩とそれを使う人間の心の成熟は、ともに足並みをそろえなければ、大きな価値を生み出すことはできないでしょう。デジタルだのはいったん棚にあげておいて、今こそ、ぼくたちは何を撮りたいのか、何を表現したいのか、そんなことをもう一度問い直すいい時期だと思っております。お手透きのときにでも考えをうかがわせてください。