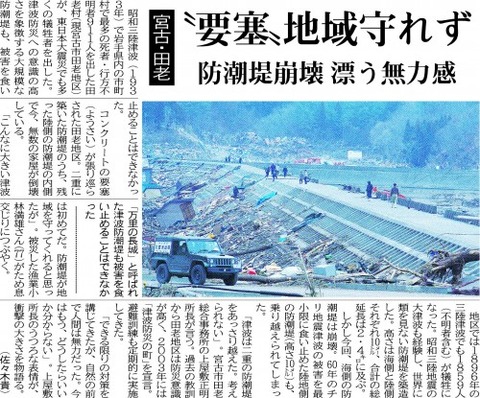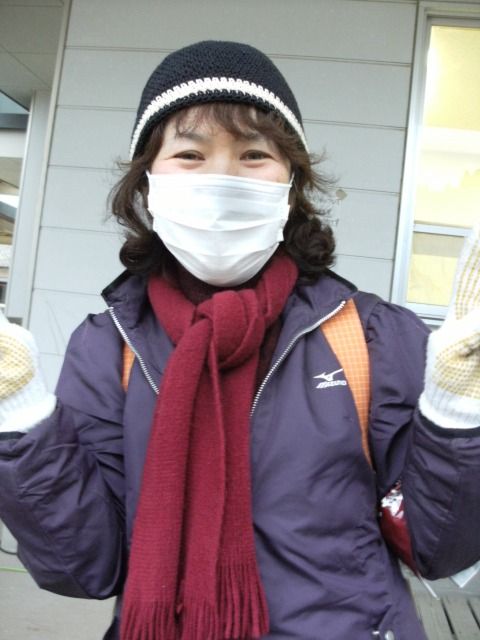余震の中で新聞を作る10 「ふんばる」人々と出会う
しかし、過酷な試練を背負った被災地でも少しずつ、人が動き始め、新たな時を刻み始めました。きょう4月2日付の夕刊を開いて、あっと声が出ました。
「苦難に負けぬ」という太字カットの記事の1つが、「陸前高田 老舗しょうゆ店事業再開 『日本一』もう一度」。
「『味にも材料にもこだわりのある手造りの店で、しょうゆ1本でも配達してくれた。ほんとうに地元の良心的な店だった』と。めちゃめちゃに醸造所や事務所は崩れ、樽がいくつも道に転がっていました。店の人々は無事だったでしょうか」
本ブログ『余震の中で新聞を作る6』でこうつづった店のお話でした。1807(文化4)年創業の八木沢商店。地場産の原料と昔ながらの製法で仕込んだしょうゆは、全国品評会で3度の最優秀賞を得たそうです。やはり土蔵や杉だるなどの醸造設備をすべて流され、社員にも犠牲者が出ました。記事の1部を紹介しましょう。
『事業を再開した1日。仮設事務所を置く陸前高田市の陸前高田ドライビング・スクールに、社員約30人が集まった。
「これ何だと思う? みんなの給料袋だ」
社長の河野和義さん(66)が真新しい銀行の封筒が入った紙袋を掲げた。長男で専務の通洋さん(37)が一人一人に手渡すと、小銭交じりとあって社員から「重いよ」と笑いが起きた。
この場で、和義さんから通洋さんへの社長交代が伝えられた。
「地獄からはい上がるなら、スピードと体力が必要。若い俺の方がいい」
通洋さんの直訴を和義さんが快諾した結果だった。
社員には今後の方針も示された。
「生きる」「共に暮らしを守る」「人間らしく魅力的に生きる」—。雇用は
守り、行方不明者の捜索やボランティア活動も本業と位置付けた。』
店に残ったものはトラック2台のみ。しかし、がれきの中から、創業の由来を記した巻物と、杉だるに生き延びた微生物が取り戻せたそうです。
「以前と同じみそやしょうゆを造るのに、20年以上はかかる。でも、生きていたら何でもできる」。こう語り、給料袋を掲げた河野和義さんの目は潤んでいるように見えます。その場に立会い、新しい時を伝えた記者の目もまた同様だったと思います。
津波にのまれた街の人々の再生の鼓動が届きましたでしょうか。
◇
『ふんばる』という朝刊社会面の大きな記事が、3月22日付から連載されています(4月3日付まで13回)。
「東北の人々の命や暮らし、古里の街を奪った東日本大震災。今も多くの人が行方不明の肉親を捜し、避難所で寒さや疲れに耐え、ライフラインの復旧を待つ。今日を生き抜くこと、希望を取り戻すこと、そして再び立ち上がること。そんな思いで支え合い、動き始めた人々を被災地のさまざまな場所で見つめる」。 こんな前文が初回に添えられました。
菅首相は1日、記者会見で東北の復興に触れ、「世界で一つのモデルとなるような新たな町づくりをぜひ目指したい」と表明したそうです。「山を削って高台に住む所を置き、海岸沿いの漁港などまで通勤する。バイオマス(生物資源)を使った地域暖房を完備したエコタウンをつくる。福祉都市としての性格も持たせる」(時事通信)
復興の主体とは誰か? 私たちは岩手・宮城内陸地震(2008年6月14日)の折にも、それを自問し、議論しました。その形が、現地支局、報道部記者たちがそれぞれに出会った人々の物語を記録し、書き継ぐ『歩む 前へ』という連載(これまで34回)になりました。
本ブログ「被災・復興と地方紙記者〜栗駒耕英で聴く」の1部を引用してみます。
『「養魚業、介護支援員、郵便局長、温泉宿経営、養護教諭、高校生、畜産農家…。震災とは、地域のあらゆる人と家族、仕事、暮らしを巻き込み、人々はその体験を共有しながら、それぞれの現場から、できるやり方で前へ進んでいる。その一歩一歩が復興への歩みであり、その主体とは一個一個の住民−」
「いろんな人に話を聴きながら、首長より政治家より重い言葉を聞くし、一人一人が主人公という思いがある。それが、われわれのニュースなのだ、と知りました。震災で耕英(注・栗原市の被災地)の人々と出会い、私の人生も変わりました」(注・若柳支局記者の話)
場にとどまり、当事者と同じ時間を生きる。それが、地方紙記者の仕事の本質なのです。
そこで出会い、聴いた1人1人の声からしか、解決すべき問題も、それを考える道筋も、必要とされる支援も、新たに生きる場づくりとしての復興の姿も見えてはきません。いま最も苦しい被災者こそが、その力−他者をも勇気づける−をもっています。
まだ発せられていない声の伝え手が、いま私たち記者−同時に当事者でもある−にできる仕事であり、それらをつなぐ場づくりが、地方紙にできる役割であろうと思います。
今回の震災での「ふんばる」も、同じところから生まれ出でました。私も、報道部や被災地の支局の記者たちに交じって、『余震の中で−』で報告してきたような場所を歩き、人と出会ってきました。『ふんばる』につづった何篇かを紹介してみましょう。
◇
東日本大震災/ふんばる 3・11大震災 (1) 高須賀昌昭さん(66)=燃料販売店主、石巻市八幡町=ぬくもり、心に赤々と/たき火から助け合う輪
「あだっていがい。あったまっから」。雪にぬれ、泥の道を行く被災者に声を掛ける人がいた。
石巻市中心部の北上川右岸にある八幡町。11日の大地震後の津波で多くの家々が倒壊した湊(みなと)地区の外れだ。
泥とがれきの県道脇に一点、赤いたき火。5、6人の輪ができている。
「九死に一生を得だんだがら。元気を出さい」。湊小の避難所での配給から帰ってきた若い女性2人に、声の主、高須賀昌昭さん(66)が言う。
「○さんはこの近所では。安否不明なんです」「給水はいつやるのですか」と尋ねてくる人もいる。たき火は小さなよろず相談所になった。
曽祖父から約120年も燃料販売店を営み、灯油、プロパンガス、炭も扱う。得意客は1000軒。誰よりも地元に詳しい。
「たき火をすると誰でも寄って、つらいことも話せるし、相談ごとも聞ける。
ぬれた木は燃えにくいんだが、先祖以来、まき、炭のプロだから」
たき火をする自宅も、1階が津波に没した。隣家との間に車が乗り上げ、周囲はがれきの山。
家族は無事だった。ザーという音に、半世紀前のチリ地震津波を経験した母キクさん(93)が「逃げろ」と叫んで2階にはい上がり、妻千代さん(62)も助かった。
高須賀さん自身は商店街で車ごと津波にのまれ、運よく窓から水中に脱出。知人の店で夜を明かし、カーテンを体に巻いて帰った。
「もらった命。まずは生き残った人たちと力を合わせようと決めた」
被災の翌日、避難所で「個人への配給はできない」と言われ、「それなら」と隣家を誘って「八幡町2丁目自主防災会」をつくった。会員は今、湊地区の水産加工会社で働く人、歯科医、年金生活の夫婦ら8家族20人。
1人の1日分がにぎり飯1個だった配給食を補うため、互いに食べ物を持ち寄ったり、流れ着いた密封の食品や缶飲料を見つけたり。津波をかぶった井戸水の砂をこして、洗い物に使ったり。
「『サバイバル飯』を考えるのも楽しい」と高須賀さん。米をサラダ油で炒めて味付けし、水を節約するチャーハンも。香ばしくて悪くない味だ。
会員で、水産加工会社に勤める主婦は津波で同僚6人を失った。送迎車で避難する途中に巻き込まれ、20代の男性従業員と自分だけが助かった。
憔悴(しょうすい)した若者は高須賀さん宅の2階に避難。長男の正忠さん(35)ら男の会員たちが車を捜し歩き、17日に遺体は確認された。
次には「遺族に伝えて回りたいが、車のガソリンがない」と会社の社長夫婦も駆け込んだ。
男の会員らは早速、津波で流された高須賀さんの営業車から、手動ポンプとホースでガソリンを抜き、給油に成功。社長夫婦は泣いて出発した。
「1日も早く仕事を再開したい」と高須賀さんは言う。在庫の灯油とガスボンベは幸いに無事。自家用のタンク車も正忠さんが、配達中に襲われた津波から守り抜いた。
「まだまだ寒い日が続く。被災して震えるお客さんたちに、たき火の暖かさを届けたいんだ」 (3月22日付)
◇
東日本大震災/ふんばる 3・11大震災 (3) 「恋し浜」の里人たち=大船渡市三陸町綾里・小石浜=/共同生活まるで家族 ホタテ産地に元気な声
「男の人だ(たち)、集まって。昼ご飯だよ」
避難所の公民館に、お母さんたちの元気な声が響く。震災発生以来、総勢約80人の共同生活を切り盛りしている。まるで大家族のようだ。
大船渡市三陸町綾里の小石浜地区。小さな湾で大半がホタテ養殖を営む30世帯が、地震とともに公民館に集まった。
「津波で8軒被災したが、全員が無事。大勢が死んだ明治の大津波の教訓で、すぐここに集まると決めている」と集落長の川原文夫さん(58)。多くの家も高台にある。
20人余りの80代も逃げた。山間の小石浜はかつて、誰もが綾里の町まで2時間の険路を歩いた。「綾里の地区対抗運動会で(小石浜は)常に一番だった」。自慢の健脚ぞろいが避難にも生きた。
「あんだどごで、いね人は?」と確認を終えるや、直ちに家が壊れた人もそうでない人も一緒の避難所生活が始まった。
米やみそ、冷蔵庫の食材や水産物、灯油やまきストーブ、ガスボンベも持ち寄り、集落の孤立にもびくともしなかった。
「ここには、若い男手もいっぱいあるんです」。配膳をしながら、婦人部長の川原律子さん(57)は頼もしそうに言う。
「恋し浜」。ホタテ養殖に取り組む小石浜青年部(佐々木淳部長)が地名をもじり、8年掛かりで全国に売り込んだ特産ブランドだ。集落を通る三陸鉄道の駅名も住民の要望で「恋し浜」への改称を実現させ、縁結びの名所に育ててきた。
高台の駅は残ったが、「養殖場や浜の倉庫、作業所はめちゃめちゃ。各地でイベントも開き、やっと波に乗ったのに」と総括担当の佐々木亨さん(41)らは無念そう。
だが、落ち込む間はない。水道が止まった後、集落の人々は「昔の生活に戻ればいい」(川原集落長)と、かつての水源だった山の水を公民館まで引いた。
そうした共同作業や家々の片付け、捜索活動に出る消防団の担い手も青年部だ。
メンバーは20〜30代を中心に8人。こんなに多くの後継者がいる浜はない。「一緒に育ち、育ててもらったから。海の仕事を選ぶのは自然なことだった」と佐々木さん。
高齢者、保育所や小学校の子ども、男たちの順に昼ご飯を出した後、お母さんたちがテーブルを囲んだ。毎日の献立づくりと食材選び、掃除、住民の健康のチェックなど、こちらも忙しい。
「集落が家族同様なのは、やっぱり、皆が同じ暮らしをしてきたから」と婦人部の川原さん。
ホタテ養殖は夫婦一体の作業だ。稚貝を育て、殻1枚1枚をひもにつって再び海に入れ、2年でやっと収穫。水揚げは朝3時だ。「海に出る時はどこの家族も一緒。声を掛け合い、一服のお茶の楽しみも、悩みも苦労も、子育てや結婚の喜びも分かち合ってきたんです」
大津波は、小石浜の稚貝、収穫期の貝を合わせ約一千万個を流したという。
「舟も失い、再生は10年掛かり。共同作業で始めるしかない」と佐々木さんは言う。痛みを包む公民館のぬくもりに「恋し浜」の火は残った。 (3月24日付)
◇
東日本大震災/ふんばる 3・11大震災 (11) 冨山勝敏さん(69)=ジャズ喫茶店主、陸前高田市=レコード1枚、夢残す/心癒やし集える場を必ず
大津波で街が壊滅した陸前高田市。約1200人が第一中学校で避難生活を送る。マットが敷き詰められた体育館に冨山勝敏さん(69)はいた。
「東京五輪のころ、古里の郡山市の高校を出て、東京でフーテン生活を送った。そこに戻って出直すようなもの」
陸前高田市のジャズ喫茶「h.イマジン」の店主。ジャズの名盤と本格コーヒーを楽しむ大勢のファンに親しまれた。店名はジョン・レノンの愛と平和の歌と「暇人」を掛けた。自らの人生観の表現だという。
「まさか、まさかと言っている間に、その店を2度も失うのだからね」
大船渡市の碁石海岸で2003年に開いた最初の店が昨年2月、火事で全焼した。陸前高田市に移り、再出発したのは昨年12月。3カ月もたたないうちに、今度は大津波が襲った。
東京の大手ホテルの会計システム責任者やベンチャー企業の役員などを経て、歩み始めた第二の人生。陸前高田の店は、築60年という旧高田町役場庁舎を手塩に掛けて改装した「夢の店」だった。
「マスターなら価値を分かってくれますね」。友人のメールが、旧庁舎との縁を結んだ。火災後、陸前高田市内で借住まいして間もないころ。
早速足を運んだ。技巧で名高い地元の気仙大工が手掛けた2階建て庁舎。ぼろぼろだったが、はりや柱は堅固だった。洋館の趣があった。
市の撤去方針に対し、保存運動が起きていた。市に掛け合うと、払い下げ額は200万円。
「一目ぼれだった。東京で第二の人生のすみかを探した時、ここ気仙地方の海岸の風光に心ひかれたように」
あの3月11日、逃げた高台から、引き潮に没する店を見た。
がれきの野と化した市街に3月20日、初めて足を運んだ。
柔らかい緑と赤の外壁、広いテラス、欧風の内装。その建物はすっかり消え去っていた。
吟味したドイツの紅茶、オリジナルのコーヒー、そしてジャズの響き。連日50人ほどでにぎわった店の跡には、革張りの椅子1脚が転がり、ジャケットのない古いジャズのレコード1枚が落ちていた。
「昔の建物だから土台は大丈夫だ。これが私の元手。木材を集めて掘っ立て小屋を建て、そこからまた始めるよ」
避難所には、Iターンして以来の友人たちが入れ替わり訪れ、応援してくれる。
「東京にはなかった人の情が何よりの財産になった。しばらく、みんな苦労の日々が続く。心を癒やしに集える場をつくるのが、次の仕事だ」
店の玄関脇の辺りに、緑の芽があった。スイセン。津波の潮と砂にもまれた後も伸びている。「咲いてほしい」と冨山さんは願う。
身を寄せる第一中学校のグランドでは今、仮設住宅の建設が急ピッチで進む。 (4月1日付)

(4月2日付夕刊2面)

(『ふんばる』 3月22日付朝刊社会面)