2020年04月18日
少年が来る
前回のエントリーに、次の機会はゴールデンウイークになりそうだと書いた時、もちろん2019年のそれを想定していたのだけれども、あっという間に時が過ぎ、2020年のゴールデンウイークが近づきつつある。そしてそれは、1年前のゴールデンウイークとはうって変わった、これまで誰も経験したことのないような大型連休となりそうだ。むしろ、その大型連休は、既に前倒しで始まっているとも言える。
このコロナ禍をどう捉えるのか、それをどう乗り切るのか、ネット上ではさまざまな情報が錯綜している。いい加減うんざりしている自分と、それでも読まずにはいられない自分。
インターネットが発達したおかげで、政府の発表やマスコミの報道を鵜呑みにせずに自分自身で情報を集めることが可能になった。それに基づく自分の意見を、SNSで発信できるようにもなった。
多様な意見が、お互いに他を説得しようと競い合う「思想の自由市場」を形成し、その市場において真理が勝利することによって社会が発展・進歩する。だから表現の自由は、基本的人権の体系の中でも優越的な地位を占めるものであり、その制約の合憲性は、他の人権に比較して厳格な基準によって判断されなければならない。
そのようにぼくは学んできたし、それは、基本的に正しいことだと思っている。
しかし、いまの新型コロナに関する情報は、一般人が適切に処理できる量を遥かに超えているのではないか。少なくとも、ぼく自身についていえば、そうだ。そして、おそらくは適切に処理できていない人が、それを自覚しないまま二次情報を発信し、それが膨大な量のコメントとともに拡散され、それがまた「炎上」などと面白おかしく報道されるというスパム情報の自己増殖が繰り返されているように思える。まあ、そんなものを見なければいいだけのことではあるのだが。
ノイズを無視する冷静さを含めて、自由な社会が維持できるのかどうかが試されているのかもしれない。
雨が降りそうだ。
君は声に出してつぶやく。
ほんとに雨が降ってきたらどうしよう。
君は目を細めて道庁前の銀杏の木を見つめる。揺れる枝の間から、風の形が出し抜けに現れるかのように。空気のすきまに隠れていた雨粒が一斉にはじけ出て、透明な宝石さながら宙に浮いてきらめくかのように。
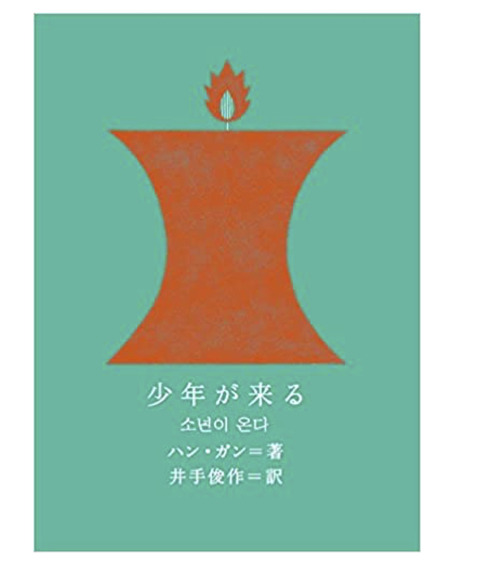 ここで「君」と呼ばれているのは、トンホという中学3年生の少年。「道庁」というのは、光州市にある全羅南道の庁舎。時は、1980年5月。
ここで「君」と呼ばれているのは、トンホという中学3年生の少年。「道庁」というのは、光州市にある全羅南道の庁舎。時は、1980年5月。
戒厳軍の侵攻が迫る中、抵抗派の拠点となった道庁に最後まで残り、投降とともに虐殺されたこの少年の思い出を中心に、作者は、光州事件に関わった人間たちの軌跡を描いていく。
トンホの家には、同級生のチョンデと、その姉のチョンミが間借りしていた。まず行方が分からなくなったのはチョンミ姉さんだ。チョンデを大学に進学させたい一心で働きづめに働いていた彼女が、自分の意思で弟を捨てるはずはない。トンホとチョンデは、チョンミ姉さんを探しに、軍・警察と市民が争う市街地に出かける。
このコロナ禍をどう捉えるのか、それをどう乗り切るのか、ネット上ではさまざまな情報が錯綜している。いい加減うんざりしている自分と、それでも読まずにはいられない自分。
インターネットが発達したおかげで、政府の発表やマスコミの報道を鵜呑みにせずに自分自身で情報を集めることが可能になった。それに基づく自分の意見を、SNSで発信できるようにもなった。
多様な意見が、お互いに他を説得しようと競い合う「思想の自由市場」を形成し、その市場において真理が勝利することによって社会が発展・進歩する。だから表現の自由は、基本的人権の体系の中でも優越的な地位を占めるものであり、その制約の合憲性は、他の人権に比較して厳格な基準によって判断されなければならない。
そのようにぼくは学んできたし、それは、基本的に正しいことだと思っている。
しかし、いまの新型コロナに関する情報は、一般人が適切に処理できる量を遥かに超えているのではないか。少なくとも、ぼく自身についていえば、そうだ。そして、おそらくは適切に処理できていない人が、それを自覚しないまま二次情報を発信し、それが膨大な量のコメントとともに拡散され、それがまた「炎上」などと面白おかしく報道されるというスパム情報の自己増殖が繰り返されているように思える。まあ、そんなものを見なければいいだけのことではあるのだが。
ノイズを無視する冷静さを含めて、自由な社会が維持できるのかどうかが試されているのかもしれない。
雨が降りそうだ。
君は声に出してつぶやく。
ほんとに雨が降ってきたらどうしよう。
君は目を細めて道庁前の銀杏の木を見つめる。揺れる枝の間から、風の形が出し抜けに現れるかのように。空気のすきまに隠れていた雨粒が一斉にはじけ出て、透明な宝石さながら宙に浮いてきらめくかのように。
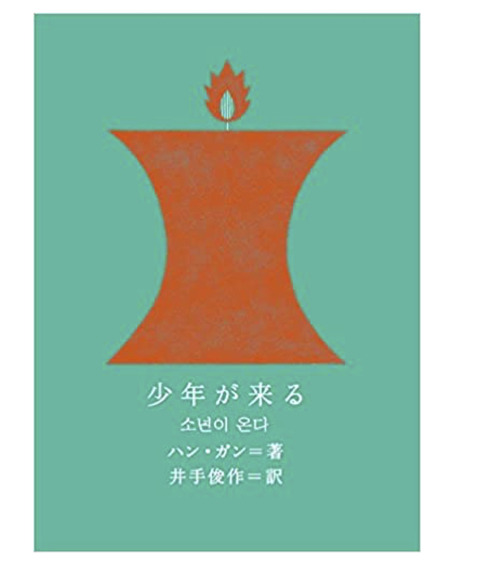 ここで「君」と呼ばれているのは、トンホという中学3年生の少年。「道庁」というのは、光州市にある全羅南道の庁舎。時は、1980年5月。
ここで「君」と呼ばれているのは、トンホという中学3年生の少年。「道庁」というのは、光州市にある全羅南道の庁舎。時は、1980年5月。戒厳軍の侵攻が迫る中、抵抗派の拠点となった道庁に最後まで残り、投降とともに虐殺されたこの少年の思い出を中心に、作者は、光州事件に関わった人間たちの軌跡を描いていく。
トンホの家には、同級生のチョンデと、その姉のチョンミが間借りしていた。まず行方が分からなくなったのはチョンミ姉さんだ。チョンデを大学に進学させたい一心で働きづめに働いていた彼女が、自分の意思で弟を捨てるはずはない。トンホとチョンデは、チョンミ姉さんを探しに、軍・警察と市民が争う市街地に出かける。
………駅前で銃撃された二人の男の遺体が、リヤカーに載せられデモ隊の先頭で行進した日、中折れ帽の老人から一二、三歳の子ども、カラフルな日傘の女性まで、多様な人々が見渡す限り黒山のようになったあの広場で、最後にチョンデを見たのは地区の人ではなくまさに君だった。姿を見ただけではなく、脇腹に銃弾を受けるのまで見た。いや、チョンデと君は最初から手を取り合って先頭の方に、先頭の熱気の方に進み出ていた。耳をつんざく銃声にみんな後戻りして走り出した。空砲だ! 大丈夫だ! 誰かがそう叫び、デモの隊列に戻ろうとする人々でごった返す修羅場の中で、チョンデの手を離した。再び銃声が耳をつんざいたとき、横向きに倒れたチョンデをその場に残して君は走った。
トンホは、チョンデが撃たれたこと、それを見捨てて一人で家に帰ってきたことを家族に言えない。
母屋から出た君は、台所横の自分の部屋に入った。ボールみたいに腰を丸め、油紙を張ったオンドルの床に横になった。気を失ったように眠りに落ちた後、数分もしないうちに、記憶には残らない恐ろしい夢を見てはっと目が覚めた。夢よりも恐ろしい現の時が君を待っていた。客部屋棟のチョンデの部屋には、当然ながら人の気配がなかった。夕方になっても同じだろう。明かりはつかないだろう。鍵は石段横の赤粘土甕の中で微動もせずにうずくまっているだろう。
トンホが道庁を訪れたのは、その住民課窓口の廊下に並べられた遺体の中に、チョンデを探すためだ。そこでトンホは、遺体係のウンスク姉さんとソンジュ姉さんに出会い、自分もまた、そのチームの一員となる。遺体の管理を総括して葬式の準備をするチンス兄さんとも出会う。
戒厳軍の侵攻が迫っても、トンホは道庁を離れようとしない。年齢をごまかして銃を受け取り、母親が迎えにきても、チンス兄さんから叱責されても。
二人称で描かれる第1章「幼い鳥」は、トンホが逃げないことを決意する場面で終わる。
その後のトンホの姿は、第2章以降、さまざまな形で語られる。
第4章「鉄と血」で、キム・チンスのその後を語る無名の男は、チンスと少年が言い争っていたことを記憶している。
おまえがここで何をするっていうんだ。銃の撃ち方も知らないくせに。
もじもじと少年が言いました。
……怒らないでよ、兄さん。
二人の言い争う声で、仲間がごそごそと目を覚ましました。少年の腕を離さずに、キム・チンスは言いました。
適当なときにおまえは降伏しろ。分かったな。降伏するんだ。手を上げて出ていけ。手を上げて出ていく子どもを殺しはしないはずだからな。
最終段階で戦列を離れたキム・ウンスクは、第3章「七つのビンタ」で、最後にみたトンホの姿を思い出す。
…………ついに道庁の方から銃声が聞こえたとき、彼女は寝入っていなかった。耳をふさいでも、目を閉じてもいなかった。うなだれも、うめきもしなかった。ただ君のことを思い出した。君を連れて行こうとしたら、君は階段の方にすばしこく走った。おびえた顔で、まるで突っ走ることだけが生きる道であるように。一緒に帰ろうよ、ねえトンホ。今一緒に出なきゃ。危なっかしく二階の欄干につかまって立ち、君は震えた。最後に目が合ったとき、生きたくて、怖くて、君のまぶたは震えた。
第5章「夜の瞳」の主人公は、道庁に最後まで残ることを選んだイム・ソンジュだ。三十センチの木の物差しで、子宮の奥まで数十回もほじくられるような拷問を生き残った彼女は、刑務所を出た後、写真集の中にトンホの姿を発見した。
君は道庁の中庭に横たわっていた。銃撃の反動で、腕と足が交差して長く伸びていた。顔と胸は空を向き、両足はそれとは逆向きに開いた状態で、その爪先は地面を向いていた。脇腹が激しくねじれたその姿が、いまわの際の苦痛を物語っていた。
息ができなかったの。
何も言えなかったわ。
つまりあの夏に君は死んでいたのね。私の体がどめどなく血をあふれ出させているとき、君の体は地中で猛烈に腐っていたのね。
その瞬間、君が私の命を助けたのよ。あっという間に私の血をぐらぐらと煮え返らせてよみがえらせたのよ。心臓が破けるような苦痛の力、怒りの力で。
この写真は、第4章で語られている写真と同じものだろうか。
五人の生徒が二階から手を挙げて下りてきたのはそのときでした。照明弾で真昼のように明るくして戒厳軍が機関銃を乱射し始めたときに、わたしが小会議室に隠れるように命じた四人の高校生と、ソファでキム・チンスと短く言い争った中学生でした。銃声がそれ以上聞こえなくなると、彼らはキム・チンスが言い聞かせていた通り、武器を捨てて降伏するために下りてきたのでした。………お分かりですか。ですからこの写真でこの子たちがずらっと並んで倒れているのは、こんなふうにきちんと運んで置いたからではないのです。一列になって子どもたちが歩いてやって来たのです。私たちが言い付けておいた通りに両手を挙げ、整列して歩いてやって来ていたのです。
ハン・ガン(漢江)といえば、首都ソウルの中央部を貫流する、韓国では流域面積第一位の大河である。韓国の1960年代〜80年代の経済成長が「漢江の奇跡」と呼ばれることから想像するに、韓国の人にとっては、おそらく象徴的な地名なのではないだろうか。これがペンネームではなく本名であるとするならば、父親ハン・スンウォン(漢勝源)は、娘にずいぶんと大きな荷物を背負わせたものだと思う。
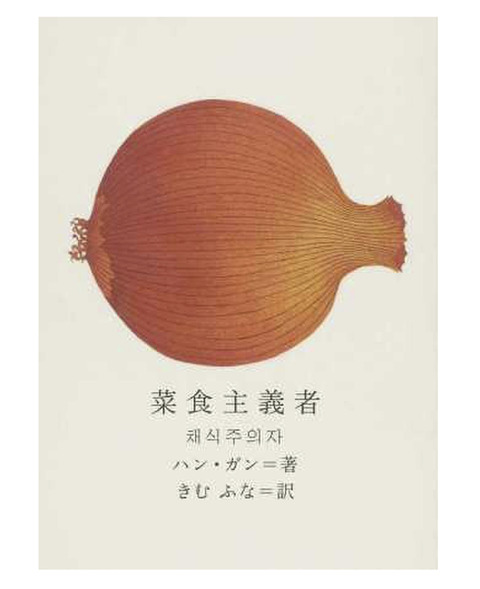 娘は、その名のとおり、韓国を代表する作家になった。
娘は、その名のとおり、韓国を代表する作家になった。
このブログでも何度か言及してきたブッカー賞は、1968年に創設された世界で最も権威のある文学賞の一つであり、もともとはイギリス連邦あるいはアイルランド国籍の作家によって英語で書かれた長編小説を対象とするものだ。2006年にその対象外の作品に対する国際ブッカー賞が創設され、このブログで扱った作家としては、イスマイル・カダレ、フィリップ・ロスといった作家が受賞している。
その国際ブッカー賞を、アジアで初めて受賞したのが、この作家の『菜食主義者』だった。日本の作家では、大江健三郎、小川洋子が候補となったことがあるが、まだ授賞した作家はいない。
そのハン・ガンが、韓国現代史の闇ともいえる光州事件に挑んだのが、この『少年が来る』という作品なのである。
トンホは、なぜ逃げなかったのか。
ミンス兄さんは、ソンジュ姉さんは、なぜ最後まで残ったのか。
軍人が圧倒的に強いことを知らないわけではありませんでした。ただ妙なことは、彼らの力と同じ位に強烈な何かが私を圧倒していたということなのです。
良心。
そうです、良心。
この世で最も恐るべきものがそれです。
軍人が撃ち殺した人たちの遺体をリヤカーに載せ、先頭に押し立てて数十万人の人々と共に銃口の前に立った日、不意に発見した自分の内にある清らかな何かに私は驚きました。もう何も怖くはないという感じ、今死んでも構わないという感じ、数十万の人々の血が集まって巨大な血管をつくったようだった新鮮な感じを覚えています。その血管に流れ込んでドクドクと脈打つ、この世で最も巨大で崇高な心臓の脈拍を私は感じました。
しかし同時にあなたは知っている。その年の春のような瞬間がもし差し迫ったら、同じような選択をすることになるかもしれないことを。小学校のときにドッジボールの試合で、すばしこくボールを避けてばかりいるうちに一人だけになると結局、正面からボールを受け止めなくてはならない瞬間が訪れたように。バスからどっと沸き上がる女の子たちの甲高い歌に引かれて広場の方へ、銃を持った軍隊が警備する広場の方へ歩いたように。しまいまで残るとしずかに手を挙げた最後の夜のように。
われわれは、光州事件について、何を知っているだろう。
1980年5月、ぼくは高校3年生だった。韓国の光州という町で、市民と軍隊が衝突したことは報道で知っていた。その後、紆余曲折を経ながら韓国の政治が民主化されていったこと、この光州事件が、その民主化の原点と位置づけられていることなどもなんとなく把握していた。
ぼくが知っていたのは、その程度のことだ。
この小説に描かれたような、軍隊による市民の虐殺が行われたことを、知らなかった。
生き残った者たちに対して、性的虐待を含む拷問が行われたことを、知らなかった。
生き残った者たちが、回復不能な心の傷を負って生き続け、あるいは自らの命を絶っていったことを、知らなかった。
その後、長年にわたる言論弾圧が行われたことを、知らなかった。
こういった場合の「知らなかった」がどの程度ほんとうのことなのか、いつも自問自答せざるを得ないのだが、この小説に圧倒された今では、やはり「知らなかった」というほかないのである。
1985年頃、東京で司法試験の勉強をしていたぼくは、深夜の居酒屋で、酔っ払った韓国人に絡まれたことがある。ぼくよりやや年上であった彼は、「日本は自由な国だ」、「日本の若者は幸せだ」、「韓国も自由な国なんだ」と、当時のぼくにはピンとこないことを繰り返し、「しかし、韓国には言論の自由がないんです、言論の自由だけはないんです」と嘆息した。
この人はいったい何を言っているのだ、言論の自由のない国が自由な国であるはずがないではないか、と思ったことを覚えている。
盧泰愚政権下で、それまで「光州暴動」とされていた事件が民主化運動の一環と位置づけられて被害者に対する補償法が成立し、金泳三政権下では、全斗煥と盧泰愚が光州事件弾圧の責任者として罪に問われた。しかし、それによってこの事件の全貌が解明されたというわけではないらしい。死亡者は2000人を超えるという説もあるが、補償法で認定されたのは154人に過ぎない。
それは、1987年の民主化宣言後も、保守系と革新系との間に厳しい対立が続いていることと無関係ではないだろう。この作品は保守派の李明博政権下で書かれ、朴槿恵政権下で出版された。この事件を闇に葬る方向の力が強い時代だったはずだ。
朴政権がキャンドル・デモによって退陣し、その後を襲った文在寅政権は、2018年11月7日、光州事件における兵士らによる女性に対する強姦や性的暴行について、はじめて公式に謝罪をした。ソンジュ姉さんの被害は、実在した。
もうすぐ事件から40年が過ぎようとしているが、全貌解明はまだ進行中なのである。
改めて思うのは、いまの韓国の政治体制は、韓国の市民が自ら血を流して勝ち取ってきたものだということだ。光州事件を原点とする市民の闘いが、軍事独裁政権を倒し、紆余曲折を経ながらではあるが、事件の全貌を闇から引き出しつつある。
その日、日が暮れるころ、父ちゃんの肩につかまってよろよろと屋上に上がったんだ。欄干にもたれて懸垂幕を長く垂らして叫んだんだ。うちの息子を返せ。殺人鬼の全斗煥を八つ裂きにしろ。脳天に血が上るくらい叫んだんだ。警官たちが非常階段を上がってくるまで、母ちゃんを抱えて入院室のベッドに投げ込むまでそんなふうに叫んだんだよ。
次も、その次も、母ちゃん同士会っては闘い、会っては闘ったんだ。別れるたびに母さん同士互いに手を握り、肩をなで、見つめ合いながらまた会おうって約束したんだ。乏しい家計の中からお金を出し合って、貸し切りバスを仕立ててソウルの集会にも行ったよ。あるときは、残忍なやつらが母ちゃんたちのバスの中に丸い催涙弾を放り込んで、お母さんの一人は倒れて息もできなくなっったんだよ。みんなしょっぴかれて戦闘警察部隊の車に乗せられたとき、あいつらはひっそりした国道の道端に一人落とし、しばらく走ってまた一人落とし……そうやって母ちゃんたちをみんな離ればなれにしたんだよ。母ちゃんは地理も分からない道端をひたすら歩いたよ。母ちゃんたちがまた集まって、お互いの背中をなで合うまで。寒さで青ざめたお互いの唇を見つめ合うまで。
従軍慰安婦問題や徴用工問題での韓国政府の対応を、大衆迎合的で国としての体をなしていないと批判する日本人は多い。キャンドル・デモで政権が倒れるような国は法治国家とはいえないなどという言説もある。
しかし、基本的人権とか権力分立といった理念は、本来、市民革命の血風惨雨の中で生まれ、定着してきたものである。仮に選挙で選ばれた政権であっても、それが国民の基本的人権を侵害するとなれば、国民は街頭でもどこでも反対意見を表明し、その退陣を求める権利を持っている。大衆のデモが政権を倒すのは世界中でみられる社会現象であり、それをおかしいと感じるとすれば、日本という国に、市民自らが血を流して政治体制を勝ち取ったという経験がないからに過ぎない。
平和な社会を誇るのはいい。しかし、隣国の市民の命をかけた闘いを嘲笑うのは、人権の歴史を知らない夜郎自大の恥ずべき所業だろう。
もちろん、そういった歴史的な意義とは別に、小説としての魅力に溢れる作品でもある。そこに描かれている人物たちは、ぼく自身の幼い頃の友人たちを思い出させるようなリアリティを備えている。
チョンデを見捨てて帰ってきた夜、トンホはチョンデのことを思い巡らす。
落ち着き払って黒板消しを学生カバンに入れたチョンデ。そんなの、なんで持っていくんだ? うちの姉ちゃんにあげようと思って。お前の姉ちゃんはこれを何に使うんだ? さあね、これをよく思い出すんだってさ。中学校に通っているとき、勉強よりもなんと週当番の方がずっと面白かったって言うんだよ。あるときなんかエイプリルフールだと言って、クラスの子たちが黒板にびっしり字を書いておいたんだって。チョンガーの先生が消すのに苦労するだろうと思っていたら、先生が週当番は誰だと怒鳴って、姉ちゃんが出ていって黒板の字をせっせと消したんだってさ。みんな授業中なのに、自分一人、廊下で窓を開けて黒板消しを棒でパンパンはたいたんだって。中学校に二年間通った中で、変だけどそのときのことを一番よく思い出すんだってさ。
ぼくの心にも、この黒板消しを棒ではたいているチョンミ姉さんの姿がいちばん印象深く刻まれている。なぜ、そうなのかは説明できない。「変だけど」と、チョンミ姉さんが語るとおりだ。しかし、なぜかは説明できないけれど印象に残る場面を、文学という形で定着させるのが、作家としての腕前というものだ。
もうひとつ、言っておきたいのは、このハン・ガンという作家は、稀に見る二人称小説の名手ではないかということである。
なぜ、第1章「幼い鳥」は、「ぼくは」という一人称ではなく、「トンホは」、「少年は」といった三人称でもなく、「君は」という二人称で語られているのか。
なぜ、第5章「夜の瞳」は、「わたしは」という一人称ではなく、「ソンジュは」、「彼女は」といった三人称でもなく、「あなたは」という二人称で語られているのか。
作家自身の一人称で語られる「エピローグ」まで含めた7章のうち、この2章のみが二人称で語られているのは、何らかの綿密な計算に基づくものなのか、あるいは作家としての職業的な直感によって選択しているものなのか。素人であるぼくにはなんとも判断できないけれども、その語り口は極めて自然で、特に第1章は、読者を1980年5月の光州に何の違和感もなく運んでいく。
二人称の小説というのは比較的珍しいし、ぼくもいますぐに思い出せるものは筒井康隆の短篇くらいなのだが、その数少ない経験からいえば、二人称の語り口というのは、「あなたはだんだん眠くなる……」式の押しつけがましさをなかなか免れないものである。しかし、ハン・ガンの文体には、それがない。
短篇集『回復する人間』の表題作も、二人称小説である。
 ………今あなたは葦の茂みの縁に横たわっている。自転車は川沿いの岩の上に投げ出されて倒れ、車輪が力強く空転している。空中から墜落した瞬間、あなたは本能的に頭をかばった。手とひじの皮膚がむけていることは明らかだ。地面にぶつけた肩と骨盤がじーんと痛みだす。
………今あなたは葦の茂みの縁に横たわっている。自転車は川沿いの岩の上に投げ出されて倒れ、車輪が力強く空転している。空中から墜落した瞬間、あなたは本能的に頭をかばった。手とひじの皮膚がむけていることは明らかだ。地面にぶつけた肩と骨盤がじーんと痛みだす。
これくらい、とつぶやきながらあなたは濡れた土の上に横たわっている。灰白色の穴の中のきずのことなど、もう感じられない。土が入った右の目がひりひりする。これらすべての痛覚はあまりに弱々しいと、何度もまばたきしながらあなたは思う。今、自分が経験しているどんなことからも、私を回復させないでほしいと、この冷たい土がもっと冷え、顔も体もかちかちに凍りつくようにしてくれと、お願いだからここから二度と体を起こさないようにしてくれと、あなたは誰に向けたのでもない祈りの言葉を口の中でつぶやきつづける。
この二人称文体の心地よさは、おそらく、このハン・ガンという作家の資質の中核部分に関わっているのではないかと思うのだけれど、漠然と思うだけで、それを解明できるような力はぼくにはない。
ただ、もっと彼女の作品を読んでみたいと思うだけだ。
トンホは、チョンデが撃たれたこと、それを見捨てて一人で家に帰ってきたことを家族に言えない。
母屋から出た君は、台所横の自分の部屋に入った。ボールみたいに腰を丸め、油紙を張ったオンドルの床に横になった。気を失ったように眠りに落ちた後、数分もしないうちに、記憶には残らない恐ろしい夢を見てはっと目が覚めた。夢よりも恐ろしい現の時が君を待っていた。客部屋棟のチョンデの部屋には、当然ながら人の気配がなかった。夕方になっても同じだろう。明かりはつかないだろう。鍵は石段横の赤粘土甕の中で微動もせずにうずくまっているだろう。
トンホが道庁を訪れたのは、その住民課窓口の廊下に並べられた遺体の中に、チョンデを探すためだ。そこでトンホは、遺体係のウンスク姉さんとソンジュ姉さんに出会い、自分もまた、そのチームの一員となる。遺体の管理を総括して葬式の準備をするチンス兄さんとも出会う。
戒厳軍の侵攻が迫っても、トンホは道庁を離れようとしない。年齢をごまかして銃を受け取り、母親が迎えにきても、チンス兄さんから叱責されても。
二人称で描かれる第1章「幼い鳥」は、トンホが逃げないことを決意する場面で終わる。
その後のトンホの姿は、第2章以降、さまざまな形で語られる。
第4章「鉄と血」で、キム・チンスのその後を語る無名の男は、チンスと少年が言い争っていたことを記憶している。
おまえがここで何をするっていうんだ。銃の撃ち方も知らないくせに。
もじもじと少年が言いました。
……怒らないでよ、兄さん。
二人の言い争う声で、仲間がごそごそと目を覚ましました。少年の腕を離さずに、キム・チンスは言いました。
適当なときにおまえは降伏しろ。分かったな。降伏するんだ。手を上げて出ていけ。手を上げて出ていく子どもを殺しはしないはずだからな。
最終段階で戦列を離れたキム・ウンスクは、第3章「七つのビンタ」で、最後にみたトンホの姿を思い出す。
…………ついに道庁の方から銃声が聞こえたとき、彼女は寝入っていなかった。耳をふさいでも、目を閉じてもいなかった。うなだれも、うめきもしなかった。ただ君のことを思い出した。君を連れて行こうとしたら、君は階段の方にすばしこく走った。おびえた顔で、まるで突っ走ることだけが生きる道であるように。一緒に帰ろうよ、ねえトンホ。今一緒に出なきゃ。危なっかしく二階の欄干につかまって立ち、君は震えた。最後に目が合ったとき、生きたくて、怖くて、君のまぶたは震えた。
第5章「夜の瞳」の主人公は、道庁に最後まで残ることを選んだイム・ソンジュだ。三十センチの木の物差しで、子宮の奥まで数十回もほじくられるような拷問を生き残った彼女は、刑務所を出た後、写真集の中にトンホの姿を発見した。
君は道庁の中庭に横たわっていた。銃撃の反動で、腕と足が交差して長く伸びていた。顔と胸は空を向き、両足はそれとは逆向きに開いた状態で、その爪先は地面を向いていた。脇腹が激しくねじれたその姿が、いまわの際の苦痛を物語っていた。
息ができなかったの。
何も言えなかったわ。
つまりあの夏に君は死んでいたのね。私の体がどめどなく血をあふれ出させているとき、君の体は地中で猛烈に腐っていたのね。
その瞬間、君が私の命を助けたのよ。あっという間に私の血をぐらぐらと煮え返らせてよみがえらせたのよ。心臓が破けるような苦痛の力、怒りの力で。
この写真は、第4章で語られている写真と同じものだろうか。
五人の生徒が二階から手を挙げて下りてきたのはそのときでした。照明弾で真昼のように明るくして戒厳軍が機関銃を乱射し始めたときに、わたしが小会議室に隠れるように命じた四人の高校生と、ソファでキム・チンスと短く言い争った中学生でした。銃声がそれ以上聞こえなくなると、彼らはキム・チンスが言い聞かせていた通り、武器を捨てて降伏するために下りてきたのでした。………お分かりですか。ですからこの写真でこの子たちがずらっと並んで倒れているのは、こんなふうにきちんと運んで置いたからではないのです。一列になって子どもたちが歩いてやって来たのです。私たちが言い付けておいた通りに両手を挙げ、整列して歩いてやって来ていたのです。
ハン・ガン(漢江)といえば、首都ソウルの中央部を貫流する、韓国では流域面積第一位の大河である。韓国の1960年代〜80年代の経済成長が「漢江の奇跡」と呼ばれることから想像するに、韓国の人にとっては、おそらく象徴的な地名なのではないだろうか。これがペンネームではなく本名であるとするならば、父親ハン・スンウォン(漢勝源)は、娘にずいぶんと大きな荷物を背負わせたものだと思う。
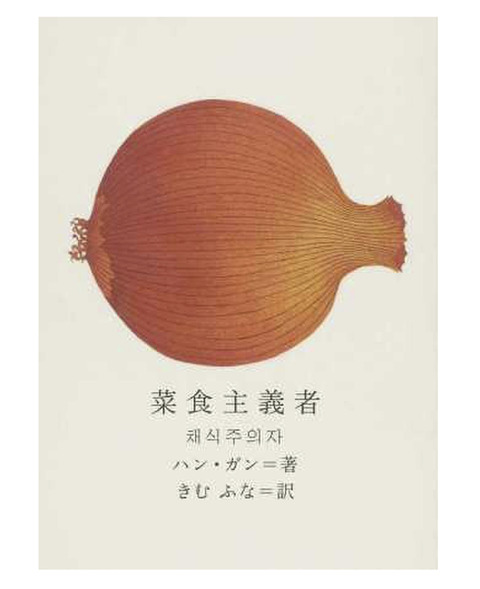 娘は、その名のとおり、韓国を代表する作家になった。
娘は、その名のとおり、韓国を代表する作家になった。このブログでも何度か言及してきたブッカー賞は、1968年に創設された世界で最も権威のある文学賞の一つであり、もともとはイギリス連邦あるいはアイルランド国籍の作家によって英語で書かれた長編小説を対象とするものだ。2006年にその対象外の作品に対する国際ブッカー賞が創設され、このブログで扱った作家としては、イスマイル・カダレ、フィリップ・ロスといった作家が受賞している。
その国際ブッカー賞を、アジアで初めて受賞したのが、この作家の『菜食主義者』だった。日本の作家では、大江健三郎、小川洋子が候補となったことがあるが、まだ授賞した作家はいない。
そのハン・ガンが、韓国現代史の闇ともいえる光州事件に挑んだのが、この『少年が来る』という作品なのである。
トンホは、なぜ逃げなかったのか。
ミンス兄さんは、ソンジュ姉さんは、なぜ最後まで残ったのか。
軍人が圧倒的に強いことを知らないわけではありませんでした。ただ妙なことは、彼らの力と同じ位に強烈な何かが私を圧倒していたということなのです。
良心。
そうです、良心。
この世で最も恐るべきものがそれです。
軍人が撃ち殺した人たちの遺体をリヤカーに載せ、先頭に押し立てて数十万人の人々と共に銃口の前に立った日、不意に発見した自分の内にある清らかな何かに私は驚きました。もう何も怖くはないという感じ、今死んでも構わないという感じ、数十万の人々の血が集まって巨大な血管をつくったようだった新鮮な感じを覚えています。その血管に流れ込んでドクドクと脈打つ、この世で最も巨大で崇高な心臓の脈拍を私は感じました。
しかし同時にあなたは知っている。その年の春のような瞬間がもし差し迫ったら、同じような選択をすることになるかもしれないことを。小学校のときにドッジボールの試合で、すばしこくボールを避けてばかりいるうちに一人だけになると結局、正面からボールを受け止めなくてはならない瞬間が訪れたように。バスからどっと沸き上がる女の子たちの甲高い歌に引かれて広場の方へ、銃を持った軍隊が警備する広場の方へ歩いたように。しまいまで残るとしずかに手を挙げた最後の夜のように。
われわれは、光州事件について、何を知っているだろう。
1980年5月、ぼくは高校3年生だった。韓国の光州という町で、市民と軍隊が衝突したことは報道で知っていた。その後、紆余曲折を経ながら韓国の政治が民主化されていったこと、この光州事件が、その民主化の原点と位置づけられていることなどもなんとなく把握していた。
ぼくが知っていたのは、その程度のことだ。
この小説に描かれたような、軍隊による市民の虐殺が行われたことを、知らなかった。
生き残った者たちに対して、性的虐待を含む拷問が行われたことを、知らなかった。
生き残った者たちが、回復不能な心の傷を負って生き続け、あるいは自らの命を絶っていったことを、知らなかった。
その後、長年にわたる言論弾圧が行われたことを、知らなかった。
こういった場合の「知らなかった」がどの程度ほんとうのことなのか、いつも自問自答せざるを得ないのだが、この小説に圧倒された今では、やはり「知らなかった」というほかないのである。
1985年頃、東京で司法試験の勉強をしていたぼくは、深夜の居酒屋で、酔っ払った韓国人に絡まれたことがある。ぼくよりやや年上であった彼は、「日本は自由な国だ」、「日本の若者は幸せだ」、「韓国も自由な国なんだ」と、当時のぼくにはピンとこないことを繰り返し、「しかし、韓国には言論の自由がないんです、言論の自由だけはないんです」と嘆息した。
この人はいったい何を言っているのだ、言論の自由のない国が自由な国であるはずがないではないか、と思ったことを覚えている。
盧泰愚政権下で、それまで「光州暴動」とされていた事件が民主化運動の一環と位置づけられて被害者に対する補償法が成立し、金泳三政権下では、全斗煥と盧泰愚が光州事件弾圧の責任者として罪に問われた。しかし、それによってこの事件の全貌が解明されたというわけではないらしい。死亡者は2000人を超えるという説もあるが、補償法で認定されたのは154人に過ぎない。
それは、1987年の民主化宣言後も、保守系と革新系との間に厳しい対立が続いていることと無関係ではないだろう。この作品は保守派の李明博政権下で書かれ、朴槿恵政権下で出版された。この事件を闇に葬る方向の力が強い時代だったはずだ。
朴政権がキャンドル・デモによって退陣し、その後を襲った文在寅政権は、2018年11月7日、光州事件における兵士らによる女性に対する強姦や性的暴行について、はじめて公式に謝罪をした。ソンジュ姉さんの被害は、実在した。
もうすぐ事件から40年が過ぎようとしているが、全貌解明はまだ進行中なのである。
改めて思うのは、いまの韓国の政治体制は、韓国の市民が自ら血を流して勝ち取ってきたものだということだ。光州事件を原点とする市民の闘いが、軍事独裁政権を倒し、紆余曲折を経ながらではあるが、事件の全貌を闇から引き出しつつある。
その日、日が暮れるころ、父ちゃんの肩につかまってよろよろと屋上に上がったんだ。欄干にもたれて懸垂幕を長く垂らして叫んだんだ。うちの息子を返せ。殺人鬼の全斗煥を八つ裂きにしろ。脳天に血が上るくらい叫んだんだ。警官たちが非常階段を上がってくるまで、母ちゃんを抱えて入院室のベッドに投げ込むまでそんなふうに叫んだんだよ。
次も、その次も、母ちゃん同士会っては闘い、会っては闘ったんだ。別れるたびに母さん同士互いに手を握り、肩をなで、見つめ合いながらまた会おうって約束したんだ。乏しい家計の中からお金を出し合って、貸し切りバスを仕立ててソウルの集会にも行ったよ。あるときは、残忍なやつらが母ちゃんたちのバスの中に丸い催涙弾を放り込んで、お母さんの一人は倒れて息もできなくなっったんだよ。みんなしょっぴかれて戦闘警察部隊の車に乗せられたとき、あいつらはひっそりした国道の道端に一人落とし、しばらく走ってまた一人落とし……そうやって母ちゃんたちをみんな離ればなれにしたんだよ。母ちゃんは地理も分からない道端をひたすら歩いたよ。母ちゃんたちがまた集まって、お互いの背中をなで合うまで。寒さで青ざめたお互いの唇を見つめ合うまで。
従軍慰安婦問題や徴用工問題での韓国政府の対応を、大衆迎合的で国としての体をなしていないと批判する日本人は多い。キャンドル・デモで政権が倒れるような国は法治国家とはいえないなどという言説もある。
しかし、基本的人権とか権力分立といった理念は、本来、市民革命の血風惨雨の中で生まれ、定着してきたものである。仮に選挙で選ばれた政権であっても、それが国民の基本的人権を侵害するとなれば、国民は街頭でもどこでも反対意見を表明し、その退陣を求める権利を持っている。大衆のデモが政権を倒すのは世界中でみられる社会現象であり、それをおかしいと感じるとすれば、日本という国に、市民自らが血を流して政治体制を勝ち取ったという経験がないからに過ぎない。
平和な社会を誇るのはいい。しかし、隣国の市民の命をかけた闘いを嘲笑うのは、人権の歴史を知らない夜郎自大の恥ずべき所業だろう。
もちろん、そういった歴史的な意義とは別に、小説としての魅力に溢れる作品でもある。そこに描かれている人物たちは、ぼく自身の幼い頃の友人たちを思い出させるようなリアリティを備えている。
チョンデを見捨てて帰ってきた夜、トンホはチョンデのことを思い巡らす。
落ち着き払って黒板消しを学生カバンに入れたチョンデ。そんなの、なんで持っていくんだ? うちの姉ちゃんにあげようと思って。お前の姉ちゃんはこれを何に使うんだ? さあね、これをよく思い出すんだってさ。中学校に通っているとき、勉強よりもなんと週当番の方がずっと面白かったって言うんだよ。あるときなんかエイプリルフールだと言って、クラスの子たちが黒板にびっしり字を書いておいたんだって。チョンガーの先生が消すのに苦労するだろうと思っていたら、先生が週当番は誰だと怒鳴って、姉ちゃんが出ていって黒板の字をせっせと消したんだってさ。みんな授業中なのに、自分一人、廊下で窓を開けて黒板消しを棒でパンパンはたいたんだって。中学校に二年間通った中で、変だけどそのときのことを一番よく思い出すんだってさ。
ぼくの心にも、この黒板消しを棒ではたいているチョンミ姉さんの姿がいちばん印象深く刻まれている。なぜ、そうなのかは説明できない。「変だけど」と、チョンミ姉さんが語るとおりだ。しかし、なぜかは説明できないけれど印象に残る場面を、文学という形で定着させるのが、作家としての腕前というものだ。
もうひとつ、言っておきたいのは、このハン・ガンという作家は、稀に見る二人称小説の名手ではないかということである。
なぜ、第1章「幼い鳥」は、「ぼくは」という一人称ではなく、「トンホは」、「少年は」といった三人称でもなく、「君は」という二人称で語られているのか。
なぜ、第5章「夜の瞳」は、「わたしは」という一人称ではなく、「ソンジュは」、「彼女は」といった三人称でもなく、「あなたは」という二人称で語られているのか。
作家自身の一人称で語られる「エピローグ」まで含めた7章のうち、この2章のみが二人称で語られているのは、何らかの綿密な計算に基づくものなのか、あるいは作家としての職業的な直感によって選択しているものなのか。素人であるぼくにはなんとも判断できないけれども、その語り口は極めて自然で、特に第1章は、読者を1980年5月の光州に何の違和感もなく運んでいく。
二人称の小説というのは比較的珍しいし、ぼくもいますぐに思い出せるものは筒井康隆の短篇くらいなのだが、その数少ない経験からいえば、二人称の語り口というのは、「あなたはだんだん眠くなる……」式の押しつけがましさをなかなか免れないものである。しかし、ハン・ガンの文体には、それがない。
短篇集『回復する人間』の表題作も、二人称小説である。
 ………今あなたは葦の茂みの縁に横たわっている。自転車は川沿いの岩の上に投げ出されて倒れ、車輪が力強く空転している。空中から墜落した瞬間、あなたは本能的に頭をかばった。手とひじの皮膚がむけていることは明らかだ。地面にぶつけた肩と骨盤がじーんと痛みだす。
………今あなたは葦の茂みの縁に横たわっている。自転車は川沿いの岩の上に投げ出されて倒れ、車輪が力強く空転している。空中から墜落した瞬間、あなたは本能的に頭をかばった。手とひじの皮膚がむけていることは明らかだ。地面にぶつけた肩と骨盤がじーんと痛みだす。これくらい、とつぶやきながらあなたは濡れた土の上に横たわっている。灰白色の穴の中のきずのことなど、もう感じられない。土が入った右の目がひりひりする。これらすべての痛覚はあまりに弱々しいと、何度もまばたきしながらあなたは思う。今、自分が経験しているどんなことからも、私を回復させないでほしいと、この冷たい土がもっと冷え、顔も体もかちかちに凍りつくようにしてくれと、お願いだからここから二度と体を起こさないようにしてくれと、あなたは誰に向けたのでもない祈りの言葉を口の中でつぶやきつづける。
この二人称文体の心地よさは、おそらく、このハン・ガンという作家の資質の中核部分に関わっているのではないかと思うのだけれど、漠然と思うだけで、それを解明できるような力はぼくにはない。
ただ、もっと彼女の作品を読んでみたいと思うだけだ。
youjikjp at 15:34│Comments(2)│
│アジア文学
この記事へのコメント
1. Posted by 無題 2020年06月02日 21:49
数年前、高校生だった頃にこのブログを見つけて以来、書評の的確さと選書のセンスが好きでずっと拝読しておりました。
このブログで紹介されていた本はどれも面白く、多分一番初めに読んだ記事は『われらが歌う時』だったと記憶しています。Kさんの書評がとにかく大好きで、どれも読んでみたいと思わせるものばかりで、今でも一番好きな書評ブログです。『われらが歌う時』もそうですが、死の棘も、カラーパープルも、わたしの名は紅も、多岐に渡るジャンルを広く網羅されていて、読む本に迷ったときはこのブログを読む、ぐらい参考にさせて頂いています。
しばらく更新が途絶えていて悲しかったのですが、この記事が更新されているのを見つけ、いてもたってもいられずコメント差し上げてしまいました。コロナの蔓延により気が滅入る日々が続きますが、どうかご自愛ください。更新いつも楽しみにしています。
2. Posted by K 2020年06月03日 00:27
無題さん、コメントありがとうございました。
身に余るお褒めの言葉をいただき、どのようなご挨拶をすればいいのか途方に暮れますが(^_^;)、このブログが、いい作品との出会いのきっかけになったとすれば、ブログ主としてこれ以上の喜びはありません。それが無題さんのようなお若い方であればなおのことです。『われらが歌う時』、面白かったでしょう!! 面白い本はまだまだあります。またいつか時間を見つけて更新したいと思いますので、ときどき覗いてみてくださいね。
身に余るお褒めの言葉をいただき、どのようなご挨拶をすればいいのか途方に暮れますが(^_^;)、このブログが、いい作品との出会いのきっかけになったとすれば、ブログ主としてこれ以上の喜びはありません。それが無題さんのようなお若い方であればなおのことです。『われらが歌う時』、面白かったでしょう!! 面白い本はまだまだあります。またいつか時間を見つけて更新したいと思いますので、ときどき覗いてみてくださいね。





















